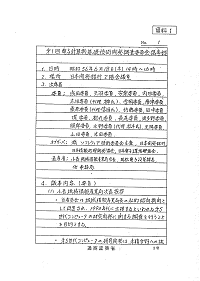【議題と資料】
議題と資料の対応は以下の通り:| (1) | 小長機械情報産業局次長挨拶 | -- | 資料1 |
| (2) | 委員紹介 | -- | 資料2 |
| (3) | 委員長互選 | ||
| (4) | 委員長挨拶 | -- | 資料4(概要) |
| (5) | 調査研究計画について | -- | 資料3(概要)、 資料5(概要) |
| (6) | 各委員の意見 | -- | 資料3(概要)、 資料4(概要)、 |
| 資料5(概要)、 資料7、 | |||
| 資料8(概要) |
【概要】
議事要旨の主な概要は以下の通り:●「(1) 小長機械情報産業局次長挨拶」では、 本委員会の目的、わが国における第5世代コンピュータの研究開発の位置付け、第5世代コンピュータ研究開発と本委員会の関係などが述べられています。
●「(4) 委員長挨拶」では、 2年間の予備調査、日本のコンピュータ産業における独自技術開発の必要性、第5世代コンピュータ研究開発の体制、国際協力などについて述べられています。
●「(5) 調査研究計画について」では、 資料3(概要)、資料5(概要)に基づく、昭和56年度調査研究計画案、第5世代コンピュータ研究開発の意義、背景、これまでの経緯等についての説明に対して、以下の質疑応答があったことが示されています。
- このプロジェクトの規模は10年間でどの程度のものか。
●「(6) 各委員の意見」では、主に
- この委員会のターゲットはどの部分か。
- 今年度の重点目標はどこか。
- 委託調査を行うソフトウェア、アーキテクチャの2つのワーキング・グループでこれだけの内容をカバーできるのか。
- 非ノイマン型を目指すということはバイナリーの思想をはずすことか。
- 心理学的モデルとしては、研究開発提案書4頁の機能要求の「知識の蓄積、活用」と「学習、連想、推論」とは同じことだ。分けてある理由は?
- 学習という意味も、個性を中心とした学習機能を有するのか、一般性を持つ人間タイプのものにするのか。
- 研究開発提案書の第5世代コンピュータ概念図では、マイクロ・プロセッサの集合化したような構成に見えるが、それぞれのマイクロ・プロセッサも知識型になるのか(集中型か分散型か)、さらにこのシステムは多目的に利用するのか。
- ユーザ・ニーズと研究開発課題との結びつきが理解できにくい。
- 電電公社、電総研との関わりについて。
- 国際協力について通産省ではどのように考えているのか。
- IBMがこのプロジェクトに参加したいといってきたらどのように対応するのか。
- 特許についてはどう扱うか、明確にしておかなければならない。
- 多彩なメンバー構成の委員会で良い結果が出ると思う。
- 本プロジェクトは海外でも非常に注目されている。
- このプロジェクトは今までになかった発想でありユニークなものである。
- ソフトウェア重視も良いが、ハードウェアも重要であり、併行して研究開発を行わなければならない。
- テーマはイメージをわかり易くし、国民的支持を得ることが重要である。
- どういう体制で進めていくかが重要な問題である。
- 民間、研究所、大学、国際間等の役割分担を検討していく必要がある。
- 第5世代の目指す方向は10年後のすう勢としては間違いない。
- これから10年間まじめに取組めば、かなりのことが、日本を中心としてやれると思う。
- 未踏型の技術開発では、いくつかの代替案を用意し、それらの評価を行いながら取捨選択していくこととなろうが、取捨選択型の研究体制は日本に育っていない。従って誰がどのように評価するかが大問題である。
- メーカは、資金、出向者、出向者が戻ったときの待遇面など考えなければならないことが多い。
- ユーザサイドからみると、機能に対する要求は新味があまりないように思える。
- ユーザ側の立場で見た場合、このプロジェクトは、良いものを建てるから上手に住めというのか、それともユーザの要求を受け入れてもらえるのか、よくわからない。
- 目標の1つである"使い易さ"についても、専門家が考えた"使い易さ"と、素人の"使い易さ"では全く異なる。このような点の検討が欠けているように思う。
- "使い易さ"はあいまいさを感じさせ、目標として設定しにくい。的確な言葉をみつけ、目標として設定した方がよい。
- 資金や成果をプールして使うことを検討しておくことが必要だ。
- 成果が各企業にとって利用できる点が素晴しい。
- 成果が社会、個人の生活にまで広がっていくことが重要だ。
- 通信の問題、研究者や人間の教育の問題も重要である。
- 新しいシステム記述用の言語が必要と思う。
- 先進的プロジェクトが現在のコンピュータ産業やソフトウェア産業等企業、社会にどのような影響を与えるかについて今後の課題である。