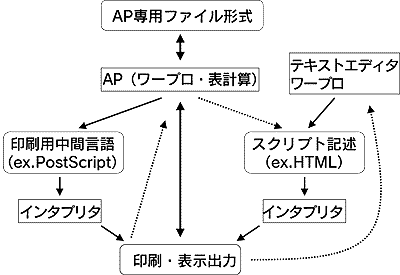
電子技術の急速な進歩によりコンピュータの小型化/高性能化は飛躍的な進化を遂げ、今やかつてのメインフレームを凌ぐ性能のコンピュータをパソコンとして個人で使える時代になった。更にWWWの出現によりパソコンを使えば、様々の情報を世界中からネットワークを介して入手することができるようになった。
しかしながらパソコンはその利用環境や目的が時代と共に急変しているにも関わらず、相変わらず「プログラムを実行するマシン」という従来のコンピュータのコンセプトをひきずったままである。TVスタイルのディスプレイ、キーボード/マウスによる入力手段という基本デザインはワークステーション誕生当時から何も変わっておらず、素人が電子情報を読むための道具にはなっていない。
マルチメディア時代になっても文書情報は情報伝達のための最も基本となるメディアであり、電子化された文書を誰もが読み書きできる道具として新しいコンセプトの情報端末が必要な時期にきている。本章では21世紀の高度情報化技術の「大衆化」を実現するための知的な文書情報インタフェースについて論ずる。
パソコンとインターネットの普及により、誰もが気軽に情報を発信したり、ネットワークを介して世界中の情報にアクセスすることが可能になってきた。高度情報化社会という言葉は10年近く前から叫ばれていたがようやくそういう時代が現実になろうとしている。このようなインフラの普及を契機に電子出版や電子新聞という、従来、紙に印刷されて配布されていたメディアのディジタル化が進みつつある。
このような情報の電子化は知識の大衆化を促し、誰もが公平に高度な知識情報に接することが可能な社会を実現する。例えば、どこに住んでいても国会図書館の蔵書を読んだり、国立博物館の展示品を観賞したりできるようになれば中央と地方との間の情報格差を縮めることが期待される。また、電子化は紙への無駄な印刷を止めることで紙の消費を減らし、貴重な森林資源の枯渇を防ぐことにもつながる。
このようにネットワークを活用した電子化社会の未来は明るいが現実にこのような電子化された情報、特に文書を簡単に扱える情報端末が存在しないという大きな問題がある。
パソコンはオフィスでの文書作成や表計算を利用した各種帳票作成になくてはならない道具として定着している。これらは従来、紙に手書きで作成されていたものであるが、コンピュータの清書機能、編集機能、表計算機能などを利用することで文書作成の効率は飛躍的に向上した。ネットワークの普及によりそのまま電子化された状態で利用されることが期待されているが、現実には一旦紙に印刷されてから配布、回覧されていることが殆んどである。その理由はパソコンが文書作成装置としては優れていても作成された文書を読み書きする道具になっていないためである。
一方、家庭ではこのような文書作成や表計算のニーズが少ないためパソコンの導入があまり普及していなかったが、WWWの出現によってインターネットを介した新しい情報発信/情報サービスが台頭し、これらの情報にアクセスするための道具としてパソコンが利用されるようになった。しかし、ここでもパソコンが情報を読むための道具として使い難い問題が顕在化しつつある。
1. 汎用コンピュータであることの問題
パソコンはそもそも汎用コンピュータとして作られており、ソフトウェアさえ変えれば何でもできるように作られている。しかしながら、汎用性が高いがゆえにその操作法や環境設定、必要なソフトの組み込みにはノウハウが必要となり使いこなすのが難しい。素人が情報アクセスのために利用するのなら、機能が限定されても操作の単純な専用端末の方が適している。
2. 電子文書表示の問題
パソコンのディスプレイは基本的にTVのデザインであり、本を読むように机に水平に置いて使えない。また、その表示解像度は低く、印刷物に遥かに及ばない。更に紙の資料のように気軽に書き込むこともできない。電子化された情報を「読み書き」するためには新しい機器形態、表示デバイスの出現が必要である。
3. キーボードの問題
パソコンの入力装置としてはキーボードとマウスが定番になっているが、誰もが使う道具としては必ずしも理想ではない。ペン入力の方が適している状況も多くある。また、キーボードの使えない人はいても、ペンを使えない人はまずいない。特に子供やお年寄りに慣れないキーボードの使用を強いるよりペンで気軽に入力してもらう方が負担が少ない。我々が日常、紙やペンを気軽に使って情報を書きつけているように気軽に入力する手段が必要である。
4. 電子文書のデータ形式の問題
ワープロで作成される電子文書はそのワープロ専用のファイル形式になっているのが普通で、それを読むためには同じワープロを使う必要に迫られる。一方、WWWではどのようなブラウザでも情報が読めるようにページ記述言語HTML(HyperText Markup Language)で記述する約束になっているが、HTMLにはレイアウト機能が殆んどなく、ワープロで作成するような本格的な文書が作成できない。今後、複雑なレイアウトを持つ新聞や雑誌を電子的に読むためには表示デバイスに依存しないポータブルで高品質出力を可能とするデータ形式を確立する必要がある。
5. 操作指示の問題
ワープロや表計算ソフトは利用者の多様な要求に応えるために様々の機能を備え、それに伴う操作の複雑化によりせっかくの豊富な機能を使いこなすことが困難になりつつある。
キーボードやマウスによるメニューのクリックだけで作成者の意図を伝えるには限界がある。また、作業が高度になる程システムが自動化してくれる恩恵は大きいのだが、利用者の意図と合わない場合にはかえって使い難くなるというジレンマに陥る。
これまではコンピュータの中の電子情報の世界と、本やノートという物理世界は分離していたが、「情報の電子化」とはその間をシームレスにつなぐことに他ならない。
現実世界と電子情報の世界を融合する技術としてAugmented Relity(仮想現実感) が注目されている[1]。Virtual Reality(仮想現実感)はコンピュータにより全く仮想の世界を電子的に構築して人間があたかもその世界に入り込んだかのように電子情報にアクセスできる仕掛けとして注目されたが、仮想世界をリアルに構築するには莫大な工数や高価な装置が必要となる。また人間が仮想世界のオブジェクトを触ったり動かしたりするインタラクションの実現にはまだ技術革新が必要である。むしろ、身の周りの道具やメモ等の身近な現実世界と電子情報をうまくリンクさせて人間の作業を知的に支援しようという立場からAugmented Reality(拡張現実感)が提唱された。例えば、机の上をTVカメラで撮影しておき、紙の上に書いた内容や人間の動作を電子的に取り込むとか、メガネを通して見ている製品の保守の手順がメガネ越しに投影されるなどの研究がなされている。このような技術は人間と機械の自然なインタフェースを実現するために今後益々重要になるが、電子的な「紙と鉛筆」の実現もAugmented Realityのひとつと位置づけて良いであろう。
紙の文書なら、
が誰にでもできる。このような紙の文書では当たりまえのインタフェースが現在のパソコンでは満たされていないのが現実である。
例えば、文書を読むためにはフラットで高精細の薄型ディスプレイが必要となる。少なくともA4サイズで300dpiの解像度は欲しい。しかし現状のディスプレイ装置の表示ドット密度は一般に100dpi前後であり、オフセット印刷の6000dpiとの比較は論外としても標準的なプリンタの出力品質600dpiにも遥かに及ばない。また、この解像度ではA4サイズの用紙1ページを原寸表示しようとしても字が潰れて読むことができない。大型のディスプレイを用いる手もあるが、大きな字はかえって読み難い上、ページ全体をひと目で見渡すことが困難になる。LCDパネルを利用したディスプレイの薄型化も普及してきたが、まだCRTの「忠実な」置き換えである。人間工学的には視線を下げる方が疲労が少ないと言われているが、水平に置いて読むようにはなっていない。更に、いずれのディスプレイも自己発光型であり、本を読むように目を近付けて長時間見続けることは疲労の原因であり、CRTの場合は更に電磁波の生体への影響が不安である。
一方、文書への書き込みに関しても古くからペン入力装置が開発されているが、以下のような問題がある。
入力デバイスの問題以外に更にシステム側の障壁もある。システムから見ると「書き込み」とはペンやマウスのイベントを取り込んで画面に表示する処理になるが、このようなソフトが常に動いている訳ではない。例えばパソコンのデスクトップ画面では表示されているアイコンをクリックすることはできても、勝手に文字を書き込めるようには作られていない。物理的な紙や本なら自由に書き込めるのに、コンピュータでは書き込みを受け付けるかどうかをシステム側が勝手に決めている、ということである。
紙の文書を電子化する際の悩ましい問題は「どういうデータ形式に統一するか?」を決めることである。電子文書の実現形態には以下に述べるいくつかアプローチがあるが(図3.10-1)、各々文書作成/編集に専用のツールを要求することが多く、組織で共有しようとすればツールの統一が必要となり、場合によっては使用するマシンのスペックまで決めかねない。逆にワープロ開発メーカは他社製品との非互換性により顧客の囲い込みを図ることになる。
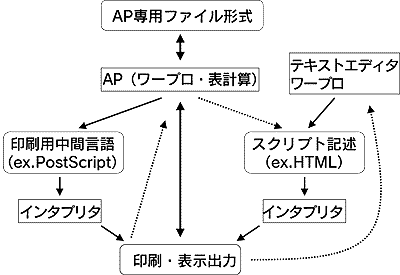
(1) アプリケーション専用ファイル形式
ワープロの持つ機能を最大限に利用しようとすればそのワープロ独自のファイル形式で格納するのが最も効率的である。この場合、文書を共有するには使用するワープロソフトを統一することになる。組織としてそのような意志決定が可能なら文書共有を実現する最も簡単な方法であり、現実的なアプローチと言える。但し、特定製品に縛られることになり、他社が新しい製品を出してきても簡単に乗り換えることはできなくなる。個人の好みや慣れを無視して特定ツールを強要することにも議論があろう。
(2) 印刷用中間言語への変換
Adobe社のPostScriptはプリンタの解像度に依存しないポータブルな印刷出力形式(中間言語)である。印刷イメージは一旦、PostScriptで記述された中間言語形式に変換されてプリンタに渡され、プリンタ側では内蔵されたインタプリタがハードウェアの解像度に応じて最終的な印刷出力を実行する。PostScriptはレーザプリンタのような高品質印刷を目的とする場合の標準出力形式として普及しており、多くのワープロソフトでサポートされている。
PostScriptを文書印刷用に特化して改良したものがPDF(Portable Document Format)であり、これもWWWにおける文書表示用標準形式として普及しつつある。
これらはいずれも中間言語を解釈/実行する専用プログラムが必要となるが、出力ハードウェアに依存しない「ポータブル性」という点で優れている。基本的にはディスプレイもプリンタと同じように扱える(c.f. DisplayPostScript)。
難点は元データ → 中間言語 → 印刷/表示という、印刷を目的とした一方向の変換処理のため、編集が不可逆であること。即ち画面を指したり、情報を書き込もうとした時に表示イメージと元のデータ表現との対応をとることが原理的に難しい。
(3) スクリプト言語による記述
SGMLは電子文書のページ記述言語として早くから標準化されていたが、どんな文書でも扱える代わりに仕様が大きく複雑で、結果的に使い難いことから実際の利用はそれほど普及していなかった。しかしその簡略版であるHTMLはWWWのページ記述に利用されたことから一気に普及し、現在その拡張仕様であるXMLが注目されている。
このようなスクリプト言語は簡単な文書の記述/表示には非常に有効であるがレイアウト機能や使えるフォントが限られており、通常のワープロに較べると自由なページ構成が作れない。また、(2)と同様にインタプリタによる解釈実行が一方向であり、表示イメージを操作しようとするとインタプリタと逆向きの対応づけが必要となる。
(4) 複合文書
近年、ワープロ文書やスプレッドシートを組合せて自由にページを構成できる複合文書技術も注目されており、OpenDocやOLE、ActiveX技術が開発されている。いずれも技術的なポイントは、はめ込まれている文書から編集に必要なアプリケーションプログラム(ワープロやお絵描きソフト等)を起動する仕掛けを実現することである。複数のオフィスツールを統合するために開発された経緯から各コンポーネントとしてアプリケーション専用ファイル形式をそのまま組み込めるのが普通である。
OpneDocはこのような部品の組み込みを一般化した枠組を提供しようとしたものであり、利用者が自分の好きなツールを組み合わせてページを構成できるよう開放した点で興味深い試みであったが広まるには至っていない。最近は同様の試みをJavaで記述することによりWebブラウザのプラグインとして提供するアプローチが現われている。
今後の電子文書普及には特定製品やハードウェアに因われないオープンでポータブルなデータ形式の確立が必要である。また、最終的には誰がどのようなツールで作成しようとも受け取った電子文書は自分の使い慣れたツールで操作できるべきである。
が必要となろう。
(1) 手書き入力の活用
自然な入力インタフェースとしてペン入力がある。FAXや筆談のように手書き入力をそのままの形で利用できる用途も多い。更にこれらの手書き情報を電子情報としてコンピュータで扱えればより高度な情報活用が可能となる。例えば手書きメモの一部を「To Do リスト」として登録し、メニューで呼び出したり検索する試みが提案されている[2]。紙に書いた場合は忘れてしまえばそれまでであるが、電子情報ならカレンダと同期させて必要なタイミングで画面に表示する、ということも可能になる。手書き情報も電子的に取り込むことによりこれまでに無かった新しい利用方法を開拓できる。
(2) ユーザの意図の抽出
ユーザの意図抽出は様々なレベルが考えられる。例えばフリーハンドの手書き情報を清書する応用を考えてみよう。絵や図形の入力はペンを使う方が圧倒的に簡単であるが、「奇麗に」書くのは難しい。この矛盾をシステムが解決してくれれば簡単に奇麗な絵が描けることになるが、実現はそう簡単ではない。例えば直線を描く場合、最初から「直線を描こう」としている書き手にとって、入力に曖昧さはなく(限りなく直線に近い線を描いていると本人は自覚している)、認識は簡単そうに見える。しかし、これは現在のコンピュータが最も苦手としている問題領域になる。
そもそもペンの動きだけからは利用者が文字を書いているのか絵を描いているかをうまく識別することが難しい。例えば短い直線と漢字の一部は区別できない。「絵の入力モード」に限定した場合でも、どういう直線を描きたいのか、例えば端点を別の図形に接したいのか、離すべきか、利用者の意図を一意に固定できない。これは自然言語処理において、一つの例文だけを考えると簡単に解釈できそうに思えても、いろいろな例外を扱えるように知識を与えるうちに単純な認識ができなくなる事情と同じである。個々の判定アルゴリズムは作れてもマクロな「状況判断/認識」ができないことに起因している。一つのアプローチとして「垂直に交わる」「接する」等のよく使いそうな幾何学的制約をシステムに組み込み、奇麗な図形を描かせる試みがある[3]。
また、近年のワープロソフトは多くの機能を実現しているがためにその操作が非常に複雑化してしまい、結局普通の利用者には使いこなせないのが現状である。このような複雑な操作をキーボード+マウス+メニュだけで操作することにそもそも問題がある。ペンやもっと画期的なポインティングデバイスの創造が望まれる。例えば「領域選択+消去ボタン」より「不要な部分を2重線で消す」という動作の方が馴染み易い。あるいは利用者の繰り返し操作を認識してシステム側が支援することにより入力効率を上げる試みもある[4]。
ジェスチャー入力も含めて、人間の何気ない操作から意図を理解し、少ない操作で望みの処理を実行してくれるような仕掛けが必要である。現時点のコンピュータの知能レベルはそれほど高くないので、むしろ状況に合わせた利用上の工夫が重要であろう。
(3) 文書の内容理解
文書処理ソフトは基本的に文字コードを表すバイト列を処理しているに過ぎない。最近のワープロソフトはスペルチェックや文体チェック機能もついているが文書の「内容を理解」してくれている訳ではない。
例えば紙の資料ではメモや覚書を自由に「上書き」できることがメリットである。このような「上書き」を電子化情報で実現する場合、上書き情報を本文とは別のレイヤとして構築し、文書上に重ね合わせて表示する方法が一般的である。しかし、このような方法では本文が編集された時に上書き情報だけが元の位置に置き去りにされてしまう。これは文書の内容を理解せずに単なる位置情報だけでリンクしていることから生じている。
文書処理をより知的にしようと考えると、文書テキストは自然言語処理に適するような構造(例えば単語や品詞等)を常に反映したものになるべきであろう。
これまで述べたような問題の解決方法の一つとして、報告者は紙のような操作感で利用できる情報端末、「紙指向端末」の研究/試作を進めている[5]。
(1) 紙指向インタフェース
紙指向端末は紙の持つ良さとコンピュータの持つ能力の融合を目指している。
<紙の持つ良さ> ・読み易い ・自由に書き込める ・ページ全体が見える ・扱いが簡単 |
+ | <コンピュータの得意技> ・検索/加工が自由 ・複製/配布が簡単 ・大勢での共有が簡単 ・大量データの高速処理 |
これらの融合により、印刷物のように読めて、ペンで自由に書き込みができ、且つ、書き込まれた情報が共有/検索できるような情報端末が実現できる(図3.10-2)。印刷物のように読めることから紙への無用な印刷を減らすことができる。自分だけのメモを書き込めることにより紙による書類配布と同じにできる。更に書き込み情報を共有することにより後述するようにコミュニケーション手段として利用できる。ペン入力が簡単で奇麗に書けるようになれば伝言メモや簡単なメールを手書きのまま送ることも普及するであろう。紙指向端末の狙いの一つは、難しいワープロ操作を覚えずとも手書き情報を活用してもっと気軽に情報交換を実現することにある。
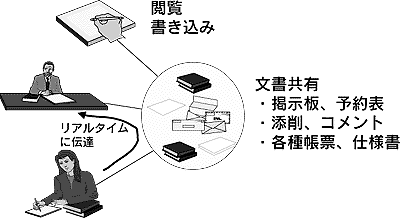
(2) 紙指向端末による文書共有
文書やメモは物理的な移動により情報伝達/共有を実現するが、紙指向端末は「書かれた情報」をネットワークを介してリアルタイム共有することでそれを実現する。
例えば会議開催通知の例を考えよう。1枚の通知に各参加者が希望日を書き込むことができ、それが全員に見えるならば集計や編集作業は不要となる。このような情報共有は従来ホワイトボードやWebで実現されるのが普通であるが、前者においては汎用の文書にはなっていない、アプリ専用エディタの利用を強いられる等の問題があり、後者ではHTMLベースの文書しか扱えない、自由な書込みができない等の不便さがあった。
この解決のためには「共有文書」という汎用化した枠組を実現した。即ち、種々の文書/帳票を作成するだけで、それらが掲示板や共有文書になる仕掛けである。これにより、例えば仕様変更の書き込みがメンバ全員に即伝わるような仕様書を作成することができる。
共有される文書情報はサーバで集中管理される方が安全性や一貫性維持の点から望ましく、紙指向端末は情報の読み書きというユーザインタフェースに特化し軽量化すべきである。そこで文書共有システムの実現方法として、文書オブジェクトをサーバに置き、描画処理部のみを端末にダウンロードして文書イメージを表示する「複合文書分散共有方式」を開発した[6]。また、ユーザインタフェース画面はページ単位の表示を基本とし、これらの共有文書を一冊にまとめたバインダとして見せる本メタファを採用した[7]。これによりユーザは目次やページめくり等の慣れ親しんでいる操作で共有文書を利用することが可能となる。
複合文書共有システムはJavaで試作中であり、紙指向端末のソフトウェアとしては小型リアルタイムOS[8]とJavaVMをベースとするシンプルな構成で実現している(図3.10-3)。
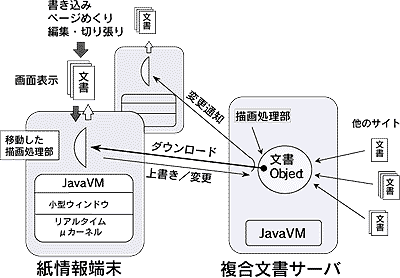
(3) ペン入力一体型の超高精細ディスプレイ
紙を目指すには少なくともA4サイズ/300dpiの解像度が欲しいところであるが、その実現には900万画素が必要となり現時点では消費電力やバスの転送速度等から考えて実現が難しい。現実解としてはA4より一回り小型のサイズで180dpi前後の液晶パネルを最初の開発ターゲットと考えている。余白を除けばA4文書のテキスト部分を全文表示できること、人間の眼の分解能から1ドットを識別できないギリギリの解像度と考えられるからである。
書き心地の向上にはペン先の材質やドライバソフトの工夫をしているが視差の低減のためにはセンサ機構を液晶パネルに内蔵する方式を研究中である[9]。入力機能付き液晶パネルによりペン入力のための余分なハードは不要となり、視差の低減(ペン先と液晶の間はガラス1枚)と装置の薄型/軽量化が同時に達成できる。
本章では電子文書の読み書き、知的な編集機能の必要性について述べた。文書情報は人間同士のコミュニケーションの最も基本となる情報メディアであって、意志表示や意志決定のために不可欠な情報表現形式である。ネットワークが活用できる時代になれば、これらの文書情報の電子化は必然の流れであり、またその作成/編集を誰でも簡単に効率良くできるようにするためのエディタやワープロ技術は今後も重要な課題である。従来の紙と鉛筆の物理世界と電子情報の世界をシームレスに接続するには自然言語言語処理や認識技術等の知的支援が必要である。
・日本語入力問題
キーボードはアルファベットのための入力装置であって漢字仮名混じりの日本語入力には向いていない。我が国は仮名漢字変換技術でこのハンディを克服してきたが、誰もが簡単に入力できるためにはペン入力の活用等のより自然なインタフェースの実現が急務である。
最近では音声入力技術も実用化の域に到達しつつあることもあり、これらの自然言語処理技術、認識技術を駆使して日本語の効率良い入力方法を確立することが重要である。日本語入力処理は非英語圏の人々に共通する問題であり、日本のその先端技術を活かして率先して取り組む課題である。
・情報の大衆化
一部の専門家の間でしか利用されていなかったインターネットが誰にでも開放されたことで、新しいビジネスチャンスが生まれ社会の活性化が実現されている。これを一過性のブームにせず、高度情報化社会を実現するには誰もが電子情報にアクセスできる「情報の大衆化」が重要である。そのためには電子情報を「読み書き」するのに相応しい情報端末、誰もが簡単に扱える情報端末の実現が急務である。情報は大勢の人が共有してこそ力になり、それによる社会の活性化は最終的に国力の強化につながる。
・市場競争原理の功罪
かつては通産省大型研究開発プロジェクトに代表されるように、国をあげて欧米諸国に追いつくための努力がなされてきたが、その目的がほぼ達せられた今日では、むしろ国が主導するよりオープンな市場での企業間の健全な競争による技術革新が重視されている。
しかしながら、市場原理は両刃の剣であり、競争によってより良い製品が生き残る健全性がある一方で、技術の善し悪しよりも沢山売れること、社会や将来よりも自分が儲かることが優先される危険がある。現にパソコン市場は一部米国企業による寡占により新しい技術が育たないとう状況になりつつある。新しい情報端末の普及のような社会インフラに関わるような技術は世の中に定着するまで時間が必要であり、競争原理で動いている企業では取り組み難い。新しい流れを生み出す研究開発はプロトタイプ試作、特定地域での実施評価の段階までを国の支援で立ち上げることが必要と考えられる。但し、思惑の異なるメーカー各社を集めて無理矢理歩調を合わせる旧来方式ではなく、むしろ優秀な研究者をリーダとするベンチャー的な小グループで競わせることが望ましい。ある意味で国家レベルでのベンチャーキャピタルの実現と言える。利益優先の企業では取り組めない課題、だが将来、国民の生活を豊かにする上で必要なテーマは国が投資して育てる機構が必要である。
・永遠のテーマとしての人工知能
人間にとっての自然なインタフェースの実現には、最終的に人間の意図を理解する知能/知性が必要となる。第五世代コンピュータで盛り上がった人工知能研究には一時の勢いが見られないが、知能の実現はすべての技術領域にブレークスルーをもたらすものであり、視点を変えて何度でもトライすべき課題である。人間の認識/理解には五感がフルに連携して働いていると考えられるが、最近のディジタルカメラやセンサ技術の進歩は目覚しく、より高度な認識レベルを実現できる期待がある。基礎研究として民間企業が取り組むには難しいテーマであるが故に、長期ビジョンに基づいた国の研究支援が必要である。微力な水の流れも何時かは堅い岩に穴を開ける時が来ることを信じてやまない。
<参考文献>