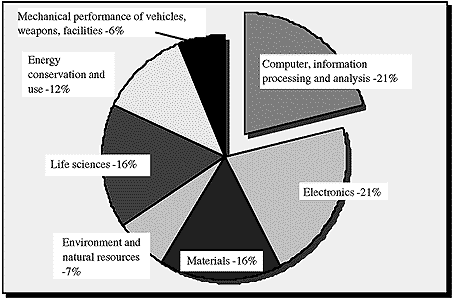
連邦政府自体は、先進的なユーザとして情報技術を直接利用することによって、情報技術の開発プロセスのうち「市場化・情報基盤整備」において主要な役割を担っている。スパイラルモデルに基づく開発モデルにおいて、情報技術のベンダに対して一定の市場と新たな研究開発投資における原資を提供する一方で、提供されたプラットフォームを適正に評価し、新たな技術的フィードバックを行なうような先進的ユーザの存在は、極めて重要である。連邦政府は一貫して、この先進的なユーザとして主要な役割を果たしてきたと言える。
まず、連邦政府が実施する宇宙・軍事関連開発は、常に先進的なコンピュータ技術のユーザであり、自らのミッションに沿ったコンピュータ技術の研究開発に対するスポンサーになっている。例えば、1982年にSmall Business Innovation Development Act(PL 97-219、PL 102-564)を根拠法として創設されたSBIRプログラムは、研究開発予算が1億ドルを超える全ての連邦機関が、その各研究開発予算のうち一定比率の予算を中小企業に出資するというプログラムであるが、同プログラムにおける情報技術関連の連邦機関別出資割合を見てみると、最も高いのがDoDの26%であり、これにNASAの25%が続いている。こうした DoDやNASAは、当該連邦機関が利用とする情報技術に焦点を絞って、中小企業を対象にその研究開発の研究公募を行なっている。
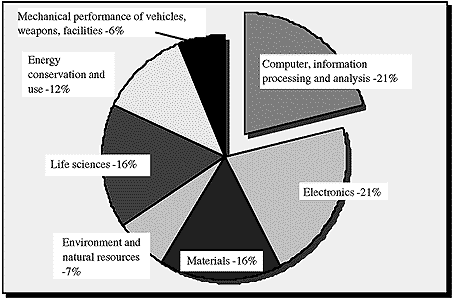
HPCCI(High Performance Computing and Communication Initiative)が開発対象としている高性能コンピュータも、幾つかの連邦機関が先進的な初期ユーザとして、高性能コンピュータの調達、評価、技術的フィードバックなどで研究開発に参加している。例えば、DARPAは軍事分野における材料研究に、NASAは航空機設計における流体計算、DOEにおける核爆発シミュレーション(核実験の停止に伴い計算シミュレーションに対するニーズが急速に拡大したと言われる)、EPAにおける大気汚染シミュレーション、のように、各連邦機関は個別ミッションのためにHPCCIで開発された高性能コンピュータを調達し、各ミッションに役立てるとともに、開発者に対して技術的フィードバックを行なってきた(注5)。
| (注5) | ただしCSTBレポートは、今後、連邦機関がベンダよりハードウェアを調達するという直接的な投資は、連邦機関の特定ミッションをサポートしたり特殊ハードウェアを利用したりする場合を除いて停止し、むしろ、大学や研究機関で実施されるような前競争段階にあるアーキテクチャやハードウェア研究に対して資金援助を強化すべきであるとしている。 |
近年では連邦機関が中心となって進めている情報基盤の整備事業が、新たな情報技術の推進力として重要になってきている。NRENによるコンピュータネットワークの整備やSupercomputing Centerはこうした事業の典型的な例と言える。連邦政府は、NRENを通じてSupercomputing Center等の計算資源やデジタルライブラリ等の情報資源にアクセスできるインフラストラクチャを構築しようとしている。ここで構築された情報基盤は、すでに述べたように新たな研究開発を触発することが期待されている。
すでに、HPCCIではネットワーク上で新たな高性能コンピュータを利用するアプリケーションとして遠隔医療、デジタルライブラリ、教育、製造(CALS)、電子商取引、行政サービス、環境モニタリング等の「National Challenge」と呼ばれるアプリケーションに関する研究開発を1994年より同プログラムに追加している。このコンポーネントには、情報アクセス技術や知的インタフェース技術のように、ネットワーク上でコンピュータを利用するための基本的なプラットフォーム技術の研究開発も含まれている(注6)。
| (注6) | それまでHPCCIが主要なアプリケーションとしていたのは「Grand Challenge」と呼ばれる、高性能コンピュータと高速通信ネットワークを利用した大規模科学技術計算であった。これらの研究は、情報技術以外の分野との学際的研究が多く、どちらかと言えば長期的な研究が中心となっていた。新たに「応用指向」で、短期的なインフラストラクチャ整備を目指してる「National Challenge」を加えたことで、長期的研究開発と短期的研究開発のバランスをとったという見方がある。 |
インターネットは、その技術的起源から国家的な情報基盤として整備するまで、連邦機関が図IV−4にあるスパイラルを一貫して支援してきた技術分野であると見ることができる。ここでは、このインターネットについてやや詳細に事例研究を行なうことによって情報技術の研究開発における政府に役割について検討してみる。
インターネットは、1960年代前半に米国ARPA(現DARPA)が企画したARPANET構想に始まる。このARPANETは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)、スタンフォード研究所(SRI)、カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)、ユタ大学の4ヶ所の電算センターを結ぶネットワークという構想でスタートしている。このARPANETは、当初から分散情報処理を指向した開放型相互接続システム(open systems interconnection)であり、その意味で最も先端的な情報技術開発課題に挑戦していたと見ることができる。すなわち、多様なハードウェアアーキテクチャを有するマシン間の通信を確保し、ほぼ全てのパケット交換ネットワークハードウェアをベースとし、複数のコンピュータオペレーティングシステムに対応可能なネットワークアーキテクチャを当初より目指していたわけである。今日、こうした技術を実現させている「パケット交換ネットワーキング技術」は、以上の経緯の中でDARPAにより採用され、そのアイディアの具体化が進められ、その後、TCP/IPプロトコルの提案につながった。TCP/IPはARPANETの通信プロトコルとして採用され、結局、今日のインターネットの標準プロトコルとして今日に到っている。
DARPAは1980年頃よりARPANET の TCP/IPへの移行作業を進め、1983年にこれを完了させている(完了と同時に、研究を目的としたARPANETの一部から、軍専用のネットワークとして用いられるMILNETとして分離された)。この間、DARPAはTCP/IPを用いた初期の実験プロジェクトのスポンサーとなった。図IV−4における「標準化・プラットフォーム化」も、DARPAが行なう研究開発プログラムのなかで進められたことになる。
特にコンピュータ科学の研究を行う大学研究者の間でTCP/IPのプロトコル普及を進めるためにDARPAがとった戦略の一つは、当時、殆どのコンピュータ科学の研究者が利用していたカリフォルニア大学の「Berkeley Software Distribution」から入手できるUNIXオペレーティングシステムとTCP/IPを統合し、フリーソフトウェアとして提供していくことであった。DARPAは、マサチューセッツ州ケンブリッジのボルト・ベラネク・アンド・ニューマン社(BBN)に資金提供を行い、UNIXで利用可能なTCP/IPプロトコルの実装を行い、さらに、BBN社が開発したTCP/IPプロトコルをバークレイのUNIXディストリビューションに統合すべく、カリフォルニア大学に対する資金提供を行った。これにより、フリーソフトウェアとして研究者が利用するUNIXベースのTCP/IPが配布され、90%以上の大学のコンピュータ科学科においてTCP/IPベースのコンピュータ間通信がサポートされた。この時期、各大学のコンピュータ科学科はLANの導入を進めようとしていたために、TCP/IPの普及の促進要因となった。こうして、DARPAの支援プログラムのなかで、TCP/IPは技術として成熟化する一方、コンピュータ科学の研究者間に浸透し始めたインターネットの標準プロトコルとして定着していった。
コンピュータネットワークが全米の研究者にとって重要なものとなることを予想し、DARPAが構築してきたインターネットを研究者全体に普及することを主導したのはNSFである。1985年、NSFは、ミシガン大学やイリノイ大学をはじめとする全米5ヶ所の大学に「Supercomputing Center」を開設し、そこを拠点としたアクセスネットワークを構築するプログラムを開始した。さらに1986年に、NSFNETと呼ばれるスーパーコンピューティングセンターを接続するバックボーンネットワークに対する出資を開始し、ネットワーキングプログラムを推進していく。さらに NSF は、1986年には、ある地域の研究機関を相互接続する多数の地域ネットワークを構築するための原資を提供している。地域ネットワークを育成することで、米国内の研究ネットワーク整備を加速する、とのNSFの戦略はこの時期に始まる。
|
|
ARPA・NSF以外の | ||
|---|---|---|---|---|
| 1986 | NSFNET (前年にSCを設置) |
−/? | − | − |
| 1987 | Merit社とNSFが契約 (MCI、IBMが協力) T1(1.544Mbps) |
−/? | − | − |
| 1988 | I I |
−/? | − | − |
| 1989 | I I |
14M(MCI+IBM=40-50M) (515/95ネットワーク) |
− | − |
| 1990 | ANS (Advanced Network &Services, Inc) T3(45Mbps) |
14M | 16M/− | − |
| 1991 | I I I I |
23M/− | 27M/− | − |
| 1992 | I I I I |
55M/− (4976/1697ネットワーク) |
40M/− | − |
| 1993 | I I I |
50M/30.1M | 55M/45M | 26M |
| 1994 | NSFNET解体−>民間移譲 I |
50M/41.6M | 60M/59M | 47M |
| 1995 | 1995 vBNS(156Mbps以上)開始 |
−/40.8M | −/77M | 38M |
NSFは1987年に、IBM、MCI、Merit社(ミシガン州の大学8校によるコンソーシアム)とNSFNETを共同運営する委託契約を結ぶ。3社グループは、1988年8月、NSFNETの中枢である5つのセンターを結ぶバックボーンとして、伝送速度1.544Mbpsの「T-1」を構築し、1990年9月には、NSFNETの管理・運営を専門に手掛ける合弁企業、アドバンスト・ネットワーク・サービス(ANS)社を設立した。1992年12月にはバックボーンが45Mbpsの「T-3」に代わり、1994年1月には、ANSの親会社の一つであるIBMが、全米でT-3の伝送速度が利用できるようになったことを発表するとともに、NSFからの委託で、バックボーンをさらに高速化して155Mbps(「OC-12」)とする準備を進めていることを明らかにした。図IV−7は、HPCCIにおいてNSFNETがNREN(National Research and Education Network)と呼ばれる新たな国家的な研究・教育ネットワークとして整備が進む過程も含めて、1986年より米国連邦政府はインターネット整備および関連研究開発に出資している予算の経緯を示したものである。本図にあるように、インターネットの整備予算は単に連邦政府のみが支出していた訳ではない。IBM社やMCI社は1989年までに、回線、機器提供、開発に相当な現物寄与(in-kind)を行っている。これらの会社は、一部連邦政府の資金援助を受けながら、インターネット整備とそのための技術開発を進めた。
また、原資はNSFより提供されているものの、多くの地域ネットワークは当該地域の大学、研究機関あるいは州政府等が全投資の90%程度をもって構築されている。例えば、アイオワ州のICNでは、州内の大学、図書館等を結ぶネットワークのために1億ドルを州が負担し、その4分の1の金額を関連教育機関が負担しているという。
米国においては、ARPANETの最初の公開デモンストレーションが行われた1972年以後、企業向けにネットワークへの接続サービスを提供する民間事業者が少しずつ現れ始めている。そうしたネットワーキングベンダのさきがけであるBBN社(前出)が1975年に設立したテレネットは、その後、Sprint社の所有となり、現在のインターネットサービスSprintNetの原型となる。1980年代後半になると、ベンチャー資本に基づくUUNETテクノロジーズ(バージニア州フォールズチャーチ、1987年設立)、パフォーマンス・システムズ・インターナショナル(PSI、バージニア州ハーンドン、1989年設立)等の中小規模のネットワーキング事業者が多く設立されるが、これらの企業は、専用回線ベースの事業以上にグローバルかつオープンなデータネットワークであるインターネットへの接続サービスへの需要が高いことに気づき、インターネット事業へ参入することになる。ところが、1990年に政府の資金により運営されているNSFNETが営利企業同士の通信に利用されていることに対する批判が連邦議会内で起こり、NSFはNSFNETのバックボーン利用規則AUP(Acceptable Use Policy)を定め、「純粋に研究・学術目的以外の利用」を禁じたことから、商用インターネットの普及が一時後退することになる。1991年3月に設立されたCIX(Commercial Internet Exchange)は、この措置によりSprint社やUUNET、PSIなどの民間サービス事業者が、NSFバックボーンに次ぐ第2のバックボーンとして確立したものである。
この間、Sprint社やUUNET等の民間ネットワーク事業者は、大学や研究機関をNSFNETのバックボーンへ接続するサービスを州政府やNSF等の資金を得ながら行い、NSFNET自体は、Merit社、IBM、MCI社の合弁による非営利企業ANS(Advanced Network & Services, Inc)によって運営管理された。さらに、ANSは、1991年9月に、民間企業と研究・学術機関間との接続を行うための子会社、ANS CO+REを設立している。
以上の経緯により民間ベースのインターネット産業基盤が整備されたことで、NSFはそれまでの統制を緩めてインターネットの管理主体を民間に移行させる方針を打ち出した。High Performance Computing and Communications ActによりNRENを政府機関や大学、学術研究機関、教育機関を接続するための専用デジタルネットワークにしようというのがNSFの方針である。1992年5月、NSFは「NSFNETを廃止し、民間サービス・プロバイダーを各地のNAP(Network Access Point)の管理主体とする」という移行計画を発表し、各地のNAP(San Francisco Pacific Telesis、CHICAGO Ameritech、WASHINGTON MFS、PENNSAUKEN N.J. Sprint)、データの流れを管理する伝送経路調停機関(Routing Arbiter Authority)、超高速バックボーン・ネットワーク・サービス(vBNS)事業者より構成される NSFNET 以降のアーキテクチャが示された。ここでNSFより資金を得て運営されるのは、スーパーコンピューティングセンタを接続する高速バックボーンであるvBNSであり、それ以外のインターネットは民間主導のシステムへ移行した。
図IV−8に、以上にまとめたインターネット普及のプロセスを整理する。
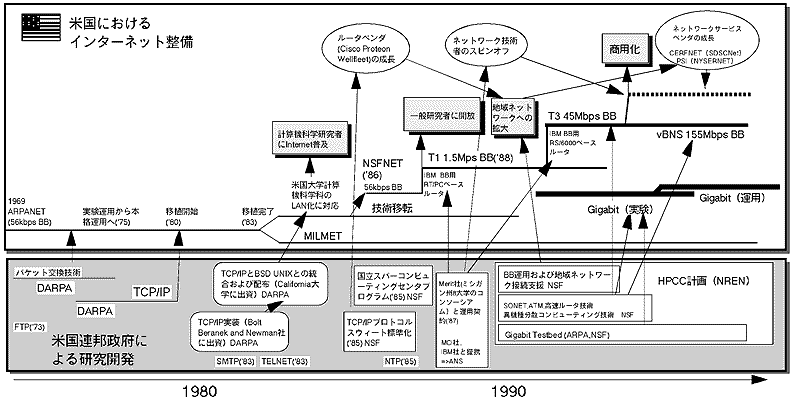
ここまででその詳細を見てきたインターネット普及プロセスの中で、米国政府が果たした役割について再度検討してみる。
・情報基盤のための先進的情報技術の研究開発支援
「研究開発」と「標準化・プラットフォーム化」
すでに述べたように、分散情報処理を指向した開放型相互接続システムとしてARPANETの研究開発の企画を提案したのはDARPAであり、その後、TCP/IP関連の基盤的な研究開発、試験運用のスポンサーとなったのもDARPAである。DARPAはインターネットの初期においてその「研究開発」と「標準化・プラットフォーム化」における主要な支援組織であった。
・情報基盤整備の推進と新たな技術展開
「市場化・情報基盤整備」と「研究開発」
一方、インターネットにおいて「市場化・情報基盤整備」の面で主要な役割を担ったのは、NSFNETの構築を進めたNSFであった。さらに、1992年に開始されたHPCCIにおいては、インターネットに関連する研究がより組織的かつ省庁横断的に実施されるようになる。すなわち、NRENプログラムの中で、異機種接続型分散情報処理、次世代の高速通信ネットワークであるギガビットテストベッドの研究が連邦政府によって実施された。この時点で、インターネットという情報基盤は、高性能コンピュータ技術という新たな技術要素と意識的に融合されることにより、より革新的なネットワークコンピューティングに向けた研究開発のためのプラットフォームとして位置づけられるようになる。
・人材育成と知的資産の集積
このように連邦政府は、インターネットの普及においてその基礎的技術の研究開発を行う大学や企業を支援してきた。こうした大学や企業が行う研究開発プロジェクトを通じて、当該分野の研究者/技術者の育成やソフトウェアの開発が行われた。ここで育成された研究者/技術者の多くは、その後スピンアウトし、インターネットビジネスを起業する。ソフトウェアは、前述したTCP/IPプロトコルとUNIXの統合の例に見られるように、フリーソフトウェアとして一般ユーザに提供され、インターネットの普及と研究者の研究環境整備の両方に貢献した。特に近年 NSF が資金援助するSupercomputing Centerの一つであるNCSAの技術者が開発したWorld Wide Webのブラウザである「Mosaic」は最も広く配布されたソフトウェアの一つであり、インターネットユーザが急増する大きな要因を作った。このように、人材育成とフリーソフトウェアという知的資産の集積が進んだことも、連邦政府が支援する研究開発プログラムの重要な効果になっている。
・インターネット関連産業の育成
連邦政府の資金援助によって実施された研究開発やインターネットの運営事業を通じて、インターネットをささえる産業基盤が醸成されていったことも重要である。
IBMは、NSFバックボーンのグレードアップに対応して自社のルーティング技術を提供したが、結果的に政府の資金援助により、ルーティング技術の高度化に成功した。T1(1.5Mbps)のバックボーンノードはトークンリングにより相互接続された多重IBM RT/PCプロセッサにより対応しているが、T3(45Mbps)バックボーンについては、RS/6000ベースのルータ技術を開発・運用している。バックボーン以外にネットワーク相互接続に用いられるルータについても、連邦政府より資金を得て研究・製品開発を行ったCISCO、Wellfleet等の米国企業が、現在もそのままルータの世界市場で優位の状況を維持している(図IV−9)。
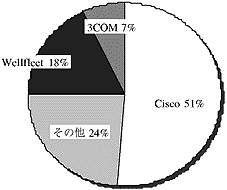
ネットワーク事業者についても同様であり、NSFより資金援助を得てインターネットへの接続業務を行っていた民間ネットワーク事業者が、前述したように今日のインターネットとユーザを結び付けるインターネット・サービス・プロバイダーあるいはインターネット・サポート・プロバイダーに成長してきている。
(2)Gigabit Testbed
HPCCIにおいてNREN構築と同じ研究コンポーネントに位置づけられるGigabit Testbedにおいても、ほぼインターネットの場合と同じような連邦政府の役割を見ることができる。1986年後半にNSFのGordon BellはBellcoreを訪問し、150Mbpsの伝送スピードを可能とする CMOSベースの高速パケットスイッチング技術について説明を受け、その数カ月後、NSF内でワークショップを開催して、将来の高速コンピュータネットワークの構想について議論を行なった。この結果を踏まえて1987年中ごろにGigabit Testbedプロジェクトの提案がNSFに提出された。1988年に、通信業界では ATM の標準化作業を進めている。1989年にGigabit Testbedプロジェクトが、NSFとDARPAにより開始され、ATM、HiPPi(スーパーコンピュータの分野で利用されているスイッチング技術)、PTM(IBMが提唱している高速スイッチングのプロプリエタリ標準)等を数年をかけて評価した後に、ATMをGigabit Testbedのスイッチング技術として採用した。1990年にはATMの最初の製品が市場に投入され、これを利用した幾つかの実用プロジェクトが推進された。さらに、DARPAはATMの「標準化」の活動に対して支援を行ない、その標準化が完了した後は、本格的に高速コンピュータネットワーキングの機器・サービスの初期の「市場化」の立ち上げに、連邦機関の主要な活動はシフトしてきた。ATMやSONETサービスの政府調達がそれである。