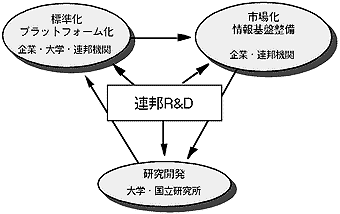
米国の連邦機関は大学と民間に対してほぼ同程度に研究開発の資金支援を行なっている点は、日本が殆ど大学を対象としていることと比較して大きな違いになっている。このような資金的背景もあって、連邦機関の研究開発プログラムは、大学と企業間の研究開発の連携が良好に行なわれることが多い。例えば、NSF が資金援助するSupercomputing Centerは、科学計算に高性能コンピュータを利用するユーザとしての大学と高性能コンピュータのベンダ間のコミュニケーションを円滑化する「場」を提供するものとして評価されている。
すでに指摘したように、米国における研究者や技術者の流動性の高さは、情報技術の開発プロセスにおける各段階がうまく結び付く環境を作り出している大きな要因であるが、各段階と関係を有している連邦政府による研究開発プログラムの存在もまた、研究開発、標準化・プラットフォーム化、市場化・情報基盤整備という各段階の活動がうまく結び付くような仕組みを提供しているものと考えられる(図IV−10)。
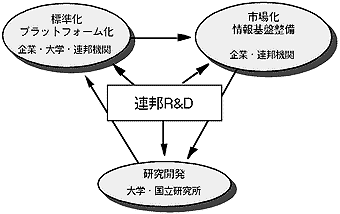
図IV−11には、こうした連邦レベルの研究開発と民間ベースの研究開発や製品のプラットフォーム化、市場化がうまく結び付いた成功例を整理している。
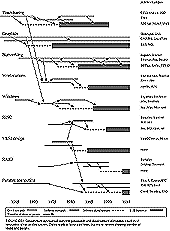
図IV−4に示すスパイラルな情報技術の開発モデルについて言える重要な点は、スパイラルモデルにおいて複数のサイクルが継続的に支援されるような研究開発プログラムの長期的ビジョンが不可欠である、ということである。我が国では、特定の技術分野について実施される研究開発支援は、最長でも10年程度であり、そうした研究開発プログラムで得られた成果が、その後の研究開発にうまく結び付かない例が多かった。
一方、米国における連邦研究開発プログラムを見る限り、ある技術分野の研究開発は、支援レベルの波は存在するにしてもこれまで継続的かつ戦略的に展開されてきているのではないか、と見ることができる。図IV−12は、過去数十年間における連邦研究開発プログラムの推移を整理してみたものである(ネットワーク部分の詳細は図IV−8を参照のこと)。
1980年代からの米国の情報技術開発の流れを見ると、「高性能計算機」、「応用ソフトウェア技術」、「広域コンピュータネットワーク」の3つがその柱となっている。高性能計算機の研究開発は、DARPAが中心となって超高速・超並列計算機のためのハードソフト技術を開発してきている。応用ソフトウェア技術としては、主に軍事利用を目的としたAI技術、大学に設置されたNSFのスーパーコンピューティングセンターなどが中心となって推進する数値計算を中心とした大規模計算アプリケーションの2つが主な研究テーマとなってきた。インターネットからNRENに到る経緯は、すでに前項で詳細に述べた通りである。
こうした個別の研究分野は、それぞれ幾つかのスパイラルによって成熟化し、新たな研究分野を開拓してきたと見ることができる。連邦政府は、すでに述べたようにそれぞれ特定の分野に対して継続的な支援を行ない、これらのスパイラルを駆動する上で重要な役割を担ってきたばかりではなく、個別の技術分野を統合していくことによってより戦略的な研究開発プログラムを企画するためのベースを作ってきた。
1989年にOSTPが構想したHPCCIは、「高性能コンピュータ」、「Grand Challenge(大規模計算問題)」、「情報ネットワーク」を個別に研究するのではなく、それらを融合した「情報ネットワーク上に分散した高性能コンピュータによるグランドチャレンジ問題の解決」という既存の研究分野横断的なコンセプトを打ち出した戦略性において注目される。さらにこの統合は、「情報基盤」をより意識し、前述した「National Challenge」の研究コンポーネントが追加され、ネットワーク上における様々なアプリケーションの開発が推進され、基礎研究と応用研究、あるいは長期的研究と短期的研究のバランスがとられることになる。すでにインターネットにおいて見たように、連邦研究開発プログラムにおいて実用化された技術はいずれ商用化され、いわゆる民間主導による情報スーパーハイウェイの具体化に結びつけようとしている。重要な点は、こうしたより多岐の研究分野を統合するような研究開発プログラムは、それまで個別の連邦機関が実施してきた研究開発プログラムを連邦政府横断的に調整することによって実現されていることである。
以下、こうした動きを情報政策的な観点から整理しておく。すでに指摘したようにHPCCIの構想化には大統領の諮問機関であるOSTPが大きな役割を担っている。OSTPは1976年国家科学技術政策、組織、プライオリティ法(PL94-282)によってFord政権下で組織された大統領府の諮問機関である。OSTPは、1982年に出されたLax Reportを受け、1983年に、FCCSET下にパネルを設置し、情報技術のR&D政策に関する検討を行なった。1985年にそのパネルのレポートが提出され、High Performance Computingの領域に国家財政による研究開発が必要であると報告している。その翌年 Goreらを含む上院科学技術委員会はSuper Computing Network Study Actを提出し、NSFが超高速計算機ネットワーク研究の中心母体となることが決定された。NRENというキーワードはこの法案から使われ始めた。OSTPが出した1987年のレポートを受けて翌年GoreらはHPCCIの原案となるHPCC Actを起草しているが、様々な議論を経て結局1991年に成立した。しかし、ギガビットレベルの通信、マルチメディア情報技術の推進などはもうすでにHPCCIを企画する段階で盛り込み済みであったにもかかわらず、1991年にNTTが公表した2015年構想がきっかけとなり、情報スーパーハイウェイとして国民的情報インフラの構築が情報戦略計画の前面に出した計画に模様変えされた。1993年のNII法案では、HPCCIの全体方針をハイエンドユーザむけの基礎研究開発プロジェクトから、NII構想を実現するための運用技術開発、パイロットプロジェクトの推進母体となるように修正、さらに、具体的なアプリケーション技術の開発をめざす「National Challenge」を対象としたIITAコンポーネントを大きな予算枠をつけて新設した。
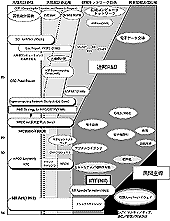
情報技術分野における連邦研究開発プログラムには複数の連邦機関が関係している。以下、HPCCIにおける高性能コンピュータや高速通信ネットワークを例に各連邦機関が実施する研究開発プログラムの概要を述べる。
HPCCIに参加している複数の連邦機関は、高性能コンピュータや高速通信ネットワークの開発サイクルでみると、概ね、図IV−13のような役割分担になっている。このようにHPCCI全体で見れば、高性能コンピュータや高速通信ネットワークの開発サイクル全体がカバーされているものの、個々の連邦機関は、各機関のミッションに適合した段階のみを担当することになる。
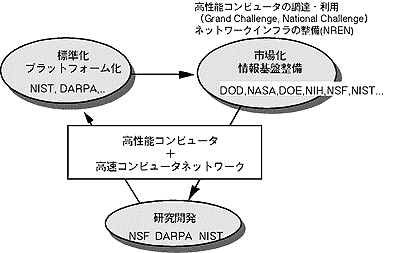
高性能コンピュータや高速通信ネットワークの研究開発を実施しているのは、NSF、DARPA(殆ど以上2つでコンピュータ科学の研究開発はカバーしている)、NIST等である。重要なことは、これらの連邦機関はHPCCI共通の研究開発プログラムを動かしているのではなく、各連邦機関が独自のミッションあるいは戦略に従って企画/実施している研究開発プログラムを、HPCCIに運用している、ということである。
高性能な軍事技術を実用化する必要があったDARPAは、従来より注目すべき技術分野の探索と絞り込みを行ない、その上で期待される成果を明確にし、当該分野に関する研究開発を重点的に進める傾向がある。そのため、HPCCIにおいてもDARPAは、高性能コンピュータや高速通信ネットワークに関する技術目標やマイルストーンについてDARPA自身がプログラムを立案し、このプログラムに沿った公募を行なう。DARPAのProgram Managerはその研究プログラムの全体を把握しており、提案審査プロセスにおいて専門家によるPeer Reviewを行なわない。一方、NSFは基礎研究を中心とし、DARPAのように技術目標等を設定せずに、自由にアイディアやアーキテクチャの提案を求めることが多い。したがって、プログラムに応じて予め公募要領を公表する場合と公表しない場合の両方がある。NSFは、提案の採否は実質的にNSF の Program Officerが判断するものの、提案の審査では外部審査員によるPeer Reviewを採用している。NISTは、今般の産業競争力強化に対する研究開発ニーズに応えるために、産業技術の研究開発プログラムや産業基盤として不可欠な各種標準化活動を推進するプログラムを強化し始めている。HPCCIとは異るが、近年NISTは市場化の可能性が高い競争前段階技術の研究開発を対象とするATPプログラムの予算を増大させている。このATPプログラム、科学技術メリットとビジネス上のメリットの両面からPeer Reviewを実施する。
一方、DOE、NIH、NASAといった連邦機関は当該機関が有するミッションにおいて高性能コンピュータを利用するユーザという位置づけになる。むろん、高性能コンピュータ上で動作するソフトウェアの開発は各機関が行なう。高速通信ネットワークによるネットワークインフラを整備するのはNSFが中心になって推進している。
このように、HPCCIでは高性能コンピュータや高速通信ネットワークの開発サイクル全体をカバーするために、連邦機関間の役割の調整と連携が図られている。従来こうした連邦機関間の調整は行なわれず、各機関が行なう研究開発が重複する場合が多く見られたが、HPCCIではそのようなことがないように、これらの連邦機関間の調整を横断的に行なうべく、図IV−14に示すような体制が組織されている。ここに、各連邦機関は、HPCCIT Subcommitteeの下にあるWorking GroupやTask Groupのメンバになっている。
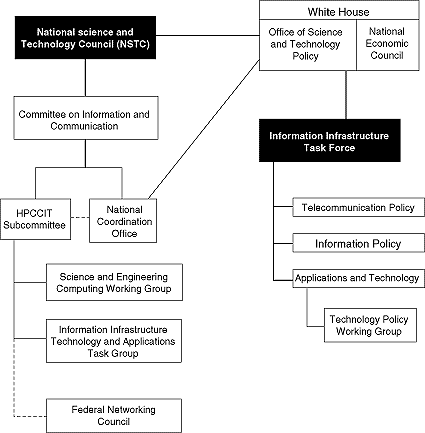
本調査レポートにおいて述べられた内容は以下のように要約することができる。
(1)情報技術分野は、独創的なアイディアやアーキテクチャによって技術の良し悪しが評価されることが多いソフト的技術の側面が強い一方、当該技術要素の上位技術として新たな機能の実現を促進するようなプラットフォーム技術が重層化されることによって技術形成が進む、という特徴を有している。
(2)その結果、情報技術の開発では、「研究開発」、「標準化・プラットフォーム化」、「市場化・情報基盤整備」という各フェーズが循環的に繰り返されるスパイラル的な進化モデルが重要になっている。
(3)米国連邦政府は、こうしたスパイラルモデルを円滑に駆動する上で重要な役割を担ってきた。各連邦機関は、独自の研究開発プログラムにおいて長期的かつ継続的な視点から、民間の活動を補完する特定のプレーヤ(「研究開発」の推進者、「標準化・プラットフォーム化」の推進者、「市場化・情報基盤整備」の推進者言い替えれば先進的ユーザ)としての役割を果たしてきた。結果的に、連邦R&D全体という観点で言えば、循環的なスパイラルモデルの全フェーズに対して一定の役割を果たしている。
(4)近年では、こうした各連邦機関の研究開発プログラムを省庁横断的に調整することによって、多くの研究分野が統合されたより大規模な研究開発プログラムが推進され、これが新たな技術融合による研究開発や情報基盤整備を促進し続けている。
(5)さらに、連邦機関の研究公募プログラムは、「革新的なアイディアやアーキテクチャの発見・発掘」、「アイディアやアーキテクチャのフィージビリティの確認」、「アイディアやアーキテクチャの技術への転換」といった幾つかの課題に対して、それぞれ有効な評価システムを提供するとともに、全体として独創的なアイディアやアーキテクチャの提案を喚起するような公平かつ透明な競争システムの維持に貢献している。