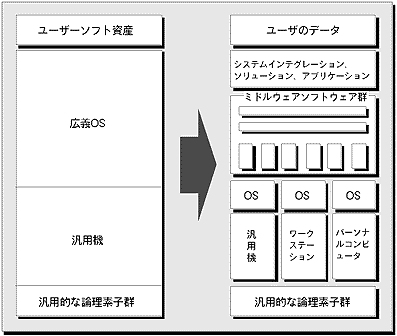
我が国では、先進技術を基盤とする新たな創造的技術立国としての再活性化が期待されて久しいなか、必ずしも十分な変革が実現されていない、との評価が一般化している。特に、情報分野における技術革新が顕著となり、先進的な情報基盤の整備がグローバルに急がれているなかで、我が国の情報産業の低迷が大きな懸念要因として注目され始めている。
ソフトウェア化が進む情報技術分野は、それ自体が新たなアイディアあるいはアーキテクチャといった個人の有する独創性を具現化するかたちで生み出されるという性格が強い。このことは、情報技術分野における低迷が、創造的技術立国を目指す日本において、実はその創造性を創出するための十分な環境が整えられていないのではないか、という深刻な問題を抱えていることを示唆している。
一方、先端的ソフトウェアを含めた情報技術全般の研究開発の動向を米国について見てみると、ここ数十年の間に創出された成果は我が国のそれと比較して極めて充実したものであり、しかもこうした日米格差がここしばらくは拡大してゆくのではないか、というのが一般的な見方である。こうした日米格差が生じる背景には、単に研究者の資質といった要因ではなく、情報技術に関わる研究開発から実用化に到るプロセスにおいて、日米間で基本的な構造の相違があるのではないか、という点が懸念されている。
本調査では、特に米国の連邦政府が行なってきた研究開発プログラムに焦点をあて、上述した日米格差の問題について検討することを目的としている。
本調査では、情報技術分野における米国連邦政府の研究開発プログラムの有用性を検討するために、「情報技術とその開発プロセスの特徴及び連邦研究開発プログラムの役割に関する検討」を行なう。
情報技術およびその開発プロセスは、他の研究領域と比較して幾つかの注目すべき特徴を有しており、そのことを理解することは当該分野における政府研究開発プログラムのあり方を議論する上で重要なことと思われる。本調査では、こうした情報技術およびその開発プロセスに関する特徴について検討した上で、そうした特徴を踏まえると、政府が実施する研究開発プログラムにどのような役割が求められるか、という点を検討する。具体的には、情報技術分野における研究開発モデルとして「研究開発」、「標準化・プラットフォーム化」、「市場化・情報基盤整備」というプロセスを循環的に経るなかで技術要素が成熟化する、というスパイラルモデルを仮定した時に、米国の連邦機関がこのスパイラルを円滑に駆動する上で有効な役割を果たしてきたのではないか、というのが主要な論点となる。また、このスパイラルモデルの視点から、過去数十年間における米国連邦機関の研究開発プログラムの経緯について議論するとともに、米国連邦機関が行なう研究開発プログラムの仕組みについても、HPCC計画を例として検討する。
本節では、研究開発における政府の役割について検討するにあたり注目しなければならない「情報技術」自体が持つ特徴について検討する。
情報技術は、その技術要素に付与される開発者の独創性に依存する割合が他の分野と比較して大きな分野ということが言える。一般に多くの技術分野では、当該分野を構成する技術要素が多かれ少なかれ自然科学的な原理によって支配されることは避けられない。ところが、情報技術の分野は基本的なハードウェア技術の分野においてはこうした自然科学的な原理によって支配される割合が相対的に大きいものの、より上位のソフトウェア領域の技術要素では、当該技術要素が前提とするアイディアやアーキテクチャが技術の良し悪しを支配する主要要因として重要になってくる。言い替えれば、技術のソフト化が進んでいると言える。
以上のことから、より成熟化・ソフト化が進んだ情報技術分野においては、技術要素の良し悪しを支配するアイディアやアーキテクチャを独創する活動が、研究開発のなかでより重視されなければならない、ということを指摘することができる。具体的には以下のようなことが言える。
情報技術は、その成熟化・ソフト化が進むにつれて、当該技術を構成する技術要素が重層化してきているという見方ができる。すなわち、あるアイディアやアーキテクチャをベースとする技術要素の研究開発や製品化は、それ以前に開発された技術要素を前提とし、その上位技術として構成されることが一般化してきているということである。例えば、一つのコンピュータを構成する技術構成を大まかに見ても、図IV−1に示すように汎用機を中心とした比較的簡単な階層から、論理的にはより複雑な階層構造を持つ技術構成へと変化してきている。
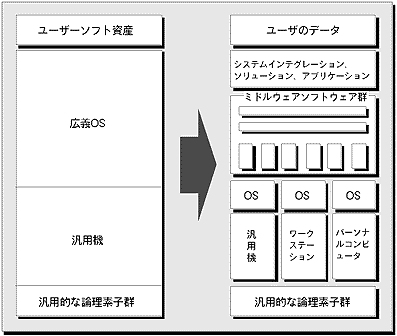
このような技術要素の重層化は、複雑化する情報システムを新たな技術要素によって効率的に高度化し、市場化する上で技術開発の自然なスタイルを提供している。ある独立した技術要素を組み合わせるような研究開発が効率的であること、情報分野における技術要素は常に完結した情報システムの一部として機能することが求められるために、他の技術要素との関係を仕様化することが重要であること、といった幾つかの要因によって、技術要素の重層化は情報システムの研究開発において自然なアプローチであったと言える。近年ではネットワーク化、デジタル化が進むことによって、情報システムを構成する情報技術は一層複雑化してきている。この場合にも、個々の技術要素は他の技術要素と特定のインタフェースを形成しながら組み合わされ、全体としては技術の重層化が進んでいるという見方ができる。図IV−2は、複雑化する情報技術の体系を分類しようとする幾つかのモデルを参考にして、重層化する情報システムのインタフェースモデルを作成したものである。ここで(I1)から(I9)は情報システムを構成するクリティカル・インタフェースと考えられているもので、特にこのインタフェース部分を中心として技術の重層化が進んでいるものと考えられる。
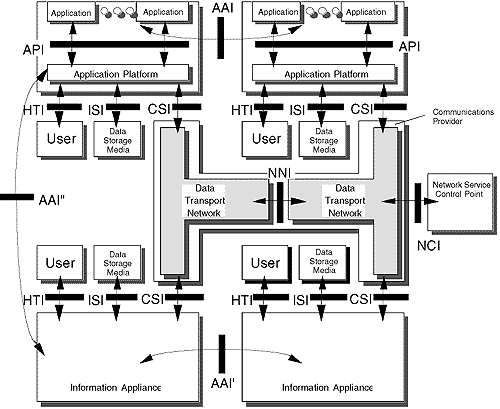
このように技術要素を重層的に構成するアプローチでは、特定の技術要素の「プラットフォーム化」を進める意味合いが大きい。ここにプラットフォーム化された技術(「プラットフォーム技術」と呼ぶこともある)とは、「当該技術要素の上位技術としてより高度な機能を提供する技術要素の創出を促進するような技術要素」を指し、情報技術を構成する上で重要な役割を担うものと考えられるものである。
有用なプラットフォーム技術は、それ自体がパッケージソフトウェアとかソフトウェア環境、ネットワークプロトコルといった製品として市場化され、市場投入された製品自体もまた新たなプラットフォームと呼べるものになる。こうした製品レベルのプラットフォームは、いわゆる現在の情報産業市場における主要な投資対象になっている(注1)。
一方、製品レベルのプラットフォームは、より高度な機能の実現を目指す研究開発の新たな投資の対象にもなる、というのも重要な点である。例えば、インターネットの技術は、情報ネットワーク上で多様な機能を実現するために行なわれた多くの研究開発とその成果としての技術要素にとっては、なくてはならない「プラットフォーム技術」であったことは明らかである。インターネット技術の上に World Wide Web という新たな情報アクセス技術のプラットフォームが提供されたように、「プラットフォーム技術」の上には新たな「プラットフォーム技術」が開発され、より上位の技術要素の研究開発を誘う。技術要素の重層化は、このようなプロセスを経て進んでいるものと考えられるのである。
| (注1) | ソフトウェアについて言えば、欧米ではプラットフォーム化されたパッケージソフトウェアの割合が1992年時点でソフトウェア全体の生産量の7割以上に達している。一方、我が国におけるその割合は3割程度である。これは我が国では個別ユーザが特注するソフトウェアの割合が高く、プラットフォーム化されたパッケージを組み合わせてシステムを構築する市場構造が、欧米ほどはっきりとしていないためだと言われている。 |
前節で指摘した情報技術がもつ幾つかの特徴によって、それらの情報技術を研究開発するプロセスについても幾つかの重要な特徴を指摘することができる。
第一に、すでに指摘した「技術要素の独創指向性」によって、プラットフォーム技術となり得るような有用な技術要素の研究開発プロセスのなかでは、他の研究分野にも増して、多様なアイディアやアーキテクチャの試行錯誤がある程度許容されなければならない、ということが言えよう。米国のNational Research Council/ Computer Science and Telecommunications Boardが公表したレポート(注2)(以下、CSTBレポート)によれば、アイディアやアーキテクチャが10年から15年のサイクルを経て実用化される事例を調べた結果として、結局、"It is hard to predict which new ideas and approaches will succeed"ということを指摘している。重要なプラットフォーム技術の基礎となったアイディアやアーキテクチャを、提案当初から有望であると予想することは極めて困難なことであった、というのである。もし、それが事実であるならば、一見無駄とも思えるような試行錯誤を行なうことも、より最適な技術を育てるためにはやむを得ないということが言えるのである。
| (注2) | Computer Science and Telecommunications Board, National Research Council; "Evolving the High Performance Computing and Communications Intiative to Support the Nation's Information Infrastructure, National Academy Press, Washington, D.C. 1995。本文書の要約と注文情報は、インターネットのhttp://www.nap.edu/bap/online/hpcc/index.html 上で入手することが可能である。 |
第二に、独創的なアイディアやアーキテクチャを創出する活動にインセンティブが与えられるような「オープンかつコンペティティブな研究開発」の環境が、活発な情報技術の研究開発プロセスを支えるインフラストラクチャとして不可欠である、という点である。多様なアイディアやアーキテクチャの提案を行なうこと自体に対してインセンティブを与える一方、適切な提案の評価システムのなかで研究資金の配分を行なうプロセスを通じて、有望なアプローチを「選りすぐる」仕組みが用意されなければならないだろう。
第三に、技術要素の重層化が進み、いわゆる「プラットフォーム技術」が情報技術において果たす役割が大きくなることで、単に特定の技術要素を「研究開発」することと、当該技術要素の「標準化」あるいは「プラットフォーム化」、そうしたプラットフォームを用いた製品の「市場化」あるいは「情報基盤構築」ということが不可分の関係を作り出している、という点を指摘することができる。さらに言えば、ここに挙げた各プロセスを循環的に重ねるスパイラルな開発プロセスが、情報技術の成熟化において重要な役割を果たしていると考えられるのである(図IV−3)。以下、本節ではこのことについてさらに詳しく検討する。
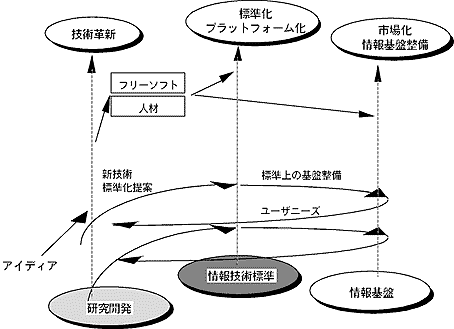
すでに指摘したように、有効な「プラットフォーム技術」は当該プラットフォームに基づく新たな製品として市場化され、そうした製品は新たな情報基盤の一つとして集積されるようになる。近年では、「情報基盤」の整備を進めようとする動きが各国で活発化しているけれども、こうした動きも一方で情報技術のプラットフォーム化を促進する要因となっていると言える。情報基盤の整備は、オープンな情報ネットワーク上で相互運用が可能な様々な製品プラットフォームを機能統合することで実現される傾向が一般化しているからである。
逆に、情報基盤を整備していくという観点で考えるならば、たとえ技術的には優れていても、他の技術要素とうまく統合され、組み合わせることができるようなプラットフォーム的な技術要素でないと、その技術要素が普及することは難しくなってきている。こうしたことから、あるアイディアやアーキテクチャに基づいて特定機能を実現している技術要素が研究開発されると、多くの場合その技術要素をプラットフォーム化しようとすることが情報技術分野における研究開発の常識的な戦略となっている。
具体的には、当該技術要素を他の技術要素と組み合わせやすいようにパッケージ化し、その組み合わせの際に必要なインタフェースを標準化することで、当該技術要素に基づく製品が市場において一定のシェアを得られるようにするのである。情報技術の標準規格を統一するにあたって、しばしば企業あるいは企業連合間の競争が行なわれるのも、有効なプラットフォームを市場化するための技術戦略的な企業行動の一つである。
ある製品が市場に投入された後に、さらに新たなユーザニーズは喚起される。一般に、情報技術の分野ではこのユーザニーズをうまく見極めることが最も重要であることは常識となっている。既存のプラットフォームに不足している機能や性能が明らかになれば、これは新たな研究開発のシーズとなる。言い方を変えれば、より高度な機能を必要とする先進ユーザが存在することは、情報技術の開発プロセスを駆動する重要な促進要因と言える。
さらに、あるプラットフォームをベースとした「情報基盤」が整備されることによって新たな研究開発が促進される場合も考えられる。この良い例が、インターネットという情報基盤が整備されたことで、TCP/IPに準拠したネットワーク技術が標準的なプラットフォームとして定着する一方、インターネットを利用するユーザニーズが安定して見込めるために、このプラットフォーム技術をベースとした新たなアイディアやアーキテクチャの提案が触発されたことである。例えば、インターネット上でWorld Wide Webや探索エージェントといった新たな情報アクセス技術の研究開発が行なわれ、これらの技術が、さらにプラットフォーム化し「Electronic Commerce」や「遠隔医療」といった研究分野を活性化させている。
このインターネットの場合を見る限り、「情報基盤」の存在は様々な形で新たな研究開発のシーズを提供している。インターネットが整備されることによって、コンピュータネットワークを利用する様々な「コンセプト」が意識され、新たなアイディアやアーキテクチャの提案に結びついた例もある。IBMやOracleが提案しているプラットフォームは、ユーザが携帯できるごく簡単な機能しか有していない端末で、むしろその端末からネットワーク上に分散している様々な資源を利用するようなプラットフォームである。これは、コンピュータネットワークが広く普及していることを前提としない限り構想することができないアイディアであり、アーキテクチャであると言える。
以上のように、ある技術要素の「研究開発」、当該技術要素の「標準化・プラットフォーム化」、「市場化・情報基盤整備」といった開発プロセスは、相互に緊密な関係をもちつつ、それぞれが情報技術の開発に本質的な役割を果たしている。しかも、これらの開発プロセスは一つの技術要素について1回のみ現れるのではなく、それ以前のプロセスの影響や重層化された技術蓄積の上に、循環的に現れる傾向がある。図IV−3に示したモデルは、情報技術の開発がまさにこうしたスパイラル的な展開に従うことを摸式化したものである(注3)。
| (注3) | 情報技術における開発プロセスにおいて、研究開発、標準化、市場化や情報基盤整備が重要な要素であることは、むしろ欧州の ESPRIT 計画においてより戦略的に考えられていた、と言える。計画創設当初から、欧州統合に向けて情報技術の標準化が重視され、さらに、標準化が市場競争力を獲得する最も重要な要因の一つであることが認識されるようになったからである。 |
ある技術要素は、本モデルに言うようなスパイラルが繰り返されるなかで、次第に技術要素が成熟化し、重層化されていくとみることができる。このスパイラルのなかで、殆どの技術要素が淘汰される一方で、ある技術要素は当初予想できない程に大規模な市場を形成することがある。
技術要素の淘汰は幾つかの理由で起こる。当然、当該技術要素で実現した機能がユーザニーズに適合せず、市場のなかで淘汰される場合が多い。我が国の情報技術市場は長く「ベンダ主導」の時代が続いたと言われているが、情報システムに対する明確な要求仕様をもっている先進ユーザも次第に現れてきている。こうしたユーザニーズに応え得るプラットフォームを開発することが、情報技術分野において市場競争力を確保する上で不可欠になっている。さらに、スパイラル的な展開モデルにおいては一度市場の支持を得ることができたプラットフォームを、さらに新たなニーズに適合すべく洗練化することも重要である。
技術要素の淘汰は、「標準化・プラットフォーム化」のフェーズにおいてもおこる。我が国企業では、そもそも自社技術要素を他の技術と組み合わせて利用できるようなパッケージ化に対して積極的でなかったと言われている。また、うまく技術要素のパッケージ化が行なわれたとしても、他の技術と結合するインタフェースの標準化が不十分であったり、当該標準をオープンにしなかったことで、うまく市場化に結び付かない場合もある。こうした「標準化・プラットフォーム化」において成功している米国の場合、しばしば見られることは技術の標準化が「de facto標準(事実上の標準)」ベースで行なわれることである。
一方、成功する技術要素は、殆ど例外なく当該技術のプラットフォーム化に成功している。一般に、ある技術要素はその上位技術として多様かつ高度な機能を実現するプラットフォームとなり得ることで、情報基盤整備におけるクリティカル技術となり、市場競争力を強化することができる。さらに、他の技術との融合は新たなプラットフォームを創出する契機を与え、一般により多大な市場へのインパクトを与えることが多い。ところが、こうしたプラットフォーム化の成否に関わる要因(市場ニーズ、他技術との融合、情報基盤等の環境要因)は、その見通しが得難く、そこに情報技術開発の困難な点がある。
前節に述べたスパイラルな開発プロセスの考え方に従うと、ある二国間で情報技術を生み出す潜在力に格差があった場合に、その原因はこのスパイラルな開発プロセスがどれだけ円滑に推進されているか、という点に求めることができると考えられる。もしこのことが正しいならば、情報技術分野における日米格差を生み出しているのは、技術を生み出す構造的な問題であって、早急にこのギャップを解消しない限りは、当面日米間の格差を縮小することも難しいのではないか、という見通しが得られる。
例えば、米国における研究者や技術者の流動性の高さは、この開発プロセスを積極的に駆動する促進要因であることは明らかである。あるアイディアやアーキテクチャの有効性が主に大学における研究開発により確認された場合に、研究者がその技術を持ってビジネスをおこし、「市場化」に結び付けるために不可欠な「標準化・プラットフォーム化」を行なって成功した事例は数多い。また、そうしたベンチャー企業が成立しやすいビジネス環境が米国では提供されていることも良く知られている。
以下、本節では米国の連邦政府自らがスパイラル的な開発プロセスを駆動する上でどのような役割を担ってきたかを検討する。
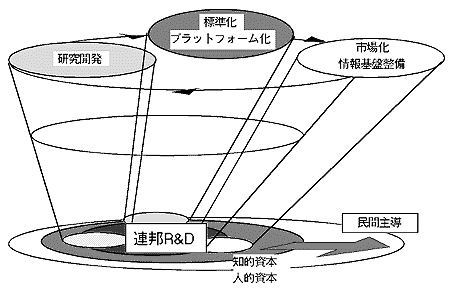
結論から言えば図IV−4に示すように、米国の連邦政府は「研究開発」、「標準化・プラットフォーム化」、「市場化・情報基盤整備」の各フェーズにおいて、当該技術要素が実用技術として成熟するまでに、何等かの形で重要な役割を担っていたのではないか、ということが明らかにしたい要点である。この図では当該技術の成熟度を1サイクルの大きさとして表しており、具体的には、価格性能比、当該技術要素に基づく製品の市場規模やユーザ数、といったものでこの成熟度を測ることができると思われる。
まず、コンピュータの創成期について見ると、連邦政府が本サイクルにおける全ての段階で主要プレーヤであったことは明らかである。ロケットやミサイルに搭載可能な高度な制御装置を実現するために、連邦政府は自らがユーザとなってコンピュータの研究開発に投資を行なった。このように米国では、連邦政府自体が情報技術分野では、最も高度かつ先進的ユーザであり続けている点は、日本には見られない重要な点であると思われる。
一般に米国では、民間企業では取り組むことが困難な巨大技術(宇宙技術や軍事技術)は、連邦政府の研究開発が担うべき重要な役割であり続けている。こうした巨大技術において求められる「通常の民生技術では考えられない」技術仕様が、しばしば民生技術においても大きなインパクトを有する技術のシーズを提供してきたことが言える。インターネット、高性能コンピュータ、知的インタフェース/人工知能、CALS等は、実はいずれも軍事目的で、特にDARPAが支援する先端的な軍事研究開発にその起源を見いだすことができる技術である。
近年では、巨大技術が民生技術に転用されるスピンオフ効果の効率が厳しく議論されるようになり、その重要性は相対的に低下してきていると言われるものの、依然として米国における政府研究予算の半分は国防研究が占めている。さらに、連邦政府が、情報技術の高度かつ先進的ユーザの役割を担うという点では、いわゆる「情報基盤」の整備事業がますます重要になってきている。インターネットを米国全体の研究及び教育分野の共通インフラストラクチャとして整備しようとする NREN(National Research and Education Network)の研究開発プログラムはその典型例である。さらに、先進的な情報技術を利用するアプリケーションとして、NII構想の下で「National Challenge」が推進されている。
以下、図IV−4を踏まえて幾つかの観点から情報技術の研究開発における連邦機関の役割について検討を行なう。
前出したCSTBレポートによれば、情報技術分野において米国の連邦政府の研究開発プログラムの支出は全体で10億ドルのオーダであり、民間が拠出している総額200億ドルから比べれば必ずしも大きな割合を占めている訳ではない。しかし同レポートは、民間企業が投資を躊躇するような基礎的研究あるいは探索的研究分野において、連邦政府の支援は欠かせないとしている。
一般に技術が未成熟でありスパイラルサイズが小さいサイクルでは、すでに何度も指摘しているように、当該技術要素の将来的な成果を予測することは難しく、むしろ技術的なリスクを無視することができない。前出のCSTBレポートは、このような典型例として RISCプロセッサを挙げている。RISCプロセッサは、IBMのJohn Cockeによって発明されたが、十数年の間IBMはこの技術の製品化に踏み切れず、結局、大学におけるRISCプロセッサの研究を連邦機関が支援した後に、始めてSun Microsystemsが製品化に入っている。
このように連邦政府の研究支援プログラムが、技術的な見通しが不透明であった研究開発に投資され、予想もしなかった成果を収めた例として、CSTBレポートは図IV−5をまとめている。
さらに CSTBレポートが研究開発における政府の役割として強調するのは基礎研究である。近年、米国の民間企業は研究開発予算を縮小する方向にあり、残された研究開発予算も短期的な研究開発予算に振り向けることが多い。同レポートはこうした傾向がコンピュータ業界や通信業界(分割後のAT&T、Bellcore)に見られる、としている。
すでに述べたように情報技術分野では、独創的なアイディアやアーキテクチャを創出する活動にインセンティブが与えられるような「オープンかつコンペティティブな研究開発」の環境が、活発な情報技術の研究開発プロセスを支えるインフラストラクチャとして不可欠である。スパイラルな開発モデル自体は、常に研究開発のフェーズにおいて新たなアイディアやアーキテクチャの提案を必要とする。有望なアイディアやアーキテクチャの提案を受け入れ、その技術的なフィージビリティを確認するチャンスを与え、最終的に有望なアプローチを「選りすぐる」仕組みが用意されなければならない。各連邦政府が独自に行なっている研究公募プログラムは、「革新的なアイディアやアーキテクチャの発見・発掘」、「アイディアやアーキテクチャのフィージビリティの確認」、「アイディアやアーキテクチャの技術への転換」といった幾つかの課題に対して、それぞれ有効な評価システムを提供するとともに、全体として独創的なアイディアやアーキテクチャの提案を喚起するような公平かつ透明な競争システムの維持に貢献している。
| Topic | Goal | Unanticipated Results | Today |
|---|---|---|---|
| Timesharing | Let many people use a computer, each as if it were his or her own, sharing the cost. | Because many people kept their work in one computer, they could easily share information. Reduced cost increased the diversity of users and applications. | Even personal computers are timeshared among multiple applications Information sharing is ubiquitous; shared information lives on "servers." |
| Computer networking | Load-sharing among a modest number of major computers | Electronic mail; widespread sharing of software and data; local area networks (the original networks were wide-area); the interconnection of literally millions of computers | Networking has enabled worldwide communication and sharing, access to expertise wherever it exists, and commerce at our fingertips. |
| Workstations | Enough computing to make interactive graphic useful | Displaced most other forms of computing and terminals; led directly to personal computers and multimedia | Millions in use for science, engineering, and finance |
| Computer graphics | Make pictures on a computer. | "what you see is what you get" and hypermedia documents | Almost any image is possible. Realistic moving images made on computers are routinely seen on television and were used effectively in the design of the Boeing 777. |
| "Windows and mouse" user interface technology | Easy access to many applications and documents at once | Dramatic improvements in overall ease of use; the integration of applications (e.g., spreadsheets, word processors, and presentation graphics) | The standard way to use all computers |
| Very large integrated circuit design | New design methods to keep pace with integrated circuit technology | Easy access to "silicon foundries"; a renaissance in computer design | Many more schools training VLSI designers; many more companies using this technology |
| Reduced Instruction Set Computers (RISC) | Computers 2 to 3 times faster | Dramatic progress in the "co-design" of hardware and software, leading to significantly greater performance | Millions in use; penetration continues to increase |
| Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID) | Faster, more reliable disk systems | RAID is more economical as well: massive data repositories ride the price/performance wave of personal computers and workstations. | Entering the mainstream for large-scale data storage; will see widespread commercial use in digital video servers |
| Parallel computing | Significantly faster computing to address complex problems | Parallel deskside server system; unanticipated applications such as transaction processing, financial modeling, database mining, and knowledge discovery in data | Many computer manufacturers include parallel computing as a standing offering. |
| Digital libraries | Universal, multimedia (text, image, audio video) access to all the information in large libraries; an essential need is tools for discovering and locating information | Pending development | Beginning development |
特に情報技術の分野で重要なことは、複数のアプローチが存在した場合に、有効なアプローチが当初から必ずしも明らかではない点である。この場合、すでに指摘したように試行錯誤的な研究開発あるいはオプション分担型(注4) の研究開発を進める必要がある。このような場合、連邦政府の研究プログラムのなかで複数のアプローチの可能性を同時並行的に探索することが有効となる。
| (注4) | ある技術課題を解決するにあたって複数のアプローチ(オプション)が存在する場合に、多重投資による不効率を避けるために、関連する機関が可能なオプションを分担して研究開発を行なう方式を言う。 |
例えば、DARPAが1983年に開始した戦略的コンピュータ開発計画(SCI 計画)のなかでは、高性能コンピュータとして多様なアーキテクチャの提案を求め、それらの研究開発に対して同時に支援を行なった。そのうちの幾つかのモデルについては重要なプラットフォーム技術となり、製品化するに到っている。同様のことは、SCIほど劇的ではなかったものの第五世代コンピュータ計画においても試みられている。
また、後述するようにDARPAは高速コンピュータネットワークのスイッチング技術についても初期の研究開発では、ATM、HiPPi、PTMといった幾つかのアプローチを同時に評価し、最終的にATMを採用するようなことも行なっている。
こうした研究開発のあり方については、研究資金の無駄使いという批判があるが、真に有用な技術を生み出すためには、幾つかのオプションについて研究開発することが不可欠であり、この場合はむしろ連邦機関が中心となってオプション分担型の研究開発体制を組織し、全体として多重投資を回避することが有効となる。