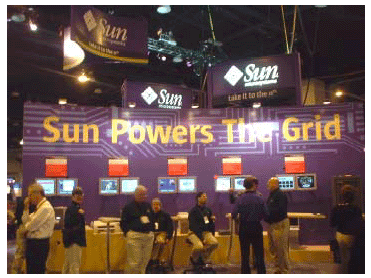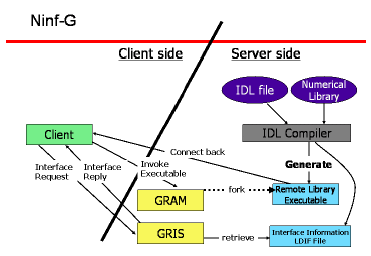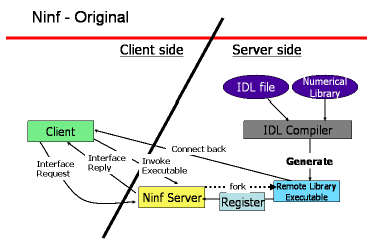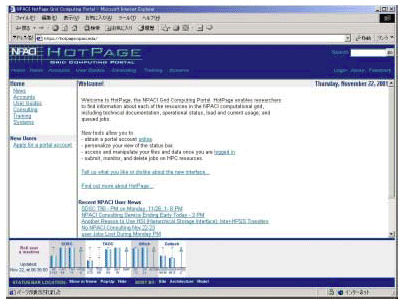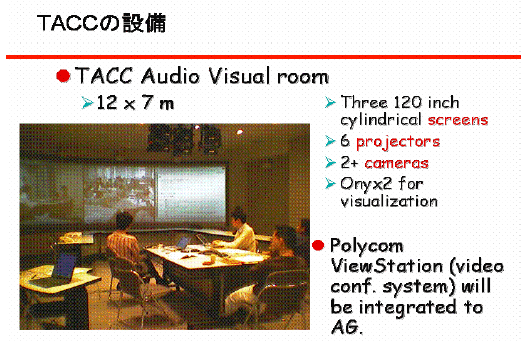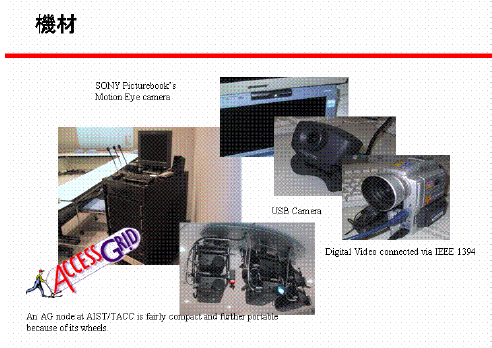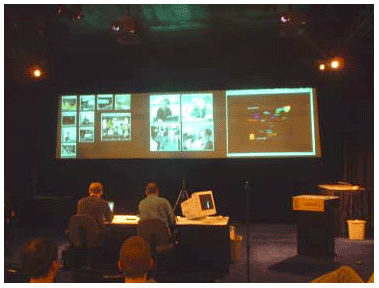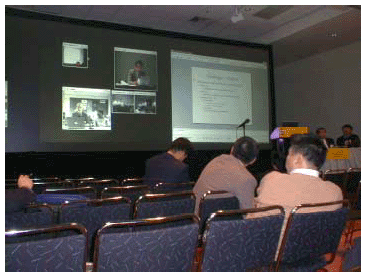戞俁復丂僴僀僄儞僪僐儞僺儏乕僥傿儞僌尋媶奐敪偺摦岦
3.4丂墳梡僔僗僥儉仌墳梡暘栰
3.4.1丂SC2001偵尒傞Grid偺嵟怴摦岦
揷拞丂椙晇丂島巘
1. 偼偠傔偵
丂Grid偲偼丄乽崅懍僱僢僩儚乕僋偱愙懕偝傟偨崅惈擻寁嶼婡丄戝婯柾僨乕僞儀乕僗丄摿庩側憰抲丄恖揑帒尮側偳偺條乆側帒尮傪廮擃偵丄梕堈偵丄埨慡偵丄摑崌揑偵丄偦偟偰岠壥揑偵棙梡偡傞偨傔偺僱僢僩儚乕僋棙梡媄弍乿偱偁傞丅Grid偵傛傝丄扨懱偺僗乕僷乕僐儞僺儏乕僞傗僨乕僞婰壇憰抲偺擻椡傪挻偊傞戝婯柾寁嶼傗戝婯柾僨乕僞張棟偍傛傃崅埑揹巕尠旝嬀偺傛偆側摿庩側憰抲偺墦妘棙梡偲偄偭偨條乆側墳梡媄弍偑奐敪偝傟丄戝婯柾壢妛媄弍寁嶼側偳偺僌儔儞僪僠儍儗儞僕偐傜價僕僱僗墳梡傑偱懡條側墳梡偑壜擻偱偁傞丅Grid偺媄弍揑側杮幙偼Virtual
Organization乮壖憐揑側慻怐偵傛傞塣塩乯偵偁傝丄暋悢偺堎側傞慻怐偵傑偨偑傞條乆側帒尮偺棙梡媄弍偵娭偡傞尋媶偑庡偨傞壽戣偲側傞丅Grid傊偺尋媶奐敪搳帒偼暷崙偱擭娫6壄3愮枩僪儖丄墷廈偱2壄儐乕儘傪墇偊丄崙嵺揑偵尋媶奐敪偑悇恑偝傟偰偄傞丅擔杮偵偍偄偰傕憤崌壢妛媄弍夛媍偵偍偄偰廳梫壽戣偲偟偰Grid偑偲傝偁偘傜傟偰偍傝丄僱僢僩儚乕僋媄弍偺旘桇揑恑曕偵敽偆怴偟偄忣曬媄弍婎斦偲偟偰旕忢偵廳梫側媄弍偱偁傞偲悽奅揑偵擣抦偝傟偰偄傞丅
杮峞偱偼丄2001擭11寧偵暷崙僐儘儔僪廈僨儞僶乕偱奐嵜偝傟偨崅惈擻寁嶼偍傛傃崅惈擻僱僢僩儚乕僋偵娭偡傞崙嵺夛媍偱偁傞Supercomputing Conference(SC
2001)偵偍偗傞島墘丄媄弍榑暥丄婇嬈揥帵偍傛傃尋媶揥帵偺撪梕傪傆傑偊丄Grid偺尰忬偍傛傃嵟怴摦岦偵偮偄偰曬崘偡傞丅杮曬崘偵偍偄偰偼丄(1)Grid偵偍偗傞僜僼僩僂僃傾偺婎斦偲偟偰帠幚忋偺昗弨偵側偭偰偄傞Globus
Toolkit丄(2)儐乕僓偵懳偟偰娙曋側僀儞僞僼僃乕僗傪採嫙偡傞億乕僞儖僔僗僥儉丄(3)崅惈擻僀儞僞乕僱僢僩夛媍僔僗僥儉偱偁傞Access Grid偍傛傃偦傟傪棙梡偟偰SC
2001婜娫拞偵奐嵜偝傟偨僀儀儞僩SC Global丄偺3審偵徟揰傪偁偰偰Grid媄弍偍傛傃尋媶摦岦偵娭偡傞曬崘傪峴偆丅埲壓丄2愡偱偼SC2001偵偍偗傞Grid娭楢偺島墘偍傛傃尋媶敪昞摍丄Grid娭楢偺妶摦傪憤妵偡傞丅3愡偱偼Globus
Toolkit偺奣梫偍傛傃崱屻偺摦岦傪丄4愡偱偼Grid Portal僔僗僥儉偵偮偄偰丄5愡偱偼Access Grid偍傛傃SC Global僀儀儞僩偵娭偟偰愢柧偟丄嵟屻偵傑偲傔傪弎傋傞丅
2. SC2001偵偍偗傞Grid娭楢偺敪昞
丂SC2001偼暷崙僐儘儔僪廈僨儞僶乕偵偁傞僐儘儔僪僐儞儀儞僔儑儞僙儞僞乕偱2001擭11寧12擔偐傜16擔傑偱奐嵜偝傟偨丅SC2001偱偼婎挷島墘丄彽懸島墘丄尨挊島墘丄僠儏乕僩儕傾儖丄Birds
of Feather(BOF)丄婇嬈揥帵丄尋媶揥帵側偳偺條乆側敪昞偑峴傢傟傞偑丄偦偺拞偱傕僉乕儚乕僪偼Grid偲僶僀僆偱偁偭偨丅埲壓偵丄Grid偵娭偡傞敪昞偵偮偄偰傑偲傔傞丅
| 亜 |
彽懸島墘
4審偺彽懸島墘偺偆偪丄埲壓偺2審偑Grid偵娭學偡傞島墘偱偁偭偨丅
| 伾 |
The World Wide Telescope: Mining the Sky
Jim Gray, Microsoft Research
揤暥偵偍偗傞僨僕僞儖壔偝傟偨娤應僨乕僞偼朿戝側検偲側傝丄岞奐偝傟偰偼偄傞偑惗偺僨乕僞傪ftp側偳偱庢傝弌偡傛偆側宍懺偱偁傝丄棙梡幰偵偲偭偰巊偄傗偡偄傕偺偲偼偄偊側偄丅偦偙偱丄揤暥偺妛夛偵偍偗傞Data
Grid乮戝婯柾僨乕僞傪Grid忋偱埖偆僀儞僼儔乯傪峔抸偟丄World Wide Telescope偲偄偆壖憐揑側揤暥戜傪嶌傠偆偲偟偰偄傞偲偄偆撪梕偺島墘偱偁偭偨丅崅僄僱儖僊乕暔棟妛偵偍偗傞Data
Grid偲堎側傞偺偼丄偦偙偵僨乕僞儅僀僯儞僌偺媄弍偑戝偒偔娭梌偡傞偙偲偱偁傞丅 |
| 伾 |
Grid Computing in the Terascale Age
Fran Berman, SDSC and NPACI
San Diego Supercomputer Center偺強挿偱偁傞Dr. Fran Berman偑暷崙丄摿偵NPACI偵偍偗傞Grid尋媶傊偺傾僾儘乕僠偵偮偄偰丄偪傚偆偳僾儘僕僃僋僩偑奐巒偟偨偲偙傠偱偁傞Tera
Grid偍傛傃偙傟偐傜巒傑傞PRAGMA偵娭偡傞島墘傪峴偭偨丅Grid偺掕媊偍傛傃崱傑偱偺楌巎傪怳傝曉傝丄Grid偺梫慺媄弍偼惉弉偟偰偒偰偄傞偙偲丄偦偟偰丄崱屻偼PRAGMA傪偼偠傔偲偡傞崅儗儀儖儈僪儖僂僃傾傗傾僾儕働乕僔儑儞偵庡戣傪抲偄偨尋媶奐敪偑妶敪偵側傞偙偲傪弎傋偨丅PRAGMA偺僐儞僥僋僗僩偱偄偊偽丄ApGrid偺傛偆側傾僕傾抧堟偺Grid僥僗僩儀僢僪偲偺岎棳偑廳梫偱偁傞偙偲偵尵媦偟偰偄偨丅Tera
Grid偼NSF偑53M$偺梊嶼傪偮偗偨戝婯柾僾儘僕僃僋僩偱偁傝丄SDSC, NCSA, CalTech, ANL偺4偮偺尋媶強丒戝妛傪40Gbps偺崅懍僱僢僩儚乕僋偱愙懕偟丄棟榑僺乕僋惈擻13.6TFlops丄庡婰壇崌寁6.8TB丄撪晹僨傿僗僋79TB丄僱僢僩儚乕僋僨傿僗僋576TB偺Grid僀儞僼儔偱偁傞丅庡偵擼偺尋媶傗幚帪娫帇妎壔側偳偺墳梡暘栰偵偍偗傞夋婜揑側尋媶惉壥憂弌傪偼偐偭偰偄傞丅 |
|
| 亜 |
尨挊榑暥
尨挊榑暥偼240審偺搳峞偑偁傝丄60審偑嵦榐偝傟偨丅搳峞榑暥偍傛傃嵦榐榑暥偺偄偢傟傕丄栺20%偼Grid娭楢偺榑暥偱偁偭偨丅Grid娭楢偺僙僢僔儑儞偲偟偰偼丄埲壓偺4偮偺僙僢僔儑儞偑奐偐傟偨丅
| 伾 |
Computational Grid Portals and Networks |
| 伾 |
Computational Grid I/O |
| 伾 |
Computational Grid Applications |
| 伾 |
Computational Grid Environments and Security |
|
| 亜 |
僠儏乕僩儕傾儖
偙偙悢擭Supercomputing Conference偱偼Globus Toolkit偺僠儏乕僩儕傾儖偑峴傢傟偰偄偨偑丄崱擭偼Globus
Toolkit偺僠儏乕僩儕傾儖偼側偔丄Grid偺奣榑揑側僠儏乕僩儕傾儖(The Emerging Grid: Introduction, Tools,
Applications)偲Data Grid偵娭偡傞僠儏乕僩儕傾儖(Data Grids: Drivers, Technologies, Opportunities)偺2審偺傒偱偁偭偨丅 |
| 亜 |
BOF
Grid偵娭偡傞BOF偼埲壓偺4審偱偁偭偨丅
| 伾 |
Global Grid Forum Advanced Programming Research Group BOF |
| 伾 |
Terascale Computing Infrastructure and You |
| 伾 |
Distributed Information Systems Lab (DISL) and ASCI |
| 伾 |
Grid Web Service |
|
| 亜 |
婇嬈揥帵偍傛傃尋媶揥帵
丂SC2001偺婇嬈揥帵偵偍偄偰偼丄Grid偁傞偄偼Globus偺僉乕儚乕僪偑旕忢偵傛偔栚偵偮偄偨丅IBM偼CoG乮Globus Toolkit偺Java
API傪採嫙偡傞僷僢働乕僕乯傪梡偄偨Globus Toolkit偺GUI僨儌傪峴偭偰偄偨丅僨儌偦偺傕偺偼Globus Toolkit偺Java
API傪採嫙偡傞CoG傪棙梡偟偰偄傞偩偗偱媄弍揑側怴婯惈偼側偄偑丄Globus Toolkit偺奺婡擻偵懳偟偰旕忢偵傛偔偱偒偨GUI傪峔抸偟偰偄偨丅Sun
Microsystems幮偼丄Sun偑僼儕乕僜僼僩偲偟偰攝晍偟偰偄傞Sun Grid Engine(SGE)偲Grid傪棈傔偨揥帵傪峴偭偰偄偨丅嬶懱揑偵偼丄Globus
Toolkit偲SGE傪慻傒崌傢偣偨乮僕儑僽偺憲怣偵偼Globus Toolkit傪棙梡偟丄儘乕僇儖側僕儑僽儅僱乕僕儍偲偟偰SGE傪巊偆乯僨儌偲丄AVAKI偲SGE偺憡屳棙梡偵娭偡傞僨儌傪峴偭偰偄偨丅Globus
Toolkit偲SGE偺僨儌偼杮峞偺曬崘幰偱偁傞嶻憤尋偺揷拞偑丄僨儞僶乕偺夛応偐傜Globus Toolkit傪巊偭偰嶻憤尋偺儅僔儞偵僕儑僽傪旘偽偟丄嶻憤尋偺儅僔儞懁偱偼SGE傪巊偭偰僕儑僽偺僗働僕儏乕儕儞僌傪峴偆偲偄偆僨儌傪峴偭偨丅恾1偼Sun
Microsystems幮偺揥帵僽乕僗偺條巕偱偁傞丅
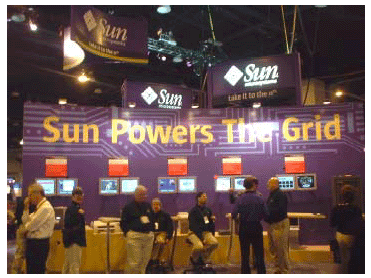
恾1 Sun Microsystems幮偺揥帵僽乕僗
丂Compaq Computer偼僆乕僗僩儔儕傾偺Grid婎斦偵Compaq偺僋儔僗僞偑棙梡偝傟偰偄傞偙偲傪丄僆乕僗僩儔儕傾偲僱僢僩儚乕僋夛媍傪峴偄側偑傜愢柧偟偰偄偨丅Platform
Computing偼Globus Toolkit傪僆僼傿僔儍儖僒億乕僩偡傞偲敪昞偟丄揥帵偵偍偄偰傕Globus Toolkit偵娭偡傞揥帵傪峴偭偰偄偨丅
傑偨丄Grid偵偍偗傞婇嬈偺庢傝慻傒偲偟偰栚傪堷偄偨偺偼丄婇嬈楢崌傪慻傓偲偙傠偑懡偐偭偨偙偲偵偁傞丅偨偲偊偽丄Platform Computing丄AVAKI丄Compaq偺嶰幮偑慻傫偱丄偦傟偧傟Grid儈僪儖僂僃傾偺僒億乕僩(Platform
Computing)丄Grid偵偍偗傞僼傽僀儖僔僗僥儉偺採嫙(AVAKI)丄僴乕僪僂僃傾僒億乕僩(Compaq Computing)偲偄偭偨傛偆偵栶妱暘扴傪偟偰Grid巗応偵弌傛偆偲偟偰偄傞傎偐丄Sun
Microsystems幮偼AVAKI偲嫟摨偱揥帵傪峴偭偰偄偨偟丄Sun Microsystems幮偲IBM偲偺尋媶幰偑崱屻偺Grid儈僪儖僂僃傾偵娭偡傞昗弨壔偵偮偄偰榖傪偟傛偆偲偄偆夛榖傪偟偰偄偨丅
丂尋媶揥帵偵娭偟偰偼丄偙偙悢擭偳偍傝Grid偵娭偟偰旕忢偵悢懡偔妶敪偵揥帵偑峴傢傟偰偄偨丅栚傪堷偄偨偺偼丄暷崙偱53M$偺梊嶼偑偮偄偨TeraGrid偺揥帵乮NPACI/SDSC乯偲傾僕傾懢暯梞抧堟偵偍偗傞Grid僾儘僕僃僋僩偱偁傞Asia
Pacific Grid Partnership for Grid Computing(ApGrid)偺揥帵偱偁傞丅ApGrid偺僽乕僗偱偼丄擔杮偺嶻憤尋丄搶岺戝丄嫗戝偐傜偺揥帵偵壛偊丄僆乕僗僩儔儕傾偺Queensland
University of Technology偲Monash University丄僞僀偺Kasetsart University丄偍傛傃娯崙偺Korea
Institute of Science and Technology Information偺僨儌揥帵偍傛傃丄億僗僞乕揥帵傕峴傢傟偰偄偨丅恾2偵ApGrid偺揥帵僽乕僗偺條巕偱偁傞丅

恾2 ApGrid偺揥帵僽乕僗
|
| 亜 |
SC Global
丂SC Global偼暷崙偺Argonne National Laboratory偱奐敪偝傟偨Access Grid偲屇偽傟傞媄弍乮堦庬偺僱僢僩儚乕僋夛媍僔僗僥儉乯傪巊偭偰悽奅拞偺奺崙丄奺搒巗偲僨儞僶乕偺夛応偲傪愙懕偟丄僨儞僶乕偱偺夛媍偺條巕傪悽奅拞偵曻憲偟偨傝丄悽奅奺抧偺島墘偺條巕傪僨儞僶乕偺夛応偱曻憲偟偨傝丄偁傞偄偼悽奅奺抧偲僨儞僶乕偲傪偮側偄偱僷僱儖摙榑傪峴偆側偳丄偝傑偞傑側僀儀儞僩偑夛媍婜娫拞偵奐嵜偝傟偨丅SC
Global偵娭偟偰偼丄屻傎偳徻偟偔弎傋傞丅 |
丂慡斒揑側報徾偲偟偰偼丄Globus偁傞偄偼Globus Toolkit偑棈傓敪昞丄揥帵偑旕忢偵懡偐偭偨偲偄偆偙偲偑偁傞丅徻嵶偼屻傎偳弎傋傞偑丄Globus
Toolkit偼Grid偵偍偗傞僜僼僩僂僃傾傪峔抸偡傞嵺偺婎斦僣乕儖偲偟偰帠幚忋偺昗弨偵側偭偰偍傝丄崱屻奺抧偱幚嵺偺Grid僥僗僩儀僢僪偺塣塩偑恑傔傜傟傞偲梊憐偝傟傞偑丄憡屳棙梡偺壜擻惈傪崅傔傞堄枴偱傕Globus
Toolkit偑嫟捠偺僜僼僩僂僃傾婎斦偲偟偰棙梡偝傟傞偙偲偼傎傏娫堘偄側偄丅偦偺傛偆側忬嫷偵偍偄偰丄儐乕僓偵懳偟偰傛傝忋埵側僀儞僞僼僃乕僗傪採嫙偡傞崅儗儀儖儈僪儖僂僃傾傗Web僀儞僞僼僃乕僗傪採嫙偡傞Portal僔僗僥儉偺尋媶奐敪偑妶敪壔偡傞偲梊憐偝傟傞丅傑偨丄Grid偺杮幙偱偁傞壖憐揑側慻怐(Virtual
Organization)偺塣塩偵偍偄偰偼幚嵺偵婄傪偁傢偣偰偺儈乕僥傿儞僌偑廳梫偵側傞偲巚傢傟丄Access Grid偺傛偆側僔僗僥儉偼桳梡偱偁傝丄崱屻Grid偺媄弍傪庢傝崬傫偱傛傝崅婡擻丄崅惈擻側僔僗僥儉偺奐敪偑朷傑傟傞丅偦偙偱丄杮峞偱偼堷偒懕偒Globus
Toolkit偺徯夘丄Web僀儞僞僼僃乕僗傪帩偮Grid億乕僞儖僔僗僥儉偍傛傃Accss Grid偲SC Global偵偮偄偰徻偟偔弎傋傞丅
3. Globus Toolkit
3.1 奣梫
丂Globus偼1995擭偵奐巒偝傟偨暷崙偺戝婯柾側Grid僾儘僕僃僋僩偱偁傝丄Argonne National Laboratory偲University
of South California/Information Science Institute偑拞怱偲側偭偰妶摦偟偰偄傞丅Globus Toolkit偼Globus僾儘僕僃僋僩偵傛偭偰嶌傜傟偨僣乕儖僉僢僩偱偁傝丄儐乕僓擣徹丄捠怣丄墦妘帒尮娗棟丒娔帇婡峔側偳偺丄Grid偵偍偄偰昁梫偲側傞偝傑偞傑側梫慺媄弍傪儔僀僽儔儕偍傛傃API偲偄偆宍偱採嫙偡傞嫄戝側僷僢働乕僕偱偁傞丅Globus
Toolkit傪梡偄偰傾僾儕働乕僔儑儞傗儈僪儖僂僃傾傪峔抸偡傞偙偲偑偱偒丄I-WAY傗GUSTO側偳偺僥僗僩儀僢僪偵傛傞幚尡傗丄Globus Toolkit傪巊偭偰Grid忋偱摦嶌壜擻側MPICH-G/G2(Grid
enabled MPI)偺幚憰側偳偑峴傢傟偰偄傞丅Globus Toolkit偼1998擭10寧偵僶乕僕儑儞1.0偑儕儕乕僗偝傟丄2001擭11寧偺帪揰偱偺嵟怴僶乕僕儑儞偼1.1.4偱偁傞丅僶乕僕儑儞2.0偺儀乕僞斉傕2001擭11寧12擔偵儕儕乕僗偝傟丄嬤偄偆偪偵僶乕僕儑儞2.0偺惓幃斉偑儕儕乕僗偝傟傞梊掕偱偁傞丅Globus
Toolkit偼奐敪偝傟偰娫傕側偄僜僼僩僂僃傾偱偁傞偑丄傑偨偨偔娫偵悽奅拞偵峀傑傝丄崱傗Grid僔僗僥儉偺僜僼僩僂僃傾僀儞僼儔僗僩儔僋僠儍傪峔惉偡傞梫慺偺帠幚忋偺昗弨偵側偭偰偄傞丅
3.2 Globus Toolkit偺僒乕價僗
丂Globus Toolkit偑採嫙偡傞僒乕價僗傪埲壓偵帵偡丅
| 亜 |
僙僉儏儕僥傿乮Grid Security Infrastructure, GSI乯
儐乕僓擣徹側偳偺僙僉儏儕僥傿僒乕價僗 |
| 亜 |
忣曬僒乕價僗乮Grid Information Service, GIS乯
Metacomputing Directory Service (MDS)/Grid Resource Information Service
(GRIS)/Grid Index Information Service (GIIS)側偳偺忣曬僒乕價僗 |
| 亜 |
帒尮娗棟乮Resource Management乯
Globus Resource Allocation Manager(GRAM)/Resource Specification Language(RSL)/Dynamically-Updated
Request Online Co-allocator(DUROC) 側偳偺帒尮娗棟偍傛傃帒尮梫媮摍偺僒乕價僗 |
| 亜 |
僨乕僞娗棟乮Data Management乯
Global Access to Storage Systems(GASS)/GSIFTP側偳偺儕儌乕僩僨乕僞傊偺傾僋僙僗僒乕價僗 |
| 亜 |
捠怣乮Communication乯
Nexus傗Globus IO側偳偺捠怣僒乕價僗 |
| 亜 |
屘忈専抦乮Fault Detection乯
Heat Beat Monitor側偳偺僔僗僥儉偺忬懺偍傛傃忈奞専抦僒乕價僗 |
| 亜 |
堏怉惈乮Portability乯
libc丆pthread library側偳崅偄堏怉惈傪採嫙 |
丂Globus Toolkit偑採嫙偡傞偙傟傜偺僒乕價僗偼昁梫偵墳偠偰屄暿偵棙梡偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偰偍傝丄婛懚傾僾儕働乕僔儑儞傊偺僀儞僋儕儊儞僞儖側摫擖偑壜擻偱偁傞丅Globus
Toolkit偼奒憌揑側峔憿傪帩偪丄崅儗儀儖偺Globus僒乕價僗偼儘乕僇儖僒乕價僗偺忋偵峔抸偝傟丄儘乕僇儖僒乕價僗偺庬椶偵埶懚偟側偄嬒堦側僀儞僞僼僃乕僗傪採嫙偟偰偄傞丅偙偙偱偼丆摿偵廳梫偱偁傞3偮偺僒乕價僗(僙僉儏儕僥傿丄帒尮娗棟丄忣曬僒乕價僗)偍傛傃Globus
Toolkit偵偍偗傞墦妘僕儑僽幚峴偺巇慻傒偵偮偄偰徻偟偔愢柧偡傞丅
| 亜 |
僙僉儏儕僥傿
丂儐乕僓擣徹傗埨慡側(secure側)捠怣傪幚尰偡傞偨傔丄Globus Toolkit偼Grid Security Infrastructure
(GSI)傪採嫙偟偰偄傞丅GSI偼岞奐尞偵傛傞埫崋壔丄X.509徹柧彂偍傛傃Secure Socket Layer (SSL)捠怣僾儘僩僐儖偵婎偯偄偰幚憰偝傟丄偙傟偵single
sign-on(僷僗儚乕僪傪1搙偩偗擖椡偡傟偽椙偄)偍傛傃埾擟(delegation)偺奼挘偑側偝傟偰偄傞丅儐乕僓偼帺暘偺徹柧彂傪擣徹嬊偵敪峴偟偰傕傜偆昁梫偑偁傞丅僒乕僶忋偵偼儐乕僓偺Globus
ID(徹柧彂偵婰嵹偝傟偰偄傞)偲儘乕僇儖儐乕僓ID(Unix偺傾僇僂儞僩側偳)偲偺懳墳昞偑偁傝丄偙偺昞偵廬偭偨儘乕僇儖儐乕僓偺尃尷偱僕儑僽偑幚峴偝傟傞丅 |
| 亜 |
帒尮娗棟
丂Globus Resouce Allocation Manager (GRAM)偼寁嶼帒尮(僾儘僙僢僒)娗棟偺偨傔偺僒乕價僗傪採嫙偡傞丅GRAM偼LSF丄NQS丄Condor側偳條乆側(僒僀僩屌桳偺)帒尮娗棟僣乕儖偵懳偡傞嫟捠偺僀儞僞僼僃乕僗傪採嫙偡傞丅GRAM偺傾乕僉僥僋僠儍偵偍偄偰偼gatekeeper偲jobmanager偑庡梫側僐儞億乕僱儞僩偱偁傞丅gatekeeper偼僋儔僀傾儞僩偐傜偺僕儑僽梫媮傪懸偪庴偗傞僒乕僶偱偁傝丄jobmanager偼gatekeeper偵傛偭偰惗惉偝傟丄幚嵺偺帒尮娗棟曽朄偵廬偭偰僕儑僽傪惗惉偡傞僾儘僙僗偱偁傞丅jobmanager偼儘乕僇儖側帒尮娗棟僣乕儖偵墳偠偨宆傪帩偪丄椺偊偽LSF宆偺jobmanager偺応崌偼LSF偺bsub僐儅儞僪傪巊偭偰僕儑僽傪僉儏乕偵搳擖偟丄LSF偺僗働僕儏乕儕儞僌偵墳偠偰儂僗僩忋偱僕儑僽偑幚峴偝傟傞丅傑偨丄偙傟傜偺帒尮梫媮偵娭偡傞忣曬偼RSL
(Resource丂Specification Language)偲屇偽傟傞尵岅傪梡偄偰婰弎偝傟丄奺僐儞億乕僱儞僩娫偱岎姺偝傟傞丅 |
| 亜 |
忣曬僒乕價僗
丂Globus Toolkit偼丂Metacomputing Directory Service (MDS)偲屇偽傟傞LDAP(Light-weight
Directory Access Protocol)傪梡偄偨忣曬僒乕價僗僔僗僥儉傪採嫙偟偰偄傞丏Globus Toolkit偺MDS偼旕廤拞娗棟曽幃(pull儌僨儖)偱偁傝乮僶乕僕儑儞1.1.2傑偱偼廤拞娗棟曽幃丄push儌僨儖偱偁偭偨乯丄忣曬偺栤偄崌傢偣傗忣曬傪奿擺偡傞柤慜嬻娫偺峔抸偺偨傔偵LDAP傪梡偄偰偄傞丅MDS偺庡梫側僐儞億乕僱儞僩偼Grid
Resource Information丂Service (GRIS)偲Grid Index Information Service (GIIS)偱偁傞丅GRIS偼寁嶼僒乕僶忋偱摦嶌偡傞LDAP偺僒乕僶偱偁傝丄GRIS偵栤偄崌傢偣傞偙偲偵傛偭偰偦偺寁嶼帒尮偵娭偡傞忣曬傪妉摼偡傞偙偲偑偱偒傞丅GRIS偑採嫙偡傞忣曬偼僨僼僅儖僩偱偼Globus
Toolkit偺僶乕僕儑儞丄寁嶼婡偺僴乕僪僂僃傾/僜僼僩僂僃傾忣曬偍傛傃gatekeeper/jobmanager偵娭偡傞忣曬偱偁傞偑丄昁梫偵墳偠偰GRIS偑採嫙偡傞忣曬傪捛壛/嶍彍偡傞帠偑偱偒傞丅GRIS偑扨懱偺寁嶼僒乕僶偺忣曬傪埖偆偺偵懳偟丄GIIS偼暋悢偺GRIS偺忣曬傪傑偲傔偰埖偆巇慻傒傪採嫙偟丄偦傟偵傛偭偰乽暋悢偺僒僀僩偵傑偨偑偭偨壖憐揑側慻怐乿偺忣曬傪採嫙偡傞MDS僒乕僶偲偟偰婡擻偡傞丅 |
3.3 Globus Toolkit偵偍偗傞僕儑僽幚峴偺巇慻傒
丂Globus Toolkit傪梡偄偰墦妘帒尮忋偱僕儑僽傪幚峴偡傞応崌丄埲壓偺傛偆側棳傟偵側傞丅
| 匑 |
僋儔僀傾儞僩偐傜儐乕僓僐儅儞僪偁傞偄偼API傪棙梡偟偰gatekeeper偵僕儑僽幚峴偺梫媮傪弌偡丅幚峴偡傋偒僾儘僌儔儉偼RSL偵廬偭偨婰朄偱僋儔僀傾儞僩偑巜掕偡傞丅 |
| 匒 |
gatekeeper偑僋儔僀傾儞僩偐傜偺梫媮傪庴偗庢傞偲丄僋儔僀傾儞僩偲gatekeeper偲偺娫偱憡屳擣徹偑峴側傢傟傞丅 |
| 匓 |
gatekeeper偼揔愗側jobmanager傪惗惉偡傞丅 |
| 匔 |
惗惉偝傟偨jobmanager偼僋儔僀傾儞僩偵傛偭偰巜掕偝傟偨僾儘僌儔儉傪幚峴偡傞僕儑僽僾儘僙僗傪惗惉偡傞丅 |
| 匘 |
僕儑僽幚峴偺惉岟/幐攕/廔椆/寢壥偺捠抦傗僕儑僽偺庢傝徚偟梫媮側偳偺傗傝偲傝偼丄僋儔僀傾儞僩偲jobmanager偺娫偱峴側傢傟傞丅僕儑僽僾儘僙僗偺弌椡摍偼GASS傪夘偟偰僋儔僀傾儞僩懁偺弌椡偵憲傜傟傞丅 |
丂 偙偺傛偆偵丄Globus Toolkit偼僋儔僀傾儞僩/僒乕僶儌僨儖偵婎偯偔扨弮側幚峴儌僨儖傪採嫙偡傞偲摨帪偵丄僕儑僽僾儘僙僗偺惗惉傗忬懺妋擣丄幚峴偺庢傝徚偟偲偄偭偨帒尮娗棟僔僗僥儉屌桳偺婡擻傪jobmanager偵擟偣傞偙偲偵傛傝丄奺僒僀僩偺僗働僕儏乕儕儞僌億儕僔乕偵埶懚偟側偄廮擃側帒尮娗棟婡峔傪幚尰偟偰偄傞丅
3.4 Globus Toolkit傪巊偭偨椺
丂偙偙偱偼幚嵺偵Globus Toolkit傪巊偭偰Grid僜僼僩僂僃傾傪峔抸偡傞椺傪帵偟丄Globus Toolkit偺巊偄曽偍傛傃桳岠惈傪帵偡丅Grid僜僼僩僂僃傾偺1偮偵丄墦妘庤懕偒屇傃弌偟偵傛傞僾儘僌儔儈儞僌傪峴偆偨傔偺儈僪儖僂僃傾偱偁傞Ninf僔僗僥儉偑偁傞丅Ninf僔僗僥儉偼僋儔僀傾儞僩丒僒乕僶儌僨儖偵婎偯偒愝寁丄幚憰偝傟偰偄傞僔僗僥儉偱偁傝丄嵟弶偺僶乕僕儑儞(Ninf
V.1)偼1996擭偵儕儕乕僗偝傟偰偄傞丅Ninf V.1偵偍偄偰偼丄儕儌乕僩儔僀僽儔儕偺堷悢傗曉傝抣偺忣曬乮僗僞僽忣曬乯傗儕儌乕僩儔僀僽儔儕偺幚嵺偺強嵼摍偼僋儔僀傾儞僩偲僒乕僶偲偺娫偱Ninf僾儘僩僐儖傪梡偄偰傗傝偲傝偝傟偰偄偨丅傑偨丄僒乕僶懁偼僋儔僀傾儞僩懁偺IP傾僪儗僗傪僠僃僢僋偡傞側偳偺娙扨側僙僉儏儕僥傿婡擻偼偁偭偨偑丄屄暿偺儐乕僓偛偲偺僙僉儏儕僥傿側偳偼側偄丅Globus
Toolkit傪梡偄偰Ninf僔僗僥儉傪嵞幚憰偡傞偙偲偵傛傝丄GSI傪棙梡偟偨儐乕僓擣徹婡峔傪Ninf僔僗僥儉偵慻傒崬傓偙偲偑壜擻偲側傞丅幚憰偵嵺偟偰偼丄Ninf僒乕僶傪Globus偺gatekeeper偵抲偒姺偊丄僗僞僽忣曬偲儕儌乕僩儔僀僽儔儕偺強嵼偼GRIS偵栤偄崌傢偣傞偲偄偆曽幃傪嵦梡偟偨丅恾3偲4偼丄偦傟偧傟Ninf
V.1偍傛傃Globus斉Ninf偵偍偗傞僋儔僀傾儞僩偲僒乕僶娫偺僾儘僩僐儖傪昞偟偨傕偺偱偁傞丅
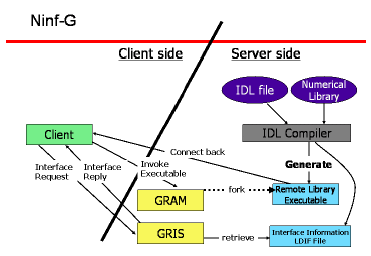
恾4 Globus斉Ninf僾儘僩僐儖
丂偙偺傛偆偵Globus Toolkit傪梡偄偰幚憰偡傞偙偲偵傛傝丄斾妑揑梕堈偵GSI偵婎偯偔僙僉儏儕僥傿婡峔偑慻傒崬傔丄懠偺懡偔偺Grid僜僼僩僂僃傾偲嫟捠偟偨僙僉儏儕僥傿婡峔傪採嫙偱偒丄憡屳棙梡偺壜擻惈偑崅傑傞丅傑偨丄GRIS偵儔僀僽儔儕偺忣曬傪搊榐偡傞偙偲偵傛傝丄懠偺忣曬僒乕價僗僔僗僥儉傪捠偟偰儕儌乕僩儔僀僽儔儕偺忣曬傪採嫙偡傞偙偲偑偱偒丄棙梡惈偑崅傑傞丅
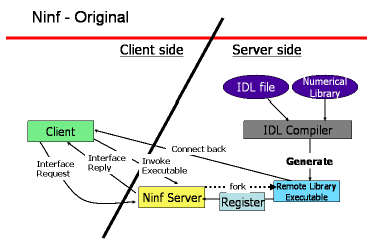
恾3 Ninf V.1 僾儘僩僐儖
3.5 Globus Toolkit偺嵟怴偺摦岦
3.5 1 Globus 僶乕僕儑儞2.0
Globus Toolkit偺惓幃斉偼僶乕僕儑儞偑1.1.4偱偁傞偑丄儀乕僞斉偲偟偰僶乕僕儑儞2.0偑攝晍偝傟偰偄傞丅僶乕僕儑儞2.0偼埲壓偺傛偆側摿挜傪帩偮丅
| 亜 |
僷僢働乕僕壔
棙梡栚揑偵墳偠偰娙扨偵僀儞僗僩乕儖偱偒傞傛偆偵丄偄偔偮偐偺僐儞億乕僱儞僩偵暘妱僷僢働乕僕壔偝傟偰偄傞丅傑偨丄僶僀僫儕斉傕攝晍偝傟偰偄傞丅 |
| 亜 |
MDS 2.1
僙僉儏儕僥傿偺婡擻傪嫮壔偟偨忣曬偺専嶕偑壜擻偲側偭偰偄傞丅 |
| 亜 |
GRAM 1.5
乮摿偵乯懴屘忈惈婡擻偑嫮壔偝傟偰偄傞丅 |
| 亜 |
Data Grid岦偗婡擻偺嫮壔
GSIftp傗Replica Catalogue/Replica Management側偳丄Data Grid岦偗偺婡擻偑嫮壔偝傟偰偄傞丅 |
3.5 2 婇嬈偲偺偐傜傒
丂SC2001奐嵜拞偺11寧12擔偵12偺婇嬈偑Globus Toolkit傪Grid偵偍偗傞昗弨揑側僾儔僢僩僼僅乕儉偲偟偰嵦梡偡傞偲偄偆婰幰敪昞偑偁偭偨丅Compaq丄Cray丄SGI丄Sun
Microsystems丄Veridian丄Fujitsu丄Hitachi丄NEC偺奺幮偼Globus Toolkit傪偦傟偧傟偺僾儔僢僩僼僅乕儉忋傊堏怉偍傛傃惈擻夵慞偺嶌嬈傪峴偭偰偄傞丅Entropia丄IBM丄Microsoft偼埲慜傛傝偺Globus
Toolkit偵懳偡傞擣抦傪怺傔丄Platform Computing偼Globus Toolkit偺彜梡僒億乕僩傪寛掕偟偨丅Globus Toolkit帺懱偼僼儕乕僜僼僩僂僃傾偱偁傞偑丄奺婇嬈偼Globus
Toolkit傪梡偄偨價僕僱僗偺揥奐傪慱偭偰偄傞偲巚傢傟傞丅
3.6 傑偲傔
丂Globus Toolkit偼Globus Project偑採嫙偟偰偄傞僣乕儖孮偱偁傝丄偄傑傗帠幚忋偺昗弨媄弍偲側偭偰偄傞丅婇嬈傕Globus傪梡偄偨價僕僱僗偺揥奐傪柾嶕偟偰偍傝丄帺幮偺僾儔僢僩僼僅乕儉傊偺堏怉傗彜梡僒億乕僩側偳傪恑傔偰偄傞丅偟偐偟丄奺婇嬈偺揥帵僽乕僗偱幙栤傪偟偨尷傝偱偼丄傑偩嬶懱揑側價僕僱僗儌僨儖偼尒偊偰偄側偄偲偺偙偲丅偟偐偟丄崱屻偺揥奐傪梊應偟偰Globus傪拞怱偲偟偨Grid偺悽奅偵嶲擖偟偰偄傞偲偺偙偲偱偁傞丅Globus
Toolkit偼旕忢偵傛偔偱偒偨僜僼僩僂僃傾偱偁傞偑丄Globus Toolkit偑採嫙偡傞偺偼掅儗儀儖側儔僀僽儔儕傗API偱偁傝丄僄儞僪儐乕僓偑棙梡偡傞偵偼彮乆偟偒偄偑崅偄丅偦偙偱丄崱屻偼Globus
Toolkit偺忋偵峔抸偝傟丄儐乕僓偵懳偟偰傛傝巊偄傗偡偄僀儞僞僼僃乕僗傪採嫙偡傞儈僪儖僂僃傾傗億乕僞儖偺暘栰偺尋媶奐敪偑壛懍偡傞偲梊憐偝傟傞丅
4. 億乕僞儖
丂億乕僞儖偲偼乽擖傝岥乿傪堄枴偡傞尵梩偱偁傝丄戝偒偔暘偗偰Web Portal偲Computing Portal偵暘椶偝傟傞丅
| 亜 |
Web Portal
懡條側Web僐儞僥儞僣偵懳偟偰僨傿儗僋僩儕僒乕價僗傗専嶕婡擻傪採嫙偟丄摑堦惈丒摟夁惈丒壜斃惈偺偁傞僀儞僞僼僃乕僗傪採嫙偡傞丅偨偲偊偽google傗yahoo側偳丅 |
| 亜 |
Computing Portal
Grid忋偵嶶嵼偡傞帒尮偍傛傃僒乕價僗偵懳偟偰丄堦尦揑丄摟夁揑偐偮壜斃惈偺偁傞僀儞僞僼僃乕僗傪採嫙偡傞丅 |
丂恾5偵暷崙NPACI偺HotPage偲偄偆Computing Portal儁乕僕偺僀儊乕僕傪帵偡丅
丂HotPage偼壖憐揑側僗乕僷乕僐儞僺儏乕僞僙儞僞乕傪儐乕僓偵懳偟偰採嫙偟丄儐乕僓偼HotPage偺WEB儁乕僕偐傜儘僌僀儞偡傞偙偲偵傛傝丄SDSC丄TACC丄Caltech側偳偺僐儞僺儏乕僞僙儞僞乕偵偁傞僗乕僷乕僐儞僺儏乕僞傊偺僕儑僽傪搳擖丄僕儑僽偺忬懺僠僃僢僋傗奺僐儞僺儏乕僞偺晧壸忣曬偺庢摼側偳傪峴偆偙偲偑偱偒傞丅傑偨丄僼傽僀儖僔僗僥儉偺憖嶌傕峴偆偙偲偑偱偒傞丅抧棟揑偵傕棧傟偰偄偰塣塩偡傞慻怐傕暿乆偺僐儞僺儏乕僞傪侾偮偺壖憐揑側慻怐偲偟偰傑偲傔偁偘丄儐乕僓偵懳偟偰偼億乕僞儖偲偄偆宍偱娙扨側僀儞僞僼僃乕僗傪採嫙偟丄儐乕僓偑娙扨偵暋悢偺僗乕僷乕僐儞僺儏乕僞傪棙梡偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傞丅崱屻Grid偺晛媦偵岦偗偰偼丄僄儞僪儐乕僓偵懳偟偰偙偺傛偆側娙扨側僀儞僞僼僃乕僗傪帩偮億乕僞儖偺採嫙偼昁恵偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅
億乕僞儖偺尰忬偍傛傃崱屻偺摦岦傪埲壓偵傑偲傔傞丅
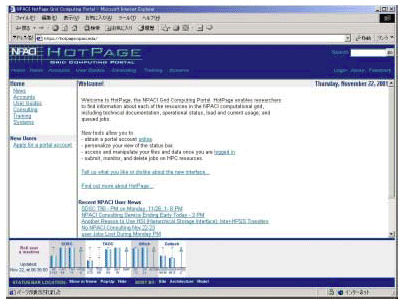
恾5 NPACI HotPage
| 亜 |
Gaussian傗Amber側偳偺傾僾儕働乕僔儑儞億乕僞儖偼偡偱偵幚梡壜擻側儗儀儖偵偁傞丅 |
| 亜 |
ScaLAPACK側偳偺儔僀僽儔儕儗儀儖偺傕偺傪棙梡偡傞億乕僞儖偺応崌偼僋儔僀傾儞僩偲偺僀儞僞僼僃乕僗摍傪峫椂偡傞昁梫偑偁傝丄娙扨偱偼側偄丅 |
| 亜 |
億乕僞儖傪峔抸偡傞偨傔偺億乕僞儖僣乕儖僉僢僩偑奐敪偝傟傟偽丄婛懚偺僜僼僩僂僃傾傪梕堈偵億乕僞儖偱棙梡偱偒傞傛偆偵側傞丅 |
| 亜 |
Grid偵偍偗傞價僕僱僗儌僨儖偲偟偰Application Service Provider(ASP)偼旕忢偵廳梫偱偁傞偲峫偊傜傟偰偍傝丄崱屻傕億乕僞儖偺尋媶奐敪偼廳揰揑偵恑傔傜傟傞偲峫偊傜傟傞丅 |
5. Access Grid偲SC Global
5.1 Access Grid
丂Access Grid偼恖偲偄偆忣曬帒尮傊偺傾僋僙僗傪巟墖偡傞僾儘僕僃僋僩偍傛傃僜僼僩僂僃傾偱偁傞丅偦偺婎杮晹暘偼戝婯柾價僨僆夛媍僔僗僥儉偱偁傝丄IP儅儖僠僉儍僗僩偱捠怣偡傞偨傔偵嫆揰悢偺僗働乕儔價儕僥傿偑崅偄偙偲傗丄僐儌僨傿僥傿PC忋偺僜僼僩僂僃傾偱峔惉偝傟傞偺偱峔惉偺帺桼搙偑崅偔丄庤傪擖傟傗偡偄偙偲側偳偑摿挜偱偁傞丅僾儘僕僃僋僩偼Argonne
National Laboratory偑巒傔偨傕偺偱丄儊乕儕儞僌儕僗僩偵偼尰嵼300柤傪挻偊傞儊儞僶偑搊榐偟偰偄傞丅抦傜傟偰偄傞斖埻偱杒暷丄儓乕儘僢僷丄撿暷丄傾僕傾懢暯梞抧堟偱偼擔杮丄僆乕僗僩儔儕傾丄拞崙偵栺80偺僒僀僩偑偁傝丄偦傟埲忋偺悢偺僲乕僪偑塣梡偝傟偰偄傞丅僱僢僩儚乕僋傪梡偄偨Computer
Supported丂Collaborative Work偲偄偆傾僀僨傿傾偼摿偵怴偟偄傕偺偱偼側偄丅偟偐偟丄Access Grid偺傛偆偵悽奅婯柾偱崅昳幙側僀儞僞儔僋僔儑儞偑壜擻偵側偭偨偺偼嬤擭挊偟偄僱僢僩儚乕僋偺晛曊壔偲峀懷堟壔偺壎宐偱偁傝丄嵟嬤傛偆傗偔尰幚偺傕偺偲側偭偰幚徹偺娐嫬偑惍偭偨偲尵偊傞丅
丂擔杮偱偼嶻憤尋丄搶岺戝丆嬨廈戝妛偵偰Access Grid僲乕僪傪峔抸偡傞偲摨帪偵丄Access Grid偱偺棙梡偵懴偊傞悢Mbps偐傜100 Mbps埲忋偺IP儅儖僠僉儍僗僩愙懕傪愝偗偰塣梡偟偰偒偨丅恾6偵嶻憤尋偺愝旛傪帵偡丅
丂尰嵼丄傎偲傫偳偺價僨僆夛媍僔僗僥儉偼TCP/IP忋偱偼H.323偲偄偆ITU-T姪崘偵弨嫆偟偰偄傞丅偙傟偼屇惂屼傗抂枛娫偺僱僑僔僄乕僔儑儞側偳傪掕傔偨僾儘僩僐儖孮偱丄Microsoft幮偺NetMeeting丄Polycom幮偺ViewStation傗ViaVideo側偳懡偔偺僔僗僥儉偑弨嫆偟偰偍傝丄弨嫆僔僗僥儉娫偱偼憡屳塣梡偑壜擻偱偁傞丅價僨僆夛媍偺庤抜偲偟偰偩偗峫偊偨応崌丄偙傟傜H.323抂枛偵懳偡傞Access
Grid偺棙揰偼嫆揰悢偑憹偊偰傕塮憸丄壒惡偲偄偭偨儊僨傿傾偺幙偑懝側傢傟側偄偲偄偆僗働乕儔價儕僥傿偱偁傞丅偙傟偼丄IP儅儖僠僉儍僗僩傪棙梡偡傞偐斲偐偲偄偆堘偄偐傜惗偠偰偄傞丅H.323偼婎杮揑偵堦懳堦偺價僨僆夛媍偺偨傔偺婯奿偱偁傝丄抂枛娫偵屇傃弌偟懁偲墳摎懁偲偄偆娭學傪壖掕偟偰偄傞偨傔丄暋悢偺嫆揰偱夛媍傪峴偆偨傔偵偼MCU乮懡抧揰愙懕憰抲乯偑昁梫偲側傞丅懡嫆揰夛媍偱偼丄慡H.323抂枛偑MCU傪憡庤偵儐僯僉儍僗僩偱捠怣偟丄MCU偼慡抂枛偐傜偺塮憸偲壒惡傪儈僢僋僗偟偰偦偺寢壥傪奺抂枛偵憲傞丅偙偺嵺偵奺抂枛偑MCU偐傜庴偗庢傞塮憸偼偁偔傑偱堦夋柺暘偵尷傜傟丄慡嫆揰暘傪QCIF乮Quarter-Common
Interface Format丆176x144 pixel乯傗FCIF乮Full-CIF丆352x288 pixel乯偺尷傜傟偨堦夋柺偵廂傔偨傕偺偲側傞丅MCU偼丄堦斒揑偵偼夋柺傪暘妱偟偨傝奺嫆揰偐傜偺塮憸傪揔摉側僞僀儈儞僌偱愗傝懼偊傞偙偲偱堦夋柺偵廂傔傞丅
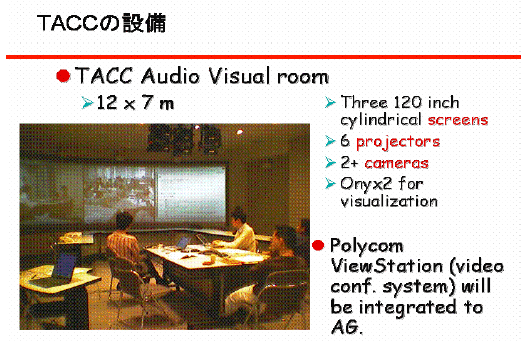
恾6丂嶻憤尋偺愝旛
丂堦曽丄Access Grid偼摉弶傛傝懡嫆揰傪巜岦偟偰偍傝丄IP儅儖僠僉儍僗僩偺棙梡傪慜採偲偟偰偄傞丅偳偺嫆揰傕懳摍偱偁傝丄偳偺嫆揰傕慡嫆揰偐傜偺姰慡側塮憸偲壒惡傪庴偗庢傞丅奺嫆揰偐傜偺塮憸偼PC乮Windows丆Linux乯偺僂傿儞僪僂偲偟偰昞帵偝傟傞偺偱丄偳偆偄偭偨戝偒偝丄攝抲偱昞帵偡傞偐偼奺嫆揰偺帺桼偱偁傞丅MCU偑峔惉偟偨偍巇拝偣偺堦夋柺傪慡堳偱尒傞偲偄偭偨晄帺桼偼側偄丅傑偨丄Access
Grid僲乕僪偺僴乕僪僂僃傾偼PC偱偁傞偨傔丄傕偟廲墶斾3:4偺堦夋柺偱偼庤嫹偱偁傟偽悢夋柺偵暘偗偰暋悢偺儌僯僞傗價僨僆僾儘僕僃僋僞偵弌椡偡傞偙偲傕梕堈偱偁傞丅Access
Grid偼PC忋偺僜僼僩僂僃傾偲偟偰幚尰偝傟偰偍傝丄幚懱偼婛懚偺僜僼僩僂僃傾偲偄偔偮偐偺撈帺僜僼僩僂僃傾偺廤傑傝偱偁傞丅偦偺偨傔丄僜僼僩僂僃傾傪嵎偟懼偊偨傝夵椙丄奼挘偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅傑偨丄僴乕僪僂僃傾峔惉偺帺桼搙偑旕忢偵崅偄丅尰偵丄塮憸偺憲庴怣偵梡偄傜傟傞僜僼僩僂僃傾VIC偼Access
Grid岦偗偵夵憿丄婡擻捛壛偑側偝傟偰偄傞丅傑偨丄墦妘抧偺懡悢偺挳廜偵懳偡傞僾儗僛儞僥乕僔儑儞偵梡偄傜傟傞DPPT乮distributed PowerPoint乯傕Access
Grid偺偨傔偵奐敪偝傟偨傕偺偱偁傝丄Access Grid偺奼挘壜擻惈傪帵偟偰偄傞丅僴乕僪僂僃傾峔惉偺帺桼搙偑崅偄偨傔丄PC偵價僨僆僇乕僪傪捛壛偟偨傝暋悢僨傿僗僾儗僀傊偺弌椡偑壜擻側價僨僆僇乕僪傪梡偄傞偙偲偱梕堈偵昞帵夋柺悢傪憹傗偣傞丅偙傟傕PC傪僾儔僢僩僼僅乕儉偲偟偰偄傞偙偲偺棙揰偱偁傞丅
丂Access Grid偺峔抸偵嵺偟偰偼丄婡嵽偺拞怱偼僐儌僨傿僥傿PC偱偁傝丄1戜偐傜4戜梡偄傞丅昞帵梡偵Windows傪1戜丄塮憸僉儍僾僠儍梡偲壒惡僉儍僾僠儍梡偵偦傟偧傟Linux傪1戜偢偮梡堄偡傞偙偲偑悇彠偝傟偰偄傞丅僄僐乕僉儍儞僙儔傗價僨僆僇儊儔偺惂屼梡偲偄偆柤栚偱傕偆1戜梡堄偡傞偙偲偑悇彠偝傟偰偄傞偑丄幚嵺偼傎偲傫偳晄梫偱偁傞丅恾7偵嶻憤尋偑峔抸偟偨僐儞僷僋僩側Access
Grid憰抲偍傛傃僨僶僀僗傪帵偡丅
丂PC埲奜偵壒惡偍傛傃塮憸梡偺僨僶僀僗偑昁梫偱偁傞偑丄僇儊儔丄儅僀僋丄僾儘僕僃僋僞埲忋偵廳梫偱偁傞偺偑僄僐乕僉儍儞僙儔偱偁傞丅僄僐乕僉儍儞僙儔傪梡堄偱偒側偄応崌僗僺乕僇偱偼側偔僿僢僪儂儞偱壒惡傪暦偔偙偲偵側傝丄僿僢僪儂儞偺悢偑嶲壛壜擻恖悢傪惂尷偟偰偟傑偆丅傕偟僄僐乕僉儍儞僙儔傪帩偨側偄僲乕僪偱僗僺乕僇傪巊偆偲僗僺乕僇偐傜偺壒惡傪嵞傃儅僀僋偑廍偭偰憲弌偟偰偟傑偄丄懠偺僲乕僪偐傜偺嶲壛幰偼僄僐乕傪暦偔偙偲偵側傞丅2嫆揰娫偺價僨僆夛媍側傜偲傕偐偔嫆揰悢偑懡偗傟偽偦傟偩偗僄僐乕偺敪惗尮傕憹偊傞偨傔丄Access
Grid偱偼偙偺栤戣偼旕忢偵戝偒偄丅
丂IP儅儖僠僉儍僗僩傪慜採偲偟偰偄傞偙偲偑Access Grid偺摿挜偺傂偲偮偱偁傞丅偙傟偵傛偭偰丄偡傋偰偺嫆揰偵偍偄偰慡嫆揰偐傜偺塮憸偲壒惡傪姰慡側宍偱庤偵擖傟傞偙偲偑壜擻偲側偭偰偄傞丅偟偐偟丄幚嵺偵IP儅儖僠僉儍僗僩傪棙梡偱偒傞娐嫬偺峔抸偼晘嫃偑崅偄丅Access
Grid偱乽儘價乕乿偲屇偽傟傞壖憐夛媍幒偵偼忢帪30偐傜40偺僲乕僪偑忢挀偟偰偄偰丄僩儔僼傿僢僋偼20 Mbps偵払偡傞丅偦傟傪庴怣偟愗傟側偄応崌丄塮憸偲壒惡偺幙偑掅壓偡傞偩偗偱嶲壛偦偺傕偺偑偱偒側偄傢偗偱偼側偄偑丄摨偠壖憐夛媍幒偵擖傞嫆揰悢偑懡偗傟偽懡偄傎偳昁梫側懷堟偼憹偊傞偨傔嫋梕懷堟暆偑峀偄偵墇偟偨偙偲偼側偄丅偙傟傑偱偺IP儅儖僠僉儍僗僩偺傾僾儕働乕僔儑儞偱偁偭偨堦曽岦偺曻憲傗彫婯柾乮悢嫆揰乯價僨僆夛媍偱偼昁梫側懷堟暆偼偣偄偤偄悢廫Kbps偐傜悢昐Kbps偱偁偭偨丅峀懷堟IP儅儖僠僉儍僗僩栐偺峔抸丆墳梡媄弍偲偄偆娤揰偱Access
Grid偼嫽枴怺偄傾僾儕働乕僔儑儞偩偲尵偊傞丅
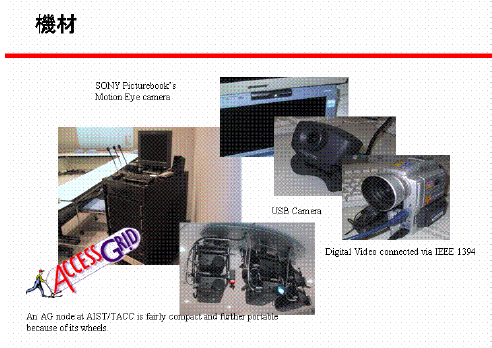
恾7 嶻憤尋偺Access Grid僲乕僪偍傛傃婡嵽
5.2 SC Global
丂SC2001偲摨帪偵丄悽奅奺抧偱條乆側僀儀儞僩傪嫟桳偟傛偆偲偄偆Grid忋偺崙嵺夛媍SC Global偑奐嵜偝傟偨丅偙傟偼丄Access Grid傪梡偄偰悽奅拞偐傜SC2001偵嶲壛偱偒傞傛偆偵偡傞偲摨帪偵丄奺僒僀僩偱傕僀儀儞僩傪婇夋丄奐嵜偟丄偦傟傪悽奅奺抧偱嫟桳偟傛偆偲偄偆帋傒偱偁偭偨丅SC2001偺揥帵夛応偵Showcase僲乕僪偑愝偗傜傟偨懠丄僥僋僯僇儖僾儘僌儔儉偺偨傔偵3晹壆乮廂梕恖悢450丄353丄162恖乯偵Access
Grid僲乕僪偑愝抲偝傟偨丅墦妘偐傜偺嶲壛僒僀僩悢偼丄9寧帪揰偺儕僗僩偵嵹偭偰偄傞傕偺偱杒暷33丄儓乕儘僢僷4丄傾僕傾懢暯梞抧堟3丄僽儔僕儖1丄撿嬌1偱偁偭偨丅傾僕傾懢暯梞抧堟偺3僒僀僩偼丄嶻憤尋丄僔僪僯乕戝妛丄杒嫗峲嬻峲揤戝妛乮BUAA乯偱偁傞丅偟偐偟丄幚嵺偵偼搶岺戝丄嬨廈戝妛丄拞崙偺惔壺戝妛側偳偐傜偺嶲壛傕偁偭偨丅恾8偵SC2001揥帵夛応偺Showcase僲乕僪偺條巕傪帵偡丅
僾儘僌儔儉偼丄Showcase僾儘僌儔儉偲3暲楍偺僥僋僯僇儖僾儘僌儔儉偐傜峔惉偝傟偰偄偨丅僥僋僯僇儖僾儘僌儔儉偵偼SC2001偺拞宲偲偟偰Keynote丄Gordon
Bell Finalist Showcase丄偦偟偰4偮偺僥僋僯僇儖僙僢僔儑儞偑庢傝忋偘傜傟偨懠丄29偺採埬偝傟偨僀儀儞僩偑峴傢傟偨丅Showcase僾儘僌儔儉偺拞偵偼撿嬌乮Center
for Astrophysical Research乯偐傜偺拞宲傕偁傝丄嶲壛幰偺嫽枴傪傂偄偰偄偨丅偙偺拞宲偵偼17僲乕僪偑嶲壛偟丄塮憸壒惡崌傢偣偰81偺僗僩儕乕儉偑棳傟偨偲偺偙偲偱偁傞丅
丂変乆傕僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞傪採埬偟丄塣塩偵偁偨偭偨丅傾僕傾懢暯梞抧堟偺Grid尋媶嫤椡懱惂ApGrid偺棫偪忋偘帪婜偱偁偭偨偺偱丄乽Can the
Asia Pacific Grid Contribute to the Science and Technology in the Asia Pacific
Region?乿偲戣偟丄奺崙嶲壛慻怐偺戙昞偵傛傞敪昞偲媍榑傪婇夋偟偨丅偙偺僷僱儖偱偼丄僨儞僶乕偺夛応丄僆乕僗僩儔儕傾偺僔僪僯乕戝妛丄偍傛傃嶻憤尋偺嶰売強傪Access
Grid偱愙懕偟丄擔杮丄娯崙丄戜榩丄僞僀丄僆乕僗僩儔儕傾丄暷崙偺6僇崙偐傜僷僱儕僗僩偑嶲壛偟偰峴傢傟偨丅巌夛傪僨儞僶乕偵偰搶岺戝偺徏壀愭惗偑柋傔丄擔杮偐傜偼僷僱儔偲偟偰嶻憤尋戝帾忣曬張棟尋媶晹栧挿偑嶲壛偟偨丅恾9偵ApGrid僷僱儖僙僢僔儑儞偺條巕傪帵偡丅
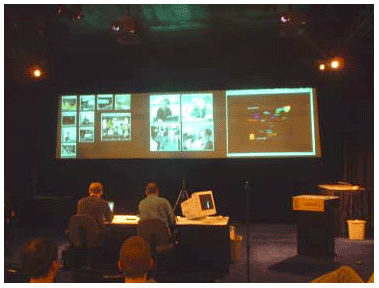
恾7 SC Global Showcase
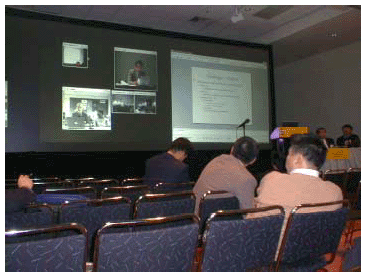
恾9丂ApGrid 僷僱儖僙僢僔儑儞
丂傑偨丄Data Grid偵娭偡傞僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞偵偼擔杮偐傜崅僄僱尋搉悾愭惗偑嶲壛偟偨丅偦偺懠丄嶻憤尋偺娭岥丄揷拞傕暿偺僀儀儞僩偺僷僱儔傪柋傔傞側偳懡曽柺偐傜嶲壛丄峷專偟偨丅
嬤擭丄壠掚偵傑偱悢Mbps偺僱僢僩儚乕僋偑晛媦偟偮偮偁傝婎姴僱僢僩儚乕僋偺峀懷堟壔傕恑傫偱偄傞丅僱僢僩儚乕僋墇偟偺價僨僆夛媍丄Computer Supported
Collaborative Work偲偄偆峫偊偼摿偵怴偟偄傕偺偱偼側偄傕偺偺丄峀懷堟僱僢僩儚乕僋偺晛媦偵偟偨偑偭偰偦偺尰幚惈偼媫懍偵憹偟偮偮偁傞丅Grid偺杮幙偱偁傞Virtual
Organization偺塣塩偵偼偙偺傛偆側僱僢僩儚乕僋墇偟偺價僨僆夛媍偼旕忢偵廳梫偱偁傝丄崱屻僙僉儏儕僥傿傗忣曬僒乕價僗側偳偺Grid媄弍傪庢傝擖傟偨廩幚偟偨婡擻偺採嫙偑朷傑傟傞丅
6. 傑偲傔
丂杮峞偱偼丄SC2001偵偍偗傞島墘傗尋媶揥帵傪傆傑偊丄Grid偺尰忬偍傛傃摦岦偵偮偄偰曬崘偟偨丅Grid偼婎斦媄弍偑惉弉偟偰偒偰偍傝丄崱偼幚嵺偺傾僾儕働乕僔儑儞傪摦偐偡抜奒偵偒偰偄傞丅Globus
Toolkit偼愻楙偝傟偨婎斦僜僼僩僂僃傾偱偁傝帠幚忋偺昗弨偲側偭偰偄傞偑丄傾僾儕働乕僔儑儞儐乕僓偑捈愙棙梡偡傞偺偼擄偟偄丅寁嶼婎斦丄忣曬婎斦偲偟偰Grid傪晛媦偟丄Grid偺儐乕僓傪峀偘傞偨傔偵偼傛傝忋埵偵埵抲偡傞儈僪儖僂僃傾傗億乕僞儖偺尋媶奐敪偑昁梫偱偁傝丄幚嵺偵悽奅拞偱尋媶奐敪偑壛懍偝傟偰偄傞丅傑偨丄Grid偺杮幙偱偁傞壖憐揑側慻怐偵傛傞塣塩(Virtual
Organization)偵嵺偟偰偼丄揹巕儊乕儖偩偗偱偺岎棳偱偼側偔丄幚嵺偵婄傪婄傪偁傢偣偰偺塣梡偑廳梫偱偁傞丅Access Grid偼懡抧揰愙懕傪峫椂偟丄IP儅儖僠僉儍僗僩傪梡偄偨幙偺崅偄僱僢僩儚乕僋夛媍僔僗僥儉偱偁傞丅尰帪揰偱偼IP儅儖僠僉儍僗僩偑偳偙偱傕巊偊傞媄弍偱偼側偄偙偲傗丄偦傟側傝偺懷堟傪昁梫偲偡傞揰側偳丄摿偵僱僢僩儚乕僋僀儞僼儔偺惍旛偑抶傟偰偄傞傾僕傾抧堟偵偍偗傞棙梡偵偼庒姳偺栤戣偼巆傞偑丄崱屻僙僉儏儕僥傿傗忣曬僒乕價僗側偳偺Grid媄弍傪庢傝崬傓偙偲偵傛傝丄傛傝朙晉側婡擻傪帩偪丄傛傝惈擻偺崅偄僔僗僥儉偲側傝丄崱屻偺Grid僥僗僩儀僢僪偺塣塩偵桳梡側庤抜偲側傞偙偲偼娫堘偄側偄丅