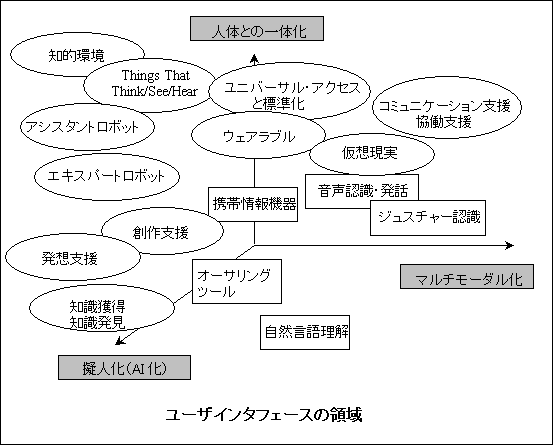 |
3.3 ユーザインタフェース
従来、計算機は専門の要員やプログラマー、限られた技術者・研究者が運用・利用してきた。その後、1980年代から徐々にオフィス等でのエンドユーザの作業用途に広がってきた。その際、グラフィカルなユーザインタフェースが操作を容易にし、初心者でも使えるツールとなった。現状、健常者がデスクトップで操作するインタフェースとしては成熟しているが、今後、インターネット化する社会インフラへの窓口として全ての人が様々な環境で使えるようなユーザインタフェースが求められる。例えば、子どもやコンピュータ・キーボードに習熟していない人々による利用、身体障害者や視聴覚障害者による利用、移動中・作業中など机に向かっていない状態での利用などに向いたユーザインタフェースが求められる。
ユーザインタフェースの目指す方向は、人間に密着し、人間の意図を理解し、個人の活動を支援すること、さらには個人の活動を増幅することである。また、その延長として、グループワークにおけるコミュニケーションや協働の支援を行うことや、環境との相互作用を仲介することも、ユーザインタフェースの目的に含まれるであろう。
また、理性的な活動のアシストだけでなく、快適さを与えたり技能を訓練する等、物理的存在としての人間の状態を安定化させたり向上させたりするためのユーザインタフェースも社会経済的な重要性を持つだろう。活動支援のためには意図を正確に理解することが必要だが、環境としてのユーザインタフェースではそのような正確性は求められず、また環境側からの働きかけが主になるため、アシストのためのユーザインタフェースよりも、むしろ実用化は早いと考えられる。
なお、組み込み機器、自動制御・観測、極限作業ロボットなどでの物理世界とのインタフェースは、ユーザインタフェースとはまた違った条件と目的のもとでの研究が必要であろう。
ユーザインタフェースの領域の有力な研究分野及びインフラ整備課題と考えられるものを図3-5に示す。
・STIMULATEプロジェクト
米国における基礎研究として、STIMULATE (Speech, Text, Image, and Multimedia Advanced Technology Effort) プロジェクトがあり、NSF、DARPA、NASA が支援の下で、1997年から3年にわたり、大学の 15 の研究グループで、音声、ジェスチャ、表情、筆跡、イメージ、ビデオなどの様々なモードによる、マンマシンインタフェースの研究が助成された。 地球観測などのデータや科学工学シミュレーションの結果データは、多くの場合3次元空間に分布し、時系列変化する膨大な量のデータとなる。それらを、様々な視点で眺め、理解、分析できるように、分かりやすい可視化をする技術が重要である。また、シミュレーション結果の可視化に留まらず、大量のデータ/情報を人間に分かりやすく伝達し、さらには効果的な探索を可能にするための、情報の可視化の研究がなされている。
・ユニバーサル・アクセス(全ての人々によるアクセス)
情報技術が真の社会インフラとなるためには、限られた技術取得者だけでなく広く一般の人々や障害を持った人々が利用できるようになる必要があり、その入口であるユーザインタフェースが特に重要である。ユニバーサル・アクセスとは、技術や施設などが、老齢者や身体上の障害を持った人々にも使える(そして、それによって社会参加の程度が向上する)という性質を言うが、新しい情報技術にはその考え方が必要である。
World Wide Web Consortium (W3C) では、1997 年から Web Accessibility Initiative (WAI)という活動で、Web のユニバーサル・アクセスに向けた指針作りをしており、既に政府機関で WAI 指針に従った Web ページを作成し始めているところもある。NSF は 1999年度に、Human-Computer Interaction (HCI)プログラムとKnowledge and Cognitive Systems (KCS)プログラムの合同で、ユニバーサル・アクセスの研究を開始した。研究課題には、従来型デスクトップ・インタフェースの代替、聴覚障害を持つユーザ向けの聴覚情報へのテキスト形式によるアクセス、運動障害を持つユーザのための入出力技術、視覚障害を持つユーザのための図形・画像情報への触知アクセスなどが含まれる。このように米国では、Web を社会参加への基本インフラと捉え、必要な措置を取りつつある。
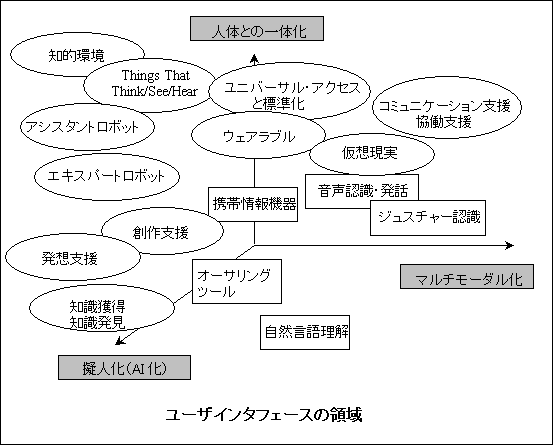 |