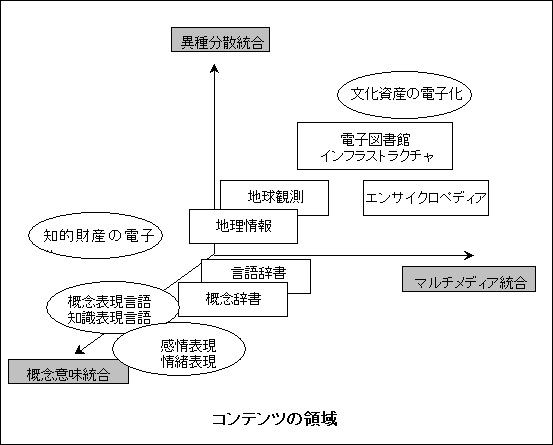 |
3.2 コンテンツ
従来、情報技術の扱う対象は科学・工学分野のデータや産業分野のデータが中心であったが、書籍の電子化、娯楽メディアの電子化など、その対象が急速に広がりつつある。しかも、従来のように孤立した計算機上で処理されるのではなく、インターネットを通して、必要に応じてやりとりされるようになっている。「データ」という計算機処理の視点からの捉え方よりも、「コンテンツ」というユーザにとっての意味の視点からの捉え方の方が、この事情をより良く表現している。
今後、情報技術があらゆる経済活動を把握し、管理・分析・効率化等に関わることを目指すとすれば、経済活動の対象となる実世界のあらゆるものの仕様、性質などの電子的表現が必要となる。また、著作物などの知的財産、ひいては文化資産全般の電子化にまで、ニーズは広がり、実現技術が開発されるであろう。
インフラ整備としては、商品・製品の電子的表現(仕様、性質、機能など商取引上の必要・参考情報など)などの標準化、国土の詳細な地理情報、各国語に対応した電子辞書、概念の辞書、さらには知識を集大成したエンサイクロペディア、などの基礎的コンテンツ(インフラコンテンツ)が重要となろう。これらインフラが整備され(望ましくは社会の共有物として無償で公開されれば)、その上に様々な用途向けインフラ(ミドルウェア・コンテンツ)、応用(アプリケーション・コンテンツ)が発展すると予想される。コンテンツには人類共有財産もあり、また文化的財産もあり、後者についてはそれぞれの文化圏において整備が必要である。それは文化圏間のコンテンツ電子化の競争であり、また、各文化圏が固有性を確保するための重要な政治社会的な手段ともなろう。
このようなコンテンツをベースとして、現在、新聞や雑誌、ラジオやテレビが供給している文字情報、音楽情報、映像情報などがディジタル化され、仮想現実などと結びついて新しいコンテンツ・ビジネスの世界を作り出すことが考えられる。
コンテンツのカバー範囲が拡大して行くためには、知識表現、情緒表現の基礎研究が必要である。また、実世界の事物の電子化のためには、紙媒体の書物・資料のデジタイズ技術(画像レベル、文字情報レベル)、三次元物体のデジタイズ技術など様々な観測技術の研究開発や、衛星画像からの地理情報の作成などの認識技術などの研究開発も重要となる。
コンテンツは表現技術で終るのでなく、表現されたコンテンツを活用する際に、コンテンツに関する財産権、プライバシーなどの問題が生じる。それらに関する法的な取り決め、権利関係を処理する機関ないしインフラの整備等をすることが、コンテンツ作成・利用に関する経済社会活動を可能にすることにも注意が必要である。
コンテンツの領域の有力な研究分野及びインフラ整備課題と考えられるものを図表3-4に示す。
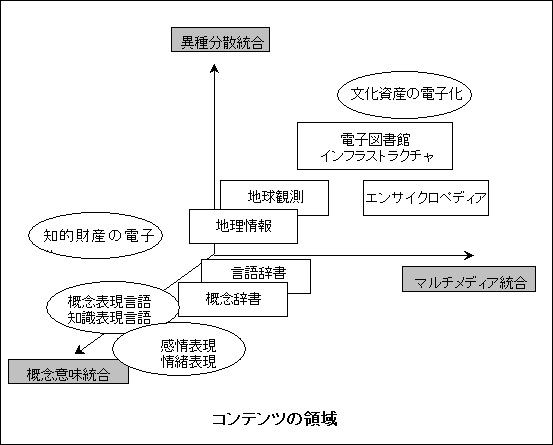 |