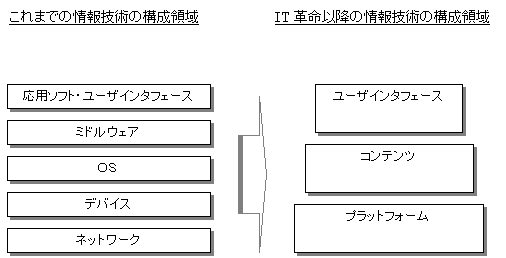 |
本章では、情報技術(IT)の技術開発分野を検討するための基礎としてITに求められる技術革新の方向を明らかにする。ITの技術革新と、その利用による社会・産業の変化は多分に相互作用的である。すなわち、技術主導で社会・産業が変わるという流れがある一方、社会・産業の問題解決に向けて技術革新の探求が行われるという流れが存在する。
ここではまず、今後の社会・産業がどのような問題に直面し、どのように変わろうとしているか概観し、そこからITに求められる技術革新の方向を検討する。
2.1 社会・産業の将来とITの役割
(1)企業・産業の発展方向とITに対するニーズ
コンピュータが企業に導入されて久しいが、製造オペレーション、経理事務など経営活動のさまざまな領域で情報システム化が進み、業務の省力化が図られてきた。コンピュータの性能向上とともに、通信技術との融合を含め、情報技術が企業経営に占める割合はますます高まっている。その結果、単なる業務効率化・省力化の道具という位置付けではなく、企業の競争力を決定する戦略的な武器という役割も担い始めた。特に、企業間情報ネットワークによって、取引先や顧客との関係の強化や、密な情報連係により大幅なコスト低減や、経営サイクルの劇的なスピードアップが進んでいる。
近年では、インターネットの急速な普及により、電子商取引(Electronic Commerce)が拡大し、その結果、企業間関係や産業構造が再編されるとともに、企業の組織編成のあり方も変わろうとしている。以下に示すのは、そのような変化の一端であるが、その変化がさらに新たな情報技術のニーズを創造することになるだろう。
●企業間ネットワーク、Eコマースの拡大
インターネットの世界的な普及により、ネットワークを介した販売・調達が拡大している。取引情報の伝達を時間的・地理的な制約なく行うことができるばかりでなく、新規の取引相手を全世界から探し、それを別な国の家庭に販売することが可能となった。
そのためにも、取引情報の通信だけではなく、商品やサービスをよりよい形態でプレゼンテーションしたり、対話的で密なコミュニケーション形式が可能となることが必要である。
●大規模・統合組織からダイナミックで有機的な組織構造への転換
ITに代表されるように著しい技術革新と、顧客ニーズの多様化に伴い、経営環境はこれまで以上に絶え間なく変化している。このような中で、競争力を維持しつつ、経営成果を高めるためには、自社の強みを強化し、その機能に特化した事業展開を指向し、そのために他の企業と補完的な連係を保ちながら事業体制を構築するようになってきた。企業組織は、必要な機能を揃えた単独の大規模組織から、複数の企業組織からなる仮想企業体(バーチャルコーポレーション)であるとか、ネットワーク組織といった形態へ転換しつつある。その場合、構成される企業間の情報伝達や情報共有においてITが重要な役割を担う。
●リアルタイム経営の精緻化
不確実な環境の中で経営の舵取りや意思決定はますます難しくなっている。経営活動における計画、実行、評価、修正の質を高め、かつ迅速に行っていくことが求められている。そのための基盤として、経営活動をさまざまな観点からモニターし、それを適切な指標によりリアルタイムで管理する仕組みが重要な経営基盤となっている。
●省力化から増力化のための情報活用
機械化や情報化によって企業の中で提携業務に携わる人数が減少している。すなわち、省力化はこれまでに大幅に進展してきた。したがって、人が活躍しなければならない領域は計画や管理、さらには商品・サービスの開発や市場開拓等非定型で、創造的な業務である。この部分に関しては、人間の作業を削減するというよりも、人間の力を引き出したり、増幅させる「増力化」のためのIT活用が期待される。そのためには、ITはいろいろな意味でより人間に近づくことが必要となる。
(2)家庭・生活の発展方向とITに対するニーズ
ITや各産業の発展によって家庭・生活も大きく変貌しており、生活の質は加速度的に高まっている。今後も引き続き次のような方向での発展が期待される。
●ライフラインの安定的供給、高機能化
生活者にとってライフラインの整備と安定的な供給は極めて重要である。電気、ガス、水道、電話、鉄道、高速道路の運用・保守の高信頼化、災害対策等のリスク管理に関して、ITが貢献できる部分は少なくない。
●情報化の空間的広がり 〜 家庭、街、道路を包み込む情報網
情報化は、家庭、街、道路の至るところに広がり、シームレスに連係される。家庭では、設備・機器、家庭電器製品がインテリジェント化され、それらがネットワーク化する。帰宅途中に形態端末を通じて、室内温度のチェックとコントロールをすることも可能になるだろう。また、高速道路においてITS(高度道路交通システム)が構築されつつあるが、道路に付帯する情報収集・加工、コミュニケーションのニーズは大きい。
●福祉・医療機能の拡充
高齢化社会が急速に進んでおり、福祉と医療に関する社会環境の整備が必要となる。同人が家庭にいながら、医師、介護サービス提供者や友人と良好なコミュニケーションを行うためのテレビ電話や使いやすいネットワーク端末の普及が進むことになる。医師との間では、診断のためのカルテや画像情報もネットワークを介してやりやり取りすることにより、遠隔診療が行われる。独居老人宅においては、家庭生活の異常や、健康状態を住宅設備、家電のインテリジェント化によって発見し、自動通報することも可能になるかもしれない。
●娯楽・文化の良質化
娯楽や文化教養の世界も、ITによって良質化、利便性の向上、そして多様化が進展する。コンピュータグラフィックスベースの映画が増加し、ゲームでは、コンテンツの高品質化が進とともに、バーチャル空間の中で多数の人が参加するネットワークゲーム等新たな形態が拡大する。文化教養面では、ネットワーク上のバーチャルコミュニティが活動しやすくなる環境が整備され、またこれまでの知的資産もネットワークリソースとして整備されることになるだろう。
2.2 情報技術を分類する新しい構成領域と基軸
以上の発展方向からは、情報技術(IT)を捉える軸が新規に追加されたり、重点が移っていることがわかる。本調査研究では、図表2.1に示すように、プラットフォーム、コンテンツ、ユーザインタフェースの3つの領域から情報技術を捉えることとする。
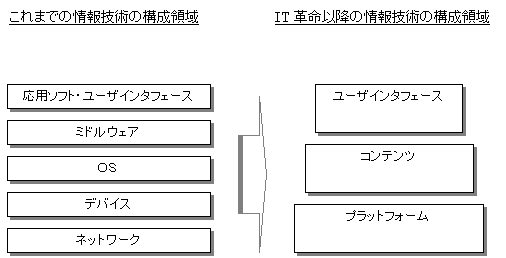 |
(1)プラットフォーム
プラットフォームは、ITの基本機能である情報処理と通信を提供するレイヤであり、中央処理装置、各種プロセッサー、記憶装置と、内部バス、外部バス、ネットワークの構成によって具現化されるものである。プラットフォームに求められる技術革新の方向は、「高速化」、「広域分散化」、「高セキュリティ化」である。
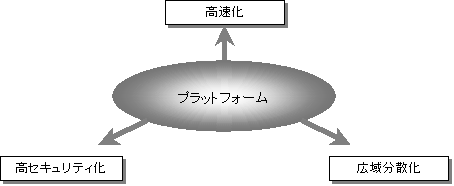 |
●高速化
分野を問わず、プラットフォームの処理能力向上は、ITの発展にとって最も中核となる性能改善課題である。
環境・気象・医学を始め科学技術のフロンティアを開拓するためのシミュレーションにおいて、より高速に計算処理することは、解決されることのない永遠の課題である。特に、新たな探求方法である計算科学の進展が今後の科学進歩を加速する原動力であり、計算機の高速化はそのための重要な前提条件となっている。
また、企業・行政の業務アプリケーションでも扱うデータ件数は加速度的に増加し、しかもそれらを瞬時に処理することが求められている。さらには、意思決定の最適化、データマイニング、金融工学、取引仲介のエージェントなど新たな分野・領域にITを利用していく上でも、これまで以上の処理能力が要求される。
●広域分散化
広域分散した機器・プロセッサーが、協調的に情報通信処理するプラットフォームの開発が期待される。
ITの利用形態は、大型計算機による集中的な処理形態から、ネットワークを介し、さまざまな装置が連携しあう分散形態に移行する。インターネットの急拡大はそれを如実に示している。従来のパーソナルコンピュータや端末だけではなく、電話、身に付けられる情報機器、家電等多様な機器がネットワークを介して協調動作することになる。
また、製造業の工場においては既にNC装置・ロボット、搬送装置等を分散制御しているが、今後は複数の工場を遠隔的に監視・制御するバーチャルファクトリーが現実化しつつある。また、電力会社ではより効率的な電源供給を行うために、発電・送電・需要家側の機器が連携し合いながら、計画・制御・監視を行う必要がある。
これらのアプリケーションにおいては、ネットワークを介した分散データへのアクセス、協調分散制御方式の高度化が要求される。
●高セキュリティ化
ITのプラットフォームが広域分散化し、社会の至る所で機能を果たすことになると、停止や誤動作等を始めとする障害が生活・企業活動に大きな混乱や危険を与えることになる。社会が安全で安定的であるためにも、プラットフォームにはこれまで以上に耐障害性の向上、セキュリティの確保といった高セキュリティ化が求められる。
電力・ガス・水道等ライフラインの供給はITによって監視・制御されている。また、高速道路におけるITS、ETCや金融ネットワークに代表されるように社会インフラの多くもITの基盤の上に成り立っている。一般の企業においても、情報システムは基幹業務に直結しており、情報システムがストップすると事業の運営を継続することが不可能になっている。これらのアプリケーションの可用性、安全性を高めるための技術開発とリスク管理が必要となる。
また、広域分散化したシステムやネットワークの中に、重要な情報が流通し、処理が実行されることから、暗号技術を中心としたセキュリティ基盤の高度化も求められる。
(2)コンテンツ
コンテンツは、情報処理、通信の対象となるデータ、情報、知識であり、データベース管理技術、マルチメディア符号化等の技術によって具現化されるものである。コンテンツに求められる技術革新の方向は、「マルチメディア統合」、「異種分散統合」、「概念意味統合」である。
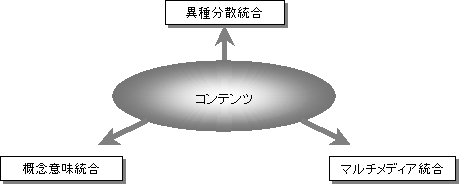 |
●マルチメディア統合
ITが対象とするコンテンツは、数値、テキスト等の単純なデータオブジェクトから、図形、イメージ等を含む文書、さらには音声、動画等を含むようになっている。
しかし、扱うオブジェクトの種類が多様化しているものの、それらを能率よくディジタル化しデータベースを作成するコンテンツ作成技術や、それらを一元的に管理できる仕組みは必ずしも十分できておらず、今後マルチメディアオブジェクトの効率的作成環境や統合的管理技術の開発が必要である。
●異種分散統合
ITで扱うオブジェクトは、タイプが多様化するだけでなく、地理的に分散し、かつ異なった形式を統一的に処理することが求められる。
異なったリレーショナルデータベース(RDBMS)処理系に対するネットワークを介した統合方式としてはRDAが提案されてきたが、今後はXML等異なったタイプのコンテンツを統合的に扱うことができる機構が求められる。
●概念意味統合
さまざまな形態、タイプのコンテンツを蓄積・管理・活用する上で、コンテンツが有する意味概念、文脈を含めたアクセスパスを用意することが重要である。現在では、テキストオブジェクトに関して意味概念検索機能が提供されてきたが、今後は図形、画像、動画等を含む意味概念検索、さらには状況に応じて必要なものにアクセスできる文脈依存検索等の機能がますます重要となる。
(3)ユーザインタフェース
ユーザインタフェースは、人間とITとの接点であり、そのための入出力技術によって具現化される。ここで入出力技術とは、コンピュータの入出力装置だけでなく、センサーやアクチュエータ等も含んでいる。ユーザインタフェースに求められる今後の発展方向は「マルチモーダル」、「人体・環境との一体化」、「擬人化(AI化)」である。
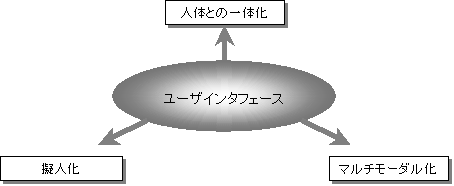 |
●マルチモーダル化(五感化)
コンピュータはこれまで数字、文字列等を中心に入出力が行われてきたが、高度なユーザインタフェースの一つの方向は、人間の五感をサポートすることである。ITが、人間活動の創造的・知的領域や、娯楽・エンターテイメントの領域に関与していくためには、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚を駆使したインターラクションが求められる。
●人体との一体化
マルチモーダル化とも関連してユーザインタフェースは人体と一体化する方向に向かっている。現在では、携帯情報機器、携帯電話等小型で持ち運び可能な端末が実用化されているが、それがウェアラブル(身に付けられる)になり、さらには身体への接近が進む。
●擬人化(AI化)
コンピュータを機械としてではなく、人間レベルでコミュニケーションし、やり取りすることは、コンピュータの用途を広げ、より知的なレベルで人間の支援を行う上で重要な要件である。具体的には、自然言語による理解・創作、音声による認識・発話や、知識の獲得、蓄積等の高度化が必要であり、人工知能(AI)、知的インタフェースの応用が望まれる。