毎年公表されているHPCC計画概要書(通称ブルーブック)の94年度版のエグゼクティブサマリーの最初のページには、次の1文が記されている。 これを政策として実現しようとしたのが、当時上院議員であったゴア副大統領である。彼は、1989年に全米高性能コンピュータ技術法案(National High Performance Computer Technology Act of 1989)を上院に提出している。当時、この法案は廃案とされたものの、彼は1991年1月に高性能コンピューティング(HPC)法案を提出し、1991年12月9日に成立した(High Performance Computing Act of 1991)。この法律は5年間の時限立法であったが、法律に示されている考え方は、現在に至る情報政策の根幹となっている。 で構成されている。また、タイトル2では、機関名を挙げ、これらの機関に対して実行計画に対する協力を要請している。
(1)HPC法成立とHPCC計画の開始(1991年〜)
この法律は、2つのタイトルから構成されている。タイトル1は、「高性能コンピューティングと研究・教育ネットワーク」と題されており、
HPC法で謳われている「実行計画」とは、法案成立とともに開始されたHPCC計画を指している。HPCC計画は、開始当初4プロジェクトから構成されていた。これらプロジェクトは、HPC法のタイトル1のテーマである、高性能コンピューティングシステム(HPCS)と研究・教育ネットワーク(NREN)が含まれている。
HPC法とHPCC計画の対応関係は、HPC法の内容を見るとわかりやすい。HPC法 タイトル1:「実行計画に対する要求事項」は、下記8点である。
|
HPCC計画の4プロジェクトは下記(HPCC-1)〜(HPCC-4)であり、それぞれが「実行計画に対する要求事項」に対応している。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPCC計画では、毎年HPCC計画実行計画書(Implementation Plan)が公表されており、(HPC-P1)に対応して、これら4プロジェクトに対する優先順位と各プロジェクト内の研究開発項目に対するマイルストンが示されている。(HPC-P8)は、これら4つのプロジェクトに係ると考えられる。
なお、(HPC-P2)は、HPC法の実行体制に関する箇所とともに後述する。
(HPC-P6)にある「グランド・チャレンジ(GC)」とは、高性能コンピュータを必要とする、科学技術研究アプリケーション(気象予測、エネルギー効率の最適化を考慮した自動車の設計、医薬の開発、星雲形成の解明など)の開発を支援するプロジェクトである。具体的には、これらの研究を支えるための高性能コンピュータ高速ネットワーク、アプリケーションの開発を指している。
ここまででHPC法とHPCC計画の4プロジェクトを示したが、HPC法では、HPCC計画の実施体制のあり方についても要求がされている。それを示した部分が、HPC法 タイトル1:「実施体制に対する要求事項」である。
|
(HPC-F1)に対応して、設置されたのが大統領HPCC諮問委員会(Presidentional Advisory Committee on High Performance Computing and Communications)である。
また、(HPC-F2)に関連して、タイトル2では下記7機関に対してHPCC計画への協力を要請している。
| ●国立科学財団(NSF) ●商務省標準・技術院(NIST) ●環境保護庁(EPA) |
●航空宇宙局(NASA) ●国立海洋大気管理局(NOAA) |
| ●エネルギー省(DOE):(※条文ではエネルギー省長官に対する要求) ●教育省(ED):(※条文では教育省長官に対する要求) |
|
また、前頁の(HPC-R1)で示した通りARPA(現在のDAPRA)に対しても協力を要請している。(HPC-P2)の省庁間の協力とは、これら協力を要請した省庁間で協力して4プロジェクトを進めることを指している。なお、実際に、HPCC計画当初からプロジェクトに参加していた省庁は、NSF、NASA、DOE、NIST、NOAA、EPA、ARPAに加え、国立衛生研究所(NIH)の計8機関である。なお、EDは92年度からHPCC計画に参加している。HPCC計画開始当初の実行体制は図表に示す通りである。なお、1992年9月には、HPCCイニシアティブを支援するために、NCO for Computing, Information,and Communicationsが設置された。
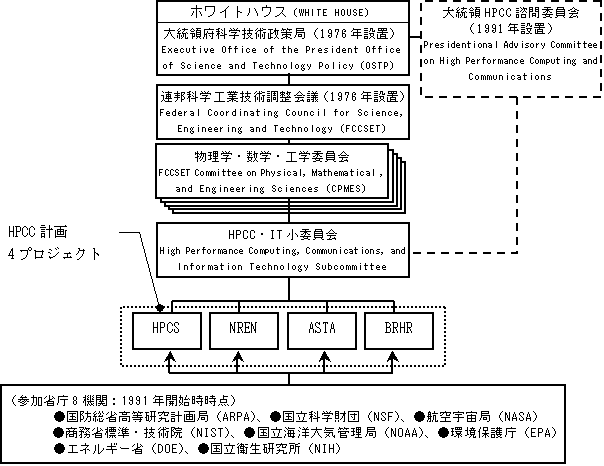 |
|
(Bluebook94, 1994 NSTC Annual Reportを参考に作成)
|
ARPA、DOE、NASA、NSFの4機関は、1989年にHPCCとは別に、独自に計画案を作成しきた。HPCC計画が、当時のその計画を参考に作成されたのかは定かではないが、これら4機関はHPCC計画でも優勢な立場を取ることになる。この4機関がHPCC計画予算に占める割合は、約80%である。
HPC法のネットワーク整備に対する要求事項では、以下の点を注文している。
|
これらの要求事項がHPCC計画当初からプロジェクトに反映されていたかは、現在インターネット上で公開されている資料だけでは把握できない。しかし、これらの要求項目はNII、Global ECにも反映されている。
以上、HPC法成立からHPCC計画のプロジェクト開始までの関係について述べたが、これらの情報政策では、軍事・宇宙開発技術研究で培った成果を効果的に利用する動きが顕著に見られる。現に、HPCC計画以降の情報技術プロジェクトでは、国防総省(DOD)(直轄機関である高等計画研究局(DARPA)、国家安全局(NSA)を含む)・航空宇宙局(NASA)が多くの研究プロジェクトに関わっている。