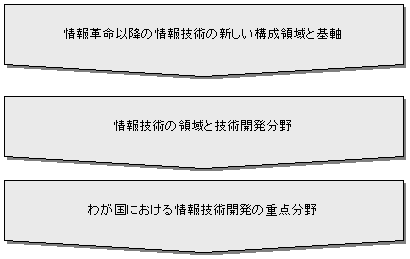
(1)諸外国における情報化ビジョンの動向
情報通信に関する急速な技術革新は、産業・社会に対して、多大な影響を与え始めている。多くの識者は、21世紀にかけて工業経済から情報経済への転換が起こると指摘している。このような変化に対応すべく、各国では情報通信環境を整備し「情報社会」の実現に取り組んでいる。そのさきがけとなったのは、アメリカのクリントン政権が提唱した「情報スーパーハイウェイ」(Information
Superhighway)と関連する一連の情報通信政策であった。ゴア副大統領によるGII(Global Information Infrastructure)構想や1996年にブリュッセルで開催されたG7
情報サミット等を経て、情報化施策が世界各国で活発に展開されている。情報社会の進展は情報産業の育成にも大きな影響を与える。各国では、情報産業をこれからの戦略産業と位置づけ、その育成策にも力点を置いている。
以上のような世界各国の状況を踏まえ、昨年度は、ソフトウェア技術を中心とする情報技術の国際的競争力確保を目指し、わが国の研究開発のあり方を検討するための基礎データ収集の一環として、「先進諸国における将来の社会システムの情報化ビジョンに関する動向」を調査した。
その中では、情報化に関して先進的と思われるアメリカ、EU(欧州連合)
*1 、シンガポール、マレーシアに関して、政府のインターネットホームページから情報化に係わる声明・ビジョン・計画を調査した。また、日本にとって特に重要なアジア・太平洋地域の他国の政府ホームページを調べ、情報化に係るドキュメントが公開されていたオーストラリア、インド、韓国に関しても同様に調査を行った。
今年度は、「情報技術開発における重点分野の調査」の一環として、まず各国に関する昨年以降の動向を調査した。
*1.欧州に関しては国別ではなく、EUレベルの政策を対象とした。
調査対象国
|
(2)わが国の情報技術開発における重点分野の選択指針
諸外国の情報化ビジョンに関する調査に加え、わが国の情報技術開発における重点分野について、図1-1に示すような流れにより、検討を行った。
まず、今後必要となる情報技術の発展方向を、社会・産業の将来像から検討し、今後の情報技術を規定する新しい領域構成の考え方と基軸を設定した。
次に、領域ごとの技術開発分野と開発すべき内容を明確にした。
最終的に、それらの結果を踏まえ、わが国がその領域の中でどの分野に取り組むべきかの考え方、指針を提示した。
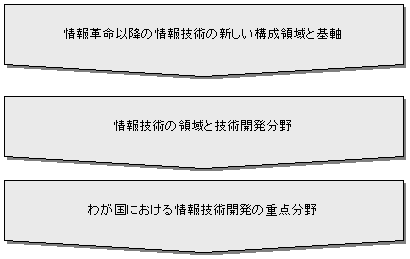
図1.1 調査研究の流れ
1.2.1 各国の動向
(1)アメリカ
2000年2月に発表された、米国の2001年度予算案に見られる情報技術研究開発計画を概観する。
予算案の中でクリントン大統領は、1999年から起こした21世紀基礎研究ファンド(21st Century Research Fund)を強調しており、その要求額は428億9,500万ドルになっている。これは研究開発費予算全体(853億3,300万ドル)の50%であり、非軍事研究としては過去最大の前年比増額(29億ドル)要求となっている。このファンドの狙いは、NIH、NSF、DOEでの基礎研究を中心に、コンピュータ、通信、エネルギー、環境等分野で、基礎と応用の相互に関連する領域の研究開発を組み合わせて、成果を増幅するようなバランスの取れた資源の投資を行うことである。
この21世紀基礎研究ファンドをベースに、科学技術イニシアチブが構成されている。主な特徴は、1)基礎研究の強化と連邦政府研究ポートフォリオのバランス、2)大学ベースの基礎研究の強化、3)NSTCによるマルチエージェンシ研究イニシアチブの推進である。この3)で強調されているのが、新たに加わったナノテクノロジ、バイオベースのクリーンエネルギーとともに情報技術への支援増加である。
この情報技術については、過去10年間にわたって実施されてきたHPCC計画(NGIを含む)と、2000年度予算から盛り込まれたIT2計画を合併して、情報技術研究開発(Information
Technology Research and Development)という新しい計画名称になっている。これはHPCC計画とIT2計画の差異についての理解・認識に混乱があったことを是正するためと国家経済会議の上級スタッフは述べている。この計画ではIT2計画に8億2,300万ドル、NGIに8,900万ドルを含む総額で23億1,500万ドル(35%増)の予算を要求している。特にIT2計画の額は対前年比で166%の増額となっており、科学技術イニシアチブの中で、二番目の伸び率である。
2001年度予算教書とは別に、IT2計画の強化継続策として、5年間というスパンで計画的に情報技術分野への政府支援を行うことを目的とした「ネットワーキング及び情報技術研究開発法(NITRD法:Networking
and Information Technology Research and Development Act)案が、第106議会下院本会議に上程され、2000年2月15日下院を通過し上院に送付された。
この法案は下院科学委員会が提案したもので、1991年のHPC法を修正し、NSF、NASA、DOE、NIST、NOAA、EPA、NIHの研究開発支出を2000年度から2004年度までの5年間についてあらかじめ認可しようというものである。
(2)EU
EUレベルの研究開発政策は、長年フレームワークプログラムとして実施されている。現在は、1998年に始まった第5次フレームワークプログラムが実施されている。 情報関連に関しては、次のような分野のプログラムが設定されており、公募プロジェクト等をとおして、展開されている。
市民のためのシステムとサービス(Systems and services for the citizen)
高品質で利用が容易なシステムとサービスを開発することを目的としている。高齢者・心身障害者看護、保健機関における遠隔サービス、環境問題、交通問題等を重視している。
新しい業務方法と電子商取引(New methods of work and electronic commerce)
事業経営や取引効率を改善するための研究開発を行う。モバイル業務システム、売り手と買い手の取引システム、情報とネットワークの安全性(プライバシー、知的財産権、認証等)を重視している。
マルチメディア関連(Multimedia content and tools)
各種マルチメディア製品・サービスに利用されるインテリジェントシステムやコンテンツの開発を目的とする。会話型電子出版(電子図書館、仮想博物館等)、教育訓練ソフト等を重視している。
重要技術とインフラ基盤(Essential technologies and infrastructures)
情報社会の基盤に必要な重要技術の開発を目的とする。コンピュータ通信技術、ソフトウェア工学、移動体通信、各種センサーインタフェース、マイクロエレクトロニクス等を重視している。
(3)シンガポール
シンガポール政府は、古くから情報技術を比較優位を持てる分野に育成するために、長期的な戦略的投資を行っている。政府は、情報化国家をビジョンとして掲げた「IT2000」を1991年に作成し、その実現を加速するため、1996年にはシンガポール・ワン計画が策定された。これは、シンガポール全土に広帯域の通信インフラを整備し、対話型マルチメディアのアプリケーションとサービスを家庭、学校、オフィスに提供しようというものである。シンガポール・ワンは着実にシンガポールの情報通信インフラの向上に貢献している。
1999年には、IT2000の次の国家計画の策定に着手し始めた。2010年までの基本計画であるICT21(Information and Communication
Technology 21)を起草中である。
(4)マレーシア
マレーシアもシンガポールと同様に、情報産業を国の戦略的産業として位置付けている。マハティール首相は、1991年に行った講演の中で、2020年までに同国を先進国にするという国家目標Vision
2020を打ち出した。今後30年間にわたり年平均7%の経済成長を実現させ、GDPの9倍増、所得4倍増を達成するというものである。その一環として、情報通信産業を戦略的に育成することを推進しており、それを実現するための開発計画がMultimedia
Super Corridor(MSC)である。
MSC計画の中で重要な事業がフラグシップアプリケーションと呼ばれる応用開発である。大きく2つに分けられ、1つは政府が主導し、公共セクター、国民が活用する「マルチメディア開発」である。もう一方は民間企業の活力を利用し、民間企業の活性化を図っていく領域である「マルチメディア環境」である。マルチメディア開発フラグシップアプリケーションとして、電子政府(首相官邸)、多目的カード(Bank
Negara)、スマートスクール(教育省)、遠隔医療(厚生省)が取り組まれており、マルチメディア環境フラグシップアプリケーションとして、研究開発クラスター(科学技術環境省)、ワールドワイド製造ウェブ(通商産業省)、ボーダレス・マーケティング・センター(MDC;
Multimedia Development Corporation)が取り組まれている。これらの中で、電子政府、多目的スマートカード、遠隔医療、スマートスクールの4プロジェクトについては、入札に基づき受託業者が決定された。
情報通信企業を誘致するサイバージャヤは、当初の予定より半年遅れ1999年7月にオープンした。プトラジャヤには首相府が入居し、サイバージャヤでは、プロジェクトの中核事業体であるMDC社等の主要企業が事業を開始している。しかし、進出予定の企業の中にも、インフラ整備状況を見極めている企業も多い様子である。
(5)インド
インドは、情報技術産業を強化し、10年のうちにインドを世界最大のソフトウェア生産国/輸出国とするための政策を展開している。まず、1998年5月、「情報技術・ソフトウェア開発タスクフォース」(National
Task Force on Information Technology & Software Development)を設置し、国家情報政策の立案に着手した。
1998年7月にタスクフォースは、「情報技術アクションプラン」(Information Technology Action Plan)を発表し、10月にはハードウェアに焦点を充てた「情報技術アクションプランパートII」を発表した。
情報技術・ソフトウェア開発タスクフォースは、情報技術アクションプランパート1の実施状況をヒアリング等によりレビューし、2000年3月にその進捗状況を発表した。それによると、108のアクションプランの内、実施済56、未実施27、実施中22、未採用3という状況であった。
(6)オーストラリア
オーストラリア連邦政府のジョン・ハワード首相は、1997年末に「成長のための投資」と題する計画を発表し、その中で今後5年間に12億6,000万ドルを投入し、投資、輸出貿易、新しい高成長産業の革新などを促進していくことを表明した。 情報政策に関しては、情報経済大臣の管轄下に国家情報経済局(National Office of the Information Economy)を設け、次のような情報化政策を推進していこうとしている。
さらに、1999年1月には、「情報経済のための戦略フレームワーク」をリリースした。そこでは、優先課題として、
を掲げている。そして、1999年7月には第1回の進捗レポート、2000年3月には第2回目の進捗レポートを発表している。
(7)韓国
韓国の情報化政策に関する主管官庁は1992年まで通信部と商工部に分かれていたが、同年統合され、情報通信部(MIC; Ministry of Information
and Communication)が新設された。金大中政権発足後は、情報産業がIMF体制克服のための産業効率化における「戦略産業」であると位置づけ、情報化政策を強化推進している。
1995年にスタートした韓国情報基盤イニシアティブ(KII; Korea Information Infrastructure Initiative)に基づき、翌年情報化促進基本計画が策定され、1997年には情報化促進アクションプランが明らかになった。
さらに、1999年3月、韓国情報通信省部は、サイバーコーリア21と題するレポートを発表した。これは21世紀が知識ベース経済へ移行するという認識の下、次の4年間で注力する3つのテーマとして、知識ベース社会のための情報基盤の強化、情報基盤を活用した国の生産性の向上、情報基盤上の新規事業の育成を掲げている。
1998年には、アジアのシリコンバレーを目指した「メディアバレー計画」がスタートした。これは建設中のソウル新空港隣接地域に、広大な埋め立て地を造成し、先端技術を持つ国内外のIT企業を集めた情報産業工業団地を建築するものである。
メディアバレーには、政府と地方自治体の支援のもと、コンベンションセンターや人材育成機関、海外との高速通信網等が整備される。海外企業には、免税措置等多くのインセンティブが与えられる。
1.2.2 まとめ
昨年度及び今年度の調査から、情報技術、情報産業を戦略的に認識し、重点的に投資している国では、社会の情報化、電子商取引等産業の情報化の進展が加速されているという印象を持つ。
その結果は、情報化水準を示す指標にも表れている。たとえば、ワールドタイムスとIDC社が経年的に行っている情報社会指標(1999)によれば、スウェーデン、米国がトップグループを形成し、他国を引き離している。注目すべきは、日本(10位)、イギリス(12位)、ドイツ(14位)といった伝統的な先進国の情報化がここ数年鈍化している反面、シンガポール、台湾、マレーシアなどのアジア諸国が急速に指標を伸ばしていることである。
昨年度及び今年度の調査結果からは、情報化社会指標を高め、情報革命の中で世界的に競争力を高めている国の特徴として、次の点が指摘できる。
情報化が21世紀の国の戦略課題であることの認識
調査した国は、いずれも情報技術が社会、経済に多大な影響を与え、経済活動を効率化し、国民生活を豊かにする上で情報化が極めて重要な要素であることを指摘している。また、情報通信産業を、それを実現するため、経済発展のための戦略産業として位置づけ、国際競争力の強化・育成を図ろうとしている。
また、このような認識の背景として、工業経済から情報経済へのシフトが進んでいること、その中で情報や知識の付加価値が高まることを理解し、産業界等関係者に対する啓発を進めている。
トップレベル組織による強力なリーダーシップ
情報化に係るイニシアティブ、プログラムを、国の元首直轄の組織として統括し、強力なリーダーシップをもって実施している場合が多い。アメリカのクリントン=ゴアや、マレーシアのマハティールのように、国家元首自身がリーダーシップを発揮し、情報化プログラムを推進している場合もある。また、それ以外の国においても、省庁の壁を超えた機能横断委員会を設置し、国家レベルの重要課題として情報化プログラムを推進している。
また、省庁レベルでも、情報と通信・放送の技術的・サービス的融合を踏まえ、ここ数年間で情報産業と電気通信産業の主管官庁を統合した国が多い。
政策立案過程でのインターネットによる対話の利用
情報社会では政策立案過程自体の変革も求められる。各国の政策立案過程において、インターネットが有効に使われていた。インターネットで政策案を開示し、それに対するフィードバックコメントを受け付けているケースが多い。例えば、インドにおいては、インターネットにより政策課題に関して広く意見を集め、計画策定していくという方式を採用していた。
国の役割と民間部門との連携、基礎研究と商用化の連係
国と民間部門との連携も重要な側面である。調査した国の情報化ビジョン・政策では、国の役割として次の点がカバーされていた。
|
一方、民間企業は、パイロットプロジェクトへの参画、研究開発を通した商品化・商用化、起業等によって貢献することになる。商品化や起業化に関して国がどこまでコミットできるかについては議論が分かれる。
他国、他地域との連携
情報社会においては、いろいろな面でグローバル化が進展する。したがって、各国の情報化ビジョン、政策も地球規模の視野を有している。規格・技術標準や取引ルールに関しては、国際標準化機構(ISO)、世界貿易機関(WTO)、世界知的所有権機関(WIPO)といった国際機関との調整が必要であり、また業界におけるワールドクラスのリーダー企業を無視することはできない。また、自国の産業競争力を高めるためには、国際的な分業とアライアンスという観点から自国産業のポジショニングをする必要がある。さらに、技術、資金の国際調達が必要であれば、それに適した優遇税制等の環境づくりが必要である。調査対象国では、他国、他地域との連携範囲は異なるが、いずれも地球規模での情報社会の進展を見通している。
人的リソースの整備と教育の重視
情報技術を開発し、活用していくのは人間自身である。その意味で、研究面、開発面、利用面に係る人材の育成を重要視しなければならない。調査した国においては、アメリカを始め各国で、教育における情報化プログラムの拡充が行われていた。また、オーストラリアでは中国等アジア諸国からの情報技術者の受け入れを支援し、マレーシア、韓国では海外企業の誘致を奨励している。
1.3.1 情報革命以降の情報技術の新しい構成領域と基軸
(1)企業・産業の発展方向とIT
コンピュータが企業に導入されて久しいが、製造オペレーション、経理事務など経営活動のさまざまな領域で情報システム化が進み、業務の省力化が図られてきた。コンピュータの性能向上とともに、通信技術との融合を含め、情報技術が企業経営に占める割合はますます高まっている。その結果、単なる業務効率化・省力化の道具という位置付けではなく、企業の競争力を決定する戦略的な武器という役割も担い始めた。特に、企業間情報ネットワークによって、取引先や顧客との関係の強化や、密な情報連係により大幅なコスト低減や、経営サイクルの劇的なスピードアップが進んでいる。
近年では、インターネットの急速な普及により、電子商取引(Electronic Commerce)が拡大し、その結果、企業間関係や産業構造が再編されるとともに、企業の組織編成のあり方も変わろうとしている。今後次のような変化が新たな情報技術のニーズを創造することになるだろう。
(2)家庭・生活の発展方向とIT
一方、ITや各産業の発展によって家庭・生活も大きく変貌しており、生活の質は加速度的に高まっている。今後も引き続き次のような方向での発展が期待され、それによって新たな情報技術ニーズが生まれる。
(3)情報技術を分類する新しい構成領域と基軸
以上の発展方向からは、情報技術(IT)を捉える軸が新規に追加されたり、重点が移っていることがわかる。本調査研究では、図1.2に示すように、プラットフォーム、コンテンツ、ユーザインタフェースの3つの領域から情報技術を捉えることとする。
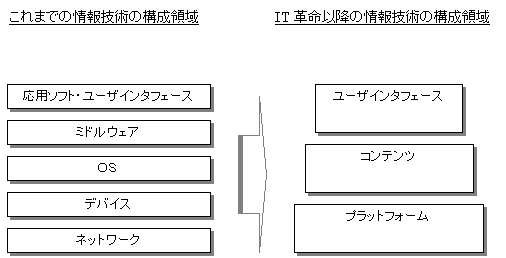
(4)プラットフォーム
プラットフォームは、ITの基本機能である情報処理と通信を提供するレイヤであり、中央処理装置、各種プロセッサー、記憶装置と、内部バス、外部バス、ネットワークの構成によって具現化されるものである。プラットフォームに求められる技術革新の方向は、「高速化」、「広域分散化」、「高セキュリティ化」である。
●高速化
分野を問わず、プラットフォームの処理能力向上は、ITの発展にとって最も中核となる性能改善課題である。
環境・気象・医学を始め科学技術のフロンティアを開拓するためのシミュレーションにおいて、より高速に計算処理することは、解決されることのない永遠の課題である。特に、新たな探求方法である計算科学の進展が今後の科学進歩を加速する原動力であり、計算機の高速化はそのための重要な前提条件となっている。
また、企業・行政の業務アプリケーションでも扱うデータ件数は加速度的に増加し、しかもそれらを瞬時に処理することが求められている。さらには、意思決定の最適化、データマイニング、金融工学、取引仲介のエージェントなど新たな分野・領域にITを利用していく上でも、これまで以上の処理能力が要求される。
●広域分散化
広域分散した機器・プロセッサーが、協調的に情報通信処理するプラットフォームの開発が期待される。
ITの利用形態は、大型計算機による集中的な処理形態から、ネットワークを介し、さまざまな装置が連携しあう分散形態に移行する。インターネットの急拡大はそれを如実に示している。従来のパーソナルコンピュータや端末だけではなく、電話、身に付けられる情報機器、家電等多様な機器がネットワークを介して協調動作することになる。
また、製造業の工場においては既にNC装置・ロボット、搬送装置等を分散制御しているが、今後は複数の工場を遠隔的に監視・制御するバーチャルファクトリーが現実化しつつある。また、電力会社ではより効率的な電源供給を行うために、発電・送電・需要家側の機器が連携し合いながら、計画・制御・監視を行う必要がある。
これらのアプリケーションにおいては、ネットワークを介した分散データへのアクセス、協調分散制御方式の高度化が要求される。
●高セキュリティ化
ITのプラットフォームが広域分散化し、社会の至る所で機能を果たすことになると、停止や誤動作等を始めとする障害が生活・企業活動に大きな混乱や危険を与えることになる。社会が安全で安定的であるためにも、プラットフォームにはこれまで以上に耐障害性の向上、セキュリティの確保といった高セキュリティ化が求められる。
電力・ガス・水道等ライフラインの供給はITによって監視・制御されている。また、高速道路におけるITS、ETCや金融ネットワークに代表されるように社会インフラの多くもITの基盤の上に成り立っている。一般の企業においても、情報システムは基幹業務に直結しており、情報システムがストップすると事業の運営を継続することが不可能になっている。これらのアプリケーションの可用性、安全性を高めるための技術開発とリスク管理が必要となる。
また、広域分散化したシステムやネットワークの中に、重要な情報が流通し、処理が実行されることから、暗号技術を中心としたセキュリティ基盤の高度化も求められる。
(5)コンテンツ
コンテンツは、情報処理、通信の対象となるデータ、情報、知識であり、データベース管理技術、マルチメディア符号化等の技術によって具現化されるものである。コンテンツに求められる技術革新の方向は、「マルチメディア統合」、「異種分散統合」、「概念意味統合」である。
●マルチメディア統合
ITが対象とするコンテンツは、数値、テキスト等の単純なデータオブジェクトから、図形、イメージ等を含む文書、さらには音声、動画等を含むようになっている。
しかし、扱うオブジェクトの種類が多様化しているものの、それらを能率よくディジタル化しデータベースを作成するコンテンツ作成技術や、それらを一元的に管理できる仕組みは必ずしも十分できておらず、今後マルチメディアオブジェクトの効率的作成環境や統合的管理技術の開発が必要である。
●異種分散統合
ITで扱うオブジェクトは、タイプが多様化するだけでなく、地理的に分散し、かつ異なった形式を統一的に処理することが求められる。 異なったリレーショナルデータベース(RDBMS)処理系に対するネットワークを介した統合方式としてはRDAが提案されてきたが、今後はXML等異なったタイプのコンテンツを統合的に扱うことができる機構が求められる。
●概念意味統合
さまざまな形態、タイプのコンテンツを蓄積・管理・活用する上で、コンテンツが有する意味概念、文脈を含めたアクセスパスを用意することが重要である。現在では、テキストオブジェクトに関して意味概念検索機能が提供されてきたが、今後は図形、画像、動画等を含む意味概念検索、さらには状況に応じて必要なものにアクセスできる文脈依存検索等の機能がますます重要となる。
(6)ユーザインタフェース
ユーザインタフェースは、人間とITとの接点であり、そのための入出力技術によって具現化される。ここで入出力技術とは、コンピュータの入出力装置だけでなく、センサーやアクチュエータ等も含んでいる。ユーザインタフェースに求められる今後の発展方向は「マルチモーダル」、「人体・環境との一体化」、「擬人化(AI化)」である。
●マルチモーダル化(五感化)
コンピュータはこれまで数字、文字列等を中心に入出力が行われてきたが、高度なユーザインタフェースの一つの方向は、人間の五感をサポートすることである。ITが、人間活動の創造的・知的領域や、娯楽・エンターテイメントの領域に関与していくためには、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚を駆使したインターラクションが求められる。
●人体との一体化
マルチモーダル化とも関連してユーザインタフェースは人体と一体化する方向に向かっている。現在では、携帯情報機器、携帯電話等小型で持ち運び可能な端末が実用化されているが、それがウェアラブル(身に付けられる)になり、さらには身体への接近が進む。
●擬人化(AI化)
コンピュータを機械としてではなく、人間レベルでコミュニケーションし、やり取りすることは、コンピュータの用途を広げ、より知的なレベルで人間の支援を行う上で重要な要件である。具体的には、自然言語による理解・創作、音声による認識・発話や、知識の獲得、蓄積等の高度化が必要であり、人工知能(AI)、知的インタフェースの応用が望まれる。
1.3.2 情報技術の領域と技術開発分野
これまで情報技術はプラットフォーム技術を中心に発達し、「情報技術≒プラットフォーム技術」と捉えられてきた。ところが、パソコン、インターネット、携帯情報機器の出現とその発達、普及により、情報技術の及ぶ範囲が、従来の科学・工学、文書作成・事務作業等から、ビジネス全般、日常生活にまで広がり出した。これにより、情報技術の扱う対象が従来の数値や図形から、より人間に身近な音声や映像などに拡大している。今や、それらがどのようなメディア(データ形式)かということより、どのような中身かを問うことの方が意味のある視点となっている。それらの対象を「データ」でなく「コンテンツ」と呼ぶことが多いのはこの事情を反映している。
また、従来、プラットフォームはそれが使いやすい場所と方法で利用されてきたが、ユーザ層・場所・用途が広がった結果として、新たな相手と状況により適したユーザインタフェースの実現が重要となった。逆に、改良されたユーザインタフェースはさらに情報技術の適用範囲を広げる。
このように、コンテンツ、ユーザインタフェースの領域が大幅に拡大した結果として、情報技術の重心が従来のプラットフォーム中心から移動しつつある。新しい情報技術を捉えるパラダイムは、もはや従来の「プラットフォーム中心」でなく、「3つの領域(プラットフォーム、コンテンツ、ユーザインタフェース)から構成される技術の総体」が適切である。「目的はコンテンツとユーザインタフェースの実現にあり、その手段がプラットフォーム技術である」と理解することが適切な場面が増えるであろう。情報技術が社会経済一般や娯楽・芸術にその対象世界を広げるにつれ、情報技術を担う人材も従来の情報技術者を中核としながら、各分野の専門家・従事者にまで広げて考えて行くべきであろう。
このように、情報技術は内部的なバランスを変化させながら、全体として産業・経済・社会全体における比重が大幅に増大する(その中で、プラットフォーム技術の絶対的重要度も高まる)。そして、情報技術の成長発展が今後の経済社会の発展の重要な部分を担うと予想される。
以下、各構成領域において、今後5年〜10年スパンで重要なものとして研究されうる主な技術及び課題を示す。
(1)プラットフォーム
プラットフォームの領域では、高速化、広域分散化、高セキュリティ化の方向への発展が求められ、それらを実現する技術も現在急速に発達中である。より高速な計算機の構築を目指す計算システムの研究、現状のインターネットの百倍〜千倍以上のバンド幅を持つ広域高速ネットワークインフラの構築が進んでいる。また、計算・データベースと広域ネットワークが融合したグローバルコンピューティングや電子図書館といった新しい研究開発分野が生まれている。これらは、現在の電力網や公共サービスのインフラに匹敵する、計算インフラ、情報インフラの実現を目指すものである。
プラットフォーム技術は、コンテンツやユーザインタフェースの前提となる技術であり、まさしく情報技術のプラットフォームとして絶対的な重要性が減ずることはない。
アーキテクチャ&新計算モデルの階層、基本ソフトウェアとミドルウェアの階層、応用システム&応用分野の階層に関する重要な技術分野は下図のとおりである。
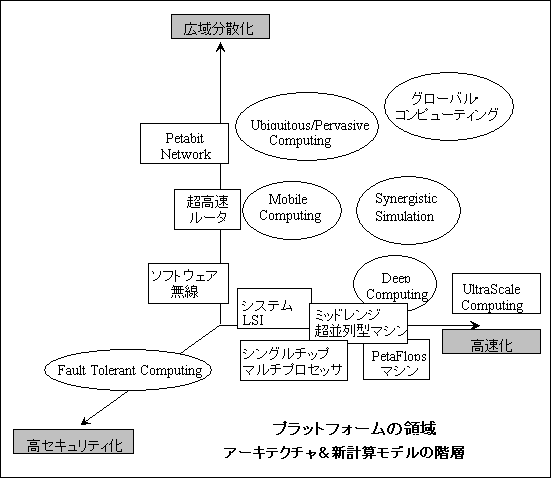
図1.3 プラットフォームの領域
(a)アーキテクチャ&新計算モデルの階層
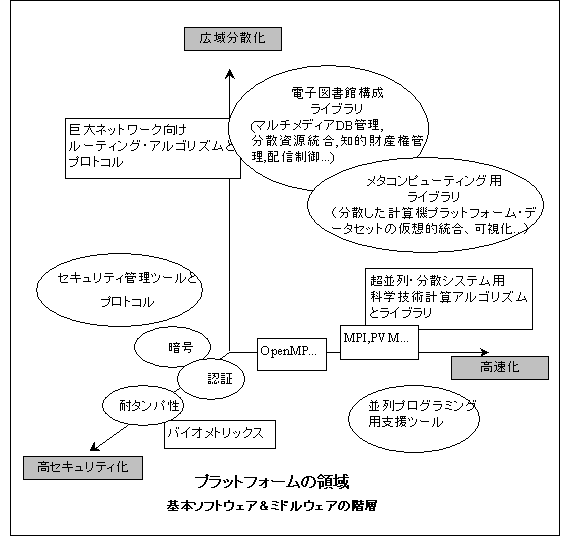
図1.4 プラットフォームの領域
(b)基本ソフトウェアとミドルウェアの階層
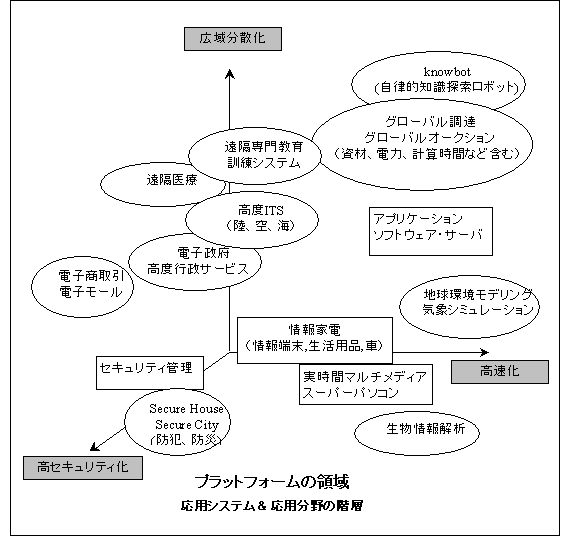
図1.5 プラットフォームの領域
(c)応用システム&応用分野の階層
(2)コンテンツ
今後、情報技術があらゆる経済活動を把握し、管理・分析・効率化等に関わることを目指すとすれば、経済活動の対象となる実世界のあらゆるものの仕様、性質などの電子的表現が必要となる。また、著作物などの知的財産、ひいては文化資産全般の電子化にまで、ニーズは広がり、実現技術が開発されるであろう。
インフラ整備としては、商品・製品の電子的表現(仕様、性質、機能など商取引上の必要・参考情報など)などの標準化、国土の詳細な地理情報、各国語に対応した電子辞書、概念の辞書、さらには知識を集大成したエンサイクロペディア、などの基礎的コンテンツ(インフラコンテンツ)が重要となろう。これらインフラが整備され(望ましくは社会の共有物として無償で公開されれば)、その上に様々な用途向けインフラ(ミドルウェア・コンテンツ)、応用(アプリケーション・コンテンツ)が発展すると予想される。コンテンツには人類共有財産もあり、また文化的財産もあり、後者についてはそれぞれの文化圏において整備が必要である。それは文化圏間のコンテンツ電子化の競争であり、また、各文化圏が固有性を確保するための重要な政治社会的な手段ともなろう。
このようなコンテンツをベースとして、現在、新聞や雑誌、ラジオやテレビが供給している文字情報、音楽情報、映像情報などがディジタル化され、仮想現実などと結びついて新しいコンテンツ・ビジネスの世界を作り出すことが考えられる。
コンテンツのカバー範囲が拡大して行くためには、知識表現、情緒表現の基礎研究が必要である。また、実世界の事物の電子化のためには、紙媒体の書物・資料のデジタイズ技術(画像レベル、文字情報レベル)、三次元物体のデジタイズ技術など様々な観測技術の研究開発や、衛星画像からの地理情報の作成などの認識技術などの研究開発も重要となる。
コンテンツは表現技術で終るのでなく、表現されたコンテンツを活用する際に、コンテンツに関する財産権、プライバシーなどの問題が生じる。それらに関する法的な取り決め、権利関係を処理する機関ないしインフラの整備等をすることが、コンテンツ作成・利用に関する経済社会活動を可能にすることにも注意が必要である。
コンテンツの領域の有力な研究分野及びインフラ整備課題と考えられるものを下図に示す。
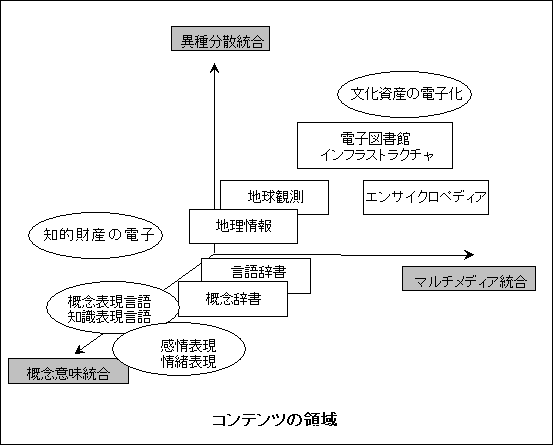
図1.6 コンテンツの領域
(3)ユーザインタフェース
ユーザインタフェースの目指す方向は、人間に密着し、人間の意図を理解し、個人の活動を支援すること、さらには個人の活動を増幅することである。また、その延長として、グループワークにおけるコミュニケーションや協働の支援を行うことや、環境との相互作用を仲介することも、ユーザインタフェースの目的に含まれるであろう。
また、理性的な活動のアシストだけでなく、快適さを与えたり技能を訓練する等、物理的存在としての人間の状態を安定化させたり向上させたりするためのユーザインタフェースも社会経済的な重要性を持つだろう。活動支援のためには意図を正確に理解することが必要だが、環境としてのユーザインタフェースではそのような正確性は求められず、また環境側からの働きかけが主になるため、アシストのためのユーザインタフェースよりも、むしろ実用化は早いと考えられる。
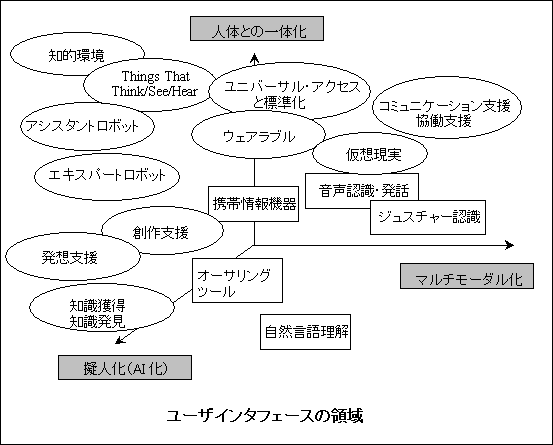
図1.7 ユーザインタフェースの領域
1.3.3 わが国における情報技術開発の重点分野選択指針
本調査研究では、情報革命以降の情報技術革新を的確に捉えるための情報技術の新たな構成と基軸を示し、その中での技術開発領域を検討してきた。最後に、そこから考えうるわが国における情報技術開発の重点分野選択指針を示す。
研究開発の重点化の必要性
安定成長、成熟時代においては、研究開発投資の効率性・有効性が問われる。アメリカを先頭とする世界的な情報技術開発競争の中で、フルラインで取り組み、全領域で良好な研究開発成果を達成することは現実的に難しい。何らかの考え方、戦略に基づき重点分野を明確化し投資を集中することにより、わが国の情報技術開発の成果を高め、情報産業の競争ポジションを向上させることができる。
技術開発領域に関する基本的認識
本調査では、情報革命に伴う情報技術の適用領域の拡大等によって、従来の情報技術の中核部分だったデバイス、コンピュータ、周辺装置、ネットワーク等を総合的に「プラットフォーム」として捉え、今後技術革新の高度な発展が期待される「コンテンツ」「ユーザインタフェース」をそれと同列に位置づける構成を提示し、その各領域において想定される技術開発分野を検討した。これらの技術分野に対して、わが国の重点分野を考える上で、まず第一に次のような基準が基本として考えられる。
その結果、領域レベルに関しては、次の点が指摘できる。
以上のような基本認識に基づき、各技術領域ごとに重点分野選定の指針を示す。
●プラットフォーム
プラットフォームに関する基礎研究においては、前述のように、アメリカの長期にわたる研究が先行しており、アメリカの状況をフォローしながら、キャッチアップしていかなければならない分野が多い。研究成果が開示されていたり、Linuxのようなオープンソース化されているものについては、それらを導入し、改善型研究を行っていくというアプローチが可能であり、わが国が得意としている方法でもある。
一方、短期的な技術開発では、情報家電、携帯電話、ゲーム機器、工作機械といったわが国が強みを持ったコンポーネントを活かしていける可能性がある。この点に関しては、産業界に負うところが多いが、国としても規制緩和や競争促進、標準化支援等の施策を積極的に行うことによって、日本発の次世代型プラットフォームを開発することを支援できる。
●コンテンツ
わが国は、ゲーム機器、ゲームソフトの分野では世界的に高い競争力を有している。今後良質なコンテンツを作る上では、ハイパフォーマンスコンピュータを援用したコンピュータグラフィックスの応用が重要となり、ゲーム機器等のエンターテイメント系コンテンツ開発用ミドルソフトでわが国がリーダーシップを握ることは可能である。
また、わが国は、アジア文化圏、漢字文化圏の中で最も高い技術力と経済力を有している。そこで、漢字及び多文化・多言語を扱うためのコンテンツ作成・管理・活用のための技術開発を行い、これらの文化圏に貢献していくことが望まれる。マルチバイト系文字コード、フォントに関わる処理技術、アーキテクチャ開発等が求められる。
知識の管理は、言語処理、テキスト処理、概念検索といった要素技術に加え、人間及び集団がどのように知識を創造し、管理、活用しているかという知識管理プロセスモデルが重要となる。わが国における知識創造プロセスや、組織的品質管理に関する研究実績を活かした技術開発が求められており、知識管理のための要素技術及びミドルウェアの開発も重点分野の一つとなろう。
コンテンツに関しては、要素技術や方式の研究開発だけではなく、現存する様々なデータを電子的表現化(ディジタル化)するコンテンツ作成技術や作成環境の研究開発、商用化、普及促進のためのインフラとなるコンテンツ作成やそのデータベース整備も重要な政策課題といえる。言語処理、知識処理のための辞書・シソーラスや、地図情報等の整備を支援することも国の役割といえる。
●ユーザインタフェース
ユーザインタフェースでは、コンピュータシステム内で行われる複雑な処理結果をいかにわかり易く人間に伝達するかというコンピュータから人間に向かうインタフェースの高度化が先行している。仮想現実(VR)などがそれに当たる技術であり、この分野の研究ニーズは今後ますます高まると思われる。
もう一つは、人間からコンピュータへ向かうインタフェースである。ここでは知識処理技術が中核技術の一つであり、わが国の人工知能研究の実績を活かせる分野である。今後は感性情報処理、マルチモーダル等非言語系の情報処理の重要性が高まり、これらは非英語圏であることの弱みが影響しない分野でもある。
また、パッケージング技術や、材料技術等の優位性を活かしたウェアラブルコンピュータの開発が重点となると考えられる。