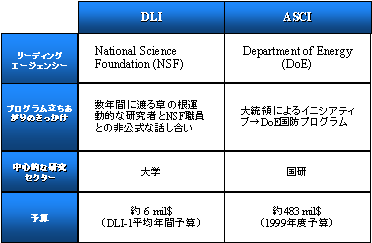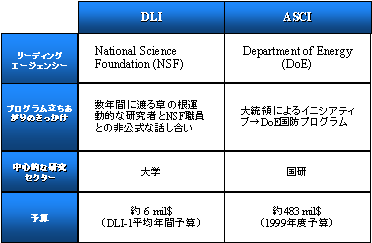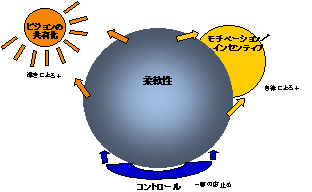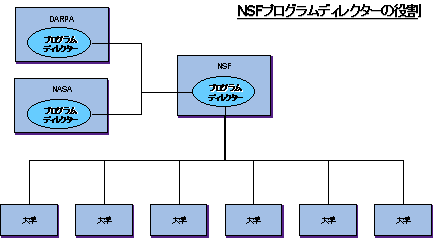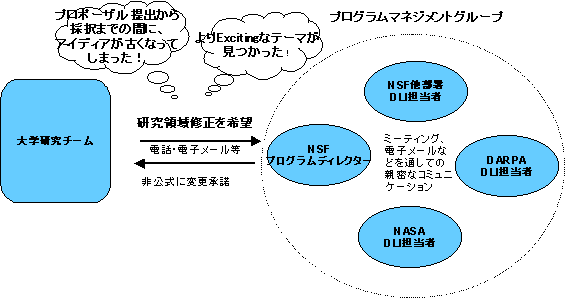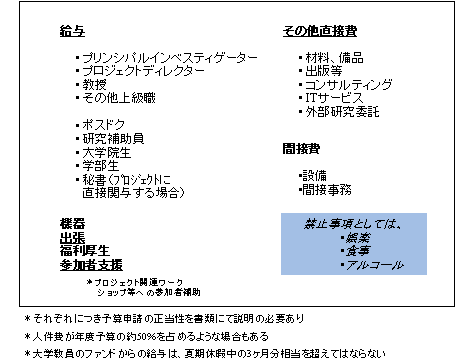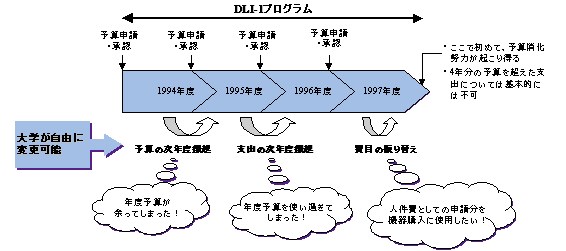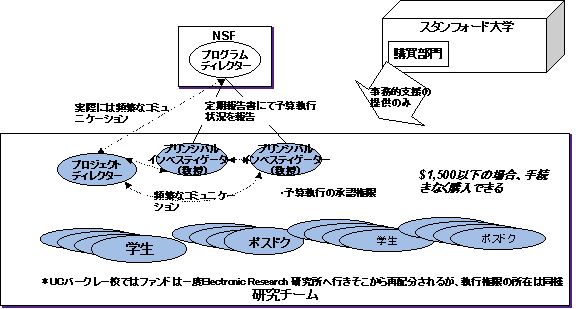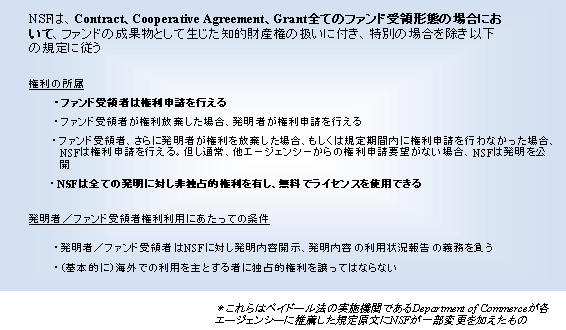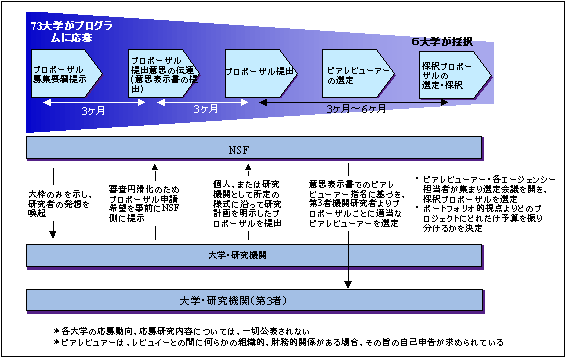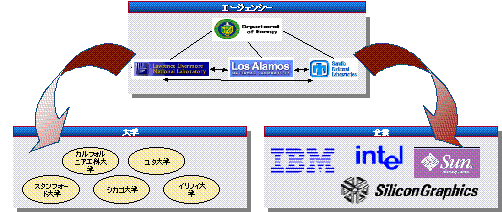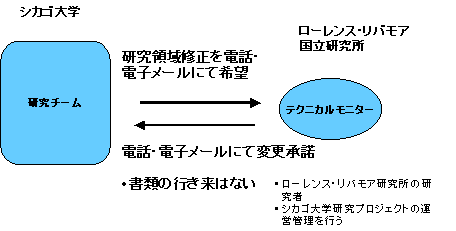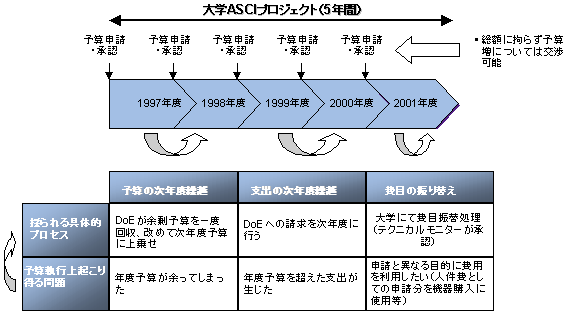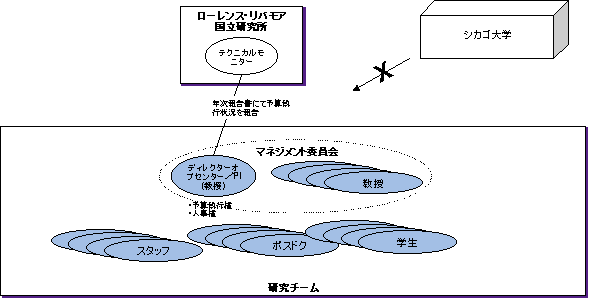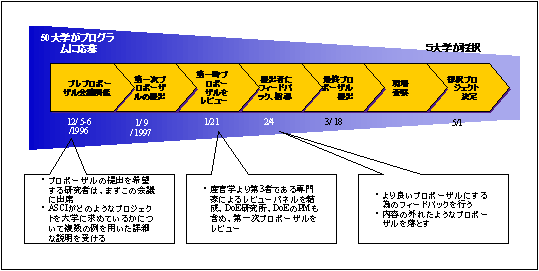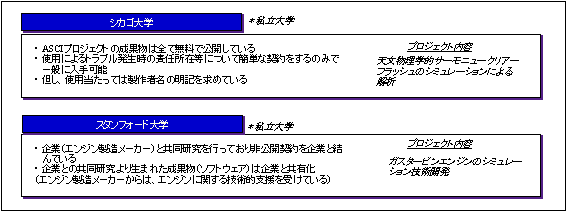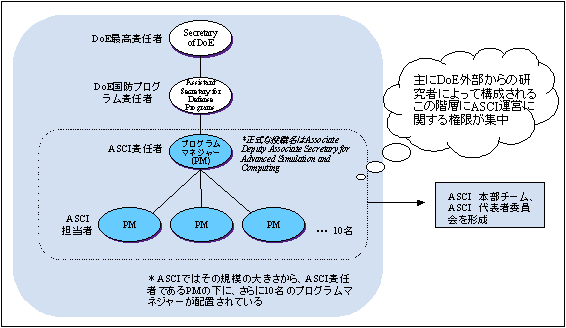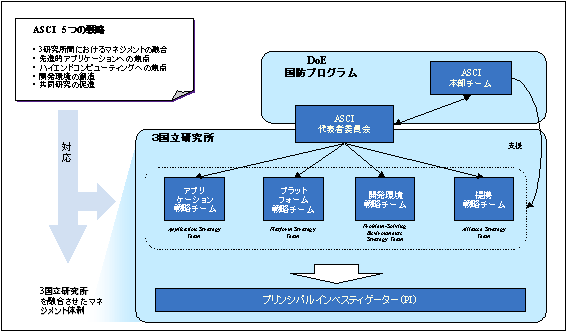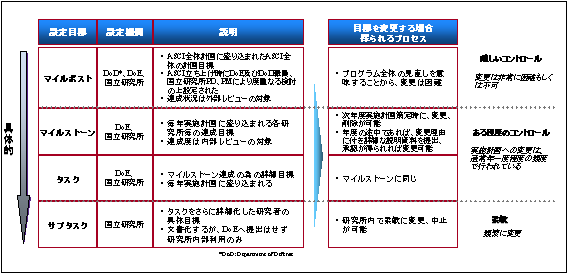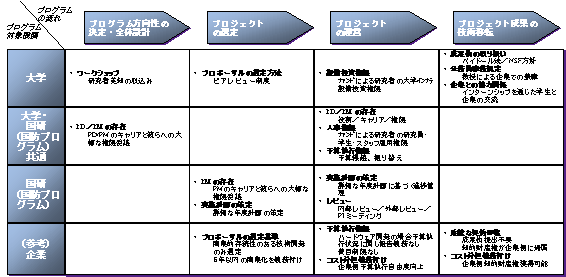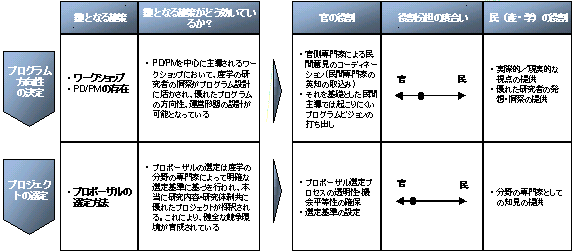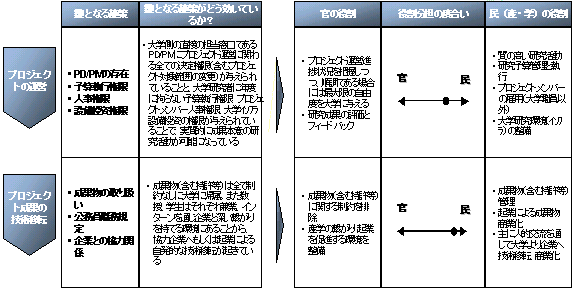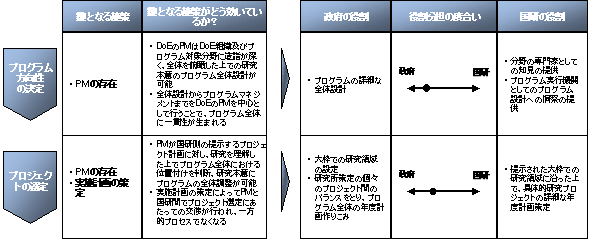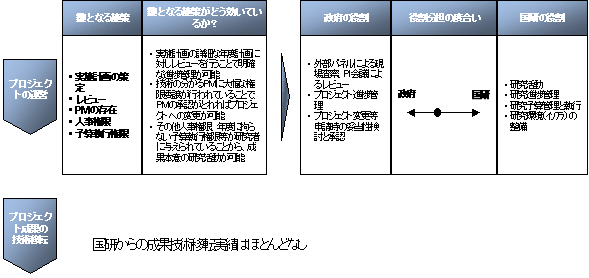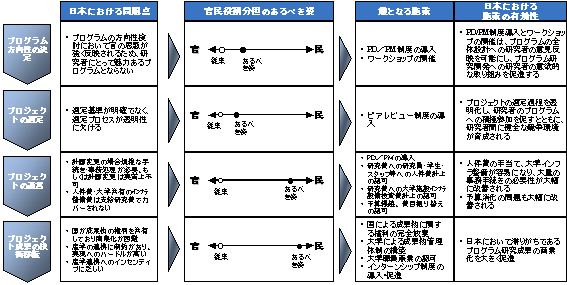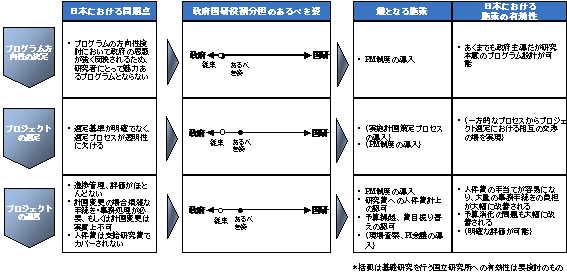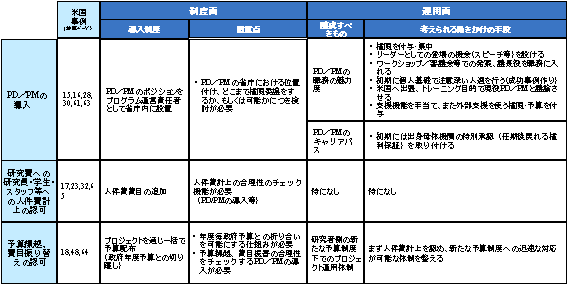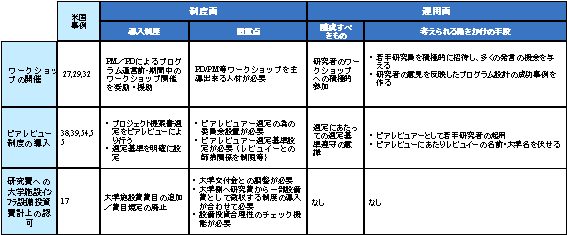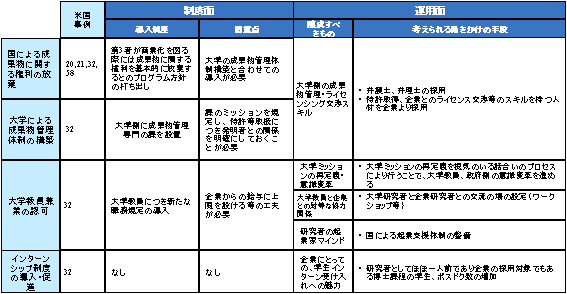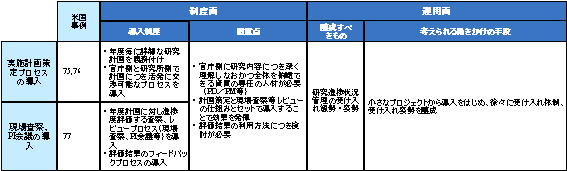【前へ】
第3章 米国連邦政府支援研究開発計画における 大学・国研の独立性と権限
情報革命の到来に向けて、わが国の先端情報技術のR&Dを強化するためには、国の重点投資と関連する仕組みや法制度の改革が必要不可欠であることが明らかになってきた。
米国は1970年代末よりこれを実施してきた。一方、わが国は旧態依然たる仕組みや法制度を温存したため、国の投資効果が阻害されるような状況となっている。
本章では、米国の国家プロジェクトのマネジメントの仕方を多くの事例によりできるだけ解り易く解説する。これらの事例は、アーサー.D.リトル(ジャパン)株式会社に調査委託して、米国の国家プロジェクトのプログラムマネージャーへのインタビューを行い、とりまとめたものである。
3.1 はじめに
(1)調査の背景と目的
現在わが国では、国立研究所や大学の独立行政法人化(エージェンシー化)が検討されており、一部、2001年度からの実施が予定されている。これらは国立研究所、大学などに研究の実施、運営に関する決定権限を委譲することで、競争原理を導入し、研究の活性化、人材の流動化を図ることを目指したものである。
本調査では、日本の国立研究所、大学の独立行政法人化に際しての権限の委譲、仕組み、制度作りに対し何らかの示唆を導出することを目的として、多くの産業のシーズとなる技術や起業家を輩出している米国の大学や国立研究所における政府主導研究開発プログラム事例について調査、分析を行った。また特に、研究者が研究開発に意欲的に取り組み、予算を研究開発本意に有効に活用できるようにしている、柔軟な管理運営の仕組みに着目した。
(2)調査対象範囲
本調査は、以下の点で大きく性質の異なるDigital Library Initiative(DLI)、Accelerated Strategic Computing
Initiative(ASCI)の2プログラムを対象として行った。
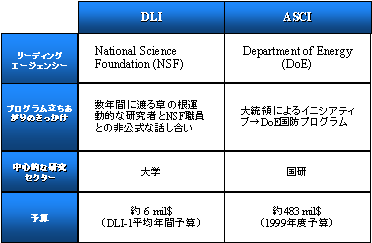
調査対象とする管理運営権限(機能)は、研究テーマ選定、実施管理、事後の取り扱いとし、主対象としては、1)研究者の選択(提案採択のメカニズム、外部との共同研究体制構築プロセス)、2)予算配分・管理(予算費目、通年度予算メカニズム)、3)プロジェクトの運営(予算、テーマの評価、目標変更や期間延長も含めた変更・打ち切りなど)、4)成果の管理(特許、ソフトウェアの著作権など)、5)
成果物の帰属(ベイドール法適用、企業との共同研究の条件決定権など)の5項目とした。
また、調査対象階層はエージェンシー以下の階層とした。
(3)検討の視点
研究者の活動に与えられる大きな柔軟性の背景には、それを支えるものがバランスして存在している。それには“ビジョンの共有化”、“モチベーション/インセンティブ”による+側への引きと、"コントロール"による−側の押さえの両面がある。本調査では各プログラムについて、これら総体の仕組みがどのように形作られているかとの観点から整理分析を行った。
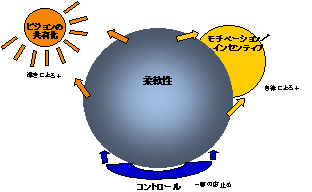
(4)本章の構成
続く3.2節、3.3節において、それぞれDLI、ASCIにおけるプログラムマネジメントの状況について説明し、3.4節でそれまでのまとめを述べる。さらに、3.5節においてそこから導き出される日本への示唆について、検討を加える。
3.2 ケーススタディ1:DLI(Digital Library Initiative)
3.2.1 DLIの概要
DLIは「電子化情報を収集、保存、整理する方法を著しく進歩させ、コミュニケーションネットワークを通じたユーザーフレンドリーな検索、情報入手、情報処理を可能にする(DLI-1)」ことを目的とする、National
Science Foundation(NSF)を中心とした産官学による共同プログラムである。エージェンシーのプログラムディレクター、研究者の作るコミュニティーの草の根的活動がやがてワークショップの開催へと結びつき、その結果として1994年から1998年に掛けDLI‐1が実施された。
DLI‐1では6つの大学が資金提供先として選ばれ、プロジェクトを実施した。DLI‐1の成果は、Inktomi、Google、LYCOS等の検索エンジン関連企業の起業に繋がっており、産業活性化の意味からDLI-1は非常な成功を収めたプログラムであると言える。
現在、DLI‐2が1998年から2002年までの計画で実施されており、資金提供先の選定が引き続き行われている。
企業のDLIプログラムへの参加は大学を通じて行われており、NSFと企業と直接のコンタクトは特に行われていない。しかし、NSFは大学が企業と共同で研究を行うことを奨励している。
3.2.2 DLIにおける柔軟性
NSFプログラムディレクターの役割
- DLIにおいては、NSFがプログラムの主体でありNSFのプログラムディレクターに参加大学への承認権限は一任されている。これによりプログラムがエージェンシー間にまたがることにより起こる手続きの硬直化、煩雑化を防止している。
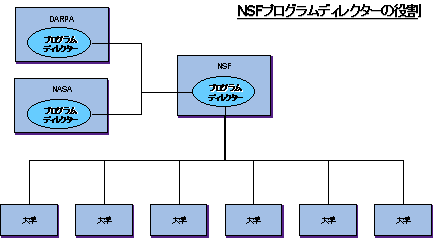
- NSFプログラムディレクターの役割は、研究領域への変更最終承認、プログラムの設計、各大学研究状況の把握・場合によってはアドバイス(報告書、現場視察、研究者との非公式なコミュニケーションを通して)、DARPA、NASAとのコミュニケーション、DLI関連ワークショップの開催等であり、研究チームが研究領域についての修正を希望する場合には、NSFプログラムディレクターは他エージェンシープログラムマネジャー/ディレクターと共に構成しているプログラムマネジメントグループの同意の上に承諾を行う。変更過程は電子メールなどでの簡単なやりとりであり、非常に柔軟な対応が可能である。書類上ではこの変更は次回の四半期報告書/年次報告書上に新たなテーマについての報告が突然現れる形となり、変更に伴う事務手続きは必要ない。なお、プログラムマネジメントグループ間でははミーティング、電子メールなどを通しての親密なコミュニケーションが図られている。
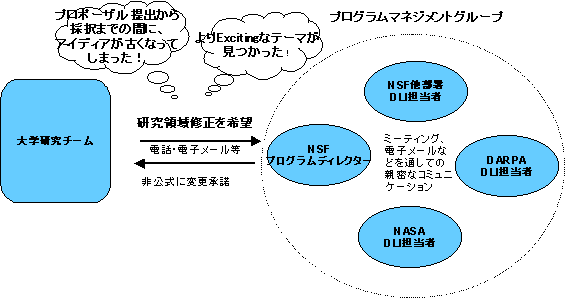
予算に関する規定
- 予算規定は、全てNSFの規定に従っている。特に研究者人件費、秘書等事務職員人件費に予算が適用できることが、予算規模に応じた柔軟な人事を可能にしている。NSFファンド予算費目は以下の通り。
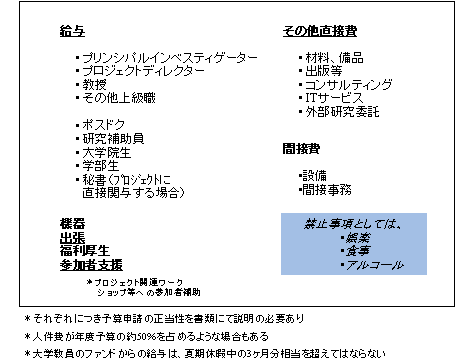
- 人件費が予算によってカバーされることから、大学内でのDLIに関する人事は、大学職員以外は全てプリンシパルインベスティゲーターの裁量により採用・待遇を含め決定が可能である。大学職員人事に関しては、大学が全権を握っている。
- 予算執行に関しては、年度ごとに予算申請が義務付けられているものの、4年間のプログラム実施期間内においては予算・支出の次年度への繰越、費目の振り替えも大学側が自由に行うことができ、年度末予算消化などの問題は起こらない。
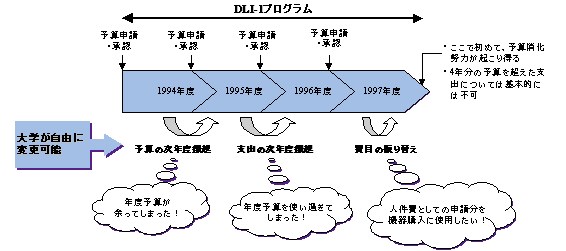
- 大学と研究チーム間を見てみると、大学は予算執行に関しては一切管理・介入は行なわず、支援の提供のみを行っている。スタンフォード大学では2人のプリンシパルインベスティゲーター(PI)がDLIプロジェクトに関する予算執行の公式な権限を有し、実際には各研究責任者が各々の判断で支出を行っている。
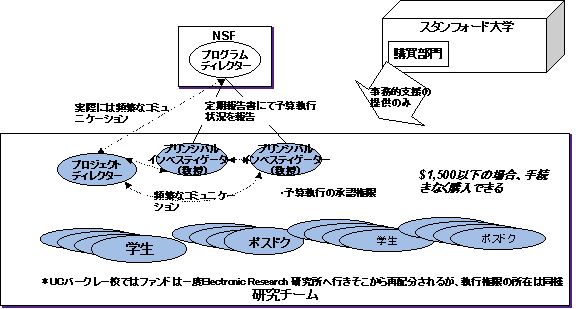
成果物の取り扱い
- 成果物に関しては、DLIでは、Contract、Cooperative Agreement、Grantの3種類のプログラム運営形態のうち主にCooperative
Agreementと呼ばれる形態が採用されており、大学側に成果物の提出は一切求められていない。また、研究より生じた知的財産権に関しても取り扱いは全く大学に一任されており、大学では組織だった支援の仕組みが機能している。これらのことから、成果として生じる知的財産権の商業利用は非常に容易。
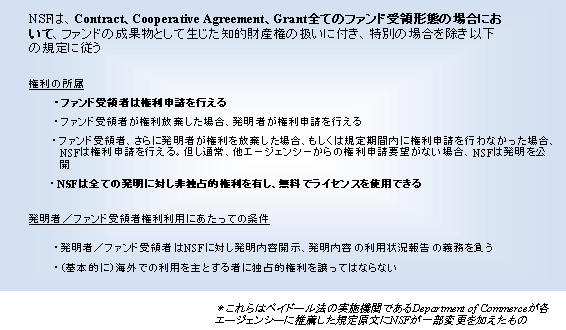
企業との連携
- DLI参加大学は、政府エージェンシー以外の企業、研究所等よりSatellite sponsorとして何らかの形で支援を受けることが強く奨励されている。しかし、大学と企業間の関係には政府は一切介入せず、この関係は大学研究チームと個別企業間の事情に合った協定により成り立っている。DLIでは政府ファンドと企業等による支援の割合は50:50にもなっており、スタンフォード大学のケースでは、支援企業は15企業。
3.2.3 DLIにおけるビジョンの共有化
ワークショップの開催
- DLIの研究対象領域であるデジタル図書館の概念は、NSF主催の度重なるワークショップによって、定義・再定義されてきている。これらのワークショップは、DLI研究者コミュニティーの形成に大きく寄与している。
- ワークショップは産官学より対象分野関係者が出席し、数日間をかけて行われる。このワークショップの存在によって、産官学からのニーズ・視点を反映したビジョンの構築が可能となっている。DLI‐2の枠組を議論したサンタフェワークショップでは、対象研究領域についてにみならず、プログラムの運営体制についても活発に議論され、DLI-2での運営体制に反映された。
プログラムディレクターの資質
- エージェンシーの担当プログラムディレクターは当該分野研究者としても一流であり、プログラムマネジメントグループ、大学研究者より絶大な信頼を受けているため、研究コミュニティーにおいて信頼できるメンバーとしてビジョン共有化過程におけるコーディネーターの役割を務められる。
- DLI担当のNSF プログラムディレクターの経歴
- 対象領域の研究者としての深い理解(情報 ・意思決定システムで博士号保有)
- プログラム立ち上げに中心的役割を果たし、マネジメントプランなどの作成も手掛ける。以来6年間(1994-)DLIの運営の担当責任者
- 上司(ディビジョンディレクター)とのミーティング義務はパフォーマンス評価の為の6ヶ月に1度のミーティングのみ。実質上は"同僚"(専門領域におけるピアー)。
- 大学側、各エージェンシー側から非常に高い評価
(参考)NSFでは、プログラムディレクターの65%が正式職員、27%が他エージェンシーからの出向者であり、約7%が数年間エージェンシーに勤務した後、研究に戻るローテーター。
コミュニティーにおける信頼関係
- これらのことから、産官学においては、厚い信頼関係に基づく研究コミュニティーが形成されており、これがビジョン共有化実現の重要な下地となっている。
3.2.4 DLIにおけるモチベーション/インセンティブ
大学研究者・大学のDLI注力へのモチベーション
- 大規模な未踏分野への挑戦
- 大規模でリスクの高い研究の結果、インパクトの高い論文がキャリアになる
- 大規模でリスクの高い研究により、研究者としての知的好奇心が満たされる(競争の結果、知的好奇心が旺盛で野心的な研究者しか一流大学教員にはいない)。
- プログラムへの研究者ニーズの反映と、当時者意識の強さ
- プログラムのコンセプトにつき研究者を招いてワークショップを開催、結果を反映させたプログラム設計を行っており、為研究者側のニーズ・興味が反映されている。また、プログラム設計より関わることで、当事者意識が生まれる。
- ファンド獲得によるメリット
- 研究者側としてはファンドから給与を受けられる、また優秀な研究者を雇える
- 大学側にとってはファンドの一部は大学間接費(施設費・人件費)として収入となり、そのため研究者にとってはファンドをとることがテニュア獲得に有利に働く
- 企業での活躍の機会
- 大学職員であっても研究領域の強みで企業で活躍、給与をもらうことが可能。大学職員は大学から支給される9ヶ月分給与の他、3ヶ月分を稼ぐことができる。また、PhDの学生にとっては、企業との共同研究の場が豊富に用意されており、企業研究所と交流を深めつつ就職の可能性を模索できる。
- 研究成果の知的財産権を利用した起業の可能性
- 研究成果として生ずる知的財産権は大学に帰属するため商業利用が容易であること、ベンチャー支援制度が整っていることから、研究者が自らの研究結果を利用して起業することが可能である。また、大学は知的財産権をライセンスアウトすることで莫大なロイヤリティー収入を得られる。
企業のDLI注力へのモチベーション
- 大学との共同研究を通じたリクルーティング
- 共同研究を行うことで、将来性の高い優秀なPhDの学生を惹きつけ、採用することができる。
- 大学との共同研究を通じた研究所のIntellectual reputationの維持・向上
- "開発"ではなく"研究"を行うXerox PARCなどの研究所では、学術的評価の高い大学と共同研究を行うことでその知的評判を維持、向上させることが重要。
- 大学と共同研究を行うことで、研究指向の研究所研究者のモチベーションを維持。
- 大学との共同研究を通じた先端技術へのアクセス
- 先端技術に造詣の深い共同研究先のPhDの学生をサマータイムジョブ等で一時的に雇用し、研究所へ先端技術の導入を図ることができる。また、その間に学生が出した研究成果については企業の保有となる。
- 課税負担軽減
- 大学研究を資金・備品提供等により支援することは、税制優遇処置の対象。
3.2.5 DLIにおけるコントロール
報告・視察受け入れの義務
- プロジェクトの開始から終結まで、四半期ごと、年度ごと、プロジェクト終結時に研究報告書の提出義務、さらに2年に一度のエージェンシー職員による一日掛りの現場視察が行われている。結果に対する評価プロセスは存在しないが、プロジェクト終結時の次期プロジェクト継続可否が評価を反映したものとなっている。
プロポーザル選定
- プロポーザルの選定は専門家によるピアレビューによってなされる。応募者と関係のない全米各地のピアレビューアーとエージェンシー職員とがワシントンに集い、各プロジェクトを評価、採択プロポーザルを決定する。
プロポーザル選定プロセス
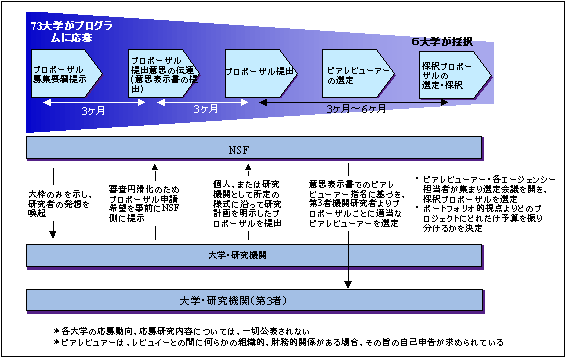
- DLIプロポーザル評価にはNSF規定評価基準に基づいた基準が用いられた。特に注目すべき点は、研究チームの組織・管理体制の十分さも大きな選定要素となっている点である。
3.3 ケーススタディ2:ASCI(Accelerated Strategic Computing Initiative)
3.3.1 ASCIの概要
ASCI開始の経緯
過去50年間に渡り米国は核兵器の製造と管理を行ってきており、核兵器の性能・安全性・信頼性維持の方法論は伝統的に主に核実験を実施することで、国立研究所、製造施設により開発されてきた。
また一方で、科学者、エンジニアは最先端の物理学の知識を核貯蔵管理へ適用する試みを重ねてきており、これは核兵器性能の数学的予測を徐々に可能にしてきた。
コンピューター性能の向上に伴いこのような数学的予測はコンピュータープログラムへと形を変え、兵器設計者に高度な情報提供をできるようになり、また多くの経験則がコンピューターコードへと変換されコンピューターコードの更なる改良が進められたことから、現在では、コンピューターによる計算と実験は大きく相互依存している。
このような状況下、クリントン大統領による"ゼロ・イールド"包括的核実験禁止条約の提案を受け、DoEを中心として1995年にASCIプログラムが立ち上げられた。
ASCIのミッション
ASCIは"核実験主体の方法論から早急にコンピュテーション主体の方法論に移行する" ため、米国核兵器貯蔵の安全性、信頼性を維持し核の危険性を減少させる上で欠くことの出来ない最先端のコンピュータモデリング、シミュレーション能力を創造することをミッションとしており、2010年までに、以下を実現することが期待されている:
- 兵器設計、生産分析、事故分析、検定を行える、高性能、フルシステム、高信頼性を有するコードを開発
- 米国コンピューター製造産業を刺激し、これらのアプリケーションが必要とするより強力なハイエンドスーパーコンピューティング能力を開発
- これらのコンピューティング能力へのアクセス、利用を可能とするコンピュータインフラストラクチャー、オペレーティング環境を実現
ASCI運営体制
ASCIプログラムでは、DoE所属の3つの国立研究所を中心として、大学、企業を巻き込んだ運営体制が構築されている。
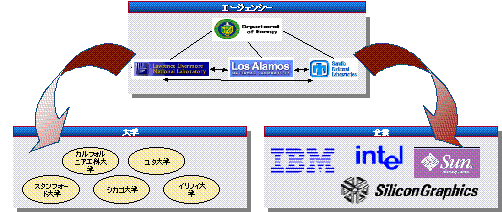
エージェンシー
- ASCIの取り組みは、ローレンス・リバモア国立研究所、ロス・アラモス国立研究所、サンディア国立研究所3つの国防プログラム研究所にまたがって行われている。
- 3つの国立研究所のマネジメントの融合はASCIの5つの戦略の一つ。
- 3研究所とDoEは緊密な協力体制によりASCIプログラムの運営を行っている。
大学
- 大学は歴史的に国防プログラム国立研究所と緊密な関係を有する。
- 国防プログラム国立研究所はその性質上得られた科学情報の扱いに関し非常に強い管理下にあり、大学との間には常にこの点で摩擦が存在する。
- しかしASCIプログラムでは、"シミュレーションが高い精度で現実を反映できることを証明する"との知的目的が大学と国立研究所によって共有されている。
企業
- 初のスーパーコンピューターは兵器開発の一環としてコンピューター産業界との共同研究により1960年代に開発された。
- 1980年代から1990年代にかけて、国防プログラムは劇的に企業との共同研究を減少させた。
- この時点よりコンピューター産業界はビジネス用高性能マシンのマーケットに注力をはじめ、以来、国防プログラムにおける超高性能コンピューティングへのニーズは満たされていない。
- 現在、ASCIを通じ、超高性能コンピューターの信頼できるマーケットの構築を目指した新たな提携が行われている。
3.3.2 ASCI大学研究プログラム
(1)ASCI大学研究プログラムにおける柔軟性
プロジェクト領域の変更
- 研究チームはプロジェクト研究領域の変更を希望する場合、大学プロジェクトの管理者となっている担当国立研究所のテクニカルモニターの承諾を得る。
- 承諾は電話、電子メール等を通じての非公式なもので書類提出は伴わず、基本的にプロジェクト研究領域の変更に関しての制約は殆どない。
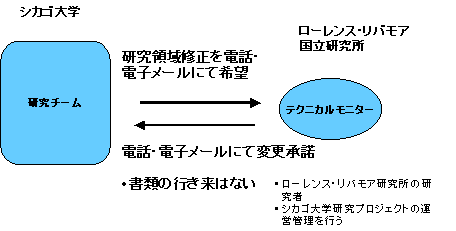
予算執行
- ASCIでは実際に資金が大学に支給されるのではなく、大学が立て替えの上DoEに請求書を送付する。ASCIでも毎年予算申請が必要だが、予算・支出の次年度繰越、年度内での費目振替は可能。さらにDoEでは予算増の交渉も認めている。
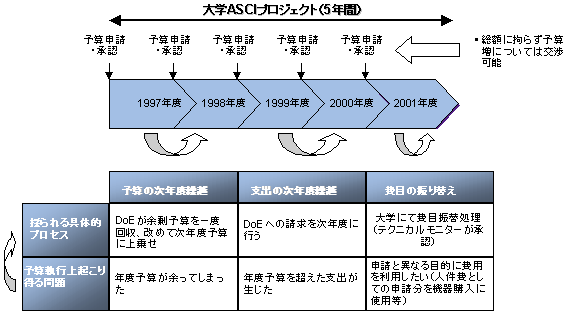
- シカゴ大学においては、全て研究チームのディレクター オブセンター(=PI)が予算執行・人事(除大学教員人事)に関する権限を有しており、大学は一切関与しない。ディレクターオブセンターは所属の事務・予算管理スタッフを有しており、大学による予算・人事に関する支援も特に受けていない。予算に応じた研究員・事務スタッフの増強が可能。
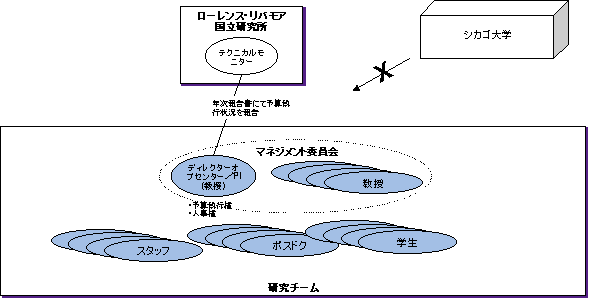
企業との連携
- ASCIにおいても企業との共同研究は自由に設定できる。但し企業はシミュレーションに関して大学に後れていること、プロジェクト終了後企業にDoEのスーパーコンピューターが利用可能ではないことから、互いに共同研究をするインセンティブは低く、実際企業との共同研究はほとんど行われていない。
(2)ASCI大学研究プログラムにおけるモチベーション/インセンティブ
- 大学研究者がASCIに注力するモチベーションとしては、以下のものが挙げられる。
- 知的興奮が得られる
- 他の研究者には出来ない研究ができる
- 将来的インパクト及びリスクの高い先端的な研究を行える
- 超高速スーパーコンピューターが利用可能
- 米国では教授職(テニュア)を得るには非常に激しい競争が必要であり、自ずと教授職を得られたような研究者にはリスクが高く先進性の高い研究を好むような野心的な研究者が多く、ASCIプロジェクトの提供する上記のような状況による知的興奮は教授にとっての強いモチベーションとなる。
(3)ASCI大学研究プログラムにおけるコントロール
- DoEはASCIプログラムにおける大学パートナーの選定に当たり、現場査察を含めた非常に厳密なプロポーザルの選定を行っている。また単なる選定だけではなく、個別のプロポーザルを厳密にDoEの要求に合ったものへと変更をさせている。
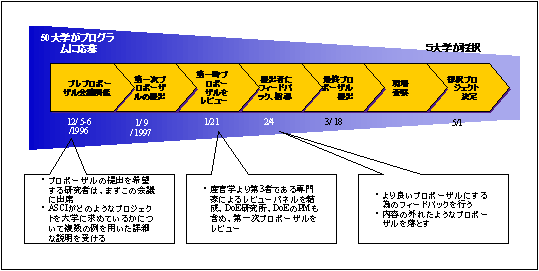
報告義務・査察受け入れ義務
- 非常に集中的な現場査察によって、研究管理体制、研究内容、研究進捗状況が事細かにチェックされる。
- 年2回DoE職員及びDoEとは無関係の独立した研究者の総勢30人が大学を2日間に渡り査察
- 大学研究チームによる発表を受け、大学職員のみならず、学生からも話しを聞く
- プロジェクト計画についてもチェックを行う
- 現場視察、年次報告書に基づく評価は、プロジェクト開始より3年目(中間評価)と5年目(最終評価)に下される。中間評価の結果、プロジェクトの中止もあり得る。最終報告の結果は、プロジェクトの次期プロジェクトへの継続可否に反映される。
成果物の取り扱い
- 研究の結果生じた成果物の取り扱いは基本的に大学に一任されているものの、DoEは以下の3点を契約条件に入れている。
1)政府にロイヤリティーの徴収なしでライセンスを与えること
2)ソフトウェアへの権利主張にはDoEの承認が必要であること
3)DoEはソフトウェアを使用しコピーする制限付きの権利を保有すること
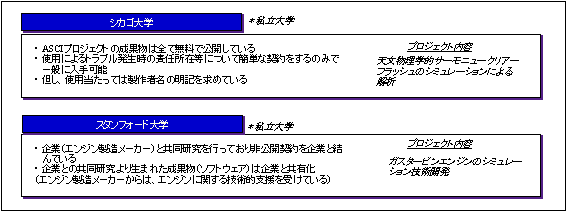
成果物取り扱い事例
3.3.3 ASCI国立研究所研究プログラム
(1)ASCI国立研究所研究プログラムにおける柔軟性
DoEにおけるプログラムマネジャー(PM)への権限委譲
- DoEにおけるASCIのプログラムマネジャー(PM)は、DoEにおいて非常に高い地位にある国防プログラム責任者に直接報告をするため、実質的にASCI運営におけるほとんどの権限を付与されている。
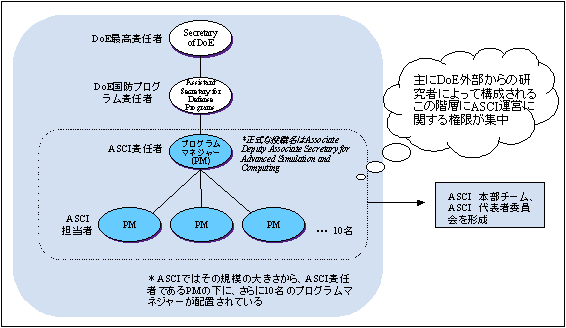
- ASCIの実質的責任者であるPMは、2年契約で一時的にDoEに在籍する一流の研究者である。PMの持つASCIの最先端技術への深い理解は、プログラム遂行において迅速かつ正確な判断と実行を可能にしている。
ASCI責任者であるPMの経歴
- カルフォルニア工科大学に在籍、現在は2年間の休職(リーブ)中
- 数学でPh.D.を保有
- ASCIの扱う全分野に渡り専門知識を有する
*そのほか、彼の下に配属されている10名のPMも全て、研究者としての資質を有する人材である。
予算執行
- 予算執行は、金額が小さい場合には研究所が自由に変更可能。大きい場合にもDoE側より文書での承認が得られれば、繰越、費目振替については変更可能である。
予算使途
(ロス・アラモス研究所の場合)
- ASCIなどのプログラム予算は、研究費の他、人件費を含む。また、研究所はプログラム予算の一部をTaxとして徴収、個々のプログラムの枠を超えたインフラ整備、LDRDと呼ばれる自主基礎研究へ充当しており、研究所の自立性がある程度担保される仕組みが存在する。
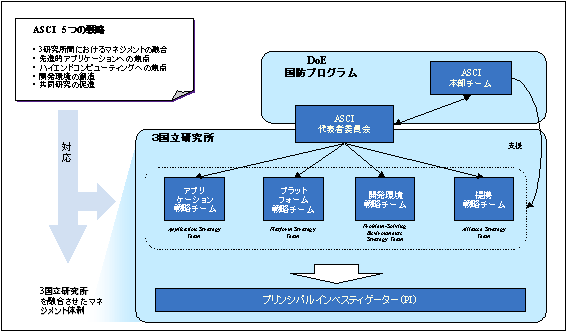
成果物の取り扱い
- ASCIプログラムにおいて開発されるソフトウェア等の成果物については、実物が研究所にあれば良く、ソースコード等の提出は必要ない。
(2)ASCI国立研究所研究プログラムにおけるモチベーション/インセンティブ
国立研究所研究者のASCI注力へのモチベーション
- 魅力的な研究環境
- DoE国防プログラムは世界最高速度のスーパーコンピュータを始めとする極めて高度な研究設備を研究者に提供することから、研究者にとってこれらの環境での最先端の研究は純粋に知的好奇心を満足するものとして大きな魅力。
- 背景:国立研究所研究者のキャリア形成(ロス・アラモス研究所のケース)
- 研究者は通常、大学院、ポスドクを経て直接国立研究所へ就職
- 就職先を選択する際に、ビジネスに興味のある研究者はシリコンバレー、大学へ、アカデミックな研究に興味のある者は大学へ、比較的応用分野に興味を持ち先端的研究環境での研究に魅力を感じる者がDoEの国防プログラムの研究所に来る
- 研究所研究者にとっては、ミッションの達成が第一目的であり、論文作成はそれほど重要ではない。ミッションの達成の為に論文作成に時間を割かないことも多い(成果の約50%程度が論文として発表される)
(3)ASCI国立研究所研究プログラムにおけるコントロール
プログラム推進体制
- ASCIプログラムの全体設計に際し、DoEはASCIの目的実現の為の5つの戦略を反映したマネジメント体制を確立。各戦略チームへ各戦略を具体化し遂行する責任を負わせた。
- DoEと研究所間での役割分担の視点から見ると、プログラム全体の遂行、運営責任・権限はDoE側が有し、各研究所は主に与えられたミッション(目的)の達成を効率的に研究所レベルで実行することに責任を負っている。
- また、研究所内のプログラム推進体制を見ると、ロス・アラモス 研究所では近年、階層構造の強化を行った。ロス・アラモス研究所では、適度な数の階層構造の導入により研究推進は効率化されたと受けとめられている。
- 階層構造の存在によって、プログラムの予算執行、配分権限は各階層へ段階的に権限配分がなされている。各階層が責任範囲内での資源配分バランスをコントロールすることで、全体の適切な資源配分バランスが実現されている。
計画策定
- 毎年ASCI年度予算の獲得後、極めて詳細な年度計画である実施計画を策定する。実施計画の策定にはDoE側が大きく関与し、3〜4ヶ月をかけてDoE側と研究所側とで案のやりとりを行う。
- 計画目標の設定、変更に対するコントロールの度合いは、目標のレベルにより段階的に異なるように全体設計されている。
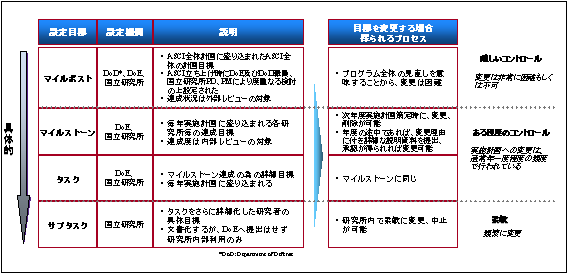
査察受け入れ・報告・PI会議
- 外部レビューと内部レビューの2種類の現場査察、進捗報告書の提出、PI 会議の開催を通じ、研究所のプログラム進捗状況はDoEにより詳細に把握され、その評価は次年度の実施計画策定にあたり反映される。
外部レビュー
- DoE職員、外部ピアレビュアー(大学、産業界、研究所の退職者等の研究者)によるレビュー。
- 全体計画のマイルポストを達成したか否かを評価 (達成か未達かで評価。達成の場合、DoE内で大きく発表)。
- 基本的には毎年一度、2〜3日間に渡り行われる。
- プロジェクトのサイズ、状況に応じて、レビューの間隔は柔軟に変更され、年数回レビューが行われるプロジェクトや、2,3年に一度しか行われないプロジェクトもある。
→評価結果は次年度実施計画へ反映。
内部レビュー
- 研究所プログラムオフィスによる研究所内部でのレビュー。
- 実施計画で設定されたマイルストーンの達成状況を評価。
- 年に一度行われる。
→評価結果は研究所内における進捗管理、資源配分の決定に利用。
進捗報告書
- プロジェクトのサイズ、状況に応じて、プロジェクト毎に異なるタイミング (3ヶ月ごと、1年ごと、2年ごと等)で進捗報告書をDoEへ提出。
PI会議
- 3研究所の研究者が、研究内容詳細を発表。
- 半年に一度開催。
- 外部者によるレビューは行われないが、DoE職員によるレビューとして機能。
- 秘密保持の必要のない公開セッションでは企業、大学のASCI関係者も参加。
知的財産権の取り扱い
- ASCIプログラムより生じた知的財産権の取り扱いは基本的にベイドール法に準拠している。
- 研究成果として生じた知的財産権は、研究所のオペレーターであるカルフォルニア大学とDoEに帰属。
- DoEはロイヤルティー料なしで成果物の利用が可能。
- 研究者が成果物に関するライセンスを購入し起業することは可能であるが、非常に煩雑なプロセスが必要であり、起業例は非常に少ない。
3.4 まとめ
3.4.1 米国モデルに見る鍵となる施策
以上までに見てきた米国政府主導プログラムについて、日本にはない形でプログラムの成果に大きく寄与していると考えられる、鍵となる施策の抽出を行った。
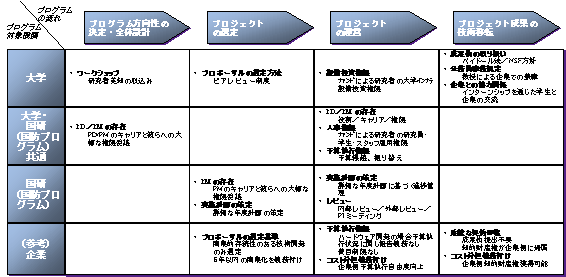
米国政府主導研究開発プログラムにおける鍵となる施策
以下さらに、これらの施策がプログラム運営の各段階において、どのように柔軟性実現の仕組みを支え、その結果官民(国研)の役割分担がどのようなっているかにつき分析を行った。
3.4.2 米国モデルに見る官民の役割
(1)大学研究プログラムの場合
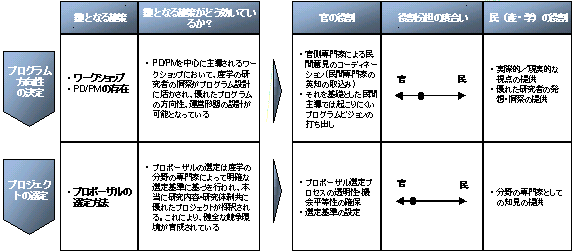
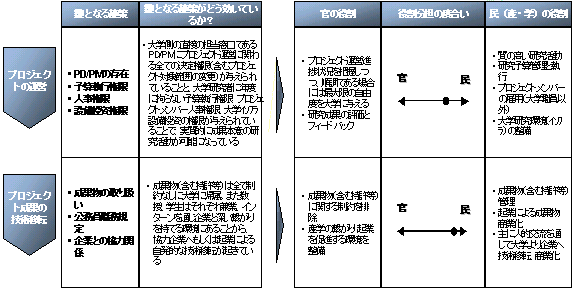
- 大学研究プログラムの立ち上がり期は、先端的なプログラムの性質上官に重要な役割がある。しかしその中でも、プログラム設計へは民間研究者の英知が有効に導入されている。
- プロジェクト運営、成果の技術移転という実施の段階においては、民間にほとんど役割が委譲され、大きな自由度が与えられている。
(2)国立研究所研究プログラムの場合
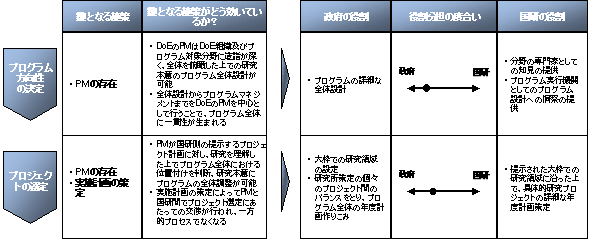
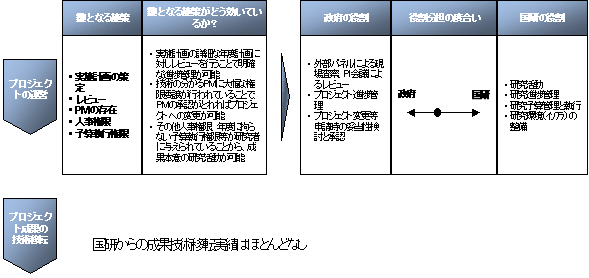
- 国研プログラムでは国としてのミッションの達成が第一義であり、政府が主導的役割をとっている。研究内容に深い理解のあるPMの存在は、具体的研究内容決定にまで踏み込んだ政府側の主導を可能にしている。
- プロジェクトの運営においても、PMを中心とした政府側の積極的なコントロールがなされている。この背景としては、ASCIプログラムの研究内容が比較的応用分野よりであり計画変更が起こりにくく、強い管理型のプログラムマネジメントが機能しやすいことがある
- 成果技術移転の実績はほとんどなし。
3.5 日本への示唆
3.5.1 日本において官民の役割を大きく整理すべき部分
(1)大学研究プログラムの場合
日本の大学における研究プログラム運営は官による管理が圧倒的に強く、官民の役割を改めて見直し、それに沿った施策の導入を検討して行く必要がある。
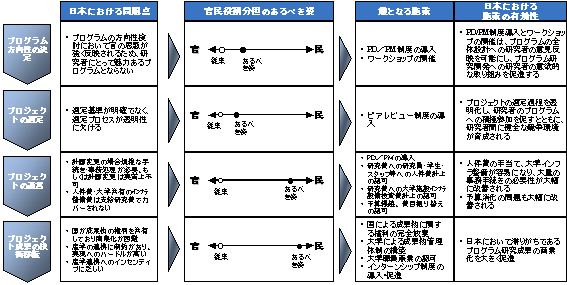
(2)国立研究所研究プログラムの場合
一方、国立研究所における施策導入の検討に際しては、国立研究所の対象とする研究分野の性質(基礎/応用)や、研究所のミッション等要因の考慮が必要である。
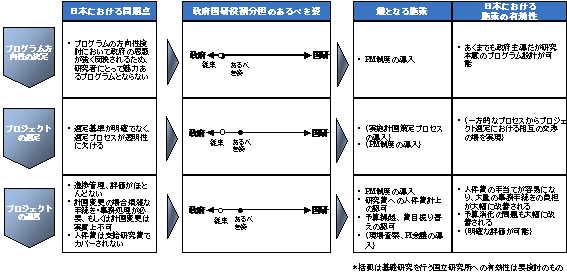
3.5.2 日本での鍵となる施策導入の検討
日本における鍵となる施策の導入にあたっては、中心となるコーディネーターが制度面での整備、運用面での醸成を進め、さらに総体のバランスを見ながら適宜調整を行っていく必要がある。
(1)大学研究プログラム・国立研究所プログラム共通
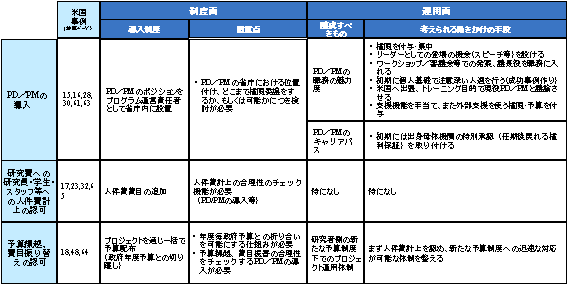
- PD/PMの導入、予算執行に関わる認可は、大学と国立研究所プログラムに共通して導入を検討すべき。ただしPD/PMの人事面は特別扱い的な準備が特に初期に必須(必ず成功させる)。
(2)大学研究プログラムのみ
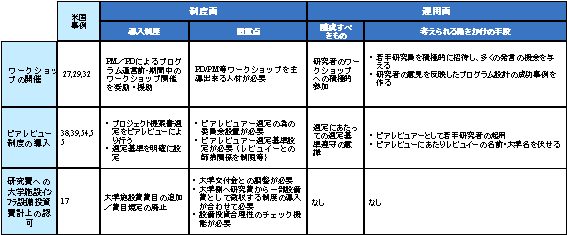
- ワークショップ、ピアレビュー制度などは比較的導入に際しての障害は少なく、高い効果も期待できる。
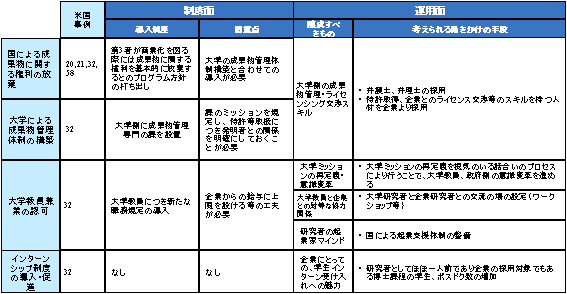
- 国による知的財産権の基本的な放棄は大学側に成果物管理、ライセンシングスキル等が醸成されてはじめて効果を発揮するため、醸成にも注力が必要。また、大学教職員兼業認可には、大学自体のミッションの「再定義」と、それに伴う大学教員、政府側の考え方の変革を進めてゆく必要がある。
(3)国立研究所研究プログラムのみ
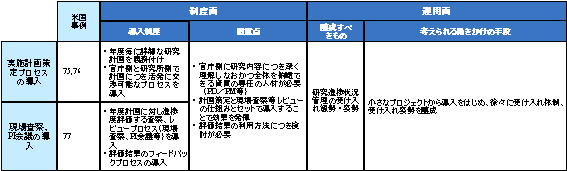
- 実施計画の策定、査察、PI会議の導入は、応用分野に近い研究を行う国立研究所に関しては、導入検討の価値がある。ただし、これらの施策の効果を引き出すには、PD/PMのような人材が育成されていることが不可欠である。
【次へ】