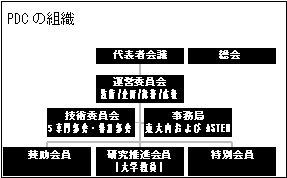
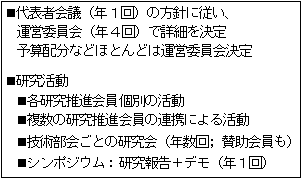
はじめに
情報通信技術に関して、米欧では大学・国研(国立研究所)が、技術シーズの供給源として産業に寄与するところが大きく、産業活性化・競争力向上を支える要素のひとつとなっている。わが国の大学・国研が同様の役割を果たしていく上で、現状どのような問題があり、どのような改革が必要か、計算機メーカ6社、および民間調査機関の有識者からヒヤリングを行なった。本章の1〜4は、その中で指摘された問題点と提言を記述する。
それらヒヤリング結果にも見られる通り、現状では産業と大学・国研の結びつきは極めて希薄である。したがって問題点の指摘も、技術シーズ供給源としての強い期待に基づき踏み込んだものとはなっていない面がある。そこで本章5には、反対に大学関係者から見た産学の関わりについて、意見を頂いた結果を載せている。
本章6では、産学協同による研究開発の事例として、1995年から5年間にわたり実施された並列・分散処理研究開発機構(PDC)を取り上げ、その成果報告シンポジウムからの抜粋を収録する。
2.1 大学・国研が産業の技術シーズ供給源となる上での究開発体制に関する問題と提言
2.1.1 わが国産業の閉塞状況の突破口としての大学・国研改革
|
(1)企業は、基礎技術を自給からアウトソーシングに切り換える必要に迫られている
情報通信分野における急速な技術革新、およびそれがもたらす競争激化と様々な社会構造の変化の中で、企業の基礎技術獲得のしかたは、中央研・基礎研を中心とした従来の自己充足的な開発から変化してきた。すなわち、核となる技術を次々と開拓し、有力なものを商品化するというサイクルを一企業内で行なっていくことが困難になり、アウトソーシングが不可欠となっている。措置のひとつとして、最近では民間企業の同業種内でのアライアンスが活発化している。しかし直近の技術を利用するのみでなく、将来に備えた基礎技術が継続的に創出・育成される仕組みを確立するには、大学や国研の、技術シーズ供給源としての役割が重要である。
(2)大学・国研改革が、情報通信産業の活性化への開始点となる
わが国の情報通信産業の伸び悩みをもたらしている諸問題は、相互に悪連鎖を形成し、いずれを根本原因として解決すべきか糸口の見えにくい状況にある。大学や国研の研究開発体制、あるいはそれらの研究機関と産業界の連携の制度もそうした問題のひとつであり、ここで米欧に遅れをとっていることが、情報通信産業競争力における劣勢の一因となっている。しかし情報通信産業において、優秀な人材や初期研究の影響はとりわけ大きく、大学・国研の改革は、国内産業および技術分野の活力再生に向けた突破口となり得るであろう。
2.1.2 研究者の絶対数確保と研究の活性化
|
(1)米国に比べ研究者の絶対数が不足しており、柔軟な雇用制度と研究者支援が必要
研究者の絶対数が米国に比べて桁違いに少なく、研究開発パワーが不足している。これが、情報技術における今の実力の差にそのまま影響している。情報技術関連の研究者が不足しているのは明らかなのだから、国の事業は研究者層の強化も目標に含めて考えるべきである。
この課題は、5年、10年、のスパンでの計画性を持った対策が必要だ。
・公務員枠の制限が研究開発人員を切り捨てている問題の解決を
公務員数削減の影響で、国立大学・国研における研究開発の実働人員、あるいはこれをサポートする人員を確保できなくなっている。
対策の一つとして、国立大学・国研で公務員の総定員枠とは別に人を採用できるような、研究者雇用の柔軟な制度が必要である。
米国アルゴンヌ研究所の遺伝子研究では、国から得た一人年分の予算で、最初の半年にバイオの研究者を雇い、残りの半年は前半のデータを整理するためにデータベースの研究者を雇うといったきめ細かな雇用をしている例もある。また、アルゴンヌ研究所はシカゴ大学が運営を任されているということもあり、シカゴ大学のポスドクを呼ぶなどの形で、研究者がこまめに往き来できる。研究開発予算を効率よく利用できるとともに、それによって世界の優秀な研究者の確保も可能になる。最先端の研究のためには、世界の一流研究者を呼んで研究体制を組めることも重要であろう。
・日本の大学に研究者を定着させる支援制度、端的には大学院生の生活費援助を
人材供給の機能に重点を置いてきた状況を逆から見れば、大学に優秀な人材が残らないので、ソフトウェア技術が大学に蓄積されないのではないか。大学に研究者がいなければ、研究はできない。研究者が、大学に集まり定着して研究できる環境の整備、特に安定した生活の支援が必要である。
米国では、大学院生が研究者として5年くらい大学にとどまる。これくらい大学にいれば、結構いいものができる。また、NSFやDARPAが大学院生を援助している。3万ドルなり5万ドルなりを与えて生活の安定を保証すると、研究者も研究に打ち込めるし、モチベーションも非常に高くなる。
日本の場合は、アルバイトをして授業料や生活費を払い、そうしてドクターを出ても大して評価されない。これでは優秀な研究者が大学に残るわけがない。日本では、もっと大学院生を援助する仕組みを作るべきである。単純に言えば、ドクター課程の学生に一人あたり300万円くらい援助したらどうか。対象者が300人としても、高々9億円だ。10億円の金を下手なソフトを作るプロジェクトにばらまくよりは、大学院生の援助に充てた方が良い。情報通信産業にとって最も重要な人材が、毎年300人、育成供給されることになる。
・世界から優秀な学生が集まり、技術活性化に貢献できる環境を
最近、日本がアジアからの留学生に対する奨学金を拡大したことは大変良い。しかし、外国人留学生の大半はドクター終了後に米国に行ってしまい、日本に何も残らない。大学でポスドクを雇えれば、彼らは日本で活躍できるし、その延長として日本の企業に就職したいという留学生は多いと思われる。米国では、大学の先生が自由に国や企業と契約を結び、そのお金で研究者を雇える。大学の学生をリサーチアシスタントとして雇うこともできる。そのため、優秀な人が世界中から集まる。
(2)大学・国研の活性を維持するには、産業との間で人の流動性が必要
大学・国研という器だけ、あるいは独立行政法人化のような枠組みの変更だけ、では研究機関の活力は保てない。活性化には、企業との間も含め、人が動くことが重要である。たとえば、U.C.サンタバーバラは、センター・オブ・エクセレンスであり続けている。今度、青色LEDを実用化した中村修二氏も行かれるというが、ここは人がよく入れ替わる。
・大学から企業への移動の仕組みを
初期研究を埋もれさせず製品化につなげるには、企業と大学との間で人が動くのが良い。しかし教官の交流だけでは、なかなかうまく行かないだろう。楽なのは学生が大学と企業の間を動くことである。そのような移動が頻繁に日常茶飯事にできる必要がある。
企業にもドクター論文を書く指導のできる人はたくさんいる。学生が望む仕事を、すべて大学の環境でできるわけではない。環境がないために、本来なら2年で済むところを5年もかかるのは、本人と国家、双方の損失だ。それを企業で肩代わりできるなら企業でやればよい。企業の実験室も、設備によっては空いていることが多い。ただし報酬の扱いは微妙かも知れない。企業が学生に給料として支払うのは制度上おかしいので、基本的に奨学寄付金のような形だろう。しかし、これも固定ではなく、ケース・バイ・ケースでできる必要がある。
大学の研究能力は大学院できまる。基本的に手足を動かして研究しているのは大学院の学生だ。大学が本気で研究を柱に存続していこうとするなら、大学院のドクターコースのあり方を、非常に良く考えないと実効が上がらないと思う。企業との柔軟な交流協力が、そのための一つの案になる。
・企業から大学・国研への受け入れの仕組みを
逆に、大学が民間の講座を設けたので教師として派遣せよという話にも、企業は喜んで応じる。最近は不景気で減ったが、一時は寄付講座というのがたくさんあった。海外の大学からは既に5〜6年前、ダブリンのインペリアル・カレッジの人が来て「学生を指導できるレベルの人が常駐して何人かで研究室を作れれば、大学の認定によりドクターコースの学生を何人か派遣できるシステムを作りました。」と誘いがあった。
企業に入った人が大学に再度行き産学協同研究をやるとか、優秀な先生がいればその講義をネットワークで企業にも公開するとかの施策も必要である。
また、企業からの研究者を、大学・国研の研究室に広く受け入れて頂きたい。その際、中小のベンチャー的な会社は、研究者派遣に関してある程度の資金的な補助があると楽になるだろう。
・産学連携に、シンクタンク企業の活用を
シンクタンクから客員教授と客員助教授を派遣し、インターシップで学生に仕事をしてもらう制度が始まっている。まだ単位を与えるまでにはいっていないが、そのような交流関係を広げ大学の先生もシンクタンクで仕事をすることが可能になれば、研究をビジネスにつなげるセンスを磨く機会となり得る。
米国では大学の先生が、シンクタンク、典型的にはSRI等を一つのキャリアパスとして次のステップに上がって行く。このように、産学の流れの中でシンクタンクが橋渡しの役割を果たす。
大学の研究を実用化する過程をスムーズにするために、シンクタンクを仲介としてスポンサーを得ることも可能だろう。
2.1.3 経営の改革
|
(1)独立行政法人化は大学・国研に求められる経営変革のきっかけになり得る
組織は追い込まれないと改革できない。企業は現在、競争の中で追い込まれ、年功序列などの従来体系ではやっていけず成果型に変えようとしている。
大学・国研にとって、独立行政法人化や学生数の減少が、そうした改革のきっかけになる可能性がある。大学・国研は、独立行政法人化により従来以上に経営を考えさせられ、結果として自浄効果を生じるだろう。特に経営資源(教員・職員・学生)とその活用が課題になる。その際、大学経営者にどこまで任免権を持たせるか、なども再検討が必要になるだろう。
・大学の教育学問と経営は、責任者の分離を
米国や英国の大学のトップは、教育学問系列と経営系列、英語でいうとprovostとpresidentとの2本立てになっている。日本でも一部私学はそういう傾向がある。学問的センスと経営的センスは全く別のものなので、責任の分離は必要であろう。
・大学は、教育機能と研究機能の分離を
大学には、教育と研究の2つの機能がある。教育の部分は給料が保証されても良いが、研究の部分は、自分の成果により稼ぐ仕組みが必要である。あるいは、大学の先生の職務を、教育・研究いずれかの選択制とする。米国の制度では、大学の先生には9カ月分の給料しか支払われず、その代わりに残りは自由にやり、良い成果を上げれば対価は先生自身のものになる。
・産業や納税者にとって役立つ存在を目指すこと
経営変革において、最も変えるべき価値観は、時間軸の大幅な短縮である。あらゆる仕組みは、地球規模での時間軸の短縮を考慮すべき状況にある。その結果として、大学・国研が、10年後も価値ある存在であることが見える方向に行かないと、企業との協同研究は難しくなる。
また、独立行政法人化以前に、現在の「官」の立場であっても公僕の意識は必要である。現在はこれに欠ける。たとえば電子政府も、官の奉仕の発想がないとうまくいかないだろう。納税者に責任を感じる経営思想を持つべきである。納税者もまた、自分が主体であるとの意識が必要で、こうした社会認識は、欧米化がもっと進んでも良い。
・産学連携をしやすい相互関係を
産学の関係の基本構造も問題である。企業が大学に資金提供する時に『奨学寄付金申込書』のような文書を書かされるが、こうした、お上が「頼みに来るから受けてやる」というスタイルは改善されないものか。
・第三者による評価が必要
大学・国研や、その研究者に対する、第三者の評価が必要である。ただし大学の研究者が教育者も兼ねている現状では、研究成果のみでの評価は高負荷を強いることを考慮しなければならない。
(2)大学・国研の劇的改革にはグランドデザインが必要
大学・国研を効率的に機能させるには、雇用制度等、法律を変える類の話を大胆に実行しないと、うまくいかないだろう。国として科学技術立国を標榜し、今までのやり方を変えるのであれば、どういう風に変えていくかという非常に大きなグランドデザインが要る。最近、大学の先生が兼職してもいい等、少しは変化してきてはいるが、いつまでも小さな第一歩ではうまくいかない。劇的に大学の役割を変えていくには、何かこれという大きな企画を幾つか作って、そこで実験をやってみるのが効果的ではないか。
米国も80年代末頃からは大学の外にいろいろ作ったりしたが、最初は最先端の研究施設を大学に作り、そこが核になった。たとえば、コーネル大学に最先端の微細加工の研究施設を作った。光関連では、カリフォルニアのサンタバーバラに専任の教授を何人か集めて全国共同利用施設のようなものを作った。
諸改革は必要であるが、米国の仕組みをそのまま持ってきても、いろいろな社会基盤の違いがある。どうやれば大学・国研が本当の意味での研究の拠点になるか、現実問題としては日本の風土・歴史・慣習を踏まえて、身近なところから的確に対処していかなければならない。
2.1.4 価値観の改革
|
(1)研究開発における産学の時間尺度の乖離が、両者間を疎遠にしている
企業と大学・国研のつながりは、ここ数年でさらに疎遠になった。原因は、技術革新・環境変化が加速する中で、企業と大学の目標設定や価値観の乖離が大きくなったためと考えられる。つまり、企業は1〜2年で成果が欲しいのに対して、大学は10年先を見て論文を書かなければならない。企業から見て市場立ち上げの想定時期が10年以上遅れ、しかも、いざその時期になると技術進歩の激しさから、実現技術は研究内容とかけ離れたものになっている、というのでは協同は難しい。
(2)大学・国研は実用化に対する価値観を再考し、産業への積極的な貢献を図るべき
大学・国研は、産業界の予備軍たる優秀な人材を供給する、あるいは自ら産業に貢献するという形で、積極的に産業に貢献する機関に変わるべきではないか。
・企業での教育を前提としない、実践的能力を備えた学生の育成が必要
日本の企業は、マスターの学生を研究所に受け入れた後、2〜3年教育してから成果を出そうとしている。しかし、米国企業では、こんなやり方は考えられない。米国の大学のコンピュータサイエンスを卒業している学生は、相当に実践的な経験を積んでおり、即戦力になる。そして企業は、その場に最適な人材を引っ張ってくる。日本の企業は、はじめからハンディキャップのある状況の中で競争している。
・大学・国研から、企業が期待するようなビジネス提案を
国内の大学・国研には、ビジネスに結びつくような研究がない。企業は事業に関わらない基礎的な研究では、興味を持てない。日本の大学の研究者は、欧米と考え方に根本的な違いがあり、研究と事業を別と考える。応用面で事業と密着すべきテーマに関しても、「我々は、あくまで研究」と距離を置くことが多い。
大学から企業に、「こんな金儲けになるアイデアがあるが、やってみないか」、と売り込みがあってこれに乗っていくスタイルであれば、やり易い。積極的に企業にアプローチすれば、資金や研究者の支援も広がるのではないか。
米国では、MITなどの研究者が、事業化フェーズまで踏み込んだ計画を企業に持ちかけてくることもある。
・製品化が見える段階まで、技術の完成度を高めるべき
いまの大学には、シーズを製品まで発展させるという気持ちのある人が、皆無とは言わないまでも極めて少ないのではないか。研究成果を商品として仕立て上げる力が必要であるが、日本の研究者にはこのような視点が欠けている。大学のアウトプットを、事業にスムーズに持っていけるケースはほとんど無い。大学が重要なコア技術を持っていても、製品化までの隔たりが大きすぎれば、すぐ製品化できる手近な技術を使ってしまう。
もっとも、米国や欧州の大学がすべて、製品になる技術の提供をきちんとやっているかというと、必ずしもそうではない。欧米の大学からプログラムをもらって製品化へのトライはしたことがあるが、バグが多く実験プログラムの域を出ていない場合が多い。ただし米国の大学には完成度の高いものもあり、利用したこともある。
・産学のあるべき関係は双方向の「チャレンジ&レスポンス」
大学・国研と企業とのあるべき関係の基本は、「チャレンジ&レスポンス」と言える。つまり2〜3年後の近い将来に目標を置いたテーマの期限付き提言に対して、それをものにする実行力と創造的な実現力で応える関係である。そのためには、価値あるテーマを創出する能力、および結果が自分の担当中に出る時間軸上でリスクを冒しても取り組む価値観が、企業と大学・国研の双方に必要である。
国に提案を出すにも、外部評価の仕組みを作るにも、これらの価値観や評価軸を前面に出せばうまくいく。今は双方向ともその姿勢が足りない。米国の大学とつきあうと、逆にそうしたテーマ設定を求められる。
・「役に立つ」ことに対する価値観が鍵か
特に米国は、人の役に立つことに対する思い入れがあって、常にそこに戻っていく。日本の大学には、人に役立つということとは無縁だというような思いがあるのではないか。この状況を解消して、製品化を含めたアイデアの実用化が、大学の中でも評価されるようにならないといけない。
大学の先生ももっと海外で切磋琢磨し、そうしたセンスを鋭くする機会を増やす必要があるかも知れない。
・研究者の意識・意欲の低下は懸念材料
米国の学生には、学位を取得しプリンシパル・インベスティゲータになることによって、その分野での研究第一人者として認められるというモチベーションやインセンティブがある。日本にはこれが欠ける。
企業で見ていると、昔の研究者は上司が何を言おうとやりたいことをやる面があったが、若い研究者の価値観(主体的な興味)がむしろ、消極的になったように思えることが懸念される。この傾向は大学でも強いためか、米国からの見学者が大学でなく企業に来るケースも多かった。
(3)言語の壁を解消して、世界を念頭に置いた研究体制を
英語は2つの理由で重要である。ひとつは、技術の国際発信のため。論文を書くときに日本語の読者だけをターゲットにしては日本から外に出ない。ソフトウェアの仕様やドキュメントも、世界の利用者を対象とする必要がある。もうひとつは、アジアの優秀な人達を日本に惹きつけるため。今や、日本以外のアジアの国々は、英語圏に適応できている。日本の大学院の講義に、英語で行なうものがあってもよい。優秀な留学生が集まることによって、日本の大学の活性化にもつながるだろう。
この英語の問題は、中期的な問題である。つまり結果はすぐに出ないが、対策は早急に必要である。
(4)TLOは、現在は未活用だが、大学が事業に積極的になる契機として期待できる
TLOが有効に機能する期待は薄い。これまで大学が持つ技術の産業化は少数の先生の個人プレーが核になっていたが、そうした人が必ずしも組み込まれていない。日本では、産業化に関わるのはアカデミックな世界にはふさわしくないと思われている向きもあるかも知れない。
その成果を利用したケースも、現実には見ない。しかし、TLOによって大学に事業化への積極性が生まれると期待できる。民間の企業が求めているもの、考えている方向に合わせて動いてくれると思うので、これからは接点ができてくるだろう。
TLOの機能が活性化するには、移転技術を事業化する際の、税制を含めた優遇措置が有効であろう。だが一方で、競争原理が働く仕組みはきちんと残す必要がある。
2.1.5 国の支援制度の改革
|
(1)研究の現場裁量権拡張を
現場裁量権の大幅な拡張が必要である。たとえば雇用に関して、米国の研究マネージャは研究者を自由に採用、解雇する権限を持っている。日本のマネージャにもこのような権限を付与すべきである。研究テーマに応じて、採用対象者に外国人を含められることも必要である。
また計画の変更などに関して、企業の開発や技術革新のスピードに見合った自由度のある制度が必要である。
(2)現実に即した予算運用を可能に
単年度予算に基づいた現状では、1年ごとの帳尻あわせや書類作成などの研究開発の実態に同期しないオーバーヘッドが大きい。これを、プール予算などに改める必要がある。米国では諸経費も含めて、予算の運用が合理的である。このような会計原則を見習うべきである。
(3)もの作りを伴う研究においては大学へも設備投資が必要
半導体産業で産学協同がうまくいかなかった第1の理由は、産業界が大学に何も期待しなかったことであろう。大学の教育にも期待していなかった。学生がチップを作る訓練をする組織を作れという提案にも、企業は当初「訓練は企業に入ってからでよい」と耳を貸さなかった。第2に、設備が競争を左右するもの作りの分野において、大学は設備投資の面で太刀打ちできなかった。国も企業も大学に殆ど投資せず、大学には最新鋭の研究設備が設置されなかった。政府支援プロジェクトが企業中心だったとも言える。超LSIの組合、基盤促進センターになってから幾つかのプロジェクトがあるが、大学は評価委員として大学の先生が参加されるにとどまっている。
(4)ナショプロ成果に対する認識改革が必要
・ナショプロの投資は増税により納税者へ利益還元されるという認識を
研究費を遣う側は研究成果が予定通りに出たかどうかで評価されるが、研究費の運用を管理する側はその結果が国策にどのように貢献したかで評価されるべきであろう。
ナショプロが実質的な開発成果を生み、産業競争力強化につながるためには、手続き主義から結果主義への変更が必要である。結果を書類で判断する現在のナショプロのやり方は改善されなければならない。
米国のナショプロにおいては、新産業・新事業に対して、会社が儲かれば税金増として納税者に利益が還元されるという考え方で出資し、産業をプロモーションしている。この考え方で良い。日本では、書類の厚さが還元だと感じる時がある。
・国の支援は、研究がビジネスに結びつくまで責任を
顕在化した市場は、放っておいても企業がやるから国の支援は必要ない。研究者のアイデアを、ビジネスチャンスにつなげるようにもっと前向きに支援するのが国の仕事だ。
Globusプロジェクトは、パッケージ化してデファクトの素地を作るまである程度国の資金ででき、国のプロジェクトとして非常に理想的なものと言える。
開発プロジェクトの成果は、政府主導で、必ず実際に適用していくことも重要である。
・研究の成果はオープンなデータを残すべき
米国では、NSF、NASA、NIHなどが基礎研究に助成金を出して、大学・国研の研究者の間にコミュニティを作っている。ディジタルライブラリ計画ではNSFが研究開発者と最後のコンシューマまでまとめてオーガナイズするといったコーディネーションをしている。これら国の助成金による成果はオープンにすることが求められるので、パブリックドメインのソフトが数多く生まれている。
日本においても、ナショプロでは書類ではなくデータを残すべきである。そのデータにより、より多くの研究者が成果を活用できる。
(5)関係省庁は縦割り・硬直的な体質を改善して、オープン、柔軟に
関係省庁は情報公開を徹底し、もっとオープンにならないといけない。縦割り組織の弊害も大きく、その解消のために、米国のNSTCのような強力な調整機関が望まれる。
組織が外部環境の変化に対応できなければ、その寿命は尽きる。しかし一方で、国にせよ企業にせよ、組織は内部からは容易に変われないという経験則がある。改革には、相当に強力な取り組みを必要とするだろう。
2.2.1 従来の産学交流
|
(1)大学の卒業生を人材供給源としてきたことを除けば、現状の産学間の関係は希薄
企業と大学との、事業断面における関係は希薄である。過去、大学と一緒になって物を作ったり、大学発の技術シーズを企業で製品化したりといった事業につながる事例は、国内では全くないと言ってよい。大学との関わりは、卒業生を人材供給源としてきたのが主だった。
海外から、Xコンソーシアム(MIT)のXウィンドウをもらってきて成果を活かしたのが例外的ケースである。
企業から見ると、教育という点を除けば、国研も大学と同様である。
(2)教育・人材提供の意義は大きい
前述のように、従来は卒業生を人材供給源としてきたのが大学との主要な関わりであったが、ソフトウェア技術は、7〜8割が人に依存する。その意味で企業としては、大学から優秀な人材を受けるということにより、大きなメリットを受けている。
また、教育機関としての大学は、非常に価値がある。特に海外の大学には、企業から人材をどんどん留学させている。しかし日本の大学には、ほんの僅かである。残念ながら、日本の大学の情報通信分野での先端研究は脆弱である。
大学・国研との協同研究が、企業側の研究者・技術者の経験や育成に役立つメリットはある。
(3)広範で普遍的な知識、あるいは最新の専門知識と、これに基づく提言が得られる
基本ソフトウェア関連では、大学の先生に委託研究を出して知恵を借りるとか、特定のアクティビティがどこにあるかを教えてもらう等の形で相談にのってもらい、良い提案をもらったことはある。
インターネットの初期にご指導頂いたこともあった。
大学の先生に社内大学院大学の講師をお願いして、社内教育のご支援を頂いている例もある。
(4)最新の開発成果供与など、企業主体による産学のつながりも
以下に挙げるように、企業が大学に対してアクションを起こすケースもある。大学に最新技術の成果に触れる機会を提供する一方、企業も従来と違った観点からの応用のアイデアやコメントを得られ、双方にメリットがある。
2.2.2 大学・国研に期待する役割および研究
|
(1)産業の進路の先導と、メタ技術によるサポートを
・パラダイムシフトの見極め/センスのあるオピニオンリーダの役割
シンクタンクとして、パラダイムシフトを見極める力や計画力、センスあるオピニオンリーダの役割を持つことを期待する。
たとえば、マイクロソフトはまだ玩具のようだったパソコンボードが出始めた頃に、その将来の可能性を見抜いた。あるいはグループウェアの開発に際し、日本の企業の多くがカメラ指向(リアルタイム指向)で取り組む中、NotesはパーソナルDBを核に実現してインターネットの時間差攻撃特性を活かすことに成功した。このように、先見性によって情報技術分野のリーダーシップをとることができる。
・企画・計画へのシンクタンク的提言
企画や計画能力の弱さが、情報技術を米国に支配されそうになっている原因である。競争力にはハードウェア・ソフトウェアの企画能力と製造能力が一体化していることが必要である。大学・国研は、企画・計画に関してシンクタンク的観点から提言できる力を持って欲しい。この意味で情報関連の研究機関には、文化系人材もしくは企業でこの種の企画活動を体験した者の参加も必要である。
マーケット研究に基づき、その中でシーズがどう活きるかを研究するシンクタンク的機能を望む。こうした予測・企画に基づく成果は、知的所有権(本質特許)になり得る。
そのプロフェッショナルとしてのシンクタンクの期待される姿は、技術者とビジョン企画立案者(企業や大学OBを含む)とで構成され、企画されたビジョンに関して技術的実現責任を負うものである。技術成果はベンチャー企業を起こして市場に成果を問うことになるだろう。
・製造能力向上を実現するメタ技術開発
メタレベル製造技術に強みを持った研究機関が出てくれば、企業も助かる。ビジネス競争力のもとである安さ・速さ・製造能力が、情報技術ではさらに効いてくる。速さの価値は、ヒトゲノム研究での解析を考えれば分かる。米国製システムは、メタレベルで効率よく作られているものが多い。メタレベルで設計でき支援ツールも充実しているので、アイデアの実現も、アイデア変更への対応も速い。その結果、日本は安さ・速さで負けている。
(2)基礎研究、コスト/ニーズ無視の研究を
・コスト無視/ニーズ無視の基礎研究を絶やさないこと
大学・国研は、産業に直結しない、あるいは大きなコストを要する基礎研究も育成すべきである。たとえば、ヒトゲノム、地球防衛などはこの部類に入るだろう。その中にはゲノムのように、結果的に巨大産業に化けるものも出てくる。
米国におけるこの種の研究の背景には、国防に関する資金や意識だけでなく、人間の知的好奇心に対する価値観が基盤にある。
企業は事業に直結した開発に注力せざるを得なくなってきている。
研究開発の一番収益率の悪い上流域、すなわち、海のものとも山のものともわからない段階のアイデアをたくさん出し形にしようと取り組んでみる研究を、どこかはしっかりとやって欲しい。
・基礎研究は、シーズ指向以外に新しい発想の知恵も必要
基礎研究もシーズ指向一辺倒ではなく、今までにない新しい発想の知恵が必要である。たとえば、これから情報家電とか携帯電話が社会に普及すると、ますます信頼性のニーズが高くなる。そのためには、ソフトウェア工学も、いまの延長では不十分になる。プロセッシングパワーが上がってくると、小型機器にもオブジェクト指向などの、よりロジカルな言語が使われるようになり、信頼性、保守性が上げられるようになる。こういうソフトウェア工学あるいは新しい発想の言語研究をはじめ、将来のニーズを見越した基礎をやるべきである。
・長期的研究では時間耐性のある基礎技術で、知的所有権戦略の展開を可能に
インフラ技術、ビジネスモデル、キルビー特許などのように、時間がたっても価値の下がらない技術の基礎となる研究を、大学・国研に期待する。
たとえば今後、性能がログリニアで20〜30年(2〜3桁)向上したときの状況、あるいはNGIの効果を予測して知的所有権に結びつける。こうしたことができている研究機関なら、企業はつきあう意味がある。ただし、価値観に接点がなければならない。
(3)短期的には、日本からの情報発信に貢献を
企業にとっては、短期的研究が最もわかりやすく協力しやすい。その部分に注力がなければ、今後交流はますます無くなるだろう。
短期的テーマの一例として、今後、サービス研究が重要になる。それらをどうやってビジネスにつなげるかが企業にとって関心事である。そのために、たとえばDFS戦略の研究は有用である。DFSは企業の意向のみで決められるものではなく、第三者が判断する必要がある。そのための社会的仕組みづくりを大学・国研がやってくれれば、日本からの戦略発信も可能になる。
2.3.1 市場・情勢の認識
|
(1)世界に通じる視野と競争意識を
・改革の努力は企業内部にも必要
公的組織に比べれば随分フレキシブルとはいえ、企業もかなり窮屈な仕組みになっている。国に提言するだけではなく、内部をまずきちんとする必要がある。たとえば、予算を必ず年度で決める問題は企業にもあり、長期的開発に関しても次年度以降について対外的にコミットすることが難しい。
・競争、協力、市場認識、すべて世界を視野に
米国では、競争原理の厳しさが、同時に非常に密なアライアンスをも生んでいる。まず産業全体として他に勝たなければならず、勝ったらその後で、今度は内部の競争を考えようという具合だ。たとえば半導体は装置産業であるから、大学はおろか敵同士でジョイントし、国の資金も使いセンターをバッと作って協力する一方で、育った学生の争奪戦を勝手にやっている。このように常に視野が広く、柔軟である。
日本では通常の思考回路に世界が入っておらず、内向きになりがちである。その結果、競争に対する意識も甘くなる。競争のためには、まず世界の相手を知ることが必要である。米国は自動車産業が低迷した時、カンバン方式が相手の武器だとわかったとたんに次々とトヨタに見学に来た。その逆があってもいいはずだが、情報通信産業がこの状況になっても調査に行かない。あるいは何を調べたらよいかわからないほど、フィロソフィが失われているからか。
ただ最近では、海外とのつきあいで、契約という概念は若い人達にかなり根付いてはきており、良い傾向と言える。
・アジア経済圏やアジアとの連携をもっと強く意識すべき
日本の経済を今後維持していくうえで、アジアとの連携の中で生きていくということがポイントになるだろう。米国の戦略は「インターネットとビジネスモデル」で世界に展開していくことであり、その中で、アジア圏という固有の経済構造を意識していく必要がある。
2.3.2 人材の活用
|
(1)研究者・技術者の処遇制度改善がなければ、全体的な技術力低下は必至
・技術者待遇の悪さからくる理工系離れも、日本の技術不振の遠因
日本は科学技術立国と言う割には、科学者・技術者を優遇していない。技術者は、恵まれた設備や環境に接することによって、より活躍できる。
日本の技術者は給与待遇等の面でひどく虐げられている。米国のソフトウェアや情報の技術者は、価値のある人なら市場原理に従って優遇され、非常な高給をとっている。この給与体系は、ベンチャーが引っ張っている。これに比べて日本の技術者は、金融関係等と比べると生涯賃金でひどく差がある。会社自身の収益が低いせいもあるが、追いつけ追い越せという産業構造がこうした給与体系に働いていたと思う。人材の理工系離れは、日本の情報産業がうまく行かないことと相当関係している。
日本では、大学卒なら皆一律の給料で採用する。この従来の仕組みには大きなイナーシャがあるので、変えるのは難しいが、初任給も能力主義にしないと優れた人材が集まらない。
・企業の製品開発力が大変な勢いで低下している事態の認識と早急な対策を
企業は今、大学で技官がいなくなった以上に、ひどいことになっていると思う。現場で物を作る面で言うと、日本の力はここ10年で壊滅的に無くなってきている。気が付いたら自分のところでは物ができないという時代になりかねない。中小企業群にもかなりボディーブローが効いている状態ではないか。
・人材がベンチャーにのみ流出することへの危機感
今後、ベンチャーに優秀な人が流れる傾向が出るだろう。給与をみればそちらに行きたくもなるのも事実である。それはある意味では良いことだが、日本の産業構造全体を考えた場合、たとえば人材のバランスや従来の日本型企業が果たしていくべき機能など、検討が必要であろう。
・日本における成果主義、能力評価の定着には時間を要する
最近、日本の企業も成果主義を導入するところが増えてきた。しかし成果主義を導入しても、企業の研究所ではテーマも多岐にわたり、研究結果を同じ基準で評価できず効果的に機能しない。
日本の競争意識の甘さの背景には、結果の均等配分を公平ととらえる発想も影響している。米国のように、機会の公平さを重視すべきである。
(2)退職金制度が、日本における人材流動性の阻害要因
米国と日本とでは、人材の流動性に明瞭な差が存在する。その差を生じる本質的な違いは、次のように言える。
米国:バーチャルな可能性に対する先払い(ストックオプション)
日本:リアルな結果に対する後払い(退職金)
両者とも立ち上げの資金負担は少ないが、退職金は流動性を阻害する。
ストックオプションはインセンティブ刺激に最適である。のみならず、テンポラリ敗者の吸収が可能、人材市場へのアプローチが容易、経営者から見て過度の流動性の歯止めにもなる、等、人材活用の仕組みがうまく循環する。
退職金制度は、将来の約束が守り得る終身雇用社会向きである。人材の流動性の観点からは足枷や敗者復活の困難さにもつながり、経営者にとっては大きな資金負担となる。昔の仕組みは、人生に比べて技術革新がゆっくり進むことを仮定していた。日本ではそれがそのままになっているため、情報化時代に適応できていない。ただ、改革は必要だが「退職金をなくす」では、もちろん済まない。技術で儲かる仕組み、ビジネスモデルを開発できる社会制度が必要である。
(3)情報化時代に対応した技術土壌醸成のために、認識・価値観の改革が必要
・知的活動や技術、ソフトウェアに対する正当な評価が必要
日本のユーザはまだ、ハードウェアにソフトウェアが付いてくるのを当然と考え、対価を払う意識がない。知的活動・技術に対して敬意を払い、知的財産を認知する価値観において、世界から遅れている。根元的な価値観は二十才を超えたら教えられないとも言うから、社内教育以前に、教育や文化の基本的な改革が必要かも知れない。
・情報通信技術の特性を考慮した体制・仕組みを
ソフトウェアは、研究開発ともの作りの違いがはっきりせず、製造技術という日本の得意技を活かしにくい。ポイントの見極めと開発リソースの集中が重要である。
研究の質の評価基準を「社会の中でのインパクトの大きさ」や「生活者の文化を変える力が強いか否か」などに求めるニーズ指向の態度も、これからの情報関連の研究者には必要であろう。
構想・着想に対して与えられる、いわば「後付けの報酬」の制度があっても良い。
旧来の発想を延命させている制度がいくつかあり改革が必要である。退職金制度もその一つと言える。
2.4.1 当面の技術シーズ獲得法
|
(1)当面のシーズ獲得の基本はグローバル協同
当面のシーズ獲得は、グローバル協同が基本と考える。米国では民間企業であっても、トップも含め外国人ということがよくある。特定の分野や市場はそれでもよし、とすべきだろう。
世界と対決するばかりではなく、たとえば次期NGIなど、日本として世界各国と協調してやっていくべきである。これは、日本が国家として国際社会の中で受け入れられるかどうかに繋がってくる。
・米国ベンチャーとの協調
米国のベンチャーを探し、開発に必要な環境を提供すると同時に、人的交流によって社内に関連技術と経験をもった技術者を育成するのが一案であろう。
・海外からの参加も認めたプロジェクト
海外のシーズを日本に引き寄せる意味では、傘と棚と予算を用意するニーズ生成のやり方も、形態のひとつとなり得る。
ヒューマンネットワークも、シーズ獲得の重要な要素である。
(2)要求の大きい領域には人が育ち、そこからシーズと人材を得られる
要求の大きいところに人は育つから、そこに人材をシーズと共に求めるのが良い。そして、良い人材は、日本に限らず世界から集めたほうが良い。
しかし、日本に海外から人材が自ら集まることは絶対に期待できない。米国のように、世界から人材が集まってくるような構造になっていないからである(企業は海外に組織があるからこそ人を集められる)。
(3)日本固有の特性の考慮など、発想を柔軟に
米国の優位・攻勢という現状に対し、対症療法としての米国追撃も緊急課題であるが、これと並行して別の取り組み、すなわち次のターゲット設定ができるはずである。
たとえば、日本の特性を活かす情報技術市場対応や東洋的価値観を活かす戦略、あるいは急激な社会環境変化に対したメタレベルでの研究設定も可能だろう。
考慮すべき日本固有の課題には、次の例などが考えられる。
これらをいち早く指摘する役割は、大学・国研に期待するところでもある。
研究の発想をニーズ指向にすることによって、いろいろな研究の種を見いだすこともできる。少子高齢化も、問題であるのみならず、ニーズを生む要素を含んでいるだろう。
そのためにニーズ指向の研究、つまりパラダイムシフトを予測しプランを作成することを大学・国研に期待する。それには経験に基づく基礎力も必要であり、そうでなければ、十分な予測もできない。
2.4.2 国に期待する視点と役割
|
(1)重厚長大だけがナショプロのテーマではない
・今日の研究開発の関心は、「大きい・高度な」よりも社会への影響に向く
具体的な研究分野としては、今は大きな計算機を作る、高度な技術を開発する、等よりも、社会システムの開発やカルチャーを動かすことに大勢の興味が向かっているのではないか。
また、情報は組み合わせによって新しいものが生まれる。ハイテク分野での米国追撃だけでなく、技術の組み合わせ企画力も重要であろう。
・個人の発想を重視した研究開発の支援も必要
協同プロジェクトは平準化されてしまい、なかなか良い結果にならないことも多い。いまは、個人の発想も重要な時代だ。インターネット技術やLinux等、個人のアイデアがデファクトになった例が多い。個人のアイデアの活性化や吸い上げの仕組みがあると良い。
(2)国家戦略として明確なビジョン・旗印が必要
グランドデザインをしっかり作り、それを縦割り行政でなく本気で推進しないと、日本に勝ち目はない。
国の税金を使う以上、国民が恩恵にあずかることを目指し、たとえばミレニアム・プロジェクトを本格的に拡大して考えたらどうだろうか。「ディジタル・ニューディール」、「ヘルシーアンドセイフティソサイヤティ」、「エコロジー」等の旗印の下に、先進的なアプリケーションを構築するプロジェクトを起こして、実現するための基盤技術、ネットワークのようなインフラ、セキュリティの認証とかいうところに焦点をあてる。
米国はプロセッサやOSの領域を席巻している。通信に強い欧州は、通信の競争力強化を目標に方針をたて、それを旗印にして5ヵ年計画でやったりしている。旗印があれば、大学の先生も学生も、そこに集まる。日本の大学では、先生も学生も、なにをやったらいいか分からない状況だといわれている。総理大臣が国家戦略としてテーマを掲げれば、大学院生もテーマに沿った研究をやりやすい。
日本も、国策としてDFSをとるという領域の設定が必要であろう。
(3)情報機器を中心としたユビキタス・コンピューティングは、重要な候補になる
日本のコア・コンピテンスという意味では、携帯電話、ディジタルTV等の情報家電、ゲーム機器などの情報機器の分野に投資すべきである。パソコンに強い米国に対し、情報家電のソフトでは、日本は戦っていけるしリードしていける。強いところを伸ばすという国家戦略ならば、これらの情報機器を核としたネットワーク、サーバも含めたモバイル・コンピューティングとかユビキタス・コンピューティング技術を伸ばすべきである。
(4)直近の技術開発は企業に任せ、国は、基礎・薄利・公益・国家安全の研究を
・国は、優秀な人材の主体性を活かす基礎研究を
目的を限定しない情報通信の基礎研究をやる優秀な研究者が1000人くらい日本にいても良いのではないか。優秀な人材はしばられない方が良い仕事をする。
たとえば、「電総研の研究テーマに注文をつけない」という考え方が必要であろう。
助走研究への支援・出資が必要である。その中から、たとえばビジネスモデルの研究に結びつけることができるものも生まれてくるだろう。
最先端の技術に触れられる環境も、アイデアを先に進ませるために重要である。
・国は、5〜10年先の基礎研究支援を
ソフトウェアの分野は、産業界から見るとソリューションで食べていかないといけない状況にあるが、これは民間の競争の世界である。国の予算で行なうのは、今の壁を突き破るような、5〜10年先を見た基礎研究がよい。たとえば、遺伝子の分析を1日か2日でするなど、今のコンピューティングパワーとは桁違いの性能目標を立て、そのための基礎研究をやる。
インターネットは、繋がる相手も10億人を超え、データもマルチメディアになっているので、従来に比べて一桁二桁大きい性能を必要としている。こうした性能的な目標性能に挑戦するような技術をシーズ志向の研究として国主導でやるべきである。
・国は、大学のサーバや高速ネットワークなど、基盤整備を
研究には3つのフェーズがある。リサーチ、フィージビリティ、すぐ製品に直結するフェーズの3つである。リサーチ・ベースのものは、失敗する可能性が高いかもしれない。したがって、あるリスクをかけて投資する。フィージビリティ段階のものは、技術を持っている大学があれば、企業は大学と協同でやる。そのためには設備が必要であり、サーバ・ファーム、ストレージ・ファームとか高速ネットワークを国の予算で構築し、安価で提供することが望ましい。通信料金の問題は、特に重要である。研究の通信は、極端に言うと、無償にするような方策が必要である。
・国は、薄利で受益者の多いシステムを
ビジネスとして儲からないシステムは、企業ではやれない。たとえば、環境システム、老齢化対応のシステム等は、受益者が社会に広く分布しているが、まとまったお金を得られない。あるいは、国のオペレーション効率化とか、遠隔医療、僻地の医療などの、国がユーザでもあるシステムに対して、国がオーガナイザーになって投資する。この種のシステムは国が取り組むべき対象として重要である。
・国は、国家安全の研究を
国としてやるなら、国を守る研究を含めるべきである。防衛(国内問題を含めた国家安全)、文化、言語、政府機能の整備などを一生懸命やる必要がある。たとえば、事業になるか否かに拘わらず、機械翻訳等に徹底的に資金をつぎ込んではどうか。
(5)企業のグローバルな活動、日本からの国際発信の支援を
・日本発の標準化にはロビー活動が必要
ある標準化の委員会に参加していた頃、数少ない日本発の標準提案に関わったことがあったが、結果的には負けた。自分たちの標準案を通すには、仲間を集めてロビー活動を展開する必要があることを知った。国が、この種のロビー活動を支援してくれると動きやすい。
・外国人からの留学生・研修生の受け入れ推進を
会社でアジアや南米諸国の研修生を受け入れている。それらの国は情報の面では途上国であっても、英語圏との壁が低いメリットがある。加えて、その国に対するビジネスチャンスも増えるし、相手国の技術力向上にも貢献できる。
現在は外国人受け入れ時の手続きが煩雑だが、制度から国際化時代に対応していく必要があるだろう。
・製品の紹介やアライアンスの支援を
通産省JETROなどでやっているかもしれないが、海外の政府とタイアップして日本製品の紹介や、アライアンスの場の設定ができると良い。日本の通産省などに、オーストラリアやイスラエル等の団体が来るが、日本もそうした促進策をもっと積極的に実施すべきである。特に中小・ベンチャー企業は、良いものを作っても紹介する機会が少ない。
(6)大学と企業の協同作業の場を供給することも有用
日本の情報通信産業では、大学・国研が企業にあまりに結びついていない。日本は現状でさえ、情報通信技術の研究者も少ないし体力もないが、大学・国研と産業の繋がりがないと、欧米との間で国の体力の差がますます拡大してしまう。
複雑系の時のサンタフェ研究所のように、優秀なヘッドの下に、関連したテーマを自由に持ち込んで一緒にできる研究サロンを作るのが効果的ではないか。特定のプロジェクト目標で縛るのではなく、コア技術を持った人たちがテーマの周辺に集まった中から、新しいモノができてくることは多い。産学の研究者が集まっているところに自分の研究テーマを持って行き、第三者の評価や競争原理の中で切磋琢磨できる環境は有用である。
欧州の国立情報研究所では、長期的な基礎研究に加えて、国民への恩恵の大きい高度な応用技術の研究もやっている。そこには企業も入ってきている。これらのプロジェクトは産業を活性化して、国家的に先進的情報社会をつくるところにつながっている。こういう仕組みは、日本にはないと思う。
欧州のスパコンの例では、大規模なコンピュータ・センタがあり、クライアントの企業が計算センタ的に運用している。このコンピュータ・センタで、大学で作ったアプリケーションなどをサービスしている。こういったコミュニティから、いろいろなアイデア・ニーズが出てくる。こういう形の産学協同もある。
2.5.1 大学に対する研究支援の現状
(1)金額的には資金が出るようになったが、長期的計画性、戦略性に欠ける
最近では大学にも、大学院を中心に結構な資金が出ている。奨学金も、何万人とかに出す話があり金額も昔より確かに行き届いてきている。
しかし補正予算的な1,2年のものが多く、使いにくい。大学に予算を付けるなら、せめて5年位の長期的計画が必要である。自分は今マッチングファンドで提案しているが、その額では複数のメーカと組むのは無理で、せいぜい1社。そうなると今度は企業が1億、大学が1億のようになり、大学分をちょうど1年で使い切るのが難しい。
面白ければ継続出資するというなら一生懸命やるが、今は1年かぎりだ。だらだら続くのは良くないが、次への連続性は必要である。補正予算などはまずやらせて見るのに使い、良い研究をしていればその先にもう少し大きなお金がつく可能性がありますよ、という制度にしてもらえるといい。また、研究に対する評価を、通産省・文部省・科技庁などで共有して欲しい。
戦略性にも欠ける。資金をプロジェクト・オリエンテッドに出して欲しい。奨学金にしても、学生審査の際にプロジェクト・オリエンテッドでなく(ジャーナルペーパーを出しているか、等)個々の学生の能力で判断するので、ばらまきになってしまう。先生がやりたいプロジェクトがあり、そこでドクターの学生を確保したい、ということから出発するポスドクの制度があればいい。先生がプロジェクトの中で取ってきてあげる、という方が、学生を動かしやすい。働きの良い学生には先生が金額に差をつけたりすれば、先生と学生の結びつきも強くなる。
特定の先生に重複してたくさん出てしまう傾向があるのも問題だ。都合の良い場合もあるが、本来は横断的に厳しく見る必要がある。 委託研究費の25%くらいを文部省が持っていってしまうのは、どういう趣旨なのかわからない。
(2)情報技術の研究員が不足している
教員の総枠を増やせないために、助手が助教授なりに昇格すれば、自動的に助手は減って行く。米国ではプロジェクト予算からポスドクを研究プロパーで抱えることもできるが、現在、日本ではその種の予算が認められない。助手が減った見返りか、今はTA(ティーチング・アシスタント)的にドクターの学生にいくらかのお金が出ており多少は役に立っているものの、絶対額が少ない。
ただし大学側にも問題はある。組織が硬直化して教員や学生の定員を重点シフトできない。「XX学部が弱いからそこを拡張する」、という具合で、強いところがさらに強くなるシステムではない。自分の組織を活性化するということが、すごくやりにくくなっている。
2.5.2 メーカからの期待が小さいことへのコメント
(1)まず大学の研究を正確に見た上で、優れた点をきちんと評価せよ
他者を評価する際、悪い点の指摘に終始して良いところを見ないのは日本人の欠点である。さらにそうした評判を受け売りで広める人まである。修正は必要にせよ、大学の技術の良い点をきちんと評価すべきだ。
デバイス関係に比べソフトウェアは、企業が大学の研究を見に行くことがとりわけ少ないようだ。ソフトハウスやベンチャーを含め、ほとんど来ない。以前、自分の研究が日経新聞に載ったときも、アクセスしてきたのは外国のメーカばかりだった。
日本の研究者は自分の蛸壺にこもる傾向があるが、他の研究も見るべきだ。企業の企画担当者も、自社内の製品企画ばかりでなく、外を技術発掘に回れば面白い技術も見つかるだろう。
TLOは新聞記事ではうまくいっていないケースが書かれすぎるが、いずれ必ず成果が出るだろう。2、3年見てから判断して欲しい。大きなプロジェクトも動き始めている。
メーカは自身の技術に妙な自信を持っているが、大学より上とばかりは見えない。全部書き換えた方がよいと思うようなソフトウェアにしがみついていることもある。
(2)大学も自分たちの研究内容をもっと見せるべき
大学も、見せるものを持たないのは問題。学生も先生も見せることを研究に対するオーバーヘッドと思っている。MITのメディアラボやスタンフォードでは大勢の見学が来るので、学生も一人ひとりが自分をアピールしたいから、やっていることを模造紙などに書いて貼っている。それによってベンチャーの話が出るかも知れない。自分のところでもよくできる学生は、ちゃんと面白いプログラムを作って見せる。見せた結果喜ばれれば、あちこち一生懸命直そうとして研究の質も高くなる。
最近は学会の活動として大学の研究所を見学するというのが減ってきた。今の日本は、見に来ないから用意をしない、見せるものがないから見に行かない、の悪循環になっている。
(3)研究成果を参照・利用した結果のフィードバックを
日本で開発したソフトウェアをみんなで良くしようという姿勢に欠けすぎている。ソフトウェアが良くなるためにはフィードバックのサイクルが必要である。虫があったから使わない、ではなくて、虫を報告したり修正したりする必要がある。あるいは、問題があるなりにも役に立てば、それを使った研究論文は頭書きにそれを書くべきだが、日本ではそれもあまりやらない。
日本のメーカは、国内のサイトに限らずフリーのソフトウェアをよくダウンロードするが、使った結果、修正案などのレポートが全く無いし、中を見たのかもわからない。吸い込む一方なので、海外の人から「日本はブラックホールだ」と評される。
ソフトウェアを作る側にも責任があるだろう。ツールやドキュメント(英語)をきちんと出すことが有用である。ツールできちんとデバッグもできるし、インタフェースを良くすることにより、使う側も使ってみようという気になる。今は裸のままパブリックにすることが多すぎる。
(4)メーカとの協同の場合も、体制としてはポスドク枠拡大を希望
メーカから実務的技能を持った人を大学に派遣し、実習を援助してもらう交流も可能かも知れない。しかし雇うならむしろポスドクが欲しい。
自分がメーカと協同研究をやることになったら、自分の自由になる金の範囲で、研究者を選んでドンとやらせる。優秀な学生と悪い学生では格段に違う。良い学生を確保するのも、先生の能力のうちだろう。
2.5.3 国の支援、プロジェクトの企画運営に対するコメント
(1)インフラ、チャレンジングなテーマにもっと投資を
基盤技術、インフラに対するお金の出し渋りが気になる。自分のやっている言語処理の分野で言うと、辞書作りが重要だが、言語のようにチャレンジングなものはお金をつぎ込んでも無理、と思われているのかも知れない。あるいは、過去にうまくいかなかったと通産関係者に思われているのか。
言語処理では、辞書以外にも言語資源として、例文に解析情報を付けたコーパスを集めることも必要である。たとえばIBMは単語の続き方の統計データに基づく予測を使って音声認識を作り成功した。欧米ではこの種の大きな言語資源構築が盛んになっているのに対して、日本ではいろいろ働きかけても、「基礎的すぎる」「文系の仕事だ」、等の話になってどうも賛同が得られない。大きな資源の構築には時間がかかり急にはできないので、危機感を持っている。音声認識と言葉の理解の違いが分からないなど、関係省庁に適切なウォッチャーがいないためかとも思う。
インフラは成果が見えにくいし、それで儲かったという話もあまり無いが、技術の基礎を押し上げるのは大切だ。
最近、通産省は事業に近い領域に目が行く傾向があるが、通産省はメーカだけでなく大学にも意見を聞くべきだ。
ベルギーにシリコンバレーならぬ「ランゲージバレー」ができて、言語・音声関係の企業を集めている。日本にはそういう動きがない。言葉というとまだものにならないと思っているのか、官僚組織ができているとテクノロジーの動きに対してスピードが遅い。
(2)評価と競争・効率重視でプロジェクトの活性化を
ベースに評価があればこそ、コンペティションも可能になる。今は応募の時に提案の間で比較されるが、本当は成果によってコンペティションは決まるべきだ。その部分の評価が、日本は底抜けになっている。実際のところ評価は難しい。評価する人は、心配であちこち見て歩くくらいでないといけない。
納入物件の評価のために、「プロジェクト評価センター」等の第三者機関を作ればどうか。
プロジェクト編成の際、メーカを均等に入れる発想はやめるべきだ。コンペティションによってどこのメーカにやるか決めれば、皆、必死でやる。参加メンバーは集中して研究すべきであり、分散研究室方式では有機的に機能しない。
会計制度などの制約をどんどん緩め、売れた分が税金として返ってくるという視点が必要だ。
(3)「未来開拓プロジェクト」は全般によい
文部省もいろいろ考え始め、大学の先生を中心にした未来開拓というトップダウンのプロジェクトがある。トップダウンとは言っても、リーダーになる先生に「これから結構大きなプロジェクトに予算がつく可能性があるから、まず何かやってみろ」という感じになる。多少の問題、たとえば学閥ができやすいとか、若い人の自発的プロジェクトでないとかいうことはあるものの、下に良い研究者を組織化しており、仕組みとしてはうまく動いている方だ。
混合型にもいいところがあるが、トップダウン型は「こういうことをやったら面白いのではないか」というのを中心に研究する場合には適している。
(4)独立行政法人化後の基礎研究に配慮を
独立行政法人化によって基礎研究が大打撃を受けるのではと心配だ。学長なり何なりがうまくコントロールしないといけない。英国の大学では利益を上げるところとそうでないところの給与に2倍も差をつけている例もあるというが、基礎研究に冷たい社会になっていくのではないかと懸念している。
現状では、わが国の大学は米欧などの大学に比べ、大学における研究員の雇用や研究予算の使途に関する現場の裁量権、研究成果の扱いなどに関して、国の会計制度や人事院制度などに起因する多くの制約を抱えている。そのような米国などに比べ障害の多い環境の中でも、最近は、産学協同研究に向けた努力がなされている。
その事例の一つとして、並列・分散処理研究開発推進機構(Parallel and Distributed Processing Consortium、PDC)について、その運営形態を取り上げる。
この運営形態をみることにより、その法制度的制約の現場への影響や、大学と企業の間の距離、相互の思い入れの温度差などが間接的ながら観察できる。ここでは、その細部にわたる分析は行なわないが、わが国の産学協同研究の実施例とし、基礎データのひとつとして意義があると考えられることから、ここに収録する。
この事例に関する紹介内容は、2000年3月8日(水)に東京大学で行なわれたPDC成果報告シンポジウム公開討論会のパネル討論「産学協同:PDCの経験と将来展望」における、東京大学
近山隆教授の説明より、抜粋編集したものである。
なお、このパネルは司会、近山 隆 教授、(東京大学)、パネリスト、富田 眞司 教授(京都大学)、後藤 敏 C&C研究所長(NEC)、林 弘 取締役(富士通研)、関口
智嗣 主任研官(電総研)、内田 俊一 所長(AITEC)であった。ここでは、産学協同研究の事例という意味合いから、近山教授、林氏、後藤氏の発言の要旨のみを取り上げた。
2.6.1 PDCの概要
PDCは、並列と分散処理のアーキテクチャから応用までの分野にまたがるわが国の大学の研究の支援と研究交流、さらに、その成果の企業への技術移転を目指して行なわれた。PDCの資金のソースは、関連企業よりの寄付、文部省のマッチングファンド、通産省の公募研究であった。
PDCの運営は、東京大学 田中英彦教授を代表者として、大学のこの分野の研究者を結集して、1995年度から1999年度まで実施された。参加した研究者は、以下の5つの技術部会に分れて活動した。
各カテゴリに参加した研究者数は、それぞれ10人内外であり、全体としては 50人強の研究者が参加した。各研究者は、わが国のその分野を代表する人々より構成されており、また、協力した企業もわが国を代表するコンピュータメーカであった。従って、大学の研究者がイニシアティブを取って、わが国の情報関連分野で行なわれた産学協同研究の草分け的代表事例として意義のある活動であった。
また、最終的な成果物は単なる論文レベルにとどまらず、実際に稼働する、並列マシン、OS、及び応用ソフトウェアなど、従来の大学における研究試作物のレベルを越えたものであった。これらの成果物については、報告書:「並列・分散処理研究推進機構 成果概要 平成12年3月」を参照のこと。
2.6.2 PDC運営の概要
(1)運営形態
PDCの運営は、代表者会議(年1回)の方針に従い、運営委員会(年4回)で予算配分を含む詳細をほとんど決定。その下で各研究推進会員が個別に、あるいは複数で連携しながら研究活動をしてきた。事務処理は東京大学内に置かれた事務局と、(財)ASTEMで行なった。
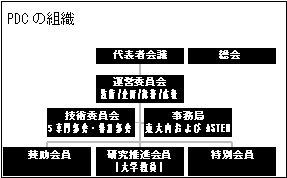
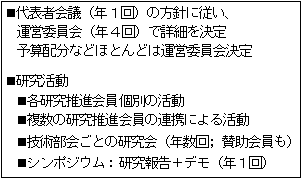
(2)収入
活動してきた過去5年間の、収入合計の内訳は以下の通りとなっている。
1)会員企業からの賛助会費:75%
これらはASTEMに集約された後、各大学への寄付、ないし共同研究資金となる。 会員には会費別にABCの種別があり、成果へのアクセス優先度も異なる。
2)文部省校費「民間等との共同研究」:12%
文部省の枠組みに、国立大と民間企業の共同研究支援制度がある。ASTEMとの共同研究の形でこれに応募した。しかし確定額が小さかったことに加え、費目制限や高天引き率などの使いにくさがあり、申請額は年々小さくなっている。
3)IPAプロジェクトよりの充当分:13%
PDCの研究のうちソフトウェア開発を主とする部分をIPAの公募プロジェクト「創造的ソフトウェア育成事業」に応募し採択された。この事業におけるソフトウェアの研究開発の一部をPDCの活動とリンクさせ、この研究費5億4千万円のうちの10%をPDCの活動費用に当てた。残りはこの事業向けの個別ソフトウェア開発に当てた。
以上の1)〜3)の総和から、事務局経費などを差し引いた分が研究費となるが、これは3億1500万円となった。
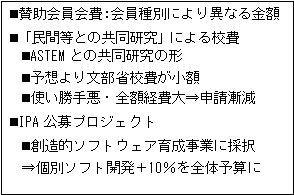
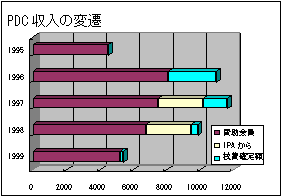
(3)支出
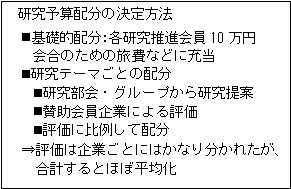
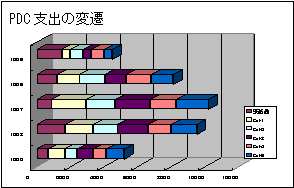
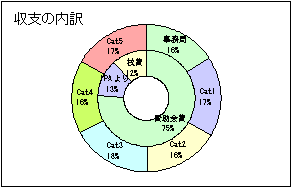
(4)成果の運用
成果は原則公開であるが、賛助会員企業にメリットを持たせるために、公開時期に差をつけ、会員企業には成果報告書の形で早く提供したりしている。ただし成果の多くは論文として詳細に発表されるので、メリットの程は疑問であった。また予算上、研究のかなりの部分を他のプロジェクトで実施したため、公開に支障の生じたケースが一部にあった。
2.6.3 賛助会員企業の意見
2.6.3.1 パネリスト:後藤 敏 氏
(1)参加のメリット
賛助会員として、という以前に日本として、この方面の研究が活性化したのは、非常に有意義である。人材育成など、間接的効果も出てくるだろう。大学との交流が限られた人脈から拡大し、大学側の人材や技術が透明に見え始めた。企業間の横のつながりも、このような機会が無いと難しい。
魅力あるソフトウェアが開発され投資効果が高かったと感じている。寄付なので特定の成果を求めないが、分野のプロモーションが図れればいいと思う。
(2)問題点
PDCへの投資は研究に十分な額とは言えなかった。一方、IPAからのようなパルス的資金やマッチングファンドは、良い面もあるが運営が難しい。PDCが無くても大学は個別に研究をしただろうが、それがオープンになり加速されたことに効果があったと理解すべきか。
企業は投資に対する成果が何かを明確にする。その観点からはばらまき的な面もあったが、今回は短期的ではなく長期的リターンを考えるべきだろう。日本発のオリジナルな成果、すぐに使えるソフトウェアの見極めはこれからになる。
(3)大学への期待
教育は是非、大学で充実させ人材育成して欲しい。特に情報通信分野の博士課程を出る人の数は米国より2桁くらい小さい。企業としては博士課程出身者なら欲しくて仕方がないので、奨学金等、効果の出やすい環境整備を含め期待する。
グローバルな競争を想定し、その中で勝てる、つまり世の中に残り価値を持ち続ける、そういう研究を期待する。元来、研究とは世界初のことをやって世の中の評価を受けるものであり、高いハードルを狙うべきである。
昔は「大学は基礎研究、企業は応用研究」と言われたが、線引きは無用である。
米国では先生が会社を持っているのも当たり前だ。企業も面白そうな基礎研究はどんどんやる。要は日本全体として人や機会を生かせる仕組みが必要だ。
2.6.3.2 パネリスト:林 弘 氏
(1)産学連携の形態
PDCは企業出資を主としたコンソーシアムによる先行基礎研究だったが、産学連携にはいくつかの形態が有り得る。
しかし、最近の国の予算は産官学の連携が条件となってきている。また産学連携は大学が先行していた基礎研究関連に比重がかかるだろう。実用化研究は個別企業とやればよい。他の産学連携の例を挙げると以下のようなものがある。
これらを見ると、基礎研究の産学連携にはそれなりの枠組みが必要と思われる。
(2)産学協同の今後の方向 国家プロジェクトの意義として、次の2点が大きい。