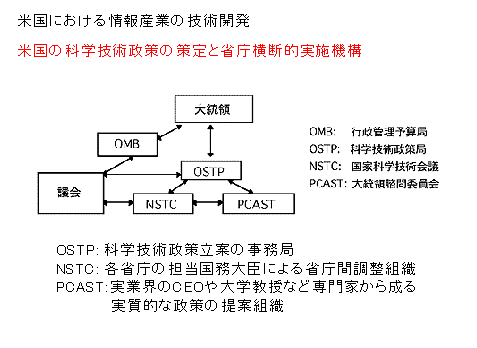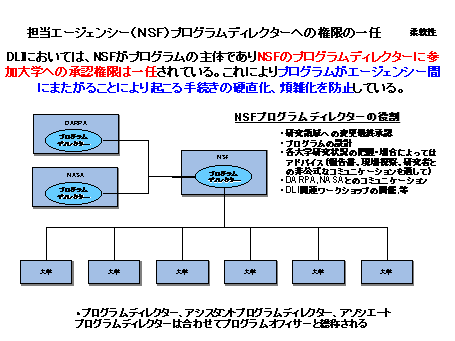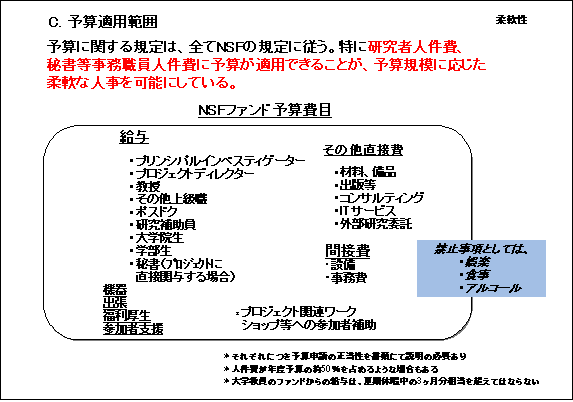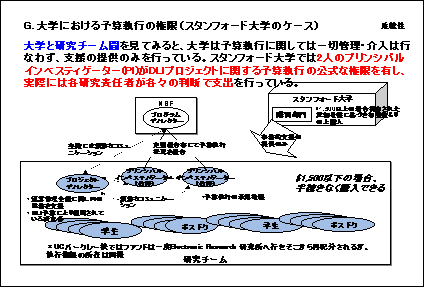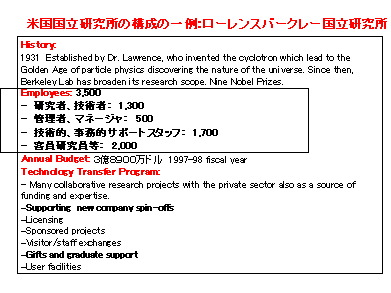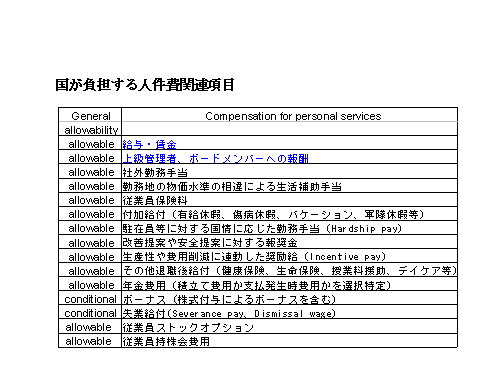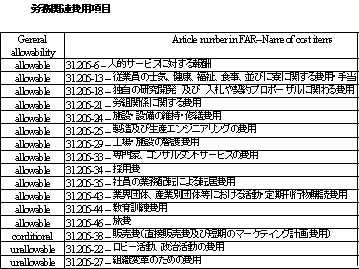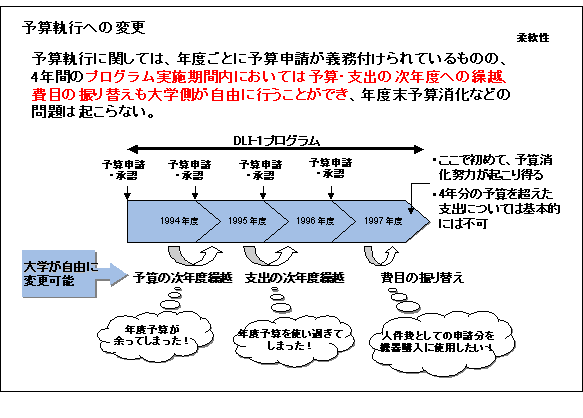第 I 編
わが国の研究開発の仕組み・制度のあり方
-わが国企業は産業の技術シーズをどこに求めるのか?-
第1章 調査の概要と提言
1.1 調査研究の背景
第Ⅰ編では、情報技術の研究開発における「わが国の仕組み・制度のあり方」の調査研究について述べる。これまで本調査研究は、情報革命の先頭を走る米国の情報技術開発の仕組み・制度と、わが国のそれを比較し、わが国の制度・仕組みの抱える問題点を指摘し、その改善策を提言してきた。今年度は、研究開発の基礎研究段階(上流段階)から、実用化段階(下流段階)に注目した調査を行った。
これらの段階は、米国においては大学や国研が中心的役割を演じており、産業のシーズとなる新技術を豊富に生み出している。米国の大学に所属する情報技術関連分野の研究者は約1600人といわれ、さらに、700の国研に雇用されている研究者が8-10万人いて、その20-30%が情報技術関連研究に従事しているといわれている。
人員構成についてみると、大学(主に州立大学)、国研ともに、公務員である研究者数は少なく、多くが連邦政府予算で雇用されたスタッフから成る。 研究リーダは、ほぼ自由に人を雇用できるため、大学院生やポスドクなどを主力に、研究者数の2-3倍の支援スタッフを有する研究チームを組織し、実用レベルの試作システムを作り、商品化を展望した評価を実施することができる。 また、学生も実用レベルの物作りの機会に恵まれ、即戦力となる能力を習得でき、研究成果の商品化を目指して起業する研究者も輩出する。
一方、日本の大学には教育の義務のない研究専門職はほとんどおらず、国研も99箇所あるものの、情報技術関連の研究者数は150人程度と推定される。 その人員構成をみても、公務員の定員削減のしわ寄せを受け、大学、国研ともに、研究開発を支援する技術、および事務スタッフが極度に不足し、国研においては、主任件研究員、大学においては、教授や助教授などの組織の幹となるスタッフのみが残り、枝葉となる支援スタッフが消えた丸裸状態にある。
従って、研究開発の内容も論文中心とならざるを得ず、先端的なソフトウェアやハードウェア試作は困難な状況にある。 近年の大学院の拡充も定員増が困難なことから助手や講師などの定員を、大学院の教授などに振り替えたため、実際にソフトウェアなどを作成できる若い研究者数が減少した上に、大学院博士課程に進学しても、その先の進路が狭められたことから、博士課程へ進学する学生が減少し、ますます実働部隊が減少し、ジリ貧傾向が深刻化している。
わが国の大学、国研は、この20年にわたり、このような空洞化が進行しており、一部の例外的な研究者を除き、産業のシーズとなるような情報技術も即戦力となる学生も生まれ難い状態となっている。国研も同様の問題を抱え、産業のシーズとなるような技術が生まれる可能性は少ない。いくら産学協同研究や産官協同研究が叫ばれても、研究開発の現場では、人不足が深刻で、研究予算が増加しても消化不良の状態となっている。また、企業も、産学、産官の協同研究から産業のシーズとなる技術を得ることについて多くを期待しておらず、大学を学生の供給源としてしか見ていないのが実状である。
わが国全体としての情報技術開発の仕組みを米国と比較すると、上記のような基礎研究段階から、産業のシーズとなる技術を生む実用化段階までを担う大学、国研の格差が大きな問題であることがわかる。
従来、わが国の企業は基礎研や中研を持ち、基礎的、または中長期的研究開発を実施し、自前で産業のシーズ技術を生み出してきた。また、情報革命以前は、デバイスやハードウェア製品の比率が高く、このような製品は研究開発段階に続く製造段階を必要とした。日本企業は、優秀なブルーカラーによるチームワークを生かし、高品質、かつ大量生産による性能価格比の高い製造技術を武器として、国際競争を勝ち抜くことができた。
しかし、ソフトウェアやコンテンツが、製品の主体となる情報技術においては、研究開発の成果が、そのまま製品と化し、販売さえもインターネット上で可能となった。この結果、わが国の競争力の源であった製造技術の優位性が競争力強化に直結しない状況となった。
その一方で、インターネットによる電子商取引などの実現により、市場の規模が全世界に拡大し、競争が激化した結果、各企業は、世界レベルの競争に勝てる技術を残し、それ以外は捨て去るという生存を賭けた経営戦略の転換を行わざるを得ない環境におかれることとなった。このため、基礎的、かつ、中長期的研究テーマのような収率の悪い“事業”はアウトソーシングせざるを得ない状況が生じた。
実際、競争相手である米国企業は、このようなテーマの研究開発は、大学や国研にアウトソーシングしている。さらに、そのような基礎的、中長期的研究テーマの上流段階は、連邦政府予算により、大学や国研が担っており、企業は、その成果を下流で待ち構えていて、産学協同研究の実施による技術移転や、大学の研究者が起業した企業を買収(M&A)して、産業のシーズを得るという、日本企業と比べはるかに有利な立場を確保している。
上記のように、研究開発の仕組み・制度を日米比較の視点から見ると、産業のシーズを生み出す基礎的、または、中長期的研究テーマを実施し、産業のシーズを生み出す強力な大学や国研を持つ米国企業に比べ、弱体な大学、国研しか持たない日本企業は、国際競争力の面できわめて不利な状況におかれていると言える。
1.2 企業の目から見たわが国の大学、国研
今年度の調査研究では、わが国のこのような仕組み・制度上の欠陥に対して、国、および企業は如何に対処して行くべきか、その方策を見出すことを目指した。すなわち、大学や国研にどのような改革を望むか、さらに、当面、産業のシーズとなる技術を如何に入手するのか、といった問題に取り組むこととした。このため「わが国企業は、産業の技術シーズをどこに求めるのか?」という調査課題を設定して、企業や大学の有識者のヒヤリングを行った。これらの調査結果は、第2章にまとめている。
この結果、企業は、わが国の大学や国研について、従来とあまり変わらない、次のような考え方をしていることがわかった。
- 企業は、大学が産業のシーズとなるような技術を生み出し、企業へ提供してくれることを現状では期待していないこと。(従来も、情報技術に関しては同様)
- 研究者の絶対数が不足しており、その研究環境や諸設備も企業が望むレベルの研究開発を実施するには不十分であること。大学が、これらの問題を解決し、企業にとって魅力ある成果を出せるレベルに到達するまでには、長い時間がかかるであろうこと。
- 多くの大学では、人手不足、研究設備の貧弱さ、研究予算不足などの理由もあって、論文重視に偏った評価システムができあがっている。このような環境で育った研究者が産業のシーズとなる実用的技術開発を行うには、かなりの意識改革が必要であること。
- 企業は大学の早急な改革に対しては悲観的ではあるものの、情報革命の荒波を乗り切るためには、教育とともに研究開発能力も強化し、これらを車の両輪と考えバランスのとれた体制のへの改革を強く望んでいること。
- そのような体制は、即戦力の学生を生み出すことになるため、企業は、大学、国研の強化のための協力は惜しまないこと。
- 文部省は依然として護送船団方式をとっているが、国立大学の独立行政法人化は、大学改革のチャンスであり、この機会に大学に経営の自主性や人事権を与え、企業会計や競争原理を導入することで改革を早めることができると考えていること。
- 現状では、多くの国立大学は、人手や予算不足のため技術移転の契約業務や諸経費の費用負担も十分できない状況にあり、なお一層の国の投資が必要であること。
1.3 研究開発の発展を阻害する会計制度などの法・制度上の問題点
わが国の大学や国研の研究開発能力の相対的な弱体化の元凶は、国の研究開発投資の不足とともに、その仕組み・制度面にも問題があることが考えられた。
情報革命の時代に入り、研究開発の現場では、その優劣が優秀な頭脳を持つ人材の多少により決定する、また、研究の進捗のスピードも大幅にアップしている。このような物作り中心から、頭脳労働中心への変化、また、アイデアや新技術の陳腐化の短期化に対して、会計制度や公務員制度など、法・制度が追随できないでいることが考えられたわけである。
この明確化を意図して、国の研究開発プロジェクト実施の仕組み・制度を、研究目標の変更やそのチーム編成などの実施権限の研究リーダへの移管や、予算の使途変更や費目間流用など予算の執行権限や成果の利用の権利関係などに注目して、調査することとした。
このため、米国の連邦政府予算で実施する研究開発計画(プログラム)における運営の仕組みや会計制度などの法・制度について、実際に採択されたプロジェクトを対象として調査し、わが国の仕組み・制度と比較した。
比較結果は、日米の研究開発の仕組み・制度に関して、その運営方法や諸手続き、予算の実施権限、会計制度、成果の管理制度など多くの点で、米国の仕組み・制度が、日本のそれらに比べ合理的、かつ実質的であり、さらに日々進化していることがわかり、研究開発の実施上で、大きな日米格差が生じていることが明らかとなった。
ここでは大きな影響を及ぼす差異について、研究開発の仕組み上の問題点と、法律を含む制度上の問題点に分けて、以下に示す。また、その、より詳細な説明を、第3章、および第4章にまとめている。
1)仕組み上の問題点
a)国全体の情報技術研究開発の将来ビジョンや戦略がない。
米国:
現役の学界や産業界の代表からなる大統領直属の諮問委員会や、省庁間の研究開発を横断的に統合・評価するOSTP、NSTPなどがあり、時代を先取りしたビジョンや戦略を指示し、それが政策となって迅速に実行される(特に、諮問委員会は強力で実効ある提言を行ってきた。古くはヤング・レポート、最近ではPITACレポートが有名)。
日本:
科学技術会議や学術会議、首相直属の諮問委員会などがあるが、メンバーの多くが情報技術開発に携わる現役専門家ではなく、関係省庁の利害対立を超越し、時代を先取りしたビジョンや戦略を打ち出せず、実質的に機能していない(メンバーの若返りと産業界や学界の第一線で活躍する現役の登用が必要)。
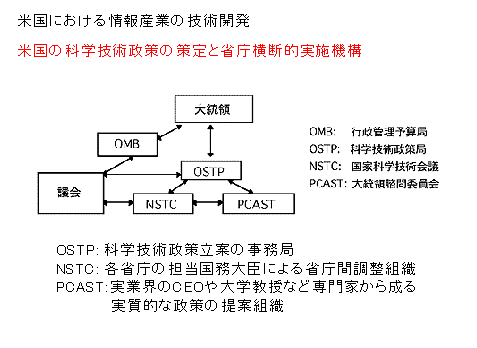
図1.1 省庁間の関連プロジェクト管理を一元化する機構の存在
- b)情報技術や研究開発の中身のわかる専門家が、
- 研究開発計画の運営やその成果を活用した起業支援などの実施を一貫して管理する仕組みができていない。このため研究面や経理面の責任の所在や研究評価基準が不明確で、情報公開や競争原理の導入も不十分。
米国:
研究開発を管轄する省庁側にプログラムマネージャやプログラムディレクタ(PM/PD)と呼ばれる大学の教授クラスの担当者がおり、研究テーマの採択、研究目標の変更、予算査定、費目管理、予算打ち切り、成果利用などを一元管理。急速に進歩する研究開発に機動的に対処している。
日本:
省庁側に専門家不在。大学教授など外部の有識者にテーマ採択や進捗評価、などをその都度依頼する。予算管理など運営は行政官が(2年ごとに交代して)実施する。このため責任者が不明確で、プロジェクトの運営方針も一貫しない。研究開発の現場担当者は、予算要求、計画変更などの説明、評価資料作成などの事務作業が膨大となる。成果利用の手続きも省庁ごとに細部が異なり、事務処理が複雑で迅速な商品化を阻害している。
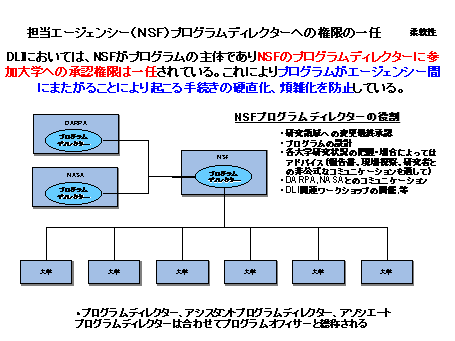
図1.2 複数の省庁からの予算も代表する省庁のPM/PMのもとに一元化
表1.1 運営に関するほとんどの権限がPM/PDと現場へ移管されている。
1)プロジェクト研究領域の変更
2)予算適用範囲
3)予算執行の変更
4)計画(プログラム)運営形態と成果の取り扱い
5)大学等における知的財産権の取り扱い
6)大学等における予算執行権限
7)大学等における人事管理の権限
8)大学等・企業間の協力関係の形成
9)企業の参画形態
|
2)法律を含む制度上の問題点
- a)国の研究開発予算の使途(算入可能費目)の規制が厳しく、
- 使途の変更などの裁量権が現場の研究リーダにほとんど与えられていない。特に人件費の規制がきびしく、研究開発の遂行に必要な人材を雇用し、希望する研究チームを組織できない。
米国:
人件費を含めほとんどの費目が算入可能。研究者や研究支援スタッフなどを自由に雇用し、強力な研究チームを組織可能。 使途の変更や費目間の流用も、PM/PDの合意を電子メイル等で得れば容易にでき、研究環境変化に機動的に対応可能。人件費については各企業の基準に従い、間接費用も算入でき、研究開発の受託がビジネスとして成立。
日本:
研究リーダは研究予算で研究者や支援スタッフを雇用できない。また、作業等を外注する場合も、仕様書を作成した上で見積書などの書類整備が必要。納品物は仕様書と一致していなければならず、変更が頻発する情報技術の研究開発では、仕様書は後から差し替えて対応。人件費については、間接費は算入不可。このため企業が、国の研究開発を受託すると赤字となる。企業の積極的参加を阻害している。
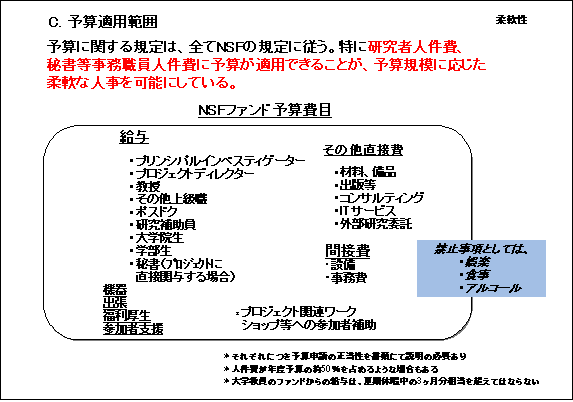
図1.3 プロジェクト予算で人の雇用が可能。ほとんどの費目が算入可能
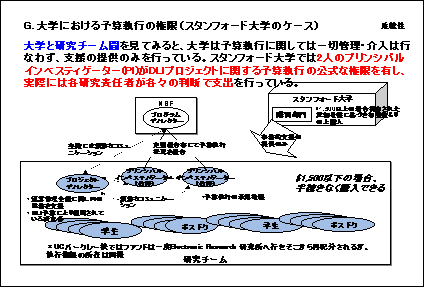
図1.4 予算の使途の規制が少なく大規模な研究開発チームを組織可能
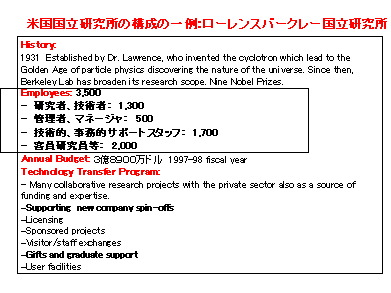
図1.5 米国の国研の人員構成例
研究を支援する管理者やサポートスタッフの数は、研究者の2倍近い。
日本の大学、国研では、このような支援スタッフはほとんど消滅。研究者は丸裸状態。
表1.2 予算の最重要費目は、人件費、労務費に関するものであり、手厚く支援されている。
裸の人件費しか算入できない日本とは大きな違い。
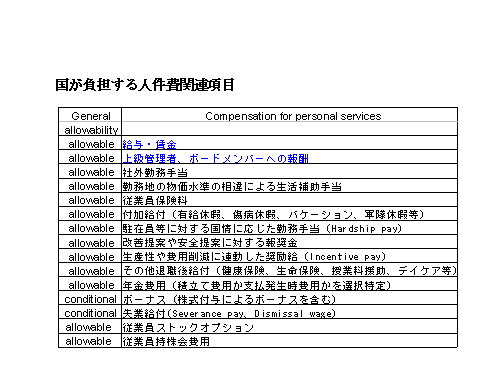
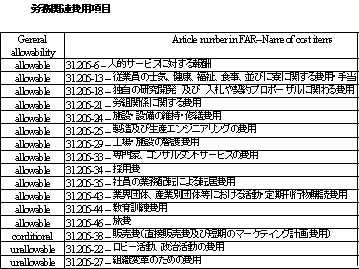
- b)国の予算が単年度会計で毎年度末決算。各費目ごとに完全消化が要求される。
- 複数の省庁から得た予算を合算して使えず別々の会計で決算。成果物も分割して納入することが要求され、多大の事務量が発生。会計検査も書類不備など形式面を重視。
米国:
プロジェクト期間を通した通年度会計。予算の余りや不足は繰り越し可能。プロジェクトの最終年度に決算。異なる省庁よりの予算も合算でき、納入物を分割する必要もなし。しかし、各年度ごとに研究開発目標の達成度合いは専門家であるPM/PDより厳しく査定される。会計検査も形式より実質的成果重視。
日本:
単年度会計であり、費目間流用規制のきびしさ、予算の完全消化の要求、異なる省庁からの予算の合算不可、および成果物の分割納入は、研究開発の現場に多大な事務処理負担を課す。このため、人手不足の大学等の研究の現場は大きな研究開発予算をもらうと論文執筆ができなくなり、返上することもあり(予算が増えても、研究パワーに転換不可)。
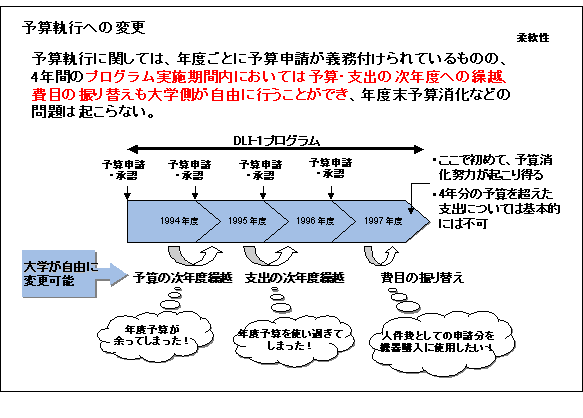
図1.6 プロジェクト期間にわたる通年度会計
この会計制度は、試行錯誤がつきものの研究開発には不可欠の制度。予算も有効利用され、
研究の能率も向上する。 さらに事務作業量も軽減。単年度会計の日本と大きな格差が生じる。
-
1.4 まとめと提言
情報技術革命は、社会の神経網にあたる技術の革新であり、その影響は全産業におよぶ。そして、さらには、企業活動のみならず、行政や社会活動の細部にまで及ぶといわれている。この革命への迅速かつ適切な対応が、国とその国民の繁栄につながることを疑う者は最早いない。これまで産業の近代化に遅れを取っていた諸国も、この革命を自国を先進国へと跳躍させる好機と捉え、国をあげての情報化ビジョンの策定とその技術開発戦略を展開している。
情報技術を生み出す資源は鍛えられた人間の頭脳であり、地下に埋蔵された天然資源などではない。ソフトウェアやコンテンツなど、まさに知識が富となる世界である。これまで蓄積された技術なくしてもコンピュータとネットワークがあれば、そこに産業の新天地が開ける。シンガポールやインドなど、これまでの重厚長大といわれる製造業では振るわなかった諸国が国を挙げて情報革命へ取り組み、数学的教育に優れた人材の活用を進め、情報産業の競争力ランキングの上位に登場してきている。
わが国も情報革命への国をあげての対応を急がなければならない。しかし、現状は「科学技術立国」が叫ばれ、科学技術基本計画が立案され、情報通信分野への国の投資も急増する勢いであるにも拘わらず、情報技術を開発し人材を育むべき、大学や国研が旧態依然たる状況にある。インフラの一部ともいえる国の研究開発の仕組み・制度は、オールド・エコノミー時代の会計制度などの諸規制を引きずっており、未だ改革の手が入っていない。情報技術分野への研究投資を増やしても、この仕組み・制度の改革なくしては、投資効果も半減してしまう。
今年度の「わが国の研究開発の仕組み・制度のあり方」の調査研究は、この面でのわが国の後進性を改めて浮き彫りにしたといえる。どのような事業を起こすにも、人、物、金といわれるごとく、人材、インフラ、資金が必要である。わが国の大学、国研は、この全部が不足し、その原因を作っているのが、人と金を縛っている会計制度や公務員制度などである。
わが国のこれら制度は米国に比較して20年以上の遅れをとっている。米国の現在の連邦政府の仕組みができたのは、大恐慌に端を発した行政改革によっているから、そこを基準とするとわが国の諸制度は、もっと遅れていると言えよう。国をあげてのニューエコノミーに対応できる仕組み・制度作りが今こそ求められている。
本調査研究結果が示唆する仕組み・制度改革は、国の会計制度や公務員制度という、わが国の行政府の根幹に触れる問題であり、省庁のレベルを超えた国を挙げての取り組みが不可欠である。現在、通信や金融などの分野では、これまでのわが国では考えられないような改革がすすめられている。大学や国研は、情報革命を遂行するための原動力となる知識と人材を生み出す場所である。その立て直しは、まさに急務である。
わが国も研究開発プロジェクトの舵取りを、できる限り研究開発の現場にまかせ、さらに予算の使い勝手にしても、米国の制度に見られるように、まず、人材を集めるために使えるようにしなければならない。人件費の間接費分の国の予算への算入などその第一歩であり、早急な改革が望まれる。
米国においては、本報告書の第4章で述べているように、会計制度などを新技術の研究開発の特質に合わせ進化させてゆく努力をひたむきに実施している。政府の研究開発契約の一般事項に記述されている内容を以下に引用する。
FAR - Part 35
研究開発契約(Research and Development Contracting)
35.002 - 一般事項(General)
研究開発プロジェクトを委託契約する主要目的は、科学技術知識の高度化と、その知識を省庁や国家レベルの目標を達成するために適用することである。消耗品や諸サービスの調達契約と異なり、多くの研究開発契約は、その実現に必要な業務の内容や方法が事前に確定できないような目的を持っている。プロジェクトの成功確率や特定の技術的アプローチの困難度などは、事前に判断が困難である。研究開発契約はこのような独特の性質を持っているが故に、その契約プロセスは産業界の最も優秀な能力がプロジェクトに参画することを促進するようなものでなければならず、プロジェクトが合理的な柔軟性と最小限の事務的負荷でもって遂行され得るような環境を保証しなければならない。
この規則は、連邦政府が、研究開発契約にあたって、合理的な理由に基づく柔軟性(例:契約者の自発的会計原則変更やFARからの逸脱を認める等)と契約者に対する行政/事務的負荷の最小化(例:民間の会計原則の全面的採用、自社内の会計原則を一貫して使用することを認める等)、を基本精神としていることを示している。
また、先端技術の研究開発の進歩は早く、法・制度は、どうしてもその進歩に遅れを取り、その障害となることが危惧される。そのような場合には、研究者は、連邦調達規則(FAR:Federal
Accounting Regulation)から逸脱することを認めている。
わが国においても、科学技術立国を国の基本理念とするなら、米国のようなその実現を促進するような仕組みや法・制度を遅滞無く整備してゆくべきである。しかし、わが国の現状を見るに、官学産の改革に向けての足取りはそろわず、ともすれば既得権維持に走り、改革の芽を摘んでしまうことさえ起こり得る状況である。情報先進国の米国の、技術と共に、このような国民重視の基本理念や法制度についてもキャッチアップすべきであり、これを2000年代の国家目標として掲げることを提言したい。
【次へ】