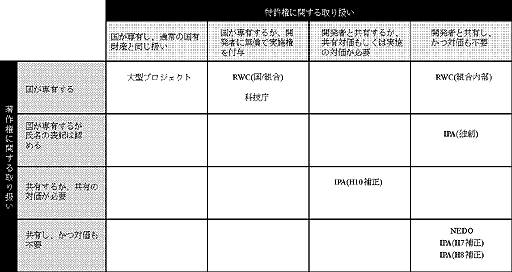
1.3.1 問題の所在
国のプロジェクトの成果としてのソフトウェアには、知的財産権に関する法律、国有財産法などがからみ、権利の帰属や行使の条件に関してやや複雑な状況が生まれる。これに対して常に正しい解を見つけることは難しいが、基本的立場は明らかに、「成果としてのソフトウェアをいち早く普及させることによって産業的効果を生み、社会に広くその利益を還元させるための仕組みをいかにして実現するか」ということである。
議論のポイントとしては、著作権・特許権による権利保護の是非、IPRの帰属先、オープンソース方式によって顕在化してきた問題などが挙げられる。
以下の各節では、ソフトウェアのIPR保護の歴史的側面、過去の国のプロジェクトにおけるIPRの扱い、有識者へのヒアリング調査などについて検討する。
1.3.2 日米を中心としたソフトウェアのIPR保護の歴史
(1)IBMのアンバンドリング政策
| ●1970年頃 IBMがアンバンドリング政策開始。 ・工業製品としてソフトウェアソフトウェア保護の気運が高まる。 ・外国でも有効(ベルヌ条約:当時既に多数の国が加盟)な著作権による保護へ。 ●その後の米国の動き ・1980年 米国の著作権法改正。(プログラム、データベースにも適用へ) ・プロパテント政策推進。 ・1985年のヤングレポート。工業所有権の保護強化を提唱。 ソフトウェア産業を戦略的輸出産業とするための施策の一環。 ・1988年 通商法改正。知的財産権保護強化。 ・1990年 日米知的財産権協議。リバースエンジニアリングに係る規制等を協議。 |
(2)日本におけるソフトウェア保護開始
|
(3)ソフトウェアの社会的地位の向上と国際機関による調整(1990年代)
|
(4)日本におけるソフトウェア権利保護の現状
ソフトウェア権利保護は従来より著作権法による保護が中心であったが、1997年4月1日から施行された新しい特許審査基準により、特許法による保護も現実のものとなった。
1.3.3 過去の国のプロジェクトにおけるIPRの扱い
通産省所管のソフト関連プロジェクトのIPRの扱いの特徴を以下に示す。
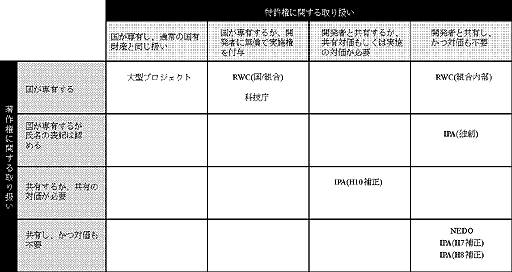
1.3.4 ナショナルプロジェクトの成果としてのソフトウェアのIPRをめぐる議論
成果を産業界に一層幅広く普及させていくと言う問題意識で、IPRに関連するいくつかの話題について、プロジェクトへの関係者13名に対してヒアリングを行った。
(1) ヒアリング結果の整理
各回答者の見解は、大まかに以下の6つの立場に整理できる。
| 1. 現状肯定派 |
成果の普及に際して現状のIPR制度に大きな問題は無い、あるいは少なくとも現時点で制度に関して困惑している事態には遭遇していないとする見方。例えば事務手続きの煩雑さなどの点でIPR制度が完璧では無いにせよ、その問題を具体的に強く指摘できる程に事業化の例がまだ多くは無いと言う認識を持っている。この主張はプロジェクト実施側の回答者に多い。 |
|---|---|
| 2. 成果全面公開派 |
国のプロジェクトの成果は基本的には100%公開すべきであり、そうすることによって成果の普及を最も促進することができるとの主張である。この背後には、ソフトウェアの普及のためにはフリーソフト的発想が重要であること、またそもそも国は基礎研究的な分野にのみ力を注ぐべきであることなどの認識が見られる。 しかし、実体として情報分野の基礎的部分が米国に圧倒されている状況がある。日本が実施すべき基礎研究の分野として成算が見えるのは何か。この選択を誤ると、見返りの期待できない投資を続けることになりかねない。 |
| 3. 国・企業独立路線推進派 |
国のプロジェクトに関連して特に大きなIPRの問題は既に受託者が事前に所有しているノウハウやソフトウェアと国の成果の切り分けの問題であると考えている。問題の一端に国のプロジェクトが企業の製品開発に近すぎる分野を設定していることがあり、国は企業活動から離れたところにその研究開発分野を設定すべきと主張している。 インフラ整備や新技術に関する社会的実験、ニーズ顕在化のための社会的プロジェクトなどが研究分野の具体例の一つである。 |
| 4. 企業優先使用派 |
国の費用を使う研究開発とは言え、実際にアイディアを出して研究開発を行うのは受託側企業である。したがって、彼らにその権利が行かないのは極めて不自然であり、最低限権利は共有することにならないとプロジェクトに参画できないと主張している。 この主張の背後には、研究開発そのものは受託側のコントロールの下で実施されるべきであること、各種事務手続きは研究開発の進行を第一に考えて簡素化されるべきことなどの主張もあり、その意味では残された課題は大きい。 |
| 5. 成果普及懐疑派 |
国のプロジェクトの成果は企業の活動とは直接結びつかないとの見解である。この意見に従うとIPRは大きな意味を持たないことになる。 この主張の論拠にはいくつかのパターンがある。 1. 成果を普及させて行こうにもその市場が見えないと言うもの。 2. そもそも国のプロジェクトでは自社内で抱えているテーマのうち事業化と言う観点では可能性が相当低いものを対象にしており、したがって当初から事業化の意欲を持っていないと言う考え。 3. 基礎的な研究開発ではテーマの将来性を判断することが難しく、したがって、事業性を考えても成功しないことが多いと言うもの。 |
| 6. 脱IPR派 |
IPRは成果普及のために一つの要素ではあるものの、現時点での最重要課題では無いと考えている。ベンチャーにとって最大の問題は顧客を確保することであるとした上で、自らが開発した技術に関する需要家とのマッチングの場を設けることが本質的な課題であり、そういう意味での支援の必要性を訴えている。販売機会の増大、チャネルの確保の問題が喫緊の課題であり、それに比較するとIPRの問題は二の次、言い換えるとまだ問題がそこまで達していないと言う見解である。 |
各立場は必ずしも対立せず、むしろ相互に共通する見方もある。逆にこうした錯綜した状況がIPR問題の込み入った事情を反映していると考えるべきであろう。
1.3.5 ナショナルプロジェクトのソフトウェアIPRのあり方
(1)ソフトウェアの種類とIPR
IPR政策は、成果普及、産業活性化の観点で検討されるべきであり、したがってプロジェクトの種類、目的、普及へのビジネスモデルや開発者の意識などに応じてIPR政策の具体的な運用方針も弾力的に対応できるようになっている必要がある。国のプロジェクトをいくつかのパターンに分類し、委託側はもとより受託側もプロジェクトの目的とそれに対応するIPR政策の意義を明確に意識して、研究開発を進めることが必要である。 以下は分類の一案である。
| 1. 基盤ソフトウェア型モデル |
成果は公共財として位置づけ、IPRも公開を原則とする。成果の波及範囲は広く、国際的デファクトスタンダードなどへの展開も考えられる。囲い込み的なIPR保護政策では無く、早い時期に公表するなどして同調者を増やすことが重要。 |
|---|---|
| 2. 応用ソフトウェア型モデル1 |
企業などでの事業に密接に関連する領域の研究開発。過去の既存の実績を元に研究開発されるスタイル。研究開発プログラムとして実施して成果を共有するかあるいは補助金的な枠で成果は100%受託側に帰属するような仕組みも有り得る。成果のビジネスモデルも視野に入れて事業化が最も容易になるような方向での取り決めを行う。ただし、うまくビジネス化できない場合は国が第三者にIPRを譲渡できる権利を留保しておくことが望ましい。 |
| 3. 応用ソフトウェア型モデル2 |
前者と似ているが、過去の積み重ねと言うよりはむしろ閃き的なアイディアで事業化を狙うような性格のプロジェクト。IPRは基本的に受託側に帰属させることが望ましい。また、採択までの手続きにも従来型の公募、審査、ヒアリングなどの一連の流れとは別に迅速にまた時期を問わず対応できるような仕組みが必要である。 |
| 4. コンテンツ型モデル |
プログラムではなくコンテンツ開発を主な目的とするようなプロジェクトを想定する。コンテンツが関与すると多くの場合、権利関係が非常に複雑になることが予想される。業界融合的な特長や新事業領域開拓などの効果を期待できるだけに権利関係の扱いには留意すべき点が多いと考えられる。波及効果が大きいであろうことから、基本的には開発者と国がIPRを共有し、比較的短い一定の時間を経た後は公開して普及させるなどの方策も考えられる。 |
| 5. 実証実験型モデル |
新しい技術のフィージビリティや各方面への影響の有無などを実際にシステムを稼動させることによって検証することを目的とする。公共性や波及効果が大きいことから基本的には成果は公開することが望ましいと考えられる。 |
実際のプロジェクト遂行の局面では事情は相当複雑になることが予想される。前述したように、これらに対して前もって規則を用意しておくよりは、その都度、誰が成果を享受すべきか、そのための最善の道は何か、といった原則を委託側、受託側共に明確に意識して適切な取り決めができるようになっていることが望ましい。それを決定するためには、特に委託側に十分な体制が必要であることは言うまでも無い。
(2) IPRの周辺の問題に関する議論
成果普及のためにはIPRだけでは捉え切れない多くの問題点が複雑に絡み合っている。最後にそれらの論点を整理する。一定の結論には至らないが、プロジェクトを推進する上で、そうした点への対応、配慮が必要と考える。
a. 起業家マインド
・ソフトハウスなどの起業家マインド
国のプロジェクトの成果を事業化するという意味で強い起業家意欲を持っているという印象が無い。日本におけるソフトウェアハウスの役割やソフトウェア市場の特性(受注生産、請負などの比較的受動的な仕事が多く、ソフトハウスが主導権を握ることのできるパッケージソフト市場などが未発達であることなど)などの経緯があり、起業意欲を持てない、あるいは持っても商業的に報われる機会が得られない構造が続いているためと考えられる。しかし長引く不況によって最近は起業家意識に目覚め改善されてきている印象がある。
・大企業の状況
景気の波によって国のプロジェクトに対する基本的対応を変える傾向が顕著。国の資金を自社資金の不足分を補う意味合いで都合良く考え、好況時には国の資金で具体的な成果を期待せずに先行的研究を行い、不況で自社資金繰りが苦しくなると、国の資金をより事業に密着したテーマに振り向ける。これは首尾一貫性の欠如としてではなく企業経営上の合理的な判断とおそらく考えるべきであろう。いずれにせよ、これを事実として認めると、プロジェクトごとにその前提を明確にして、それに見合ったIPR対策を打ち出す必要がある。
また、国の資金による基礎研究成果の事業化成功には、技術そのものに加えて、技術開発の方向性や市場の熟成などの周辺環境の問題もあり、ことはそう容易では無い。ヒアリング回答者から聞いた、過去に参画した大プロの成果で事業化に成功したものは一つも無い、との嘆息を交えた述懐もそうした事情を反映している。
・多様化する個人の動機 〜著作者人格権を重視する新たな個人パワー〜
台頭が著しいオープンソース方式を支える技術者のマインドにも注目の必要がある。彼らの動機は、自分のソフトウェアが人の役に立つことの充実感、一定の技術者仲間中での名声、技術的な関心などであり、金銭的欲望で行動している訳ではない。
一方で、国のプロジェクトで良質の特許が出ない原因の一つに、国との共同特許では企業内の研究者技術者がインセンティブを持てないとの状況があった。自社内の仕事の関連で特許出願した方が、報奨制度などで自らの金銭的利益に結びつきやすいと言う理由である。
こうした表面的には相矛盾して見える個人の価値観の多様化は、これまでは企業内に埋没していた個人の意志や嗜好が相対的により顕在化した力になるであろうことを推測させる。
b. 国のプロジェクトの範囲
意見は必ずしも一致せず回答者の立場や考え方を反映したものとなっている。(順不同。)
| 1.基礎研究 | 基礎研究というとやや誤解の可能性もあるが、狭く限定せずインフラ整備なども含めた公共の用途を対象にすべきとの意見(成果のIPRもすべて公開すべきとの論旨につながる)。研究開発の一環として国が景気対策に手を染めるべきでは無いと主張。応用ソフトなどは補助金やベンチャー支援予算の範疇で考え、研究開発とは別の次元の話であると言うのが基本的見解である。さらに進めて、ポスト情報時代・環境時代に備えて、エネルギー、食糧、生命科学、社会環境などの研究開発が必要との主張もある。 |
|---|---|
| 2. ワンアイディア型の研究開発 |
従来のような積み重ね型研究開発で成果を出すものだけでなく、ワンアイディアで製品になるような研究開発テーマも増えてきた。こうしたテーマは多くの場合、ベンチャー企業が有していることが多いが、これを国の予算で支援することを考えると、現在の各種の制度はやや硬直的に過ぎるきらいがある。従来とは異なる枠組みのプロジェクトを考える必要がある。 |
| 3. 社会実験型プロジェクト |
新技術が予想外の問題・困難を生むことは技術発展の歴史の常識である。特にネットワーク社会では技術は瞬く間に全世界に広がり、否応なく多くの人々がその技術に関与せざるを得なくなることを考えると、技術のアセスメントの重要性が増す。こうした分野を国が行うべきとの主張であるが、情報分野では技術の有用性を事前に評価することが困難で実際にある程度の規模で使用してみないと客観的な判断を下せないことが多いことを考えると、この主張には一層の説得力が加わる。 |
| 4. 社会的ニーズ |
これまでの国のプロジェクトはシーズ主導の傾向が強く、それが成果が大きな産業につながらなかった一因と考える。まずは市場ニーズが重要で技術はそれにしたがって育成されるとする見解。この前提に立つと、国の役割はニーズ顕在化のためのプロジェクトを起こして技術シーズを高めることにあるとされる。 |
| 5. オープンソース |
オープンソース方式によるソフト開発を、望ましいこと、国も積極的に関与すべきことと捉える意見も比較的多い。さらにNPO的活動をもっと広範囲に支援すべきとの意見もある。ただし、メーカの回答者の指摘として、オープンソースへの関与に対する懐疑的な見解も見られる。すなわち、「それが第三者の権利を侵害していないことの証明」、「動作の保証」が実質的には不可能と言う特性(限界と言うべきか)を持っており、このためメーカあるいはベンダーとしてはオープンソースへの積極的な対応を躊躇せざるを得ない現状がある。国がこの活動を支援する場合でも同様で国の資金的支援を基に作られ使われているソフトウェアが第三者の権利を侵害していた場合への対処を考えると、現実的には関与は容易でない筈と指摘している。 一方で、ベンチャー企業からは、今後は単なるソフトウェア製品の販売ではなくソフトウェアを媒介としてサービスを売る時代の到来が確実であり、国もそれへの対応をすべきとの主張もある。これはオープンソースを基にしたビジネスモデルとかなり近い関係を前提にしているようにも考えられる。 |
c. 社会的文化的な背景
ヒアリングでは、問題の所在を社会的・文化的背景に押し込めて具体的対策案の検討が棚上げされてしまうことを避けるために、なるべく具体的に論ずるよう意識した。にも関わらず、下記のいくつかの問題が指摘されている。
・人の移動
ソフトウェアの事業化は単にIPRの問題に帰着できず、ノウハウを所有する人の移動によって実現されることも多い。
例(MOSAICのケース) : IPRを元に事業化を試みたSpyGlassは失敗し、オリジナルを開発したマーク・アンドリーセンがベンチャー企業に移籍して新たにコードを書き直すことでNETSCAPEとして普及した。
日本は、人の移動が米国に比較して非常に少なく、少数存在する人の移動も米国と逆の方向に向いている。米国では大学人が企業に移籍するのに対し、日本では企業の研究者・技術者が学位を取得し大学に移動する現象が常識的である。この差は社会的・文化的背景の違いによるものと考えるしか無いが、成果の普及を促進するダイナミズムを減ずることは確かであろう。
・優秀な人材が大企業指向
日本の学生は官公庁、大企業、大学などへの就職をステータスシンボルと考える傾向があるが、一方、米国の大学生の成績優秀者はベンチャーを指向すると言われ、好対照である。日本のベンチャー企業は、創業者はそれなりの夢と熱意と覚悟の元に事業を起こすが、組織を拡大しようとしたとき良い人材の確保は至難の技となる。
以上、各回答者の立場や見解の相違に基づいて出された多様な意見を整理した。意見のいくつかは、現在の「IPRとそれに関連する国の政策」の深刻な問題点を示唆している。今後の議論のポイントを提供する主旨で、いくつかについて短く試案を掲げる。
(国が今後のIPR政策の立案・実施で特に考慮すべきと考えられる点)
以上は、問題点の一部であり、それほど難しい課題とは見えないものもあるが、現場では、深刻な問題となっている。
上の点も含め、最終的に重要なのは将来を見据えた研究開発領域に関するポートフォリオ分析の必要性の認識であろう。基礎研究と言い、応用領域の研究と言い、ともすれば委託側・受託側共にその時々の景気動向に左右されて近視眼的に判断し勝ちである。研究開発の成果が社会や産業に影響を及ぼすにはある程度の時間を要する。また、研究開発を推進する人々の意識の変革にはさらに長い時定数が必要である。これらを考えると、将来の国の姿を見据えたバランスの取れた、研究開発目標に関する恒常的な検討と見直しを行いつつ、それと一体化した時代に合ったIPR政策の推進が強く求められる。