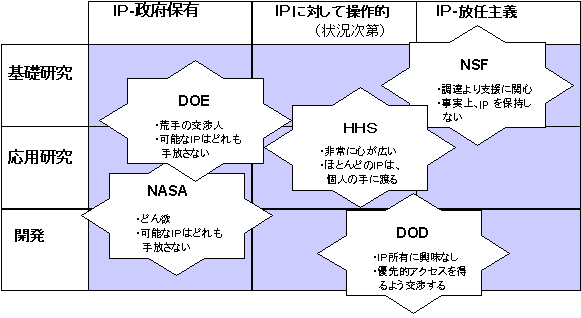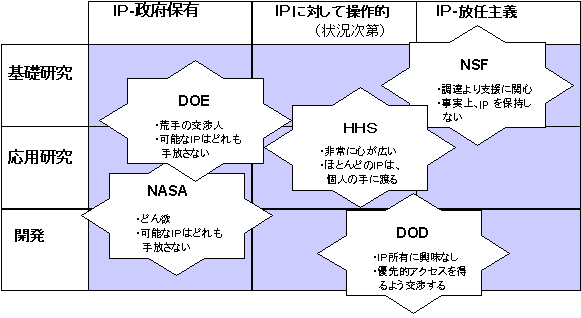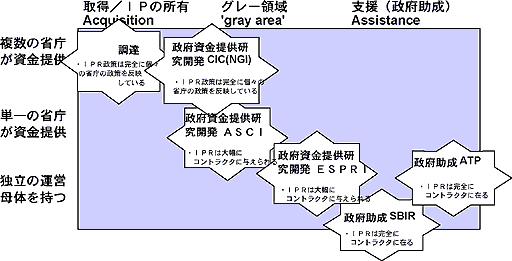【前へ】
1.2 米欧の研究開発プロジェクトにおける知的財産権の取り扱い
1.2.1 知的財産権(IP)の概要について
(1)IPの種類
- 4種類のIPがある(著作権(Copyright)、特許(Patent)、登録商標(Trademark)、企業機密(Trade
secret))。
- 政府資金による研究開発プロジェクトから生じるIPは、著作権と特許である。
(2)IPに関連した法的権利
- 所有権(Ownership):著作権または特許に対する法的「権利保持者としての資格」。
- 利用権(Licensing rights):サードパーティが著作権または特許で保護されたIPを利用する法的権利。
−排他的 or 非排他的
−ロイヤリティ無し or ロイヤリティ有り
- 版権(Publishing rights):そのIPを、条件を設定してサードパーティに配布することができる法的権利。
- 介入権(March-in rights):サードパーティが所有するIP対して、「アクセスする」/「開発に影響を及ぼす」/「使用する」権利。
コントラクターは、IPを所有することができるが、版権を持つことはできない (この場合、IPを自分自身で使うことだけができる)
か、あるいは、IPをサードパーティにライセンスすることを強制される(その場合、IPを商用に使う彼らの能力は限定される)。
政府は様々なレベルのコントロールにより、IPの所有権自体は持つことなしに、IPが将来有益に使われることを確実なものとすることができる。
- 技術開発時に、その技術(が有益なものになるよう)実現の方法に発言権を持つ。
- 版権を管理する。(特定の戦略的技術(暗号解読技術等)に関して。)
- 輸出規制等による管理。(特定の技術の商業取引による敵国への技術移行防止。)
(3)政府資金によるプロジェクトから生じたIPの取り扱いに関する基本哲学
IPの取り扱いは多様を極めるが、究極的には国益を最優先するという目的で一致している。
・ 商用化に近い場合、IPは製品開発できる民間に移転されるのが望ましいと判断される
- 後の政府資金プロジェクトで利用する場合、IPは政府に帰属するのが望ましいと判断される。それによって政府はロイヤリティを支払うことなくそのIPを政府が選ぶ組織に提供できる。
1.2.2 IPに関する法律と政策の背景
(1)IPの法律と資金を拠出する各省庁との関係
- IPの法的取り扱いは、基本的に資金を出す各省庁によって規定される。
- 連邦政府調達購入経費(1996年度1千975億ドル)を見ると、IPが高い比率で生まれる研究開発は全体の15.8%。
- そのうちおよそ半分が契約上は「所有/調達」され、残りは「支援」「協力に関する合意」と位置づけられる。
(2)FAR(Federal Acquisition Regulation)の概要
1. 政府とIPとの関係 ・・・これは、原則としてFARによって規定される。
- 政府の資金提供によりNGOが開発したIPのほとんどは、政府「所有」扱いとなる。(これが全研究開発の約半分をしめる)
- FARは、調達と関係省庁によるサービスにおける、IPに関わるさまざまな条例(例えばBayh Dole法など)の特定の実装を定義している。
- 個々の省庁は、各自のFARバリエーションを制定することが許されており、それが政府のFARに対して優先される。
2. FARと特許 ・・・ FAR 27.302「コントラクターが特許の所有を要求する権利」による。
- 特許に関して政府のコントラクターがその所有を要求する権利を認めている。
- しかし、さまざまな形式的理由による例外が設けられている。
- コントラクターの特許所有が商用化に結びつかない場合、政府がそれを阻むことができる。
3. FARと著作権 ・・・ FAR 27.404「データ(技術の著作権)」による。
- 成果の著作権に関する権利(使用、複製、公開)は自動的に政府に帰属する。
- そのデータがすでに著作権を含む場合、政府は著作権のライセンスを受ける。
- コントラクターからの要求があれば、政府は著作権を譲与することができる。
- 著作権がコントラクターに譲与された場合も、政府はその使用、複製、公開に関する無制限のライセンスを保有する。
- 著作権の譲与が認められない例外も存在する。
4. ソフトウェアの著作権 ・・・ 明確にFARで規定されている。
1976年 著作権条例(1980年に改訂)
- ソフトウェアは「文学的」作品とみなされ、その創作時に著作権が発生する。
(システム、操作方法、プロセスは除外)
- 政府自体が開発したソフトウェアには、特別な条項がない限り著作権がない。
- 政府資金の提供を受けてコントラクターが開発したソフトウェアには著作権がある。
こうしたソフトウェアは商用化が認められる。
- 政府はそのソフトウェアのライセンスを所有して他のコントラクターの使用を認めることが一般的に行われている。その場合は、第二のコントラクターはオリジナルのかたちでそのソフトウェアを商用化することはできない。
5. その他
FAR 27.104(a) :「政府は、研究開発プロジェクトから生まれた技術を、最大限商用化することを奨励するものとする」
(3)ヨーロッパの場合:Espritプログラムの例
ヨーロッパのIPに対する基本哲学は(Espritプログラムに関する限り)、コントラクター側にIPの権利が属するものとし、商用化プロセスを遂行できる手に委ねるものとなっている。
1.2.3 省庁によるIP取り扱いのバリエーション
(1) FARの適用
- FARは、各省庁が独自のFARを設定し、「法律、行政指令、条約、国際的合意が定める特定の必要性に合致させるために」手続き、条項を適用することを認めている(FAR27.101)。
- 大部分の省庁がこれを適用するため、IP政策は省庁による大きなバリエーションが見られる。
- これは、IP取り扱いに関しては個々の折衝の余地が大きいことを意味する。
- 1997 年度の政府資金提供による研究開発のうち、各省庁によるプロジェクトが占める割合と、各省庁のFAR名を以下に示す。
| 省庁 |
政府資金提供研究開発比率 |
各省庁のFARバリエーション |
|
DOD |
47% |
Defense FAR supplement (DFARS) |
|
HHS |
18% |
HHS Acquisition Regulation (HHSAR) |
|
NASA |
14% |
NASA FAR supplement (NFS) |
|
DOE |
10% |
DOE FAR supplement (DEARS) |
|
NSF |
4% |
All NSF R&D funding is made as awards(grants)
and therefore not covered by the FAR |
|
Others |
4% |
|
Note: DOD, HHS, NASA, DOE and NSF together comprise
93%
Source: Federal Funds for Research and Development, 1995, 1996
and 1997
- FARはロイヤリティの支払い、独占権、出版義務といった項目について明文化していない。
各省庁は独自のガイドラインを設けてこれを実践しているのが現状である。
- 契約(FAR)か助成金かCRADAかなど、資金提供のメカニズムによっても、規制には大きな相違が見られる。
- たとえばDARPAには、「その他のR&D取り引き」というカテゴリーがあり、IPの取り扱い条件設定でDARPAが最大にフレキシブルに対応できるようにしている。
(2) 組織による性質の違い
- 各省庁のIP政策は、各省庁の(組織的、歴史的)性質と研究自体の目的の違いによって左右される。
(3)研究の内容による性質の違い
- 開発に重点を置く省庁の場合、プロジェクトの成果は商用製品に近いものとなる。この場合、省庁の目的は商用化となり、それに最も適した組織(大抵の場合、民間組織)にIPが譲与される。
- 基礎研究に重点を置く省庁の場合は、プロジェクトの成果は「基礎的知識」となり、これがさらに新しい研究開発に応用されることもある。この場合、次のプロジェクトに関わる組織がそのIPに(無料で)アクセスできるようにすることが重要であり、IPの帰属先として最も適切なのは政府自身となる。
(4) まとめ
各省庁のIP政策の違いは、その省庁の性質と研究の内容によって左右される。
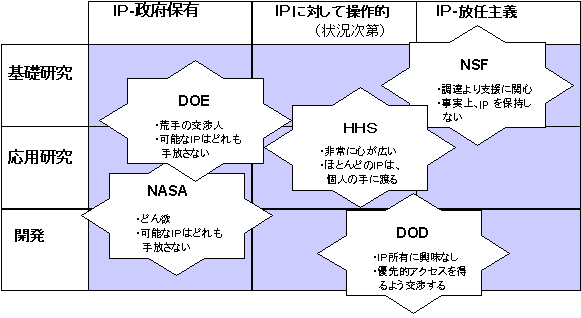
1.2.4 資金提供メカニズムによるIP取り扱いのバリエーション
(1)概要
- 特定省庁のIP政策は、その資金源と契約形態によって分類される。
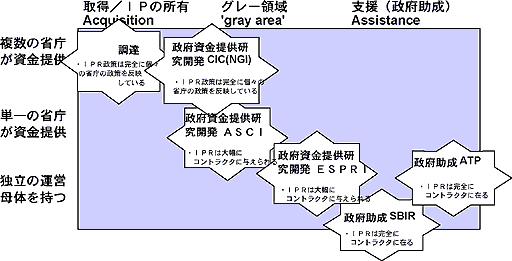
(2)政府資金提供研究開発
- 政府の資金提供研究開発プロジェクトは、その目的、商用化への道筋の長さ、関係庁によって、IP政策が大きく異なる。
a.ASCI(The Accelerated Strategic Computing Initiative)
- ASCIは、核兵器のバーチャル・テストとプロトタイプ化をサポートするDOEのコンピュテーション資源を拡大する目的で実施された数カ年におよぶプロジェクトである。
- ASCIでは、政府によるIP所有と支援というふたつの側面の混在が見られる。
- IP所有 : 政府はスーパー・コンピュータ技術を調達することによって、それを国防他重要プログラムに適用し、核兵器のストックパイル・シミュレーションを可能にしようとしていた。
したがって国防上必要な研究プログラムとしてDOEのFAR、DEARSの規制を受け、これら省庁はその通常としてIPを所有する。
- 支援 : スーパー・コンピュータ技術は、たとえ大きな商用市場があったとしても、政府省庁が優先的な顧客とみなされている。こうした技術は製品として十分な商業市場を確立し難いので、SGI、IBM、
Sun 、DECなど国内企業の国際競争力を強める目的から、政府の資金提供は「補助金」的な意味合いを含んでいる。
- また、プロジェクトの目的はスーパー・コンピュータ技術を用いることにあり、コンピュータ自体にはない。したがってコンピュータ開発の経緯で生まれたIPはいくらか偶発的なものである。
- DOE自体の政策の影響:
- DOEはIPを保有する傾向が強く、また輸出規制によってこの戦略的IPの商用販売を制限する。(DOEの「所有」観念と基礎研究への関わり)
- 以上の結果、ASCIのIP政策はケース・バイ・ケース的な対応が見られる。
b.CIC(Computing, Information, and Communications )
- CICは、National Information Infrastructure (NII)に関する行政イニシャティブ研究開発から派生したものである。
- CIC の場合はアンブレラ・プロジェクトとして複数の省庁が資金提供に関わっており、IP政策はそれぞれの省庁の方針によって定められる。
c.CIC-NGI
- CICのうち特にNGIプロジェクトは、DOD、NSF、NASA、 DOEが資金提供しているが、これもCICと同様、スポンサー省庁によってIP政策は大きく異なる。
- NGIプロジェクトから生まれるIPの大部分は、DARPAの典型的な政策にしたがって民間企業に移転されると考えられる。
- 当初NGIの政策提案は議会で「企業福祉」との非難を浴びたが、その後IPの取り扱いは注意深くモニターされている。
d.ヨーロッパの場合:ESPRIT
- ESPRITプロジェクトでは通常、IP所有と重要な用語(Foreground IP, Background IP,利用、アクセス権、フル・パートナー、アソシエート・パートナー、ライセンシー、重要機密など)について規定した契約が交わされる。
- EUは政府がIPを所有しなくとも、コントラクター以外にも複数の組織にアクセス権を譲与することを強調している。
- だが、原則が守られる限りにおいて、EU政府はIPの取り扱いが関係組織間で自由に交渉され取り決められるのを認めている。
(3)政府調達
- 経費削減のため、政府調達プロジェクトでは、政府自身の使用に付すためにすでに市場にある製品を購入する傾向が強まっており、その場合はIPは民間企業が保有し、新しいIPもプロジェクト契約からは生まれない。
- 政府独自の分類により、すべての調達プロジェクトは契約上は「所有」とみなされる(R&Dの場合は、所有、支援、開発協力に分けられる)。調達プロジェクトの契約はすべて、FARとその省庁の定めたFARによって規定され、IPが生じる場合はその取り扱いは調達を行う省庁の性質と政策に左右される。
(4)政府助成
- 助成制度では、プロジェクトの目的は支援を受ける側が定める。
- 「助成制度」プロジェクトとして用いられた政府の資金は、IPの民間譲与に寛大である。(「所有」プロジェクトとは大きく異なる。政府所有はすべての調達プロジェクトと一部の研究開発プロジェクトに見られ、その政策は各省庁の方針に従うものである。アメリカ政府に貢献する製品やサービスを取得することがその基本的な目的である。)
- 支援金はOMB Circular A-110が包括的に規定する中で各省庁がガイドラインを設定するもので、ビジネス組織以外の非営利団体や大学が受ける。
- 協力に関する合意では、Tech Transfer Act とCRADAが定めるところによって規定される。
条件はフレキシブルで、参加する企業のガイドラインに合致するよう調整されることもある。
つまり政府省庁が研究を支援するのは、連邦の法律の権限によって民間へのサポートや活性化をはかるという目的で行われる。
- またここには明解な政府がIPを所有するプロジェクトか、あるいは明解に助成制度プロジェクトかに分類され得ないグレーエリアがあり、政府に益さなくともIPが政府所有となったり、また反対に助成制度として扱われたりするプロジェクトも存在する。
a.SBIR(Small Business Innovation Research)
- SBIRプログラムの目的は、スモール・ビジネスの活性化によって革新的な技術の開発、商用化をはかることである。これは明らかに支援プロジェクトであり、政府は支援の受領者の選定に関わりはするが、IPは民間企業に譲渡される。
- 1982年のSmall Business Innovation Development Act によって生まれ、1992年のSmall
Business Research and Development Enhancement Actによって2000年まで継続することが決定された。
- 1億ドル以上のextramural R&D予算を持つ省庁はSBIRプログラムを設置することを義務づけられ、その予算の規定の割合(1983年には0.2%だったが、徐々に拡大して1997年度は2.5%)をそれにあてるように定められた。
- 支援金には付帯条件はなく、支援金は革新的なコンセプトの実現可能性を探る企業への支援(7万5000ドル)と、その中から実際に商用化まで遂行できる企業への支援(75万ドル)の2段階に分類される。付帯条件がないことによって、他のプロジェクトに比較として官僚的な手続きが少なかったことが長点として挙げられるが、一方でSBIRプロジェクトの成果のレベルはあまり高いものとはなっていない。
b.ATP(Advanced Technology Program)
- ATPは、ハイリスク、ハイポテンシャルな技術の研究開発を支援することで産業を活性化するという目的に基づいて1990年に設立され、1999年度には2億6000万ドルで運営される。すでに商用的な成功を収めたプロジェクトも数件ある。
- 運営はDOCに属するNISTが行う。
- ATPプロジェクトは「協力に関する合意」として成り立っており、IPは基本的に民間企業に移転される。プログラムの性質上、支援金の受領者は技術の特許申請ができる営利組織を含まねばならない(非営利組織の場合は、合意に基づいてその企業から支払いを受けることができる)。企業が単独で支援金を受ける場合が多いが、これは商用化を簡単にすることやIPの契約を簡略化することにもつながる。ATPプロジェクトから生じた特許は、米国企業に帰属しなくてはならない。また重要なのは、IPは支援を受ける民間企業に授与されるが、企業が商用化に失敗した場合、政府はIPを差し押さえる条項を設けることができる点である。
【次へ】