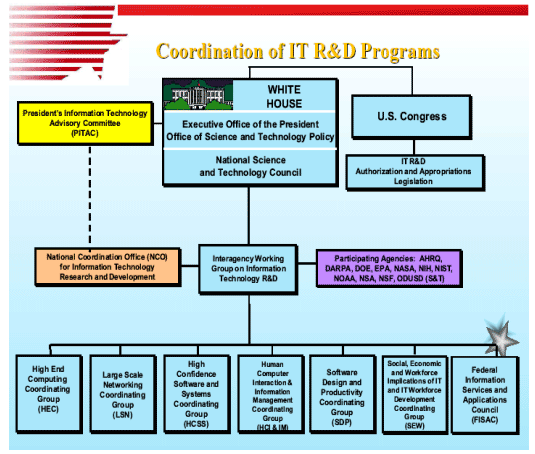
図2.1 NITRD推進体制
第2章 米国のハイエンドコンピューティング研究開発動向
ブッシュ政権初のFY2002 Blue Bookは 2001年8月に開示された。政権が民主党から共和党に交代しての最初であり内容に期待したが、ページ数も50ページとFY2001の1/4の内容になって期待はずれ。 IT
R&D計画自体が民社党特に政敵であるゴア氏の功績が大きいので、あまり宣伝したくないというのも感じられた。基本的な枠組みは共和党になったからといって大きくは変わらず従来の枠組みを踏襲している。名前だけは先頭にNetworkingを付けて、NITRD
(Networking and Information Technology and Development)に変更している。従来から2001年9月に下院を通過したNITRD法案は、上院を通過していないので正式な法律にはなっていないが、Blue
Book内にも法案通過の記述があり政策はその流れを継承していると思われる。(長期に渡るIT研究開発予算が認可されたのでは無いと言うことであろう。)
内容は具体的な研究内容の紹介が多かったFY2001とは異なり、どのような目的でどのようなブレークスルーを目指すかといった一般国民受けのする概念の表現に変わっている。従来の省庁間をまたがる推進体制と6つのPCA(Program
Component Area)自体は変化していない。
全体の推進体制をNational Coordination Office(NCO)の発表プレゼンテーション資料 “Federally-Funded Information
Technology Research and Developmentモ( Jan 9 2001 発行)から見てみると図2.1の様になっている。
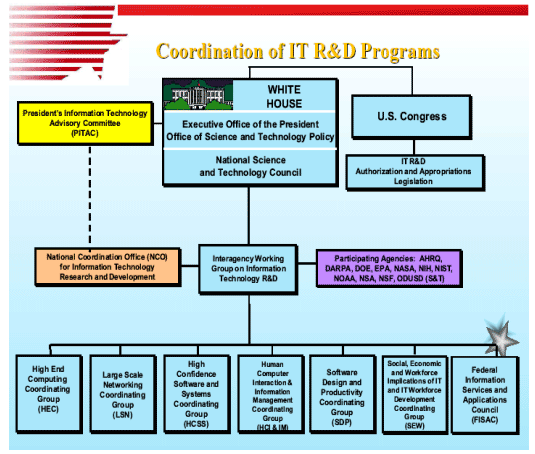
図2.1 NITRD推進体制
NITRD計画の研究開発実体は、次の6つのPCAので推進されており、以下のグループ(Coordination Group)がある。
| 1) | ハイエンドコンピューティング(HEC: High End Computing) ここは更に2つに分かれている。(図2.1には記述はされていない) ・High End Computing Infrastructure and Application (HEC I&A) ・High End Computing Research and Development (HEC R&D) |
| 2) | 大規模ネットワーク(LSN: Large Scale Network) |
| 3) | 高信頼性ソフトウエアとシステム(HCSS: High Confidence Software and System) |
| 4) | ヒューマンコンピュータインターフェース及び情報管理(HCI&IM: Human Computer Interface and Information Management) |
| 5) | ソフトウエアの設計と生産性(SDP: Software Design and Productivity) |
| 6) | 社会、経済及び労働力の面から見たIT労働力開発の意味(SEW: Social, Economic and Workforce Implication of IT and IT Workforce Development) |
NITRD計画への参加省庁は下記12省庁である。
| 1) | National Science Foundation (NSF) |
| 2) | Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) |
| 3) | National Institutes of Health (NIH) |
| 4) | National Aeronautics and Space Administration (NASA) |
| 5) | Department of Energy Office of Science (DOE/OS) |
| 6) | National Security Agency (NSA) |
| 7) | National Institute of Standards and Technology (NIST) |
| 8) | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) |
| 9) | Agency for Health Research and Quality (AHRQ) |
| 10) | Office of the Deputy Under Secretary of Defense for Science and Technology(ODUSD (S&T)) |
| 11) | Environmental Protection Agency (EPA) |
| 12) | Department of Energy National Nuclear Security Administration (DOE/NNSA) |
基本的に昨年FY2001と同じであるが、ODUSD (S&T)は昨年はOSD/URI(Office of the Security of Defenseユs University Research Initiative)と記述されており、監督省庁名が変更された。
2.2.2 High End Computing予算規模
既にNITRD FY2003の予算要求は発表されているが、詳細のIT研究開発予算の配分はこれからになる。よってFY2002 Blue Bookで纏められているFY2002の要求予算にて各省庁の予算規模を見てみる。表2.1に予算要求額を示す。
表2.1 NITRD計画 FY2002年度 予算要求
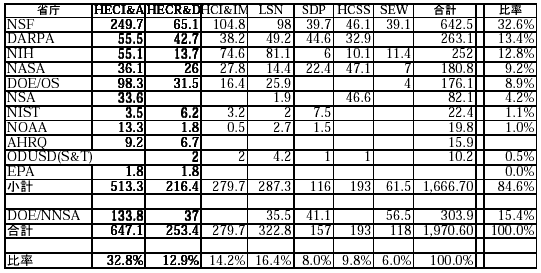
NSFが最大の予算を使い、IT関連の取りまとめ的な役割を果たしている。
FY2002のHEC関連であるHEC I&及びHEC R&Dの予算要求額は合計で900.5Mドルであり、IT関連予算の50%弱を占める。米国がもっとも重視していることがうかがえる。
既にFY2003の省庁毎の予算要求はでており、Office of Science and Technology Policy (OSTP)が発表する資料(
http://www.ostp.gov/html/NetworkingI
TR&D.pdf )によるとNITRD総額ではFY2002実績値の3%増加の$1,890Mになっている。PCA毎の分類はまだ纏まっていない。表2.2に予算概要を示す。
| 2002 ($M) |
2003 ($M) |
増加率 | |
| National Science Foundation | 676 | 678 | 0% |
| Health and Human Services | 310 | 336 | 8% |
| Energy | 312 | 313 | 0% |
| Defense | 320 | 306 | -4% |
| NASA | 181 | 213 | 18% |
| Commerce | 43 | 42 | -2% |
| Environmental Protection Agency | 2 | 2 | 0% |
| TOTAL | 1,844 | 1,890 | 3% |
2.2.3 NITRDの研究テーマ
FY2002 Blue Bookでは中長期の研究課題を10個の研究のチャレンジ課題、および7つの国家的グランド・チャレンジ課題の2つのグループにカテゴリ分けして纏めている。
あまり専門技術的でない言葉で国民に語るように、書き方を変えている。
2.2.3.1 研究チャレンジ
中長期の研究課題が中心となっている。詳細項目は各PCAで検討されているはずだがここでの表現はPCAの枠を消している。以下の10に分類されている。
| (1) | 次世代コンピューティングとデータ記憶技術 HEC I&A が中心、ASCIを含む |
| (2) | シリコンCMOS における障壁の克服 HEC R&Dが中心。量子コンピュータ、DNAコンピュータ、光テクノロジ |
| (3) | 21世紀のための多目的、安全、拡張可能なネットワーク LSN中心でスケーラブルが強調されている。SII(Scalable Information Infrastructure) |
| (4) | 科学と工学における米国の強みを維持するための先進的IT HECC,LSN含む。モデリング、シミュレーション等ハイエンドアプリケーション |
| (5) | 重要なシステムにおける信頼性と安全な運用の確保 HCSS中心。高信頼性とセキュリティ |
| (6) | 現実世界のためのソフトウェア作成 SDP中心。高品質なソフトウエア設計と生産性 |
| (7) | 人間の能力と万人の進歩に対する支援 HCI中心。ユニバーサルアクセス、可視化、口語による対話等 |
| (8) | 知識世界の管理と実現 IM中心。ディジタルライブラリ、データマイニング、検索エージェント等 |
| (9) | 世界レベルのIT 要員の教育と育成の支援 SEW中心。ITリテラシー、指導者の訓練等 |
| (10) | 利益を最大化するためのIT の効果についての理解 SEW, FISAC(米連邦政府情報サービス・アプリケーション協議会)関連と思われる。 |
なお、わずかながら各チャレンジの省庁毎の代表的研究課題は紹介されている。これには必要以上に詳細研究内容を発表しないと言う国防上の気遣いも感じられる。
2.2.3.2 国家的グランド・チャレンジ・アプリケーション
国民に直接利益のある国家的グランドチャレンジとして次の7つをあげてる。
| (1) | 次世代の国防と国家安全保障システム |
| (2) | 全国民のための改良された健康管理システム |
| (3) | 科学的に正確な人体の三次元機能モデルの制作 |
| (4) | 大規模環境モデリングとモニタリングのためのIT ツール |
| (5) | 生涯学習のための世界最良のインフラストラクチャの創出 |
| (6) | 危機管理のための統合IT システム |
| (7) | 先進的航空管理のための技術とシステム |
これらはNITRD計画が中心であるが、その他の研究開発の成果も含まれている。近未来の国民生活に影響の強い、分かり易い研究開発となっている。
2.2.3.3 ハイエンドコンピューティング(HEC)の目指すブレークスルー
HECで特に関係の深い4つの研究チャレンジについて、各が追求するブレークスルーは次の様になっている。
(1)次世代コンピューティングとデータ記憶技術
(2)シリコンCMOS における障壁の克服
(3)21世紀のための多目的、安全、拡張可能なネットワーク
| − | 光ネットワーキング(フロー、バーストとパケット交換。アクセス技術。毎秒ギガビットレベルのインタフェース。プロトコルの階層化。) |
| − | ネットワークのダイナミクスとシミュレーション(自動管理、自動リソース回復、ネットワーク・モデリング) |
| − | 耐故障性と自律的管理 |
| − | リソース管理(発見と仲介、事前予約、共同スケジューリング、ポリシー駆動型の割当メカニズム) |
| − | 無線技術(発見、共存とコンフィギュレーションのための技術標準) |
| − | 帯域幅に対する要求を支援する能力の増強 |
| − | 頑強性の改善、数十億のデバイスの一時的相互作用の取扱いとネットワークの遠端からのアクセスを最大化するためのネットワークの増強と拡張。これにはユビキタス・ブロードバンド・アクセス方式、無限ネットワーキング、セキュリティとプライバシ、ネットワーク管理等の研究がある。 |
| − | 地球規模のネットワークおよび情報インフラストラクチャを理解すること(エンドトゥエンド・パフォーマンス、バックボーン構造、アプリケーション) |
(4)科学と工学における米国の強みを維持するための先進的IT
2.2.3.4 FY2003予算に見る研究開発目標の特徴
FY2002 Blue Bookは同時多発テロ以前にまとめられたものであり、この対策は意識的には加味されていない。先に述べたOSTPのFY2003予算の分析資料にはテロ以後の対策を含むNITRDの目指す重点目標が簡潔にまとめられている。詳細は別途FY2003
Blue Bookに纏められるはずであるが、それの予告が見られるのでここに紹介する。
次の様な技術の開発を達成することを重点課題に挙げている。
| (1) | エンドツーエンドの光ファイバーネットワーク これはネットワークバンド幅とネットワーク・セキュリティの大幅の向上をもたらす。 |
| (2) | クラスタおよびGridコンピューティングを可能にする新しい技術 これは科学研究ネットワークのための高性能計算機への初めてのアクセスをもたらす。 |
| (3) | ネットワーク・セキュリティ・プロテクション技術で次のようなものを含む。 不正侵入検出、リスクおよび弱点解析、大規模情報レポジトリーの管理、運用 |