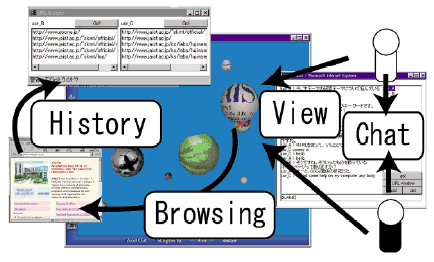
図 3.4-1 WWW探索アウェアネス環境
報告者: 國藤進委員
3.4.1 はじめに
グループウェア研究が一段落した1990年代になって、同期・対面環境ではあたりまえの存在感、実在感や臨場感が双方向通信環境では欠落していることに気づき、存在感、実在感や臨場感などのアウェアネスを補完する研究[14]が勃興してきた。その草分けはDourishらの「だれがだれと話し、だれが話し手や聞き手の周辺にいるか、彼らはどの様な行為をしているか」[1]といった日常の同期・対面作業ではあたりまえの情報が双方向通信環境では欠けているという認識から出発した。そこで報告者らは存在感や実在感のアウェアネスを伝達する双方向通信環境構築を踏まえて、最終的には対面環境以上の臨場感のアウェアネスを伝達する双方向通信高品位A-V環境を構築してという研究目標を立てた。
実際、分散協調作業の進捗を支援するにはアイコンタクトのできる環境を必要とするという視点から、石井はすでにゲイズアウェアネス[9]の提供できる環境を構築していた。仮想空間でのオフィスでの出勤感や連帯感を高めるための位置アウェアネスの研究[3]、会話開始のためのきっかけを作るための同じ作業をしていることを相手に気づかせる存在のアウェアネス研究[15]、インフォーマルなコミュニケーションを促進させるインタレストアウェアネスの研究[16]などが積極的に行われた。このような研究の延長線上にナレッジアウェアネス[28]、情報取得アウェアネス[11]、WWWアウェアネス[18]、コミュニティアウェアネス[8][20]などのさまざまなアウェアネス研究が行われている。最近のグループウェア、CSCW関連の国際会議では、何らかの意味でアウェアネス関連の研究と言えるものが激増している。
そこで報告者らは臨場感、氛囲気、気配、熱気、凄みなどのアウェアネスを伝達できる遠隔コミュニケーション技術の研究開発を行った。これにより、分散環境でも対面環境と同様な突っ込んだ遠隔会議[15]や遠隔教育[21]が可能となることが期待できる。さらに、日本学術振興会・未来開拓学術研究推進事業宮原プロジェクト「未来映像・音響の創作と双方向臨場感通信を目的とした高品位Audio-Visual
Systemの研究」の深い感激をも伝達できる電子的A-Vシステムの提供により、深い感性をも共感できる双方向通信基盤が構築できることが期待される。
まず3.4.2節で、同期・対面環境で自明の存在感、実在感、臨場感を、双方向通信環境でも伝達できる遠隔アウェアネス通信の研究のサーベイ[14]を行い、報告者ら独自のアウェアネス通信の体系的分類を行った。それによると、アウェアネス研究の分類には、協調作業におけるアウェアネス、情報・知識共有におけるアウェアネス、臨場感支援としてのアウェアネス、視覚・聴覚以外のアウェアネス、気配や状況のアウェアネスといった分類が考えられ、それぞれ活発な研究開発がされている。
それに対して報告者らは浅い感性を伝達する個別アウェアネス研究を3.4.3節で、それらを統合するアウェアネス研究を3.4.4節で、さらに、深い感性を伝達するアウェアネス研究について3.4.5節で述べる。報告者らは従来から非同期の分散環境であるWWW環境で、存在のアウェアネスや動作のアウェアネスを提供する環境の構築を行ってきた。高品位なテキスト、手書き文字、静止画像や動画像を用意することによって、どれだけ対面環境と同等あるいはそれ以上のA-V環境に近づきうるか、そのために何を用意すべきかが課題であったが、「高品位」A-V環境を用いることにより、著しく感性の伝達が効果が高まることを明らかにした。
浅い感性の個別アウェアネス研究として、報告者らは情報取得アウェアネス[11]、WWWアウェアネス[18]、WWW探索アウェアネス[22]、およびカンバセーションアウェアネス[4]という概念を実現する環境の構築について3.4.3節で述べる。それらの統合アウェアネス環境の構築については、デモ展示会場におけるコミュニティの知的活動を支援するコンテクストアウェアネス環境の構築事例[6][24]を、3.4.4節で紹介する。
深い感性のアウェアネス研究の第一歩として、宮原プロジェクトの成果の脳科学的インプリケーションを明らかにする実験を行った。この結果は、3.4.5節に要約されるように、高品位A-Vシステムの静止映像を用いて高品位映像を表示すると、アルファ波が従来画像よりも発生するという興味深い成果[2]を得た。
勿論、深い感性を伝達するには、宮原プロジェクトのように視覚・聴覚の見えざる因子を探すというアプローチ以外に、触覚や嗅覚のような他の感覚情報を伝達することでアウェアネスを深めるアプローチがある。これに関して岡田らは多地点同期型メディア空間におけるアウェアネス支援方法を研究した。試作した芳香発生装置を用い、臭覚情報の提供の効果を確認する臭覚アウェアネスの研究[19]を行った。また宗森らはローケーションアウェアネスの研究として、遠隔地での移動グループ間の気配の伝達実験を行った。お互いに離れており、かつ移動中の環境における気配といったアウェアネスを、双方向に伝達する方法として、音や振動の効果的な利用法を検討し、実際の遠隔地間でシステム[17]に適用した。
3.4.2 アウェアネス研究の分類と動向
アウェアネスを分類する軸にはさまざまなものがあり、多くの人々によってアウェアネス関連研究が行われているが、ここでは便宜上、5つの分類についてのみ述べる。
3.4.2.1 協調作業におけるアウェアネス
協調作業のプロセスを、同じ場所に集合するコプレゼンス、他者の存在や動作に気づくアウェアネス、円滑な会話を進行できるコミュニケーション、そして実際に協調作業を行うコラボレーションという四つの軸で分類するのが松下・岡田の分類[16]である。中川のWWWアウェアネス[18]はこの存在と動作のアウェアネスを、WWWの利用者がリアルタイムに利用できるようにしたものである。なおチャットベースのツールCHOCOA(http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/free/chocoa)も存在のアウェアネスを利用したツールである。
3.4.2.2 情報共有、知識共有の場としてのアウェアネス
山上は「協調行動過程支援において必要となる情報共有過程に関して、グループメンバが相互認知し、気づくという概念」[28]として、ナレッジアウェアネスの概念を提唱した。すなわち、オフィスにおける知的生産性を向上させるための、情報の共有を促進するコミュニケーション手段という概念の提唱である。このナレッジアウェアネスの特殊なものとして、組織におけるノウハウ知の共有促進、組織知の再利用促進をはかる仕掛けを実装したのが門脇の情報取得アウェアネス[11][12]である。この研究の方向性は、ナレッジマネジメントにおける情報共有あるいは知識共有の重要性として再認知されつつある。なお学習環境の討論の誘発を目的としたナレッジアウェアネス研究[21]もある。
3.4.2.3 臨場感支援としてのアウェアネス
形式知を暗黙知に変換する、あるいは暗黙知を暗黙知のまま伝達するには対面環境と同様な臨場感を提供する必要がある。そのようなツールをそれぞれ内面化支援ツール、社会化支援ツール[13]と呼ぶことにすれば、それらはどのような機能を提供すべきであろうか。既存のマルチメディアグループウェアが視覚・聴覚情報の伝達装置であることに注目し、アイコンタクトのみならず画面上のどこを見ているかの動作をアウェアさせる装置が石井のClear Board[9]である。
3.4.2.4 視覚、聴覚以外のアウェアネス
臨場感は視覚、聴覚以外の情報の伝達も伴って、初めて成立するという立場で、臭覚、触覚、味覚情報までも分散環境で伝達しようという研究開発もある。岡田らの研究では、森林やお化粧の匂いを伝達する特殊な装置[19]を研究開発中である。化粧品や花の仮想空間上でのバーチャルショッピングには必要な機能かもしれない。なお味覚のアウェアネスの研究のみ、不思議なことに未だ行われていないようである。
3.4.2.5 気配や状況のアウェアネス
ビットの世界と物理世界を融合した気配や状況を伝達できる環境を構築しようというのが石井のタンジブルビッツプロジェクト[10]である。各種センサによる情報獲得、レーザを含む多様な出力装置を活用し、気配や状況に応じたアウェアネスを提供することにより、デジタル世界に相互交流できる物理世界を実現できる。デジタル空間と物理空間が融合する、あるいは仮想世界と実世界が融合する新しい知の空間を設計する場合、新しい建物のアーキテクチャをデザインするときなどに有効であろう。
3.4.3 浅い感性を支援する個別アウェアネス研究
本節では、浅い感性を支援するアウェアネス研究のうち、報告者らの個別研究成果のトピックについて述べる。
3.4.3.1 情報取得アウェアネス
山上のナレッジアウェアネスの概念を組織知の共有・再利用プロセスに活用しようという研究から生まれた。門脇は「システム内に蓄積されている情報の再利用を促すために、コンピュータを用いて、情報の存在、周囲の情報共有活動などをユーザに気づかせる技術」として、情報取得アウェアネス概念[12]を導入する。具体的には時節の視点からのアウェアネス、組織の視点からのアウェアネス、他者の視点からのアウェアネスを提供した情報共有促進支援システムGGG(information Grasp with fishGlobe for GoldFISHes)[11]を実現した。上記3種のアウェアネスを付随機能として付与したGGGを実際に13人のユーザが3ケ月に渡って試用、評価実験した。その結果、共有情報の検索数、参照数でそれぞれ1.3倍、1.5倍の増加、複数参照数で平均5.4倍の増加が見られ、本ツールの有効性が確認された。
3.4.3.2 WWWアウェアネス
ネットワーク上の分散環境の会議に変えた途端、対面環境の会議では当たり前の視覚情報の一部がアウェアされなくなる。特に最も多用されるWWW環境で、複数のユーザが同一のホームページを覗いているとき、同一のホームページを見ているのはだれか、彼らが今そのホームページのどこを見ているか、それを見て感じた印象は何か、これらを専用のWWWアウェアネスサーバを通して、「透かす」ように見せることにより、WWW上のコミュニケーションやコラボレーションをサポートするのが、富士通北陸システムズと報告者らで共同開発したWebアウェアネス表示環境WebCoordinate[18]である。それぞれの人固有の「赤ペン」を表示できるようにしており、ソフトウェア開発の分散レビューや実際の大教室での講義運用などが試みられている。
3.4.3.3 WWW探索アウェアネス
WWW上で複数の人間で協力しあってブラウジングしようとしたとする。その際、報告者らは既存のWWW環境では、複数の人間が探索しているという行動の把握、しかも他者がどの辺りのWWW空間を探索しているかの実態を認識できない。そこで、共同してWWW空間を探索するのに有用なURL表示の可視化とそこでの視点のリアルタイム表示を行い、ブラジングを協調して行う行為をWWW探索アウェアネス(あるいはコラボレーションブラウジング)と呼ぶ。WWW探索アウェアネス情報を提供するシステムを坂本が試作[22][23]した結果、他人の存在、動作をある程度予測でき、他ユーザとの円滑なコミュニケーションを促進し、一人では見つけられないホームページを多数見つけ出せることを実証した。ホームページ間の位置関係の空間配置は、リンクのジャングルを探索する際の手掛かり情報を提供する。納豆ビュー[27]の探索モードでの改良版とも言える。WWW探索アウェアネス環境を図 3.4-1に示す。
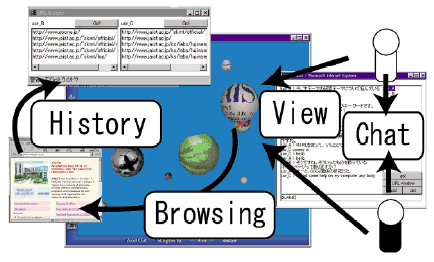
図 3.4-1 WWW探索アウェアネス環境
3.4.3.4 カンバセーションアウェアネス
インターネット上でテキストベースコミュニケーションを行う割合は圧倒的に多いが、その際仲間同志のコミュニケーション過程のリアルタイムでの実態を分析表示する社会性指向ツールはほとんど存在しない。実世界における社会的コミュニケーションと同様なだれが話者で、だれが聴者なのか、だれがだれだれに対して発話しているのか、聴者はだれに対して発話を返したか、だれが特定のキーワードに関して特に発話頻度が高いか、あるいは発話したのかといった発話状況をリアルタイムに表示することで、カンバセーションアウェアネスの提供を試みた。これらのメタ情報をリング上の空間配置状況としてリアルタイムに表示するシステムを、伊藤が構築[4][5]した。その結果、カンバセーションアウェアネス表示機能のない通常のグループメイルに比べて、メッセージ総数と平均文字数で、それぞれ50%と71%の増加が見られた。また対話関係の成立や継続対話回数の増加も見られた。特に、継続的対話関係の支援において、本システムがきわめて有効であることが実証された。カンバセーションアウェアネス環境を図 3.4-2に示す。
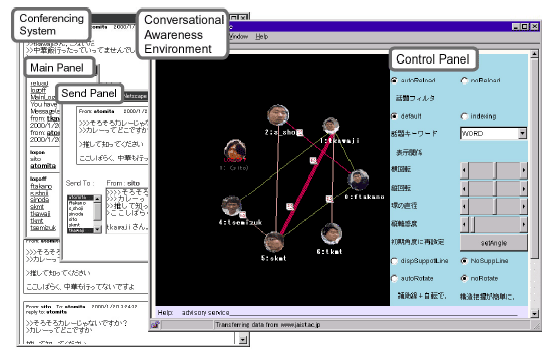
図 3.4-2 カンバセーションアウェアネス環境
3.4.4 浅い感性を支援する統合アウェアネス研究
浅い感性を支援する個別アウェアネス研究の統合・集大成として、図 3.4-3に示されるデモ展示会場内のコンテクストアウェアネス環境の構築がある。デモ展示会場で赤外線バッチを着けると、特定の展示物の情報が個々人のパームガイドに表示される。その表示を読み、気になることや気づいたことをどんどんメモとして書き込んでいくと、メモ書きのアノテーションからコミュニティ内の情報交換やインフォーマルコミュニケーションの偶発的開始がおこり、これにより新しい知識が創発される。また展示物を見た感想をテキスト入力すると、その感想テキストが漫画風に要約されるというエンタテイメント性の高いツールも試作した。
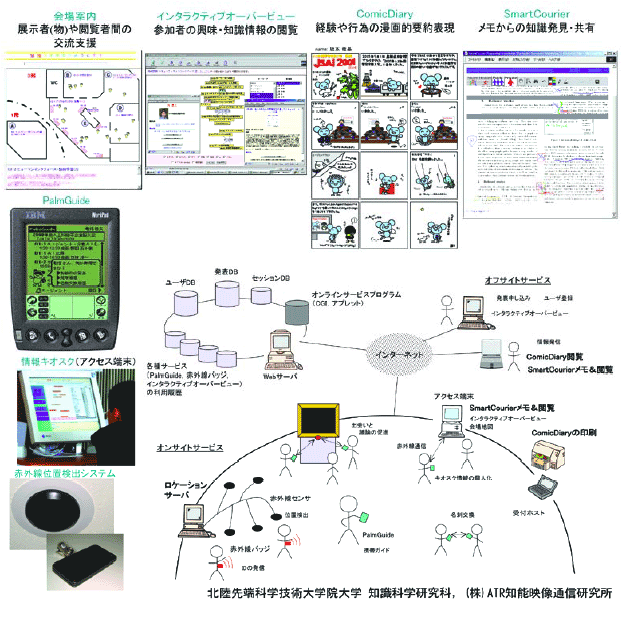
図 3.4-3 コンテクストアウェアネス環境の構築
3.4.4.1 ComicDiary: 経験や行動履歴の漫画的要約表現[25][26]
多くの要素から成り立っている情報に対して、その構成要素の関係把握を視覚的に容易化させることを目的として、情報の視覚化に関する研究は盛んに行われてきた。しかし、これらの研究は単に要素同士を、有向グラフなどを用いてそのまま視覚化しているにすぎず、周囲の状態や経験や思い出といった、対象物とそれを取り巻く状況や前後関係などを表現するにはいたっていない。本研究では、漫画を用いた経験や思い出の視覚化手法を提案した。これは、C-MAPという展示会場における個人化されたガイドシステムのログを用いて、その会場で何を見たのか、何に興味を持ったかなどを、漫画を用いて表現する、親しみやすい視覚化手法である。
この個人化された漫画生成サービスは、展示会場においてユーザが見て感じたことをストーリー化し、その流れに沿った、親しみやすい表現手法である漫画を自動生成することによって、展示会での思い出をより留めてもらう効果をもった視覚的記憶媒体を提供することを目的としている。具体的に、今回はC-MAPシステムという個人化された展示ガイドシステムによって得られる個人的なサービス授受の時系列データや興味データと、ユーザにかかわらず静的に判明している会場データやタイムテーブルなどを組み合わせることで自動的にストーリーを生成、漫画化し、印刷物として個々のユーザに配布することにより実現した。
状況表現手段として漫画を使用する利点は以下の通りである。
(a) 親しみやすい。
(b) 一覧性が高い。
(c) 表現力が高い。
(d) 時系列に沿った表現が可能。
経験や行動履歴を表現するにあたり、報告者らが対象としているユーザの種類は広範囲におよぶ。例えば、今回のプロトタイプの母体であるC-MAPは、さまざまな種類の展示会場におけるサービスの提供を対象としているので、ユーザの年齢層は広域におよび、訪れる多くの閲覧者に受け入れられやすい媒体であることは、この漫画要約サービスにおいて重要な意味をもつ。よって、(a)、(b)のユーザに対する親和性は大変重要である。また当然のことながら、展示会場での経験を静的なメディアに写像するためには、(c)、(d)に代表される表現力も重要な要素である。報告者らが普段目にする表現方法の中で考えると、これらのことを同時に兼ね備えた表現方法という意味で漫画は稀有な存在である。例えば、文章は(c)、(d)は確実に兼ね備えているが、(a)、(b)に関しては弱い。箇条書きにすれば(b)の部分はクリアされるが、代わりに(c)を損なうことになる。また、画像は(d)の要素が欠如しており、動画は(a)、(c)、(d)には長けているが、(b)の能力が致命的に低い。これら利点と欠点は文字や画像に固有の特徴に起因するものであり、その両方を含んでいる漫画は両者の良い点と悪い点を多重に継承しているといえる。さらに、これらの利点と、何より漫画にはストーリーを表現するための手法としての歴史的実績があるという点で、報告者らは漫画を経験や行動履歴を表現することに対して信頼に足りる、適切な表現手法であると結論づけた。
一方で、漫画は
(e) 正確さに欠ける。
(f) コマ数を制限すると、多くのことを表現できない。
などの今まで述べた特徴とトレードオフの関係にある欠点をもっている。これらは漫画のもつ仕様なので、制作者はこれら制約の中でいかに表現するか、また制約を逆に利用するかを考えなければならない。さらに、生成という観点から見た場合、漫画は上記の欠点とは別に、より根本的な以下の問題をかかえている。
(g) 作成に専門的スキルを要する。
この問題は主に素材の作画とベースとなる物語の生成に分けることができるが、そのどちらも自動生成という観点からは解決が難しい。しかし、本研究で行ったサービス提供のプロトタイプの作成にあたっては、根本的な絵やストーリーが自動生成されているかどうかは問題ではないと考え、今回はこの部分には焦点を当てず、漫画制作の経験者のスキルによって解決した。
このプロトタイプに対するユーザの反応と有意義性を確かめるため、第15回人工知能学会全国大会において、運用実験を行い、使用感に関するアンケートを採取した。ここでは、本システムが出力した漫画と、見学した対象のアブストラクトをテキストのリストとして表現するC-MAPの別サービスを比較した。これによると、両者の有意義性に有意差は見受けられないが、漫画による経験の表現自体は利用者にまったく抵抗なく受け入れられていることが判明した。また、アンケートのフリースペースに書かれた意見には、「○○の見学の記録を入れて欲しかった」など、漫画の内容に関するものが多く、漫画の表現を用いていることに対する意見は皆無であった。今後は、ユーザの希望する内容と漫画家が書く内容のマッチングに関する機能付加を、ユーザモデリングの技術を応用して行っていく予定である。なお本研究は第15回人工知能学会全国大会ベストプレゼンテーション賞を獲得した。
3.4.4.2 SmartCourier: アノテーションからの知識発見・共有[6][7]
本研究は、展示会場における参加者個人の状況や興味といったコンテキストに応じて、展示見学に関連する個人化された情報提供による効率的な情報獲得の支援や、参加者間に共通する知識や興味から参加者コミュニティにおける交流や知識共有を支援することで、展示見学への参加を通してなされる知識流通、知識創造の促進を目標としている。ここで構築したSmartCourierは、ユーザによる展示会場に関連する資料群へのアノテーション行為からその興味関心を抽出し、これを材料として情報の個人化や知識共有を支援するシステムである。
本研究では、ユーザの興味関心を抽出する対象としてアノテーションに注目し、その利用形態を個人的利用と組織的利用の2つに分けて考える。最も一般的なアノテーションの利用は個人的に行われる。すなわち、ユーザが閲覧するさまざまな資料や論文などの中から、特に注目すべき箇所を視覚的に附加し明示することで、ユーザ自身による情報の継続的活用、再利用性を高める一般的行為であると言える。このような行為は報告者らが研究対象とした展示会場でも数多く観察された。すなわち、情報の効率的収集と記録のため、視聴すべき演目や発表プログラムにマーキングしたり、興味深い発表へのコメントなどをその資料へ記しておいたりするような作業は、そのユーザの興味関心に応じて、自然に行われる作業であると言える。
一方、このようなアノテーションは、継続的組織において共有される場合もある。例えば小規模な研究グループのように、ユーザがある程度相互に興味関心の趣向を把握しているようなコミュニティにおいて、資料に関連するアイディアなどの知識の共有や効率的な情報取得のため、相互に役にたつような情報を評価し、これを共通のマーキング記号を使って示すといった作業が行われる。例えば、報告者らの研究室では、参考となる論文について、それを読んだ者が、内容の難度と質を示すシールを貼りつけ、コメントを残していくことで、資料検索をより効率的に行っている。しかしながら、このようなアノテーションの共有による効率化は、展示会場のような不特定多数の参加者が存在し、集団としては一過性のものである場合、物理的に書類の共有が困難であるというほかに、その展示会場において参加者が持つ興味関心に差異があり、他者のアノテーションが役に立たないといった問題がある。
そこで、本研究では、これらの問題に対処するため、ユーザによる資料へのアノテーション行為から、ユーザの興味モデルを構築し、これによって興味・関心に適応的な情報共有と情報検索のためのガイダンスを行うシステムを構築する。本システムのクライアントは、展示会場のブースに設置される液晶タブレットを備えたPCキオスクマシン上で動作することを前提に構築された。クライアントはウェブブラウザ上のJava
Appletとして動作し、ユーザはクライアントを通して、展示会場に関連する種々の資料を検索、閲覧し、アノテーションを記入することができ、記入したアノテーションは、インターネットを通して展示会終了後に確認することができる。これらアノテーションの対象となる資料については、そのイメージとアノテーション認識のための文書書式情報、キーワード情報をContent
Databaseとしてサーバ側に保持する。システム中のStroke Managerは、ユーザのペンストロークをその形状とストローク間の時間的距離的近さから分類し、文書中のどのキーワードに関連づけられたアノテーションであるかを決定する。この情報をもとにUser
Profile Generatorがユーザの興味モデルを生成する。興味モデルは、アノテーション数によって重みづけられたキーワードセットによって表される。
ユーザは個人的に資料を閲覧しアノテーションを記入することができるほか、興味関心が近い参加者同士で互いのアノテーションを共有することができる。また、一般に、未読の資料であっても、興味関心が近い他者がその資料を評価していれば、似た評価を下す可能性が高いという前提を利用した協調フィルタリングを用いて、未読資料のリコメンデーションによる情報の効率的取得を支援している。これらの機能により、ユーザは小規模な継続的組織におけるアノテーションの共有が果たす、情報取得の効率化と知識の共有といった役割を、一過性の集団でしかない展示会場においても享受することができる。本システムにおいて、ユーザ間の類似度はユーザ興味モデル間の相関係数によって求めている。また、協調フィルタリングの評価予測は、類似ユーザグループの興味モデルを使い、平均2乗誤差法を用いて行っている。また、ユーザのアノテーション行為と資料検索による情報の再利用を効率化するツールとして、手書きペン入力されたアノテーション記号の検索やこれらの一覧表示といった機能も備えている。
本システムは、上記人工知能学会全国大会において公式サービスの1つとして提供し、複数の参加者に利用された。アンケートなどを集計し、より詳細な使用実験を行い、研究内容は学会誌[7]に掲載された。
3.4.5 深い感性を支援するアウェアネス研究
高品位映像の評価技術についての研究は、まだ始まったばかりであり、その確立は複合現実感などを含む新たな感性評価技術の基盤作りとして重要である。本研究では、高品位映像の客観評価法の1つとして自発脳波が利用できないかを検討し、高品位画像システムにより提示されるR、G、B各4096階調の再現が可能である高品位映像について脳波を指標とする客観評価法の開発[2]を試みた。
脳波測定実験では、高品位映像と基準映像をそれぞれ鑑賞しているときのアルファ帯域波にどのような違いが生じるのかを明らかにし、アルファ帯域波を客観評価指標として導入することを試みた。映像の提示方法は映像1枚につき100秒間、インターバルを25秒間おいてランダムに4回提示して、これを1ブロックとした。100秒間のうち前半50秒間、後半50秒間のどちらかに基準映像を提示し、残りの50秒間は高品位映像を提示した。高品位映像と基準映像のどちらが先であるかはランダムである。実験回数は1日3ブロック(休憩含む)を目安として計12回を連日で行い、毎日はじめの1ブロックは実験環境の慣れを考慮して予備的な計測とし、時間効果を考慮して2ブロックのうちランダムに選ばれた1つを解析対象としたため、1名当たり4日間で計4ブロックが解析対象とされた。
上記の提示方法により、解析対象とした100秒間のうちの50秒ずつについての順序効果、時間効果は均等化、ランダム化されている。100秒間連続して映像を提示したのは、高品位映像と基準映像の違いである階調数の変化が脳波に与える影響以外の要因を極力抑えるためである。解析対象としたデータは上記提示方法により得られた100秒間の提示を1件として、計192件である。一般にアルファ波は後頭部において振幅が大きく、出現頻度も高いことや、前頭部は瞬きによるアーチファクトが混入しやすいことから後頭部周辺のO1、O2、P3、P4について解析を行った。なお図
3.4-4に示すように国際10-20法に基づき脳波電極を装着し、EOG、ECGも同時に計測した。

図 3.4-4 電極配置図

図 3.4-5 脳波解析結果
図 3.4-5の実験により得られたパワースペクトルの例を示す。アルファ帯域である8〜13Hzにおいて、基準映像観察時よりも高品位映像観察時にパワーの増大が認められる。このような高品位映像観察時のアルファ帯域波パワーが増大する傾向を有意水準5%で検定した。その結果、解析対象とした192件すべてにおける両側t検定では有意水準5%で有意であった。各映像(48件)ごとの検定については映像「MIROKU」、映像「FACE」において有意水準5%で有意であった。他の2枚については、有意水準5%は満たしていないが、高品位映像観察時のほうが、アルファ帯域波パワーが高い傾向にあることが認められた。また、主観評価実験により得られた主観評価値と脳波測定実験により得られた客観評価値との相関係数0.85であり、比較的高い相関が得られた。したがって、有意水準に満たない映像についても、主観評価結果との相関は高い。
本研究では、高品位画像システムにより提示されるR、G、B各4096階調の再現が可能である高品位映像について、脳波を指標とする客観評価法の開発を試みた。高品位映像と基準映像の間に定量的な差があることを差分電力により確かめ、同時に、変化位置を観察するために高品位映像と基準映像それぞれの微分映像を求め、差分処理により分析した。その結果、階調数の違いによる微妙な階調変化のある領域が観測された。そして、脳波を指標とした客観評価法の有効性を検証するために、高品位映像の物理要因・特性が主観評価実験結果、客観評価実験結果に与える影響をそれぞれ比較し、主観評価実験結果と客観評価実験結果の関係を求めた。その結果、分析された評価映像の性質と各評価実験結果との間に対応がある可能性が示唆された。基準映像に対して高品位映像は主観評価法、客観評価法においてともに高い評点を与える傾向にあることが示され、主観評価法と客観評価法は比較的高い相関関係にあることが示唆された。以上により、本研究で提案した脳波計測による客観評価法が高品位映像の評価として有効である可能性が示唆された。ただし、本実験は評価映像枚数が4枚という制約における評価実験であるため、高品位映像の選定方法については今後さらなる深い検討が必要である。
今後の課題として評価者および映像の選定方法を体系的に検討する予定である。本研究で提案した客観評価法が、高品位映像を必要とする深いアウェアネスや複合現実感などを含む新たな感性評価技術の基礎的基盤として貢献することを期待したい。
3.4.6 おわりに
本報告では、最近グループウェアやCSCW研究における主要研究課題の1つであるアウェアネス研究について、報告者らの研究成果を中心に、その研究開発動向を述べた。アウェアネス研究は分散環境において、同期・対面環境以上の臨場感を提供するには如何にするかという問題提起から出発したアイコンタクト提供という研究から出発し、存在のアウェアネス、動作のアウェアネス、嗅覚・触覚のアウェアネス、形式知のみならず暗黙知のアウェアネス、メタ情報やメタ知識のアウェアネスの研究と進展しており、その研究開発の最前線は止まることを知らず、前進している。新世代グループウェアの設計者が対面環境では失われた臨場感を相手に提供したいとき、自分の使用するマルチメディア、ヒュマンメディアの特性を十二分に理解し、新しい世代のグループウェアのためのアウェアネス環境を構築しなければならない。
今後の課題として、美的、精神的に高度化した人々が、21世紀指向のVisual-Audioシステムに要求する深い感性をノンコンタクトで客観的に評価する方法を、脳科学の知見を考慮して、模索していく必要がある。脳波、fMRI、PET、振動などの生体計測装置を駆使した分析法で得られた知見を、宮原プロジェクトの高品位Visual-Audioシステムの研究でこれまでに得られた知見と統合し、どのような深い感性を伝達したいかに応じた臨場感アウェアネスにあふれた新世代のグループウェアを構築したい。そのため、匂いの伝達や触覚の伝達の研究をスタートしておくことが、深い感性情報の伝達には必要である。報告者らは感性から理性を除いた「深い感性」の空間にひそんでいる見えざる因子を発見し、それをデジタル技術に翻訳するという名人芸的プロセスを通して、臨場感、氛囲気、気配、熱気、凄みなどのアウェアネスを伝達できる21世紀型Visual-Audioシステムを構築できると確信している。そのような研究は21世紀なかばにおいて、情報ソムリエあるいは知識ソムリエの活躍するマルチメディア脳科学という学問分野に昇華するであろう。
参考文献
| [1] | P. Dourish and S. Bly: Supporting Awareness in a Distributed Work Group, in Proceedings of CHI'92, pp. 541-547, ACM, 1992. |
| [2] | 林秀彦, 國藤進, 宮原誠: 高品位映像の評価−脳波を指標とする客観評価法−, 映像情報メディア学会誌, 56, 6 (2002). |
| [3] | 本田新九郎, 富岡展也, 木村尚亮, 岡田謙一, 松下温: 在宅勤務者の疎外感の解消を実現した位置アウェアネス・アウェアネススペースに基づく仮想オフィス環境, 情報処理学会論文誌, Vol. 38, No. 7, pp. 1454-1464 (1997). |
| [4] | 伊藤禎宣, 國藤進: カンバセーションアウェアネス支援: カンバセーション状況の視覚化による新たなコミュニケーションツールの提案, 人工知能学会第39回人工知能基礎論研究会, 東京電機大学, AI学会資料SIG-FAI-9903, pp. 87-92 (Nov. 1999). |
| [5] | S. Ito and S. Kunifuji: Supporting Conversational Awareness in Text-based Conference System, Proceedings of KES'2000 Vol. 1, pp. 221-224, University of Brighton (Aug. 2000). |
| [6] | S. Ito, Y. Sumi, and K. Mase: Supporting Knowledge Sharing by Document Annotation at an Exhibition Site, Proceedings of the 15th Annual Conference of Japanese Society for Artificial Intelligence, Shimane Kenmin-Kaikan (May, 2001). |
| [7] | 伊藤禎宣, 角康之, 間瀬健二, 國藤進: SmartCourier: アノテーションを介した適応的情報共有環境, 人工知能論文誌, 17 (2002). |
| [8] | T. Ishida (ed.): Community Computing and Support Systems, Springer, Lecture Notes in Computer Science 1519 (1998). |
| [9] | 石井裕: グループウェアのデザイン, 共立出版 (1994). |
| [10] | 石井裕: Tangible Bits: 情報の感触/気配の伝達, 情報処理, Vol. 39, No. 8, pp. 745-751 (1998). |
| [11] | 門脇千恵, 爰川知宏, 山上俊彦, 杉田恵三, 國藤進: 情報取得アウェアネスによる組織情報の共有促進, 人工知能学会誌, Vol. 14, No. 1, pp. 111-121 (Jan. 1999). |
| [12] | 門脇千恵: 組織情報の共有過程分析に基づく情報共有促進支援法の研究, 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士論文 (Mar. 1998). |
| [13] | 國藤進: オフィスにおける知的生産性向上のための知識創造方法論と知識創造支援ツール, 人工知能学会誌, Vol. 14, No. 1, pp. 50-57 (Jan. 1999). |
| [14] | 國藤進, 加藤直孝, 門脇千恵, 敷田幹文: ナレッジマネジメント時代のグループウェア, 日科技連出版社 (July 2001). |
| [15] | 松下温, 岡田謙一: コラボレーションとコミュニケーション, 共立出版 (1995). |
| [16] | 松浦宣彦, 日高哲雄, 岡田謙一, 松下温: VENUS: Interest Awarenessを利用したインフォーマルコミュニケーション環境, 情報処理学会論文誌, Vol. 36, No. 6, pp. 1332-1342 (1995). |
| [17] | 宗森純, 宮内絵美, 牟田智宏, 吉野孝, 湯ノ口万友: 電子鬼ごっこ支援グループウェアの試作と適用, 情報処理学会グループウェア研究会, 2001-GW-39, pp. 25-30 (Mar. 2001). |
| [18] | 中川健一, 國藤進: アウェアネス支援に基づくリアルタイムなWWWコラボレーション環境の構築, 情報処理学会論文誌, Vol. 39, No. 10, pp. 2820-2827 (Oct. 1998). |
| [19] | 永野豊, 本田新九郎, 大澤隆治, 太田賢治, 重野寛, 岡田謙一, 松下温: 仮想空間内の風と香りの表現手法, 情報処理学会第58回全国大会 (Mar. 1999). |
| [20] | 西田豊明, 畦地真太郎, 藤原信彦, 角薫, 福原知宏, 矢野博之, 平田高志, 久保田秀和: パブリック・オピニオン・チャンネル, NTTコミュニケーション科学基礎研究所主催CMCC研究会第2回シンポジウム論文集, pp. 59-66, 奈良県新公会堂 (Sep. 1999). |
| [21] | 緒方広明, 矢野米雄: アウェアネスを指向した開放型グループ学習支援システムSharlokの構築, 電子情報通信学会論文誌D-II, Vol. J80-D-II, No. 4, pp. 874-883 (1997). |
| [22] | 坂本竜基, 國藤進: コラボレーションブラウジング: WWWアウェアネスを利用した新しいブラウジング方式の提案, 人工知能学会第10回"AIシンポジウム'99", 早稲田大学国際会議場, AI学会資料SIG-J-9901, pp. 97-102 (Dec. 1999). |
| [23] | R. Sakamoto and S. Kunifuji: Collaborative World Wide Web Browsing System through Supplement of Awarenesses, Proceedings of KES '2000, Vol. 1, pp. 233-236, University of Brighton (Aug. 2000). |
| [24] | R. Sakamoto and S. Kunifuji: A Visualization of Users' Contexts on Proxy Server, Proceedings of the 15th Annual Conference of Japanese Society for Artificial Intelligence, Shimane Kenmin-Kaikan (May 2001). |
| [25] | 坂本竜基, 中尾恵子, 角康之, 間瀬健二: 経験や行動履歴の漫画的要約表現, 2001年度第15回人工知能学界全国大会, 島根県民会館 (May 2001). |
| [26] | R. Sakamoto, K. Nakao, Y. Sumi, and K. Mase: ComicDiary: Representing Individual Experiences through a Comic, SIGGRAPH 2001 (Aug. 2001). |
| [27] | 塩澤秀和, 西山晴彦, 松下温: 「納豆ビュー」の対話的な情報視覚化における位置づけ, 情報処理学会論文誌, Vol. 38, No. 11, pp. 2331-2342 (1997). |
| [28] | 山上俊彦, 関良明: Knowledge-awareness指向のノウハウ伝播支援環境: CATFISH, 情報処理学会, 93-DPS-59-8, pp. 57-64 (1993). |