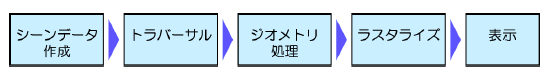
�} 3.10-1�@3�����O���t�B�b�N�X�̏����̗���
3. �����J���̐V�����W�J�Ɠ��O�̓���
��: �{�c�꘩�ψ�
3.10.1 �@�͂��߂�
�@CG�Z�p�̂������ȉ��p�̏�Ƃ��ẮA�f��ł̓��B��A�j���[�V�������삪��������B����ŁAWeb�u���E�U��ł̃R���e���c�APC��ƒ�p�r�f�I�Q�[���@�ł̃��A���^�C��CG�f���ȂǁA�C���^���N�e�B�u��CG�f�����L���s��ɐZ�����Ă���B
�@�{�ł́A�C���^�[�l�b�g��ł̃O���t�B�b�N�X�Z�p�A���A���^�C��CG���x����n�[�h�E�F�A�Z�p�Ƃ��̋�̓I�ȓW�J��ł���ƒ�p�r�f�I�Q�[���@�̌���A����ɁA�C���^���N�e�B�u�O���t�B�b�N�X�̉��p�Ƃ���VR��AR�A�C���X�^���[�V�����A�[�g�Ȃǂ̎���ɂ��ďq�ׁA�C���^���N�e�B�u�O���t�B�b�N�X�̏��������l�@����B
3.10.2 �@�C���^�[�l�b�g��̃O���t�B�b�N�X
�@�C���^�[�l�b�g����āA���܂��܂ȏ����肳���悤�ɂȂ����B�e�L�X�g��摜�A�f���A�����̔z�M�Ɣ�r���āA3�����`��f�[�^�̔z�M�́A����قǔM�S�ɂ͊��߂��Ă��Ȃ��悤�ł���B���̗��R�Ƃ��ẮA�`��f�[�^�̗e�ʂ��̍Đ��@�\�̖��Ȃǂ���������B�{�߂ł́A�C���^�[�l�b�g��ł�3�����O���t�B�b�N�X�f�[�^�̎�舵���Ɋւ���A�������̎��݂ɂ��ďq�ׂ�B
3.10.2.1 �@�|���S�����_�N�V����
�@�|���S�����_�N�V�����Ƃ́A�\�����������̂̉�ʂɕ\�������傫����d�v�x�Ȃǂɉ����āA3�����`��f�[�^�̏ڍדx��ω��������@�ł���B���̎�@�́A�Ⴆ�A�C���^�[�l�b�g��ł̃f�[�^�z�M���ɉ���̑��x�ɍ��킹�ēK�p������A���A���^�C���ł̌`��f�[�^�̕\���i�`�揈�����x�ɍ��킹��j�֓K�p�����肷�邱�Ƃ��l������B
3.10.2.2 �@WEB3D
�@WEB3D[1]�́A���N�O����CG�̐V�������p����Ƃ��Ęb��ɂȂ��Ă����Z�p�ł���A���ɃC���^�[�l�b�g�V���b�s���O�̗��p�ȂǂɊ��҂���Ă���B�C���^�[�l�b�g�u���E�U��ł�3�����O���t�B�b�N�X�̕\���Z�p�Ƃ���VRML���ꎞ���b��ɂȂ������A���̌�̓W�J���L�єY��ł���BWEB3D��VRML�ȏ�ɒ��ڂ𗁂тĂ���傫�ȗ��R�Ƃ��ẮA�ȉ��̂悤�ȓ_����������B
�i1�j�@���Ȃ��f�[�^��
�@VRML�ł̓|���S�����b�V���Ō`���\�����邽�߁A�Ώی`��ɋȖʂ��܂܂��ꍇ�ɂ̓f�[�^�ʂ����傷��B����AWEB3D�ł͋ȖʁiNURBS�p�b�`�j�ڈ������Ƃ��ł���̂ŁA�f�[�^�ʂ����Ȃ��Ă��ނƂ������_������B
�i2�j�@�\���̎�������
�@�]���̂悤�ɑ��ʑ̂ŋȖʂ��ߎ����ĕ\����������A�Ȗʂڕ\�������ق������炩�ȕ��̂�\���ł���B�l�̂���łȂ��A�ԑ̂Ȃǂ̃C���_�X�g���A���f�U�C���ł͎��R�Ȗʂ𑽗p���Ă���̂ŁAWEB3D�ł̃f�[�^�\���̕����\���̎�������ɂȂ���B�܂��AWED3D�ł́A���s���������ł͂Ȃ��_�����╨�̕\�ʂւ̉f�荞�݂�\�����邱�Ƃ��ł���B�Ⴆ�Ύԑ̂ւ̕��i�̉f�荞�݂��{�����Ƃɂ��A�����̎�����\�����邱�Ƃ��ł��A�ԑ̂̃��A���������シ��B
�@�ȏ��2�_���Z�p�I�ȑ傫�ȗ��R�ł��邪�A����ȊO�ɁA�}�b�L���g�b�V���ł̊J�����x�ꂽ���Ɓi�����̃f�U�C�i���}�b�L���g�b�V�����g���Ă���j�AVRML�R���\�[�V�A���̑̎��i��c���c�̂̑ǎ��ňӌ��̏W����ł������j�Ȃǂ��AVRML���\�z�ȏ�ɐZ�����Ȃ��������R�Ƃ��ċ�������B
3.10.2.3 �@���̖��ߍ���
�@�f�ނ̎��W���l�b�g���[�N����ĊȒP�ɍs����悤�ɂȂ������ƂŁA�l�b�g��œ��肵���f�ނ����H���g�ݍ��킹�č�i���d�グ�邱�Ƃ��\�ɂȂ����B�������A�ł��オ��̍�i����A�f�ނ̃I���W�i���e�B�ʂ��邱�Ƃ͍���ł���B�摜�≹�y�ւ̓d�q�������Z�p�͐��N�O���猤������Ă��Ă��邪�A3�����̌`�f���ւ̏�ߍ��݂̋Z�p�͎n�܂�������ł���B���̂悤�Ȓ��쌠�ی�̂��߂̋Z�p�́A�����[�V�����f�[�^�Ȃǂ̑��l�ȑf�ނւ̊g�傪�\�z�����B����́A�V���O���\�[�X�E�}���`���[�X�̍l���̂��ƂɁA�R���e���c�̍ė��p�ɒ��ڂ��W�܂�ƍl�����A���̂悤�Ȓ��쌠�ی�̂��߂̋Z�p���d�v�x�𑝂��ƍl����B
3.10.3 �@���A���^�C��CG�̃n�[�h�E�F�A�Z�p
�@���A���^�C��CG���x����n�[�h�E�F�A�Z�p�̑啔���́A���ڂ���Ă���O���t�B�b�N�{�[�h�i�r�f�I�J�[�h�j�̋Z�p�ƌ�����BGUI�̔��W�ɔ����A�O���t�B�b�N����ʂɍ����ɕ`�悷��@�\�����O���t�B�b�N�`�b�v�������J������Ă����B�O���t�B�b�N�J�[�h��PC�̒��ʼnʂ����������N�X���債�Ă��Ă���A���̐S�����̃O���t�B�b�N�`�b�v�́ACPU�̐i���X�s�[�h�ɕC�G���鐨���Ői�����Ă���B�{�߂ł́A3�����O���t�B�b�N�X�̏����̗���ƁA�������̎�@�ɂ��ďq�ׂ�B
3.10.3.1 �@�����̗���
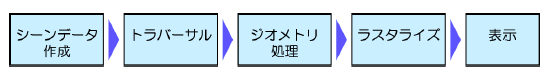
�} 3.10-1�@3�����O���t�B�b�N�X�̏����̗���
�@�} 3.10-1�́A��ʓI��3�����O���t�B�b�N�X�̏����̗���������Ă���B�e�i�K�̏����̓��e�͎��̒ʂ�ł���B
| �i1�j | �V�[���f�[�^�쐬 �\�����郂�f���f�[�^�Ȃǂ̍쐬��J��������у��C�g�̐ݒ�B |
| �i2�j | �g���o�[�T�� �V�[���f�[�^�����߂��ĕK�v�ȕ`��I�u�W�F�N�g�ƕ`�施�߂����i�K�֓n���B |
| �i3�j | �W�I���g������ ���f���̍��W�ϊ��A�����v�Z�A���e�ϊ��A�N���b�s���O�����Ȃǂ��s���B |
| �i4�j | ���X�^���C�Y �W�I���g���f�[�^�̃��X�^����V�F�[�f�B���O�����AZ�o�b�t�@�����A�e�N�X�`�������Ȃǂ��s���B |
| �i5�j | �\�� �r�f�I�������̒l��ǂݏo���\������ |
3.10.3.2 �@�������̎�@
�@�} 3.10-1�ł̃��X�^���C�Y�ƕ\���̕����́A�����̃O���t�B�b�N�J�[�h����n�[�h�E�F�A�Ŏ�������Ă���B���݂�3�����O���t�B�b�N�J�[�h�ł́A���ɃW�I���g�������̕������n�[�h�E�F�A�Ŏ������A�����`����������Ă���B3�����O���t�B�b�N�X�̕`��̍������́A�ȉ��̂悤�Ȃ��܂��܂ȃA�v���[�`������B
3.10.3.2.1 �@�W�I���g�������̍�����
�@�W�I���g�������ɂ́ACPU�ōs�����@�i�\�t�g�E�F�A�ɂ��A�v���[�`�j�ƁA�O���t�B�b�N�v���Z�b�T�ōs�����@�i�n�[�h�E�F�A�ɂ��A�v���[�`�j������B
�@�\�t�g�E�F�A�ɂ��A�v���[�`�ł́APentium��SSE���߂��g�p������@�ƁAAMD��3DNow!���g�p������@�Ȃǂ�����B
�@����A�W�I���g���G���W���ƌĂ��W�I���g���������p�ɍs���`�b�v���n�[�h�E�F�A�Ƃ��Ď�������A�ŋ߂�3�����O���t�B�b�N�{�[�h�̂قƂ�ǂɓ��ڂ����܂łɂȂ��Ă���BCPU�̉��Z���x���\��������A�W�I���g���G���W���͕s�v�ł��邪�A����ł̓W�I���g���G���W���̏����\�͂�CPU�������Ă���B
3.10.3.2.2 �@�O���t�B�b�N�v���Z�b�T�̕���
�@�O���t�B�b�N�v���Z�b�T����ڂ��ĕ`�搫�\�����コ�����@�ł���A�n�C�G���h��OpenGL�p�O���t�B�b�N�A�N�Z�����[�^�̂قƂ�ǂ��̗p���Ă���B���X�^���C�Y�̕��U�����ł́A���X�^���C�Y�v���Z�b�T�̐�������ʂ��ו������āA�e�X���b�h�̏��������蓖�ĂĂ���B
3.10.3.2.3 �@�f�[�^�]���̍�����
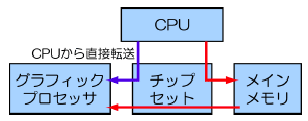
�} 3.10-2�@�f�[�^�]���̍�����
�@�} 3.10-2�Ɏ����悤�ɁA��ʓI��CPU�ŏ������ꂽ���f���̃f�[�^�́APC�̃��C���������ɕۑ�����Ă���O���t�B�b�N�v���Z�b�T�ɓ]�������B�����ŁA���C���������Ƀf�[�^��]�������ɁACPU���璼�ڃO���t�B�b�N�v���Z�b�T�Ƀf�[�^��]������A�f�[�^�]���̍��������\�ɂȂ�B
3.10.3.2.4 �@nfiniteFX�G���W��
�@nfiniteFX�G���W��[2]�́AnVIDIA�Ђ��O���t�B�b�N�v���Z�b�T�uGeFORCE3�v�p�ɐv�����A�[�L�e�N�`���ł���A���݂ł�2����ڂ�nfiniteFX�������\����Ă���BVertex�V�F�[�_��Pixel�V�F�[�_���\���v�f�Ƃ��Ă���A����2�͂Ƃ��Ƀv���O���}�u���ł���BVertex�V�F�[�_�ł́A�Ǝ��̃��C�e�B���O���f�����`������A���̕\�ʂւ̉��ʂÂ��̂悤�Ȏ葱���^�̃W�I���g��������\�ł���BPixel�V�F�[�_�ł́A�s�N�Z���P�ʂł̃��C�e�B���O��e�N�X�`���Â��Ȃǂ��`�ł���BMicrosoft�Ђ�DirectX8[3]�ɂ��ȏ��2�̃V�F�[�_�@�\���܂܂�Ă��邪�A����́AXBOX[4]�̃O���t�B�b�N�G���W�����J������nVIDIA�Ђ��AMicrosoft�ЂɃ��C�Z���X�������̂ł���B���҂����ڂɌ��т����Ƃɂ��ADirectX��API����āA�n�[�h�E�F�A�@�\��p�������i���ȃ��A���^�C���O���t�B�b�N�X���������Ă���B
| ���� | CPU | �僁���� | ��� | �⏕�L�� | 3���� �O���t�B�b�N�X |
�T�E���h |
| ��1���� �i72-93�j |
8bit | 2KB | 256 _ 2404 bits/pixel |
ROM | NA | �r�[�v�� ���m���� |
| ��2���� �i90-96�j |
16bit | 128KB | 512 _ 44815 bits/pixel |
ROM | NA | FM���� �X�e���I |
| ��3���� �i93-99�j |
32bit | 2MB | 640 _ 48024 bits/pixel |
ROM CDROM |
�W�I���g�� + ���X�^�G���W�� |
FM���� CD���� |
| ��4���� �i99- �j |
128bit | 32MB | 640 _ 48024 bits/pixel |
DVDROM CDROM |
�W�I���g�� + ���X�^�G���W�� |
CD���� �T���v�����O |
3.10.4 �@�ƒ�p�r�f�I�Q�[���̌���
�@���߂Ẳƒ�p�r�f�I�Q�[���@�u�I�f�b�Z�C�v(Magnavox��)���o�ꂵ���̂��A�D�y�~�G�I�����s�b�N�̊J�Â��ꂽ1972�N�ł������B���̌�30�N�̔N�����o���ƒ�p�r�f�I�Q�[���@�̌����{�߂ŊȒP�ɏq�ׂ�B
3.10.4.1 �@�ƒ�p�r�f�I�Q�[���@�̐�����
�@�C�V���́u�t�@�~���[�R���s���[�^�v���o��i1983�N�j����ȑO����A�������̉ƒ�p�Q�[���@����������Ă����B�ƒ�p�Q�[���@�̐������\ 3.10-1�ɂ܂Ƃ߂����A���̕��ނ̓n�[�h�E�F�A�̃��f���`�F���W�ɂ��킹�����̂ł���B��q���邪�A�Q�[���̊O���̎������I�ɕς�����̂́A3�����O���t�B�b�N�X�@�\�����ڂ���A�Q�[���̒ɑ�e�ʂ̕⏕�L�����f�B�A���g����悤�ɂȂ����A��3����̃r�f�I�Q�[���@�ł���B
3.10.4.2 �@PS2�E�Q�[���L���[�u�EXBOX
�@���݂̉ƒ�p�r�f�I�Q�[���@�́APS2�i�\�j�[�A1999�N�j�A�Q�[���L���[�u�i�C�V���A2001�N�j�AXBOX�i�}�C�N���\�t�g�A2001�N�j��3���嗬�ƍl�����Ă���B��v�ȋ@�\�̔�r��\
3.10-2�ɋ�����B
�@3�@��̒��ł́AXBOX��������PC�ɋ߂��A�[�L�e�N�`���ƂȂ��Ă���A�n�[�h�f�B�X�N��LAN�|�[�g�܂Ŕ����Ă���BPS2�ł́A�R�A�ƂȂ�Emotion
Engine�ɃW�I���g���G���W�����܂܂�Ă���A���̃��f�B�A�v���Z�b�T�𒆐S�ɍ\�����ꂽ�A�[�L�e�N�`���ƂȂ��Ă���B����Q�[���L���[�u�ł́ACPU�ƃ��C���������ȊO�̗v�f�́A�ق�Flipper�ƌĂ��1�`�b�v�ɏW�ς���Ă���B
�@XBOX�ł́A�O���t�B�b�N�X��API��DirectX��p���Ă���APC�Q�[���̊J���҂��ڐA���₷���悤�ɂȂ��Ă���B����APS2�ł́ALINUX�ɂ��J�������Ƃ��Ă���A�~�h���E�F�A�̊J�����d�v�Ȉʒu���߂Ă���B
�@�`�搫�\�͌㔭��XBOX��3�@��̒��ł�����D��Ă���A���b125���K�|���S���A���Ȃ킿30�t���[��/�b�̏ꍇ�ɁA1��ʖ�400���|���S���ō\�������V�[����\���ł���B
3.10.4.3 �@�X�v���C�g����|���S����
�@��3����̃r�f�I�Q�[���@����A3�����O���t�B�b�N�X�̕\���@�\�����ڂ����悤�ɂȂ����B����ɂƂ��Ȃ��A�Q�[������̃X�^�C������ς��邱�ƂɂȂ�B��2����̃r�f�I�Q�[���@�܂ł́A�X�v���C�g�A�j���[�V�����ƌĂ��2�����̉摜�i�ʏ�: �h�b�g�G�j�������ƂŁA�Q�[���̉�ʂ��\�����Ă����B����A3�����O���t�B�b�N�X�̕\���@�\�����ڂ���邱�Ƃɂ��A�ȉ��̂悤�ȃ����b�g��������B
| PS2 | �Q�[���L���[�u | XBOX | |
| CPU | MIPS�x�[�XEmotion Engine �i295MHz�j |
PowerPC�x�[�XGekko �i485MHz�j |
Pentium�� �i733MHz�j |
| �僁���� | 32MB | 43MB | 64MB |
| �O���t�B�b�N�X | Graphics Synth�i147MHz�j | Flipper�i162 MHz�j | NVIDIA�� �i250MHz�j |
| �\�����\ �i�|���S��/�b�j |
66���K | 6-12���K | 125���K |
3.10.5 �@�C���^���N�e�B�u�O���t�B�b�N�X�̉��p����
�@�r�f�I�Q�[���ȊO�̃C���^���N�e�B�u�O���t�B�b�N�X�̉��p����Ƃ��āA�o�[�`�������A���e�B�iVR�j��g���������iAR: Augmented Reality�j�A�|�p�ւ̉��p�Ƃ��ẴC���X�^���[�V�����A�[�g�Ȃǂ���������B�{�߂ł́A�����̂������̗��������B
3.10.5.1 �@VR / AR�̗�
�@VR��AR�̗�Ƃ��ẮA��Âւ̉��p����r�I�����B��Ì���ł̌o����P����ςނ��߂̃c�[���Ƃ��Č����J�����ꂽ���̂�����������A�Ⴆ�A��������Z���^�[�ł̔]��ᇎ�p�V�~�����[�V�����V�X�e��[5]��A�č��m�[�X�L�������C�i��w�ł̓��K����p�̃T�|�[�g�V�X�e��[6]�Ȃǂ���������B��҂̗�ł́A�����ɂ����g���b�L���O���u�ŏp�҂̓��̈ʒu���v�����Ȃ���A�����g�ŎB�����a���̕��ʂ����A���^�C����CG�Ő�������B�p�҂́A�������ꂽCG�摜���w�b�h�}�E���g�f�B�X�v���C��Ŏ��ۂɌ��Ă��銳�҂̐g�̂Əd�ˍ��킹�Č��邱�Ƃ��ł��A�a���ɂ��܂����×p�̐j���h����悤�ȃT�|�[�g������B
�@����A�č�MIT�̐Έ�O���[�v[7]�ł́A�u�^���W�u���E�r�b�g�v�Ƃ����R���Z�v�g�ŁAGUI�ɑւ��V�������[�U�C���^�t�F�[�X�̌������s���Ă���B���̃R���Z�v�g�ł́A�d�q�I�ȃf�W�^���̏��ɕ����I�Ȍ`��^���邱�ƂŁA�C���^�t�F�[�X�̎��̊������サ�A�������E�Ɖ��z���E�Ƃ��V�[�����X�ɂȂ���ƍl���Ă���B�Ⴆ�A�uI/O
Bulb�v�ł́A�e�[�u����ɒu���ꂽ���z�̖͌^�ɂ��鑀����{���ƁA���̌����̉e���v�Z����ăe�[�u����ɕ\�������B�f�B�X�v���C��̉��z��ԓ��ł̃��f���ɑ��Ăł͂Ȃ��A���̂Ƃ��đ��݂���͌^�ɉe�����e����邱�ƂŁA��蒼���I�ɗ����ł���C���^�t�F�[�X�ƂȂ��Ă���B
�@��q�̉��p�ȊO�ɁA�X�[�p�[�}�[�P�b�g�̓������̌��A�I�[�_�[���[�h�̃L�b�`���̎g������̌��A�I�[�g�o�C�̉^�]�V�~�����[�^�ɂ�鎖�̉���̊w�K�Ȃǐ��X�̎��݂��Ȃ���Ă���B
3.10.5.2 �@�C���X�^���[�V�����A�[�g�̗�
�@�C���X�^���[�V�����A�[�g�Ƃ́A1970�N�̌㔼���납��A�G��⒤���̂悤�ȃt�@�C���A�[�g�̔��e�Ŋ���Ȃ���i�ɑ��đ����p������悤�ɂȂ����p��ł���B���݂ł́A�R���s���[�^��p�����C���^���N�e�B�u�ȍ�i������������悤�ɂȂ�A���{�l�̍�Ƃł͊��r�Y[8]�������ł���B�ނ̍�i�ł́A���Ɖf���̃C���^���N�V�������e�[�}�ɂ������̂������A��{����Ƃ̃R���{���[�V�����ł���uPiano�v��A�u���]�i���X�E�I�u�E�t�H�[�`4�̋��v�Ȃǂ���\��i�Ƃ��ċ�������B�����̍�i�ł́A���ҁi�������͊ϋq�j���Ō�������A�e�[�u����ɐݒu���ꂽ�_�C�A�������肷��ƁA�R���s���[�^�������̃C�x���g�ɏ]���ă��A���^�C���ʼnf�������A��X�N���[���ɓ��e����d�g�݂ɂȂ��Ă���B
�@�C�O�ł́ASIGGRAPH�iwww.siggraph.org�j��Ars Electronica�iwww.aec.at�j�AMilia�iwww.milia.com�j�Ȃǂ��A�C���X�^���[�V�����A�[�g��i�̃A�J�f�~�b�N�Ȕ��\�̏�Ƃ��ėL���ł���B
3.10.6 �@������
�@�ȏ�A�C���^���N�e�B�u��CG�̍\���v�f�Ɖ��p��Ȃǂ��ȒP�ɏq�ׂ��B���{�́A�ƒ�p�r�f�I�Q�[���̕���ɂ����ď�ɐ��E�̃g�b�v�̍��Ɉʒu���Ă��邪�APC�Q�[���̓W�J��ژ_��XBOX�̓o��ɂ��A����̓Q�[���s��̍��킪�\�z�����B����ɁA�C���^�[�l�b�g����������ŁA�ƒ�p�r�f�I�Q�[���@�͒P�Ȃ�r�f�I�Q�[���@�ł͂Ȃ��A�ƒ�ɂ����郁�f�B�A�Z���^�Ƃ��Ă̒n�ʂ��m������悤�ɂȂ邩������Ȃ��B����ŁA�}���ɕ��y�������o�C���[�����ACG�̐V���ȉ��p����Ƃ��čl������B�߂������A���ׂĂ̏��[�����V�[�����X�ɐڍ����A�C���^�t�F�[�X�Ƃ��Ă�CG���ʂ��������͂܂��܂��d�v�ɂȂ�Ɨ\�z����B
�Q�l����
| [1] | http://www.web3d.org/ |
| [2] | http://www.nvidia.com/view.asp?IO=feature_nfinitefx |
| [3] | http://www.microsoft.com/japan/directx/default.asp |
| [4] | http://xbox.jp/ |
| [5] | �����ق�: ���z���ɂ�����]��p�V�~�����[�V�����V�X�e��, ����w��O���t�B�N�X��CAD������, Vol. 95, No. 47, pp. 41-46 (May 1995). |
| [6] | Andrei State et al.: Technologies for Augmented Reality Systems: Realizing Ultrasound-guided Needle Biopsies, Proceedings of SIGGRAPH 96, pp. 439-446. |
| [7] | http://tangible.media.mit.edu/ |
| [8] | http://www.iamas.ac.jp/~iwai/ |