3.4 ナレッジマネジメントとIT
3.4.1 はじめに
ナレッジマネジメントとは、ナレッジワーカーが強力なIT(Information Technology:情報技術) の助けを借りながら、企業の営存 [14]
の価値を高めるようなナレッジを、創造・共有・再利用するプロセスを合理的にスピード化、効率化するマネジメントのことである。ナレッジマネジメントは一般に「人、組織文化、プロセス、技術、知識」の5つの視点
[2] から分析されることが多い。本章では、ナレッジマネジメントによる知識創造企業の実態を踏まえて、AI技術を含むITがどのようにナレッジマネジメントに貢献できるか、21世紀知識産業を創出するITビジネス展開について提言する。具体例として、国立大学でのナレッジマネジメントの実践事例も紹介する。最後に、日米のIT格差の根源に関する問題提起を行い、ナレッジマネジメント格差解消の縁としたい。
3.4.2 ナレッジマネジメント
近年、知識に関する組織論とITが融合し、知識の創造・共有・再利用に関するIT活用のあり方、技術開発の方向性に新たな展開が見られ、ナレッジマネジメント[1,
3, 5, 17, 18, 19, 25] と称する一大研究領域が勃興してきた。ナレッジマネジメントは野中郁次郎の一連の著作 [23, 24] を端緒とし、トーマスH.ダペンポートの組織論研究[2]
をベースとし、実践的ITが根づいている欧米を中心に進展してきた。
野中は「知識創造企業」[24] で、マイケル・ポラニーの暗黙知の理論 [28] に着目し、形式知と暗黙知の知識変換プロセスを共同化、表出化、連結化、内面化という4つのプロセスからなるモデルを用いて、知識創造のプロセスを明らかにした。更にこのモデルと「場」、「知的資産」の三者をバランスさせ、活性化させる役割としての「知のリーダーシップ」[3]
の重要性を喚起している。これに対して、ダペンポート[3] はナレッジマネジメントのフレームワークとして、「人、組織文化、プロセス、技術、知識」の5項組をあげている。彼はナレッジマネジメントを支える五つの主要概念として暗黙知と形式知、コード化戦略と個人化戦略、知識マーケット、実践の場、無形資産を指摘し、ナレッジマネジメントを実践するプロジェクトのタイプ分類を試みている。
3.4.3 ITによる支援
1980年代のクライアント・サーバシステムの導入、グループウェアの普及、インターネットやイントラネットのインフラとしての導入・普及促進を経て、1990年代になってモバイル端末の普及、データウェアハウスの設立、サプライチェーンマネジメントの登場といったITをナレッジマネジメントに導入し成功した事例の報告が相次いで起こった。ITとしてはグループウェア技術、データベース技術、マルチメディア技術を中心に各種マイニング技術、情報フィルタリング技術、アウトラインプロセッサ技術が活用されている。すなわちインターネット上に、知識を取り扱うための知的技術が実装され、人間中心のユーザインタフェースを備えた情報システムによるナレッジマネジメントが期待されている。これら各種ツールを著者らのカテゴリ[16]で分類したのが、図3.4-1である。
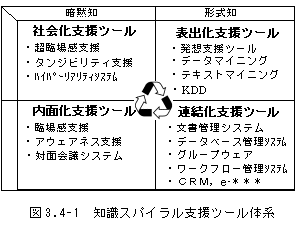 この動きを受け、新しいナレッジマネジメントソフトの販売、ソリューションサービスやコンサルティングサービスの登場、付随する教育・訓練・調査・出版業界の胎動が起こり、新たにナレッジマネジメント市場が形成されるようになってきた。最新の調査によると、米国では2000年での市場規模予測はほぼ50億ドルを越えると言われている。 この動きを受け、新しいナレッジマネジメントソフトの販売、ソリューションサービスやコンサルティングサービスの登場、付随する教育・訓練・調査・出版業界の胎動が起こり、新たにナレッジマネジメント市場が形成されるようになってきた。最新の調査によると、米国では2000年での市場規模予測はほぼ50億ドルを越えると言われている。
情報処理業界と密接に関連するナレッジマネジメントソフトの販売に眼を転じると、いくつかの注目すべきソフトウェアが登壇してきた。データウェアテクノロジィー社のKnowledge
Management Suit 、ロータス社のLotus Notes/Domino R5.0 、マイクロソフト社のMicrosoft Site
Server 3.0が注目されている。国産ソフトとしては、NEC のStarKnowledge 、三谷産業のSELFシステム、NTT データのKnowledge
Serverがある。具体的事例として最も整備されているのは、アーサーアンダーセン社のMicrosoft Site Server 3.0上に構築されたKnowledgeSpaceであろう。 |
表3.4-1 関連WWW サイト[29]
|
企業名
|
URL名
|
|
日本IBM(株)東京基礎研究所
|
http://www.trl.ibm.co.jp/projects/s7000/pgindex/kmgt.htm
|
|
NEC(株)
|
http://www.sw.nec.co.jp/Star/SK/
|
|
(株)NTT データ
|
http://www.knowhowbank.com/
|
|
アーサーアンダーセン
|
http://www.knowledgespace.com/index.htm
|
|
コンパックコンピュータ(株)
|
http://www.compaq.co.jp/solution/km/index.html
|
|
(株)ジャストシステム
|
http://www.justsystem.co.jp/km/index.html
|
|
マイクロソフト(株)
|
http://www.microsoft.com/japan/dns/knowledgemgt/
|
|
ロータス(株)
|
http://www.lotus.co.jp/home.nsf/topframe
|
|
(株)日本総合研究所
|
http://www.jri.co.jp/pro-eng/kwh/chisiki/workshop97/sld001.htm
|
3.4.4 AIによる支援
トマス・ダペンポートの近著[2] によると、ナレッジマネジメントを支援するAI関連技術としてデータマイニング、知識レポジトリー、事例ベース推論、制約ベース推論、エキスパートシステム
[35] に注目している。このそれぞれについて活用状況を概観しよう。
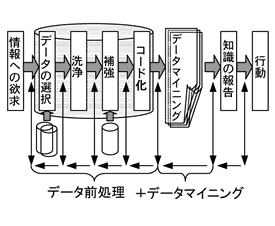
図3.4-2 知識発見の工程[35] |
最も注目されるのがPOS データや金融データへのデータマイニング技術の適用である。データマイニングは知識発見プロセスの最初の部分であり、図3.4-2に示すように、様々なデータ前処理をした上で、機械学習や統計手法を適用して、意味のあるパターンやルールを見いだす。問題は膨大な生成されたパターンやルールの中から、人間にとって理解可能な有意なものをフィルタリングできるかどうかにかかっている。同様のアプローチがマーケティング、医療データベースや遺伝子データベース分野で利用されて、多くの成功事例が報告されている。なおこの延長上の技術として、インターネット上の膨大なテキスト情報から必要な情報を探索するテキストマイニング技術が注目されており、そのナレッジマネジメントへの適用可能性が検討されている。
文献[2] では、「優れたシソーラスがオンライン知識レポジトリーに本質的である」と主張しており、組織が興味をもつ用語体系(知識レポジトリー)を利用した情報検索ツールの有用性を強調している。このような研究は、人工知能研究者にとってオントロジー工学
[20] の重要性を喚起している。キーワードの部分一致に基づく高速情報検索アルゴリズム技術はほぼ確立し、情報検索研究の次なるターゲットはシソーラス検索、意味検索、内容検索、連想検索
[8, 27]、類似検索 [22] 技術に移っている。そこでの主要研究課題はドメインオントロジーをいかに確立するかということと、キーワードベクトル法 [34]
を中心とする統計的フィルタリング技術の確立と、そのナレッジマネジメントへの適用である。
事例ベース推論、制約ベースシステム、エキスパートシステムについては、ここでは紙数の関係で、同一のカテゴリで論じる。膨大な事例ベース推論、制約ベースシステム、エキスパートシステムが開発され、その成功例も多々報じられているが、現在も運用されているのは、そのうちの数%にしかすぎない。解くべきタスクや伝えるべきコミュニケーションがフォーマルに近い領域、(例えばワークフロー管理システム
[31] 、稟議支援システム)では、確実にそのデジタル化、IT化が推進しつつある。しかしながらインフォーマルタスクやインフォーマルコミュニケーションを支援する領域では、ナレッジマネジメントまで視野にいれると、形式知のみならず暗黙知まで伝達しなければならず、そのために解決すべき研究課題はあまりに多いのが現状である。アウェアネス[7,
33] 、タンジビリティ [6] を手掛かりに、暗黙知まで伝達すべきナレッジマネジメント支援環境の研究がやっと開始し、21世紀知識社会を支える基盤整備研究が、先端的研究機関で行われている。
3.4.5 実践事例報告
執筆者は、日本で初めての国立大学院大学JAIST(北陸先端科学技術大学院大学)の教授になって、9年経った。この間、情報科学センター長や知識科学教育研究センター長も併任した。国立の研究機関特有のコラボレーションに関する諸問題に直面しながら、民間企業の研究所に18年間いた経験を生かし、それら諸問題の解決に奔走してきた。ここでは、そのなかでナレッジマネジメントおよびITに密接に関連する話題を取り上げたい。
(1) JAIST 情報環境を利用したサービスシステム
JAIST では、教職員・院生を含め一人一台のワークステーションあるいはパーソナルコンピュータの情報環境がインフラストラクチャとして提供されている。この情報環境を活かすべき最初はボランティア・グループ中心に各種のサービスシステムが開発されてきた。ホームページの整備、修士論文・博士論文等の公開、広報部門によるJAIST
ニュースの発行はいうに及ばず、学生による授業評価システム、セミナー室等の予約システム、就職指導システム等のユニークなサービスシステムが定着している。

図3.4-3 JAIST シャトルバス |
(2) シャトルバスの開通
金沢と小松の中間という「地の不利」のせいで、JAIST の足回りは非常に悪い。金沢市内からの路線バスは朝夕一便の状態であった。執筆者も最初の半年間、車の免許を持っていなかったので、毎夜タクシー帰宅の有様であった。そこで当然、教職員・学生から路線バスの整備の大号令が起こるのだが、いつまで立っても埒があかない。山の中の大学院大学で人数が少ないのが災いして、地元の行政機関が運動するも、採算が合わないとバス会社は動かない。事務局の主要メンバもやりたいという意向は持っていることをうすうす確認したが、「前例がない」というお役所主義で躊躇していた。そこで1994年の秋にインフォーマルに「何が問題か」を執筆者なりに分析したところ、財源の問題と交通事故時の対策の問題が主要な課題と分かった。たまたま当時の研究科長から材料科学研究科の某教授を紹介された。彼の話だと材料科学系では、実験での事故を想定し学生全員、掛け捨て保険に入っていることが分かった。そこで保険屋さんに会った所、「次年度の4月から通学路も保険の対象になる」という話を聞き、このナレッジのもつ重要性に気づいた。そこで執筆者は「財源は教官の校費負担、関係者全員掛け捨て保険に入る」という名案を思いつき、総務部長・会計課長・副学長・学長とミドルアップダウンにキーパーソンを説得した。その後、紆余曲折の説得工作を経て、現在本学の本予算の中で地元の鶴来駅とJAIST
の間をピストン往復するシャトルバス(図3.4-3参照)が、土日も含み無事運行している。すなわち結果的に教官の校費負担は0で運用している。またシャトルバスに接続する電車路線への居住者増の影響で、利用者も毎年のように増加している。
(3) 研究費執行管理システムの研究開発と全学利用
1995年9月末の卒業式打ち上げパーティで執筆者は事務局長、会計課長と雑談していた。このとき「常に予算残の分かる研究費執行管理システムがあるといいね」という話をしていて、研究科長と図書館長も大いに賛同した。1995年10月の教授会で、情報科学センター長である執筆者が出席していなかったにも係わらず「情報科学センターに上記システムを作ってもらおう」という決議がなされてしまった。酒の席での発言が執筆者に振りかかってきた。そこで執筆者とセンターの敷田助手は事務局側の全面協力を経て、本学の伝票管理ワークフローの実態を調査した。
企業では当然の如くやっているサポート業務なので、最初は既存のグループウェア、例えばワークフロー管理システムを導入すればいいと気楽に考えていた。ところが極めて恵まれた情報環境と言われる本学でも、それでは実現が困難と判断した。その理由の第一は教職員のそれぞれが自分の好きなメーカのパソコン等を利用しており、大学という組織は極めてヘテロなハード、ソフト混在文化ということを認識させられた。結果的に、全員の使えるツールは電子メール(今ならWWW)のみということが分かった。しかも国立機関特有の会計検査院の会計検査に耐えうるシステムにするために、各種の工夫が必要と分かった。
そこで敷田が同年12月末までに第-1版を試作、2-3 の教官がこれを試行し、デバッグ・改良し、1996年4月より第0版を情報科学研究科全体で運用し、評判が良いので順次、材料科学研究科、知識科学研究科と全学で使用ということになった訳である。このシステムCERES
の詳細は文献 [13, 30, 31, 32] を参照していただくとして、日本特有の「ハンコ」行政や会計検査に耐えうるような伝票の特注、ドットインパクトプリンターの使用、相見積り書の添付等の工夫を行った。既存のワークフロー管理システムは全ての情報が電子的なビットに変換されてインターネット上を流れているという業務フロー改革を前提に構築されている。我々のシステムは、国の制度等により電子化することの出来ない実世界上の業務フローの存在を認め、これに合わせて実世界指向のワークフロー管理システムCERES
[32] を構築した。
(4) WWWアウェアネスシステムWebCoordinate
ネットワーク上の分散環境会議に変えた途端、対面環境の会議では当たり前の各種情報の伝達がアウェア(知覚)されなくなる。電子メール、WWW 、グループウェア、マルチメディアグループウェアのどれを使おうと、所詮、視覚と聴覚のみに訴えることになり、触覚、嗅覚等の情報のアウェアネスも失われてしまう。また視覚情報においても誰が誰をみているか、彼らが今何をしているか、誰の回りに誰がいるかといった各種の情報が欠落してしまう。WWW
上のブラウジング作業において、誰が同じホームページをみているか、そのホームページのどこを見ているか、それを見て感じたことを赤ペンで表示できるような仕掛けを提供するのが、富士通北陸システムズと我々で共同開発したWeb
アウェアネス表示環境WebCoordinate [21] である。このシステムの有効性は遠隔レビュー等で確認[4] された。富士通北陸システムズとJAIST
との間で特許申請も行い、2000年3月20日には商品化され、既に十数件のユーザに販売済みである。地元の大学や各社のWWW の教育システムとして好評発売中である。
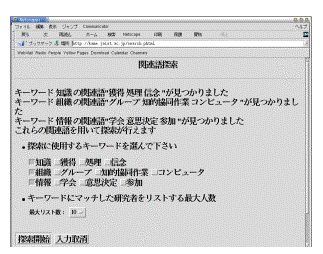
図3.4-4 関連語に基づく連想検索システム |
|
(5) 連想検索型サーチエンジン
執筆者が富士通国際研にいるとき、拙研究室の渡部はKeyword Associator[34] というキーワードベクトルに基づく連想検索型サーチエンジンを研究開発した。これはインターネットのニュースグループから関連度の高いニュースを情報探索する世界で初めてのサーチエンジンで、今年から富士通のテキストマイニングツールとして商品化された。この研究に勇気づけられ、JAIST
でもこの研究の改良研究を続けているが、なかでも図3.4-4に見られるように、顧客のニーズに関連する専門研究を行っている研究者を探すキーワードベクトル等に基づく連想検索システムの研究
[8]がナレッジマネジメントには有効との指摘がある。
実際、石川県の会社の方が県内の大学、公設研究機関の研究者のアンケート結果に基づき、共同研究の相手を探すシステム [27] に適用し、それなりの成果をおさめた。
|
|
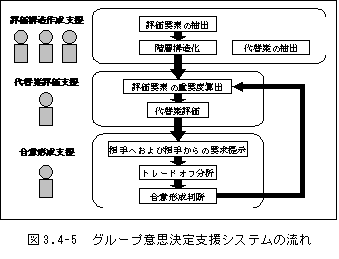 (6)
意思決定支援グループウェア (6)
意思決定支援グループウェア
執筆者は第5世代プロジェクトの一環として、専用ワークステーションであるPrologマシンPSI 上に、主観的評価法AHP に基づく意思決定支援グループウェアGRAPE[15]
を研究開発した。これは同一の意思決定木のもとにグループメンバそれぞれの衆知を結集し、合意形成を促進するグループウェアである。JAISTではこのアイデアをあたため、汎用ワークステーションSUN
やパーソナルコンピュータWindows上に各種の意思決定支援グループウェア [9] を研究開発している。なかでも加藤の合意形成支援グループウェアGroup
Navigator [10]は互いに異なる価値観の人々が感度分析に基づく価値観のすり合わせをし、合意形成を促進するという機能を持つ(図3.4-5)。評価実験によると、意思決定の知的生産性を倍以上向上するという注目すべき成果を得ている。なおこのソフトの一部はフリーソフトウェアとして、石川県工業試験場の加藤により公開されており、既に23機関に導入利用されている。
|
3.4.6 実践事例からの教訓
ナレッジマネジメントに関する調査、我々の組織内でのナレッジマネジメント実践事例を通じて、幾つかの教訓を得た。それらを箇条書きすると、つぎのようになる。
| 1) |
組織ダイナミックスの機微を察して、意思決定のキーパーソンを説得することが重要である。トップダウンでもボットムアップでもないミドルアップダウンの意思決定
[23] が、日本の組織では特に求められている。 |
| 2) |
組織内部の仕事のやり方の実態を正視してから、システムの設計に入る。その際、早急に変えられない制約は無理に変えず、実世界指向の組織文化に合わせたシステム設計が望まれる。「実相観入の精神」で、問題の本質を掴み、問題解決に役立つナレッジを発見することが大切である。 |
| 3) |
電脳文化の熟成の程度に合わせ、最も多くの人々が使用している情報環境の周辺に経営資源を投入することが必要である。「昔電子メイル、今WWW 、近年i-モード、さて将来は...」というところであろうか。 |
| 4) |
往々にしてメイルを読まない年配の人がその組織のキーパーソンであることがありえる。これらの例外的人々の自尊心を傷つけない秘書等への自動転送メイルシステムも導入した。
|
| 5) |
テキスト化できない情報を口頭で残す必要がある場合がある。そのような情報は無理に形式知化、テキスト化する必要はない。それにより、そのような情報をもっている人々の存在価値が高まる。
|
| 6) |
ノウハウは出来る限り自然言語で良いからテキスト化し、前例(=事例) として残す。それにより組織の構成員が転勤・転職しても、業務に必要な組織知を残すことができる。組織知をアウェアさせる情報共有、知識共用、ノウハウ共有システム
[11、12] の研究開発が急激に進展している。ナレッジマネジメントソフトの標準機能であるXML 上の情報共有、知識共有ツールを活用して、分社化等に伴うコーポレイツ・アルツハイマー症を防ぐ必要がある。 |
| 7) |
価値観の異なる人々をコーディネイトし、オフィスの知的生産性を向上さすツールの研究開発 [16] が求められている。我々は既に感度分析を利用した意思決定の生産性を倍以上向上させる合意形成支援グループウェアの研究開発
[10] に成功している。 |
3.4.7 日米の情報技術格差の根源
1980年代の日本企業の奢りを横目に睨みながら、ゴア副大統領の情報通信ハイウェイ計画、クリントン大統領の新千年紀に向けてのITフロンティア計画Bluebook2000等を通して、米国は1990年代に入ってITを駆使したインフラ構築と企業革新を徹底的に成し遂げた。米国と日本の景気の動向に端的に示されているように、米国は様々の組織のインフラの整備等を通して、インターネットを中心とするグローバリゼーションを成し遂げ、極めて効率的な利益の出る組織を世界市場相手に構築した。こうして日米の景気構造は逆転し、日本は産業構造のIT遅れの現状に四苦八苦している。
このことはナレッジマネジメント市場においても同様である、ナレッジマネジメントは当初から形式知中心のコード化戦略と呼ばれるものと、暗黙知中心の個人化戦略と呼ばれるものが存在した。欧米は前者に秀でており、日本は後者に秀でていることは歴史の教訓であるが、急激なIT化、インターネット化、グローバリゼーション化が欧米に味方したのは、衆目の一致するところコード化戦略であろう。企業のリストラ、ビジネスプロセスリエンジニアリング、M&Aに代表される組織革新を経て、欧米企業は過激なまでに変身した。その結果、組織のフラット化、効率化が起こり、短期での企業利益は向上したが、人の移動が激しくなり、それぞれの組織のコアコンピータンスを担っている知識人が流出した。ここに新たなコーポレイツ・アルツハイマーという知の流出現象が起こった。そこで再び野中の知識創造企業が注目され、野中は「ナレッジマネジメントの父」と称されだしたのである。
一般に日本のITが遅れた理由として、次のような理由が知られている。
| 1) |
インフラの整備の遅れ:ラスト1マイル問題に象徴されるように、日本のネットワークインフラストラクチャの整備は、アメリカより10年近く遅れている。米国ゴア副大統領の光データハイウェイ構想のような魅力的なインフラストラクチャ整備が国家プロジェクトとして必要である。 |
| 2) |
タイプ入力文化の未成熟:タイプ入力文化が未成熟で、ネットワークの血流に必要なデータの蓄積が欧米に比べて圧倒的に少ない。ブラインドタッチ教育、英語教育を含めたIT教育立国にするため、なすべきことは余りに多い。 |
| 3) |
通信回線の回線使用料のコスト高:東京−金沢間の回線使用料をNTTとATTとで比較すると、諸経費を含め10倍高い。例えばビデオ1本を転送するのに、日本では4000円かかるが、アメリカではVODがこの1/10,
すなわち400 円で済む。この日米の回線コストの解消問題は政治の力を借りても解決すべきである。 |
| 4) |
ナレッジにコストをかける意識の欠如:日本は伝統的にハードに対してはお金を払うが、ソフトやノウハウといったナレッジに対してはお金を払いたがらない。この意識が知的財産権意識の欠如につながり、大きな国家的損失を生み出しつつある。更にビジネスモデル特許でこの格差が広がる傾向にある。 |
| 5) |
企業文化のグローバリゼーション遅れ:世界的なグローバリゼーションの中で、世界的な産業の棲み分けが起こりつつある。日本全体の産業構造のリストラを含む賃金体系や雇用体系の早急な整備が望まれている。 |
| 6) |
競争のない談合体質の問題:国内の関連企業が談合しあい、公平な競争を妨げている業界がある。金融、建築業界などのように国際的に競争力のない業界は、多いに反省し、インターネットによる国際入札、競争入札を標準とすべきである。 |
| 7) |
規制緩和の問題:国の会計制度や各種規制が国際的な競争入札を妨げている局面がある。国際的なグローバリゼーションに適した制度に変えるべきである。ハンコ行政、根回し行政の長短を見極め、インターネット時代、IT時代に適した参画型の行政制度に改正すべきである。 |
| 8) |
プロジェクト会計制度の見直し:米国の政府支援研究開発においては効率重視のマネジメント [26] が可能で、通年度会計や費目間流用の規制緩和等の実施による事務処理負担の大幅な軽減が図られている。これにより、プロジェクト実施期間中、予算の次年度への繰越し、支出の次年度への繰越し、費目の振り替えを自由に行うことができる。 |
参考文献
[1] アーサーアンダーセン・ビジネスコンサルティング編:図解ナレッジマネジメント、東洋経済新報社、1999.
[2] T. H. Davenport and L. Prusak: Working Knowledge, Harvard Business
School Press, 1998.
[3] Diamond Harvard Business: 「特集」ナレッジ・マネジメント、1999年9月号.
[4] 藤田充典、中川健一、國藤 進: 共有WWW による遠隔レビュー作業の効果に関する考察、情報処理学会主催、DICOMO'99
シンポジウム、pp.501-506, 1999年6月.
[5] ビル・ゲイツ: 思考スピードの経営、日本経済新聞社、1999.
[6] 石井裕他: タンジブル・ビット―情報の感触・情報の気配、NTT出版、2000.
[7] S. Ito and S. Kunifuji: Supporting Conversational Awareness in Text-based
Conference System, Proceedings of KES'2000 Vol.1, University of Brighton, pp.
221-224, 31 August, 2000.
[8] T. Kanai, J. Li, and S. Kunifuji: Related Document-based Information
Filtering Applied to the Association Model Information Retrieval System, Proceedings
of KES'2000 Vol.1, University of Brighton, pp. 225-228, 31 August, 2000.
[9] 加藤直孝、中條雅庸、國藤 進: 合意形成プロセスを重視したグループ意思決定支援システムの開発、情報処理学会論文誌、Vol.38,
No.12, pp.2629-2639,1997年12月.
[10] 加藤直孝、國藤 進: 異なる評価構造を持つ参加者間の合意形成支援法の提案と実装、情報処理学会論文誌、Vol.39, No.10,
pp.2927- 2936,1998 年10月.
[11] 門脇千恵、爰川知宏、山上俊彦、杉田恵三、國藤 進:情報取得アウェアネスによる組織情報の共有促進、人工知能学会誌、Vol.14,No.1,
pp.111-121,1999年1月号.
[12] 門脇千恵、國藤 進、中川健一:Web での協同作業を支援するアウェアネス技術、bit、共立出版、2000年8月号、pp.2-7.
[13] 木村緒理恵、敷田幹文、國藤 進: 実世界ワークフロー管理システムの実現に関する研究、情報処理学会DiCoMo論文集、pp.527-532、1997.
[14] 北川敏男: 情報学の論理、講談社現代新書、1969.
[15] 國藤 進: 知識獲得支援グループウェアGRAPE 、郵政省電気通信局電気通信技術システム課監修「マルチメディア時代のグループウェア」、オーム社、pp.165-176、1993年11月.
[16] 國藤 進: オフィスにおける知的生産性向上のための知識創造方法論と知識創造支援ツール、人工知能学会誌、Vol.14, No.1,
pp.50-57, Jan. 1999.
[17] 黒瀬邦夫: 富士通のナレッジマネジメント、ダイヤモンド社、1998.
[18] J. Liebowitz and T. Beckman: Knowledge Organizations -What Every Manager
Should Know-, St. Lucie Press, 1998.
[19] J. Liebowitz(Ed.): Knowledge Management Handbook, CRC Press, 1999.
[20] 溝口理一郎:オントロジーの基礎と応用、人工知能学会誌、Vol.14,No.6, pp.977-988,1999年.
[21] 中川健一、國藤 進: アウェアネス支援に基づくリアルタイムなWWW コラボレーション環境の構築、情報処理学会論文誌、Vol.39,No.10,
pp.2820-2827, 1998年10月.
[22] 野村直之:ナレッジマネジメントの実践動向と技術評価について、人工知能学会誌、pp. - 、2001年1月号.
[23] 野中郁次郎: 知識創造の経営、日本経済新聞社、1990.
[24] I. Nonaka and H. Takeuchi: The Knowledge-Creating Company, Oxford University
Press, 1995.
[25] 野村総合研究所: 経営を可視化するナレッジマネジメント、野村総合研究所広報部、1999.
[26] 内田俊一、牧村信之: 国の資金によるIT研究開発における仕組みや法制度に起因する研究環境の日米格差について、情報処理、Vol.41, No.10,
pp.1168-1173、2000年10月.
[27] 奥野博之、堀井 洋、加藤直孝、敷田幹文、國藤 進: 企業ニーズを研究シーズに関連づける情報探索システムの試作、人工知能学会研究会資料SIG-FAI-9901-36,
pp.69-174, 1999.
[28] マイケル・ポラニー著、佐藤敬三訳: 暗黙知の次元−言語から非言語へ、紀伊国屋書店、1980.
[29] 斎藤主税:ナレッジマネジメントにおける情報技術の動向、北陸先端科学技術大学院大学 國藤研究室セミナーレポート、1999年9月13日.
[30] M. Shikida, C. Kadowaki and S. Kunifuji: Towards a Real-world Oriented
Workflow System -Based on Practical Experiments for Three Years-, Proceedings
of KES'99, Adelaide, pp.46-49, 31 August, 1999.
[31] 敷田幹文、門脇千恵、國藤 進:フローに連携した組織内インフォーマル情報共有手法の提案、情報処理学会論文誌、pp. -
、2000年10月号.
[32] 敷田幹文、門脇千恵:ナレッジマネジメントに向けた実世界ワークフローシステムの開発と運用、人工知能学会誌、pp. -
、2001年1月号.
[33] R. Sakamoto and S. Kunifuji: Collaborative World Wide Web Browsing System
through Supplement of Awarenesses, Proceedings of KES'2000 Vol.1, University
of Brighton, pp. 233-236, 31 August, 2000 .
[34] 渡部 勇: 発散的思考支援システムKeyword Associator、計測自動制御学会合同シンポジウム論文集、pp.411-418、1991.
[35] 山口高平: ナレッジマネジメントとAI関連技術 (招待講演) 、人工知能学会研究会資料SIG-J-9901-14, pp.65-68, 17
Dec. 1999 .
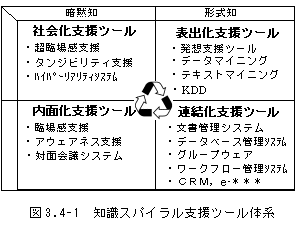 この動きを受け、新しいナレッジマネジメントソフトの販売、ソリューションサービスやコンサルティングサービスの登場、付随する教育・訓練・調査・出版業界の胎動が起こり、新たにナレッジマネジメント市場が形成されるようになってきた。最新の調査によると、米国では2000年での市場規模予測はほぼ50億ドルを越えると言われている。
この動きを受け、新しいナレッジマネジメントソフトの販売、ソリューションサービスやコンサルティングサービスの登場、付随する教育・訓練・調査・出版業界の胎動が起こり、新たにナレッジマネジメント市場が形成されるようになってきた。最新の調査によると、米国では2000年での市場規模予測はほぼ50億ドルを越えると言われている。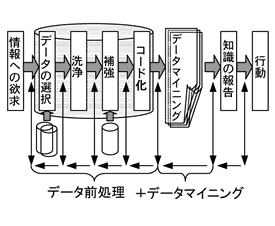

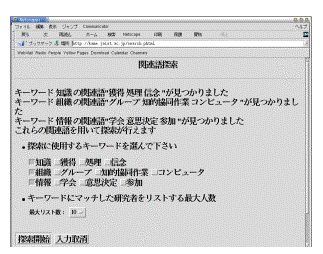
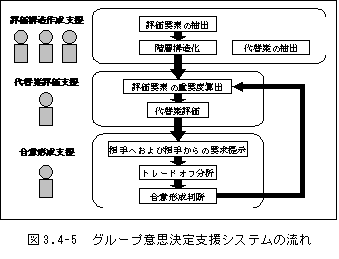 (6)
意思決定支援グループウェア
(6)
意思決定支援グループウェア