3.研究開発の新しい展開と内外の動向
3.1 RoboCupに見る新しい研究開発の進め方
3.1.1 はじめに
ロボカップは、「2050年にロボットサッカーチームがワールドカップチャンピオンとFIFAのルールで戦って勝つ」という目標を達成するためのグランドチャレンジ問題である。これまでに良く知られたグランドチャレンジ問題は、故ケネディ大統領が立てた「10年間で月に人を着陸させ、無事地球に戻す」というアポロ計画である。当時、ソ連の有人人工衛星の成功に衝撃を受けた米国が名誉挽回のために打ち立てた計画であり、人の月面着陸そのものはランドマークとしての意味はあるものの、それを実現するための要素技術からシステム工学まで多種多様な分野で研究開発が促進され、それらの成果が実用に供せられた。人類の月面着陸が達成されたのは、ライト兄弟の飛行機の発明から約50年後のことであった。ロボカップも同じように、ヒューマノイド型ロボットが発表され始めた90年代後期から約50年後に上記の目標を設定したわけである。現在、シミュレーションリーグ、小型リーグ、中型リーグ、AIBOリーグが行われており、ヒューマノイドリーグも2001年から試行される予定である。
ロボカップの目標を達成する過程でもさまざまな技術が生み出されると期待されるが、それを重要な社会的問題や次世代産業の技術基盤に展開していくことは重要な課題である。この課題を推進するために、災害救助問題に展開しているのが、ロボカップレスキューである。現在、シミュレーションシステムだけでなく、実ロボットでもテストコースを使用した競技が行われており、世界で100以上の機関が参加している。また、国際的な協調を推進するために非営利団体による組織化と研究推進が検討されている。このような政治的に中立なレスキューチームの構成はインフラストラクチャとしてレスキューチームを構築する上で重要な課題であり、21世紀に相応しい平和国家として国際貢献を進めていく上でのわが国のキーワードともなろう。
3.1.2 ロボカップの活動
ロボカップは、日本発信の国際的なプロジェクトである。1997年に人工知能国際会議(IJCAI-97)を名古屋に誘致するに当たって、その目玉のプロジェクトとして1995年の人工知能国際会議評議会に提案され、実行に移されることで、一気に世界的な脚光を浴びるようになった。ロボカップは
IJCAI-97 の誘致のために提案されたものではなく、1991年頃からロボット工学や人工知能の研究者が共同で構想を暖めていたものであった。1997年にロボカップの第1回世界大会が開催されることになると、そのために国内予選であるジャパンオープンが翌年から開催され、また、プレカップ大会が1996年に開催された。当初は、次の3つのリーグで競技が行われた。
(1) シミュレーションリーグ
(2) 小型リーグ(F-180リーグ)
(3) 中型リーグ(F-2000リーグ)
小型リーグと中型リーグは実機ロボットを用いたリーグである。シミュレーションリーグでは、サッカーサーバに対して、両チームの22個のプレーヤ(プログラム)がネットワークを介して通信を行ってサーバ上の共通のフィールドでサッカーを行う。サッカーサーバでは、できるだけ現実の社会を模倣するような制約が加えられている。このリーグでの課題は、マルチエージェントシステムの分散制御であり、サッカーサーバとの通信において、通信容量の制限や通信の不安定性にうまく対応できることが不可欠である。
実機ロボットリーグは、車輪型ロボットを使ったものであり、その大きさによって2つのリーグに分かれている。小型リーグ(F-180リーグ)のロボットのサイズには、床占有面積が180cm2以下であり、大きさは直径18cm以内という制約が設けられている。フィールドは卓球台1台分である。1チームのロボットは最大5台で、サッカーボールはオレンジ色のゴルフボールを使用する。ロボットのセンサーはロボットに搭載されたものだけでなく、天井に設置されたカメラ(グローバルビジョン)が使用できる。そのため、各ロボットは、チームを識別するために色のついたマークをつけることが義務付けられている。小型リーグでの課題は、グローバルビジョンを含む多様なセンサーを使用した自律システムの制御であり、個々のセンサー情報が不十分な中で、いかに情報を統合して適切な判断を速やかに下すことができるかが重要である。
中型リーグ(F-2000リーグ)のロボットには、床占有面積が2000cm2以下、大きさは直径45cm 以下というサイズの制約がある。フィールドは5m×7mであり、1チーム最大4台で構成される。中型リーグではグローバルビジョンは使用せず、各ロボットがセンサーの情報を処理して独自に判断を行うことが条件となっている。中型リーグでの課題は、自分自身が得る情報だけで判断を下し、行動をする自律的ロボットの開発にある。つまり、中型リーグでは、許された環境にセンサーを埋め込むことができないような環境での自律ロボットの制御が重要な研究課題となっている。
以上3つのリーグが第1回世界大会から開かれている。それに加えて、ソニー4足ロボットリーグも第2回世界大会でエキシビションが行われ、第3回世界大会からは正式リーグに昇格している。このリーグの特徴は、同じハードウェアを使用していることであり、与えられたハードウェアをいかに活用するかが課題である。使用しているロボットAIBOには、18個のモータがあり、また、ボディが動くことによってカメラから得られる画像が激しく揺れるので、入力情報の処理とモータ制御が極めて難しい問題となる。
2000年のメルボルンで開催された世界大会では、ロボットがプレーヤではなく、「観客」としてロボカップに参加した。ボールを追うことは言うまでもなく、歓声が上がったほうを見たり、笛が鳴ると音のした方向を見るなど、視覚や聴覚情報を統合し、適切なものを見たり聞いたりする機能を実時間で実現することがポイントである。想定される状況が観客を含めたものであるので、サッカーよりも状況認識が難しくなる。もちろん、知的な観客というのが、必ずしも完全な状況認識が必要というわけではない。
2002年に福岡と釜山で開催される世界大会ではヒューマノイドロボットリーグも開始されることになっており、2000年の第4回世界大会ではデモンストレーションが行われ、青山学院大学のロボットが自律制御でペナルティキックの実演を行っている。もちろん、2002年はワールドカップ日韓大会が開催されるのに合わせて、同時期にロボカップ大会が開催される。これは、1998年のパリ大会と同様である。
日本のプロサッカーチームがジュニア部門を持つことを義務づけられているように、トップレベルの技術だけでなく、技術の裾野を拡大することは技術展開には重要である。
ロボカップの普及のためにロボカップジュニアの活動も展開されている。こちらはサッカーだけでなく、ダンスもその対象となっている。ただし、ハードウェアを開発するのは多大なコストがかかり、ノウハウも必要なので、ハードウェアは市販品を使い、複数の玩具メーカが共通仕様で商品を販売している。また、レゴマインドストームの使用も検討されている。
さらに、2001年からは、ロボカップの成果を災害救助に利用するためのロボカップレスキューが始まる。これはサッカー同様、シミュレーションリーグと実機ロボットリーグに分かれている。
3.1.3 ロボカップの展開
ロボカップは、単なるロボットサッカーではなく、「ランドマーク型のグランドチャレンジプロジェクト」として構想された。北野氏(科学技術振興事業団北野共生システムプロジェクト総括責任者/ソニーコンピュータサイエンス研究所)は、研究の動機づけを3つのタイプに分類している。「研究者の興味によって開始されるもの」、「社会的なインパクトの強いグランドチャレンジプロジェクト」、および、「ランドマーク型グランドチャレンジプロジェクト」である。最初のタイプは一般的であり、多くの研究がこのタイプに属する。2番目の「グランドチャレンジ」型研究は、社会的に大きなインパクトを与えるタイプのプロジェクトであり、2000年にクリントン大統領(当時)が宣言したガン撲滅プロジェクトなどが挙げられる。
3番目の「ランドマーク型グランドチャレンジプロジェクト」は、米国のアポロ計画に代表される大きな夢のあるプロジェクトである。その夢はグランドチャレンジのような困難な課題であるが、それ自身の持つ社会的なインパクトはそれほど大きくない。実際、アポロ計画の「月面に人を着陸させ、無事地球に帰還させること」という目標それ自身は記念碑的な夢であり、関心のない人もいるだろうが、その目標を達成する過程で生み出された技術やノウハウが、実社会に大きな波及効果をもたらしたことは疑いもない。コンピュータチェスもやはりランドマーク型グランドチャレンジの一つである。
ロボカップを提案した時点から、ランドマーク型グランドチャレンジとして「夢」を追求する戦略が打ち出され、ロボカップ世界委員会という世界組織の確立と世界各地での大会の企画が次々と行われた。この結果、研究開発が世界で定着し、非常にアクティビティの高い研究コミュニティの形成に成功している。残念ながら、日本国内に目を転ずれば、世界のレベルが一気に向上したため、小型リーグはほぼ壊滅状態、中型リーグもベスト4に残れない、実機リーグは人材・予算ともジリ貧状態である。オリンピックの発祥の地ギリシャが、オリンピック競技では華々しい活躍をしていないのと同じような状況になっており、いかに「ロボカップのギリシャ化」を克服するかが焦眉の急である。そのため、ロボカップの普及のためにロボカップジュニアの企画なども行われている。
これは、地方自治体の地域活性化プロジェクトと組んで展開されつつある。
話しが脱線したが、ロボカップの真の目的はサッカーロボットの開発だけではなく、その過程で生み出される技術をさまざまな分野に展開することを通じて、新たな技術革新を引き起こすことである。とくに、ロボカップでは、行動計画立案、分散協調、行動知能の分野で成果が出てきているので、それをより社会的なインパクトの大きい分野へ展開することが課題である。
3.1.4 ロボカップレスキュー
ロボカップのより明確な標的として選ばれたのが「ロボカップレスキュー」である。大規模災害が発生したときに、ロボットで構成される救助隊を派遣し、被害を最小限にとどめる「国境なきロボット救援隊」を構築するための技術開発を進めようというプロジェクトである。
ロボカップレスキューは、上述した研究プロジェクトのタイプでいえば、ランドマークプロジェクトから社会的なインパクトの強いグランドチャレンジへの展開と位置付けられる。サッカーと災害救助とは、マルチエージェントシステム、協調計算、実時間処理、ロバストな計画立案実行、などの多くの共通点がある。しかし、エージェントの数は非常に多く、その種類は多種多様であり、得られる情報は不確実で限定的であり、補給などのロジスティクスプラニングなど、タスクに依存した問題が数多くある。ロボカップサッカーからロボカップレスキューへのスムーズな技術移転を行うためには、このようなタスクに特有の課題を解決しなければならない。
災害救助活動のためにこれまでさまざまな災害シミュレーションが開発されてきているが、それらの多くは極少数の側面のシミュレーションしかできず、多くの複雑な要因の連関までは反映されていない。例えば、地震災害での要因としては、津波や液状化などの一次被害、建物等の被害、火災、交通機能、ライフライン、人的被害、医療や避難者の社会生活上の被害などがある。火災延焼のシミュレーションでは、このような要因の影響、特に、水道、ガス、交通機能などのライフラインのそれを勘案した包括的なシミュレーションは手つかずの状態である。
ロボカップレスキューでは、このような問題点を解決するために、サッカーの場合と同様に、シミュレーションプロジェクトとロボット&インフラストラクチャプロジェクトが始まっている。両者のプロジェクトが取り組む研究課題は以下のものが挙げられている:
(1) 包括的な災害救助シミュレータの開発とそれを用いた救助戦略の開発
(2) リアルタイムレスキューディシジョンサポートシステム(RDS)の開発
(3) レスキューロボットの研究と個別運用試験
(4) ディジタル機器を装備した救助隊の研究
(5) レスキューロボットとディジタル機器を装備した救助隊である Digitally Empowered Rescue Agents(DERA)とRDSとの統合運用の研究
シミュレーションシステムでは、さまざまな要因を統一的に取り込むためにモジュール構成を採用しており、そのためのシミュレータカーネル、災害事象をシミュレーションするモジュール群、地理情報システム(GIS)などのセンサー群、レスキューエージェントの開発に着手している。また、実データや実ロボットとのインターフェース群、情報表示システムも同時に開発中である。その基本的なアイデアは、インターフェースプロトコルにある。現在、その標準化を進めており、それが設定されると、さまざまなレスキュー機器の相互運用あるいは、国際的な相互運用が可能となろう。
|
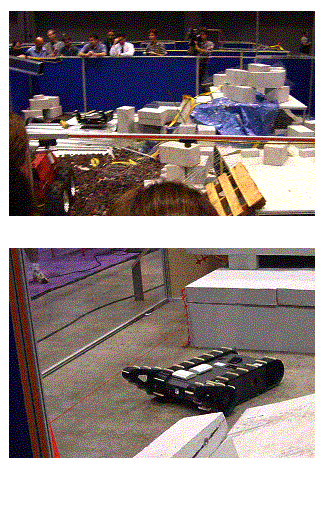 実機ロボットでのレスキューの活動は日本では行われていなかったが、AAAI-2000(第17回全米人工知能会議)で“Urban
Search and Rescue Robot"という競技が開催された。この競技は、NISTが作成したStandard Test
Course で、『Robot must enter fallen structure and search for victims.
Robot judged on number of victims found and on relaying location of
victims』を競うというものであった。優勝したRWIのチームは、キャタピラ型(10m以上の高さから落下しても故障せずに動く)ロボットと大型の円筒形のロボット2台から構成され、キャタピラ型ロボットがtrail
blazerの役割を果たし、マップを作成し、それをもう1方のロボットに通知し、通知を受けたロボットが救援に駆けつけるという構成になっている。他のチームの出来は今一歩であった。 実機ロボットでのレスキューの活動は日本では行われていなかったが、AAAI-2000(第17回全米人工知能会議)で“Urban
Search and Rescue Robot"という競技が開催された。この競技は、NISTが作成したStandard Test
Course で、『Robot must enter fallen structure and search for victims.
Robot judged on number of victims found and on relaying location of
victims』を競うというものであった。優勝したRWIのチームは、キャタピラ型(10m以上の高さから落下しても故障せずに動く)ロボットと大型の円筒形のロボット2台から構成され、キャタピラ型ロボットがtrail
blazerの役割を果たし、マップを作成し、それをもう1方のロボットに通知し、通知を受けたロボットが救援に駆けつけるという構成になっている。他のチームの出来は今一歩であった。
この経験を基に、ロボカップレスキュー国際委員会(委員長:田所諭神戸大学助教授)は、このテストコースを実機ロボットリーグの競技場として使用することに決定した。現在、参加を表明しているのは、米国の大学・軍・民間を含め様々な機関、ドイツのCSやAI関係の国立研究機関(GMDやDFKI)、オーストラリアの大学、その他世界中のさまざまな組織である。
ロボカップレスキュー委員会が想定するプロジェクト推進の方略として次の3点に注目している。
(1) 協調的かつ競争的研究開発
(2) 広範囲な社会問題や産業分野への展開
(3) 非営利団体(NPO)主導の国際プロジェクト
|
すなわち、Linux型のコミュニティを形成し、技術的な研究開発を進めるとともに、さらに、国際的にはNPOの下に世界各国の組織と連携していこうというアイデアである。国際組織の下に世界各国の下部組織が共同で事業を進めるというのは、珍しいことではない。FIFAはサッカーの国際組織であり、非常に規模は大きいものの、国から独立した団体である。オリンピックも、やはりオリンピック委員会という国際的な委員会で運営されている。また、研究開発がNPOで実施されているのは米国ではよく見られ、バイオの領域では、Salk
Institute、Cold Spring Harbor Laboratory、Scripps Research Instituteなどが著名であり、コンピュータサイエンスでのAI技法を用いたソフトウェア開発の研究で有名であった
Kestrel InstituteもやはりNPOである。
3.1.5 おわりに
ロボカップあるいはロボカップレスキューは、日本の若手研究者が組織を越えて提案をしたグランドチャレンジであり、その夢に共感する世界中の研究者が参加し、育てているプロジェクトである。その規模は年々拡大し、底辺も広がっている。そこには、新しい研究の進め方を考え、それを実行する活力が伺える。残念ながら、わが国ではそのような従来の学会の枠を越えた若い力を支援していくシステムが未整備である。省庁の再編を機に、このような元気のある若い力を国の活力としていく施策が求められている。
参考文献
・The RoboCup Federation homepage
http://www.robocup.org/
・北野宏明, 田所諭著『ロボカップレスキュー』2000年, 共立出版
・北野宏明著『大人のための徹底!ロボット学』2001年, PHP出版
・北野宏明, 田所諭, RoboCup-Rescue 技術委員会:
RoboCUp-Rescue, 電子情報通信学会, Vol.84, No.1 pp.42--48, 2001年1月
・Frank, I., Tanaka-Ishii, K., Okuno, H.G., Nakagawa, Y., Meada, K., Nakadai,
K., and Hitano, K.:
"And The Fans are Going Wild! SIG plus MIKE", Proceedings of the Fourth
International Workshop on RoboCup (RoboCup-2000), 267--276, RoboCup, Melbourne,
Aug. 2000.
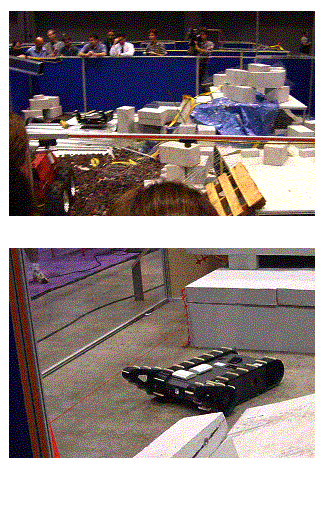 実機ロボットでのレスキューの活動は日本では行われていなかったが、AAAI-2000(第17回全米人工知能会議)で“Urban
Search and Rescue Robot"という競技が開催された。この競技は、NISTが作成したStandard Test
Course で、『Robot must enter fallen structure and search for victims.
Robot judged on number of victims found and on relaying location of
victims』を競うというものであった。優勝したRWIのチームは、キャタピラ型(10m以上の高さから落下しても故障せずに動く)ロボットと大型の円筒形のロボット2台から構成され、キャタピラ型ロボットがtrail
blazerの役割を果たし、マップを作成し、それをもう1方のロボットに通知し、通知を受けたロボットが救援に駆けつけるという構成になっている。他のチームの出来は今一歩であった。
実機ロボットでのレスキューの活動は日本では行われていなかったが、AAAI-2000(第17回全米人工知能会議)で“Urban
Search and Rescue Robot"という競技が開催された。この競技は、NISTが作成したStandard Test
Course で、『Robot must enter fallen structure and search for victims.
Robot judged on number of victims found and on relaying location of
victims』を競うというものであった。優勝したRWIのチームは、キャタピラ型(10m以上の高さから落下しても故障せずに動く)ロボットと大型の円筒形のロボット2台から構成され、キャタピラ型ロボットがtrail
blazerの役割を果たし、マップを作成し、それをもう1方のロボットに通知し、通知を受けたロボットが救援に駆けつけるという構成になっている。他のチームの出来は今一歩であった。