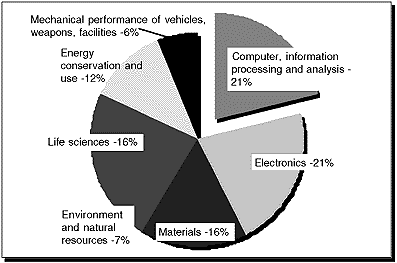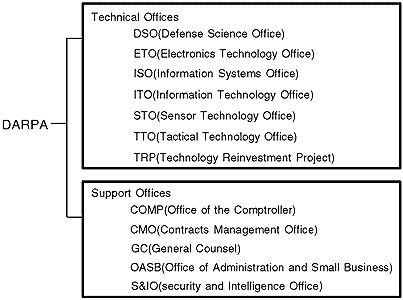
(1)組織概要
DARPA は、PL85-325(DoD Directive 5105.41)を根拠法とするDoDの外局として分離独立された連邦機関であり、DoD内部における研究開発プロジェクトの企画、実施を所轄している。DARPAに対して1994年度に認められた研究予算は21.6億ドルであった。
| (注1) | 詳しくはhttp://www.arpa.milを参照のこと。 |
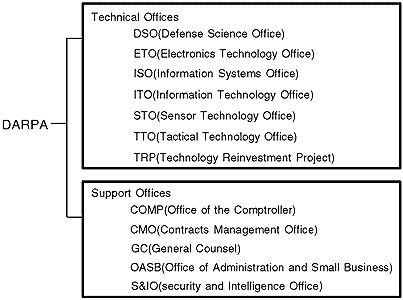
DARPAの組織は図:付1−1のようなものである。DARPAの職員タイプは「Program Manager」、「Office Director」、「Director DARPA」の3階層がある。DARPAは前述したおよそ20億ドルの研究開発予算に基づく研究プログラムを、200人弱の職員(このうち半分の100名弱は Program Managerである)で対応している。後述するように、Program Managerは個別プログラムの企画や提案審査などを担当する専門スタッフであり、5年以上の関連実績経験を企業、大学あるいは軍関係で積んでいるのが通常である。Program managerは常に専門分野における研究コミュニティとの関係を維持し、技術・研究動向に精通するとともに、革新的なアイディアのシーズを探索していることが期待されている。
DARPAが実施する技術プログラムは、主として新規性あるいは革新性を有する技術を対象として高リスクな研究開発に焦点をあてるものとなっている。1992年度にDARPAの技術プログラムが注目する領域は高性能コンピュータ/高温超伝導/ニューラルネットワーク/先端材料/衛星技術/人工知能/高速データネットワーク/ロボティクス/高品位ディスプレイ/ソフトウェア/国防関連製造技術等であった。このなかには1983年より開始された戦略的コンピュータ計画が含まれるほか、HPCC計画においても最も多くの資金分担を得て高性能コンピュータや高速通信ネットワークの研究開発を推進している。
DARPAが実施する研究開発プログラムは、大きく技術的フィージビリティを確認するプロジェクトとプロトタイプシステムを開発するプロジェクトに分類される。このようにDARPAは、技術開発/コンセプト実証から純粋科学/次世代先端的基礎技術開発まで広範囲な研究開発活動に関与しているが、総じて言えることは、これまで国防上有意と思われる研究分野の開拓から技術開発を対象として、戦略的に一定の要求仕様を定めた先端技術の研究開発プログラム("program")を企画し、推進してきたことである。例えば、超並列コンピュータ技術や高速データネットワーク技術といった特定分野において DARPA は、産学官の連携を確保し、今日極めて重要と考えられているこれらの分野のコンセプト作りから実用化に到るまでの研究開発を推進するために、研究開発プログラムを企画立案してきた。
軍事分野の研究開発において生み出された技術成果を民間分野に移転する観点からは、DARPA の研究開発プログラムについても、程度の差こそあるものの他の軍事研究開発プログラムと同様の批判がなされた。しかし、DARPA は確実に軍事予算が圧縮されている今日にあっても、軍民両用技術開発や軍事技術の民間移転を目的とした研究開発プログラム(Technology Reinventment Program)のコーディネータとして重要な役割を与えられている。
NSFは、P.L.81-507(the National Science Foundation Act of 1950)を根拠法とする連邦機関であり、科学及び工学に係わる基礎的研究や教育を企画・支援することを主な目的としている。NSFは、2,000以上に及ぶ大学や研究機関に対して資金供与を行なっており、基礎研究分野における学術機関への連邦資金供与の25%をカバーしている。
| (注2) | 詳しくはhttp://www.nsf.govを参照のこと。 |
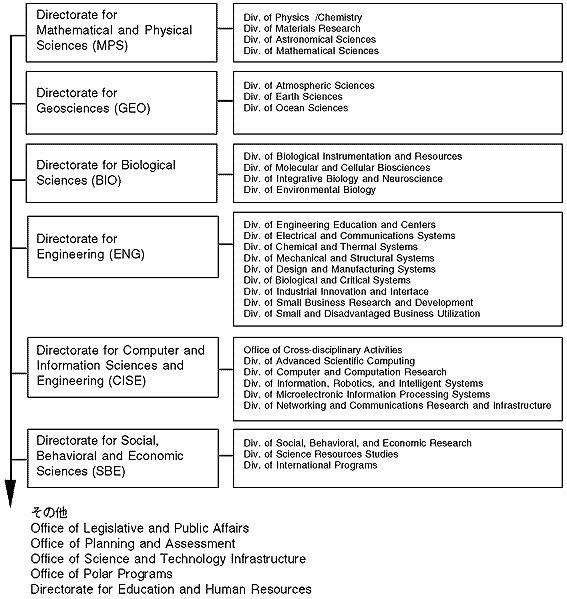
図:付1−2に示すようにNSFの組織は、各分野において資金供与を行なう研究プログラムを実施する部局より構成されている。各部局に所属し、研究プログラムの運営スタッフとなる「Program Officer」には2つのタイプがある。「rotator」と呼ばれるProgram Officerは1〜2年間に限って大学等よりNSFにきているスタッフであり、残りが常勤スタッフである。やや古い数字であるが1987年時点でrotatorは約100人、常勤スタッフは約200人である。
NSFは、医療といった一部分野を除く殆どすべての科学及び工学分野を対象に研究プログラムを実施している。NSFが主に研究支援の対象とするのは、大学、学術団体、非営利目的研究所、中小企業、(例外的に)他の連邦機関、定職を有しない個人等であり、分野としては基礎研究分野に力点が置かれている。逆に、技術支援、パイロットプラント、商用目的の製品開発、特定研究や技術革新がおよぼす市場調査といった活動は支援対象に含めていない。近年では、産業競争力の増進に利する科学技術の研究開発を産学共同で推進するために、ERC(Engineering Research Centers)やSTC(Science and Technology Centers)の支援プログラムなども実施している。
前述したDARPAが、ある技術分野を特定し、一定の技術目標を設定するミッション志向であるのに対して、一般にNSFの場合は、広範囲な基礎研究分野において優れた研究をサポートしている、ということが言える。ただし、NSFについても、NSFに課された独自ミッションがあり、これを遂行するための戦略的研究開発分野を設定し、比較的重点的な研究支援を行なう場合もある。ここにNSFが重視する点は当該プログラムが以下のような目標を有している場合である:
情報技術分野は、図:付1−2にある CISE が担当部局である。情報技術分野でNSFが実施する重要なプログラムには、1985年に開始されたSupercomputing Centerの支援プログラムとNSFNETの構築プログラム、HPCC計画がある。HPCC計画では、NREN(National Research and Education Network)の構築、各コンポーネントにおける基礎的研究(例えば、Grand Challengeにおける学際的な計算科学研究、National Challengeにおけるデジタルライブラリ)において主要な役割を担っている。
NISTは、従来商務省の下部組織である NBS(National Bureau of Standards)を前身とするが、1988年の包括通商および競争法において「技術基盤の構築・強化」を目的とした連邦研究開発機関の再編のなかで拡大改組された。NBSは標準や規格に係わる事業を行なう機関であったが、NISTとなって以降、特に産業分野における研究開発プログラムの企画立案、推進、製造分野における中小企業の助成等を進める組織として重視されはじめた。DARPAが軍事部門においてクリティカルな重点技術の研究開発をサポートしたのに対して、NISTは産業競争力にインパクトをおよぼすクリティカルな技術の研究開発を促進することが期待されている。
| (注3) | 詳しくはhttp://www.nist.govを参照のこと。 |
NISTはその傘下に独立した研究機能を有する研究機関を有している点で、DARPAやNSFとは異なる。情報技術分野における研究所は、情報技術の標準化において重要な役割を担っている他に、コンピュータネットワーク(セキュリティやネットワーク技術)、電子商取引といった広範な研究開発を実施している。
ATP(Advanced Technology Program)は、新たなNISTのミッションとして1990年に創設された研究支援プログラムであり、NIST Actを根拠法としている。ATPは、高リスクでありながら米国の経済に対して重大なインパクトを与え得る技術を、単一企業もしくは企業連合が研究開発する活動に対し、複数年度にわたって資金援助することを目的としており、当初は大きな予算を確保して行なうプログラムにはなっていなかった。
しかし、同プログラムに対する産業界の関心は極めて高く、1994年に同プログラムをあらゆる技術分野を包括する国家プログラムとし、オープンな研究公募のメカニズムのなかで運用していくことが決められた。ATPを通じて拠出される予算規模も急速に増大し、NIST当局は、さらに産業界と連携しながら、ATPを1997年までに年間7億5千万ドル規模の研究支援プログラムにまで拡大したいとしている。
DOEは、特にエネルギー分野を中心として国家的安全保障に関わる研究開発を実施している機関であるが、その初期において原子爆弾の開発に主要な役割を果たしたことからもわかるように、原子核物理学を始めとする広範な基礎科学分野において研究開発を実施している。
DOEは、これらの研究開発を傘下の幾つかの国立研究機関を中心として実施している。そうした研究所には、Ames National Lab.、Argonne National Lab.、Fermi National Lab.、Lawrence Berkeley Lab.、Lawrence Livermore National Lab.、Los Alamos National Lab.、Oak Ridge National Lab.、Sandia National Lab. 等がある。さらに、DOEは民間への技術移転プログラムにおいて重要な役割を担っており、上記の研究機関の研究者と民間企業の研究者が共同研究を行なう、CRADAs(Cooperative Research and Development Agreements)を結び、産学連携を推進している。
| (注4) | 詳しくはhttp://www.doe.govを参照のこと。 |
DOEは前述のように物理学を中心とした基礎科学研究やエネルギー関連の研究を主要な研究対象としているが、そうした研究分野との関連で幾つかの情報技術に関連する研究開発を実施している。
1950年代初期に、John von Neumannの指導の下でスタートしたApplied Mathematical Science(AMS)プログラムは、そうした研究の一つの起源になっている。1983年にAMSプログラムは改編され、Scientific Computing Staffに組み込まれ、解析・数値的手法、情報分析手法、先端的な計算コンセプト、エネルギー分野における計算科学といった研究が DOE 全体で推進されてきた。同プログラムのなかでDOEは多くの並列コンピュータを購入・開発し、計算科学分野における主要な成功事例を生み出すとともに、全米の研究者に対してこうした計算資源を提供している。HPCC計画において、DOEはGrand Challengeにおける計算科学的研究を中心に研究開発を進めている。
NIHはPublic Health Serviceの下部研究機関であり、1887年に1研究室として発足しているが現在は生命科学分野における最も中心的な研究機関として、独自の研究所における研究開発と関連機関(大学、メディカルスクール、病院等)への研究支援を実施している。
NIH予算はおよそ100億ドルである。連邦 R&D 予算に占める生命科学分野に対する支出は年々増加しており、その殆どはNIHに配分される(NSFは、広範な基礎研究分野に資金援助を行なっているが、NIHとの関係から生命科学や医療に関する研究開発への資金援助は対象外となっている。)その81%が研究公募等に基づくグラントで、1,700近い機関のおよそ35,000プロジェクトに対して資金援助を行なっている。これらのグラントはNSFと同様にPeer Reviewにより審査されることになっている。一方、全体の11%の予算はNIH内部の研究機関が実施する2,000程度のプロジェクトに支出される。
| (注5) | 詳しくはhttp://www.nih.govを参照のこと。 |
NIHは生命科学分野における研究開発を主目的としており、当該研究分野に関連する情報基盤的な研究開発(例えば、ヒトゲノムといった遺伝子データベースの整備や医療機関等を結ぶネットワーク整備等)や、生命科学分野における計算科学(例えば、薬品設計や蛋白質の三次元構造解析等)について、研究開発を進めている。これらの分野は、HPCC計画におけるNIHの主要担当分野になっている。
| (注6) | 詳しくはhttp://www.arpa.mil/sbir/sbir/sbir.htmlを参照のこと。 |
SBIRは、連邦政府の研究開発支援を中小企業に対して行なうことを目的として、1982年にSmall Business Innovation Development Act(PL 97-219、PL 102-564)を根拠法として創設されたものである。SBA(Small Business Administration)が調整役となって、研究開発予算が1億ドルを超える全ての連邦機関が、その各研究開発予算のうち一定比率の予算を中小企業に出資することになっている。当初、この比率は1.25%であったが、1992年のSmall Business Research and Development Enhancement Act により毎年この数字を増やし、1997年には2.5%にまで引き上げる予定である。ちなみに、1991年におけるSBIRの全出資額は4億8,300万ドルであり、このうち情報技術分野は後述するように全体の21%にあたる約1億ドルである。
SBIRプログラムが、情報技術分野において重要な役割を担ったことを推測させるデータが図:付1−3である。1980年から1993年の間にハイテク分野を対象とした企業の創業件数を分野別で比較しているこの図より明らかなように、ソフトウェア分野は際立ってハイテク企業の創業が活発だった分野であり、全体のおよそ31%を占めている。創業当初、中小規模であったこれらのハイテク企業のなかに、SBIRプログラムの支援を受けて研究開発を行ない、技術力や商品開発力をつけていったソフトウェア開発ベンチャーが少なくないことは容易に想像できることである。
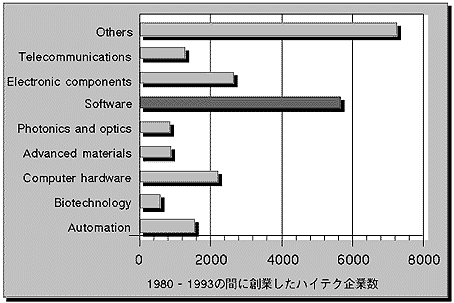
一方、情報技術分野はSBIRプログラムのなかでも比較的重点的に支援された研究開発分野でもあった。図:付1−4は、SBIRプログラムが出資した割合を研究分野別に示したものである。全体の5分の1が情報技術分野に出資されていることがわかる。
連邦機関別にSBIR総出資額に占める情報技術分野の割合を見てみると、最も高いのは DoDの26%であり、これにNASAの25%が続く。3番目に情報技術分野の割合が高いNSFは18%ですでに全連邦機関の平均である21%を下回っている。全SBIR出資額の約半分を占める DoD において情報技術分野への出資割合が高いことが、SBIR全体としても情報技術分野の割合を高くしている要因となっている。