
会場のMarriottホテル
報告者: 大須賀昭彦委員
人間主体の知的情報技術調査ワーキンググループ活動の一環として、Autonomous Agents 2001への参加、米国におけるエージェント研究開発動向の調査などを行ったので報告する。
日程: 2001年5月29日から6月6日まで
調査員: 大須賀昭彦委員
主な調査先:
(1) Autonomous Agents 2001
(2) Carnegie Mellon大学
(3) SRI International
1 Autonomous Agents 2001
International Conference on Autonomous AgentsはACM他が主催する、自律的エージェント技術に関する国際会議。MA(International Conference on Mobile Agents)やICMAS(International Conference on Multi-Agent Systems)等と並び、エージェント技術の国際会議としては最大規模のもの。2001年はカナダのモントリオールで開催され、248件の論文投稿中57件がフルペーパとして採択された。エージェント分野の著名な研究者が多数出席し、参加者は約500名となった。
(1) 招待講演
招待講演は4件行われた。以下に講演概要を紹介する。
Microsoft主席研究員Eric Horvitzの"Attention, Intention, and Initiative: Toward
Insightful Interactive Agents"では、ユーザの心理を考慮した種々のツールに関する研究が紹介された。特に、ユーザの注目点を検知してGUIの制御を行うデモを数多く見せていた。Officeアシスタントは失敗であったとの見解から、このようなGUIに至ったとのことである。
Pennsylvania大学教授Norman Badlerの"Embodied Agents with Behavioral Consistency"の講演は、コンピュータグラフィックスの作成に関するものであった。バーチャルキャラクタのCG作成において、人間の挙動の一貫性(体の各部の動きに矛盾がないこと)に注目して、よりリアルな挙動を実現する技術が紹介された。
Brandeis大学教授Jordan Pollackの講演は、ロボットへの学習機能の搭載に関するものであった。人間を模するロボットにおいて、すべての機能をプログラムで実現するのは事実上困難であり、機械学習が必要になるとの主張が展開された。
Carnegie Mellon大学準教授Tuomas Sandholmの講演は、Autonomous Agents Awardの受賞記念講演で、エージェント技術を用いたオークションに関するものであった。複数の商品を扱うオークションはNP完全となり、近似的にも多項式時間で解けないので、ここに人工知能技術を適用して解決しようという研究が紹介された。
(2) 一般講演

会場のMarriottホテル
一般講演は、3トラックの並列で、18セッションが行われた。以下にセッションの内訳を示す。
(a) 学習、推論、プランニングに関するセッション
(b) マルチエージェントに関するセッション
(c) 擬人化、人間対エージェントに関するセッション
(d) e-コマースに関するセッション
(e) ソフトウェア工学に関するセッション
学習関連は3セッションが開かれ、プランニングの拡張や、BDI(Beliefs, Desires and Intentions)に関する発表が多く見受けられた。例えば、J.
Broersen(オランダVrije Univ. de Boelelaan)らの"The BOID Architecture"の発表では、BDIアーキテクチャをobligationの概念で拡張するBOIDアーキテクチャが提案された。これにより、エージェント間の競合解消などが容易に実現できるとのことである。
マルチエージェントは5セッション開かれ、標準化が進むエージェント間コミュニケーション言語に、いかに意味を形式化して導入するかといった話題が多数あった。例えば、J.
Pitt(英国Imperial College)らの"Interaction Patterns and Observable Commitments
in a Multi-Agent Trading Scenario"、および"Denotational Semantics for
Agent Communication Languages"の発表では、AUML(Agent UML)、およびFIPA(Foundation
for Intelligent Physical Agents)ACL(Agent Communication Language)に形式的意味論を与えることにより、厳密な分析を可能にする手法が提案された。
擬人化関連は3セッションで、感情の導入や人間との対話などに関するモデルの形式化、試作結果の報告が行われた。
e-コマースは2セッションの他に、パネルディスカッションも開催され、いずれも多数の参加者を集めていた。
ソフトウェア工学関連は5セッションで、エージェントソフトウェアの要求仕様獲得、設計方法論、開発支援環境などが報告された。例えば、A. Perini(イタリアITC研究所)らの"A
Knowledge Level Software Engineering Methodology for Agent Oriented Programming"の発表では、エージェントアプリケーション開発における早期の要求定義を支援する開発方法論Troposが提案された。この方法論により、従来のエージェント指向開発方法論に欠けていた早期の要求定義が可能になるとのことである。エージェント分野でのソフトウェア工学は、ここ1、2年で研究が活発化しており、ソフトウェア工学分野で最大規模の会議であるICSE(International
Conference on Software Engineering)でも、エージェント技術に関する発表が増加している。
(3) ワークショップ
ワークショップはfull day workshop 9件、half day workshop 5件が開催された。
(a) Full Day Workshops
(b) Half Day Workshops
以下で、2つのワークショップの概要を紹介する。
| (a) | Agent Oriented Information Systems (エージェント指向情報システムワークショップ) このワークショップはエージェント技術の情報システムへの応用に関するもので、約40名が参加し、招待講演1件を含め、8件の発表があった。M. P. Singh(米国North Carolina 大学教授)の招待講演"Commitment Machine"は、柔軟なエージェントの動作記述をcommitment(公約)の概念を用いて実現する手法を提案したものであった。BDIなどの同様な手法よりも容易に利用できるとの印象を受けた。その他、要求定義、モバイルエージェント、オークション、オントロジー、情報収集などの話題についての発表があった。 |
| (b) | The Second Workshop on Agent-Oriented Software Engineering (エージェント指向ソフトウェア工学ワークショップ) |
(4) その他のイベント

AIBOサッカーリーグの様子
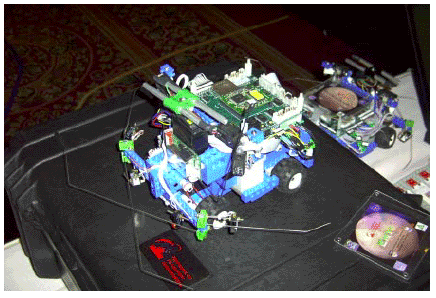
RISEにおける惑星探査車両
ロボットイベントでは、AIBOサッカーリーグ、ロボカップジュニアなどが行われた。Toronto大学のRISE(Robotics in Space
Exploration)プロジェクトは、宇宙探索をロボットで行うというものであった。6台の惑星探査車両のそれぞれがCPUを持ち、ある程度は自律的に動作しながら、互いに通信することによって協調してタスクを遂行するデモが行われた。
デモンストレーション会場では、SemanticWebとモバイルエージェントに関するデモが多く見受けられた。FIPA標準を盛り込んだ組み込み向けモバイルエージェントLEAPによる、PDAとPC混在環境上でのスケジュール調整のデモなどが行われた。他にはインタフェースエージェントに関するもの、DAML(DARPA
Agent Markup Language)に関するものへの関心が高く、見学者を多く集めていた。

デモンストレーション会場の様子
パネル討論"Agents in E-Commerce"では、ECにおけるエージェント技術の現状がパネラから紹介された後、社会的問題やその他のWeb技術などとの関連について討論が行われた。
2 Carnegie Mellon大学Katia Sycara教授訪問
Sycara教授の研究グループは10名前後のメンバーで知的エージェントの研究に取り組んでいる。DARPAからの出資や企業との提携により多数のプロジェクトが推進されているが、特にDAMLやユビキタスコンピューティングに関する研究が多い。以下に現在のプロジェクトリストを示す。
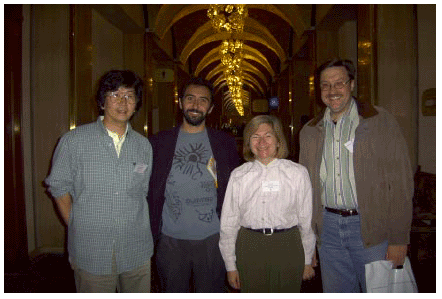
Sycara教授と研究グループメンバ、報告者
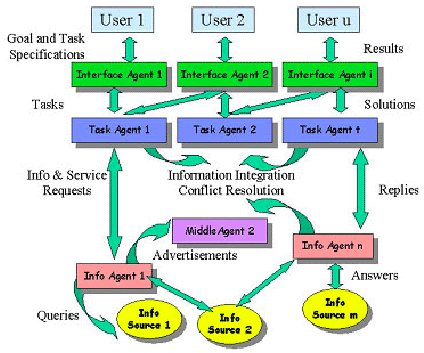
Retsina MultiAgent Infrastructureの構成
この中で、以下の2つのプロジェクトについて議論した。
Retsina MultiAgent Infrastructureは異種エージェントのコミュニティを支援するオープンなマルチエージェント基盤である。この基盤上のエージェントはピアツーピアで相互に作用しながらコミュニティを組織する。このコミュニティの構造は外部環境やネットワーク構造などの影響を受けず、エージェント間の関係から柔軟に構築される。これにより、Retsinaではマルチエージェントの集中管理が不要となり、エージェントによる分散サービスの提供が可能となる。
Intelligent Agent Matching Systemは、登録されたサービスの意味的な検索を行うサービスマッチメイキング技術である。オントロジーをチェックするオントロジーフィルタ、サービスの入出力の型チェックなどを行うシンタックスフィルタ、サービスの入出力条件の論理的な整合性をチェックするセマンティクスフィルタが用意されている。サービスマッチメイキングは、Webサービスにおけるサービスディレクトリ規約UDDI(Universal
Description, Discovery, and Integration)の出現によってその重要性が広く認識されつつあるが、この研究は、Webサービスが広まる前から進められてきた。これまでは、独自のサービス記述言語を用いていたが、現在はこれをDAMLへ適用する試みが行われている。
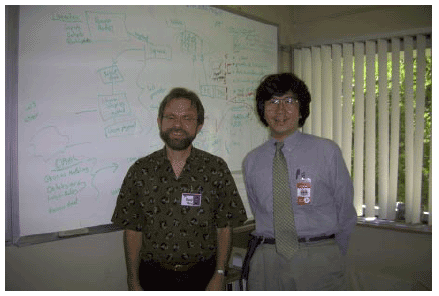
David Martinと報告者
3 SRI International David Martin氏訪問
David MartinはDAML-S開発の中心的な人物で、Carnegie Mellon大学のSycara教授の研究グループとも共同して活動している。現在Webサービス分野においてサービス仕様記述言語の標準となりつつあるWSDL(Web
Service Description Language)は、記述力不足の面があると言われている。このため、MarinはDARPAの支援によって主流になりつつあるDAMLを基にした、新たな仕様記述体系DAML-Sの研究を進めている。DAML-Sではサービス仕様をプロファイル、サービス・モデル、サービス・グラウンディングの3種の情報で記述する。プロファイルではセキュリティレベルなどを記述する。サービス・モデルではサービスを利用するためのプロセスを記述するが、WSDLよりも言語としての記述力を高めている。サービス・グラウンディングではサービスへ接続するための情報を記述する。
今のところ、DAML-SはSRIや大学主体で進められており、産業界への普及見込みは不明である。しかし、サービス仕様記述言語の記述力向上は今後の重要課題であると思われ、DAML-Sの成果が何らかの形で影響をおよぼす可能性が高い。