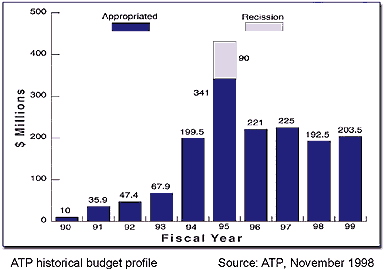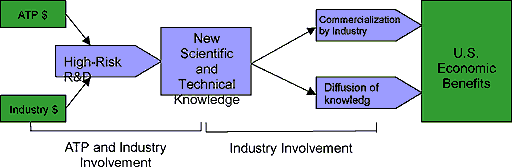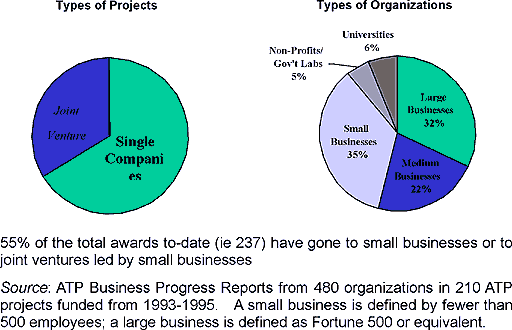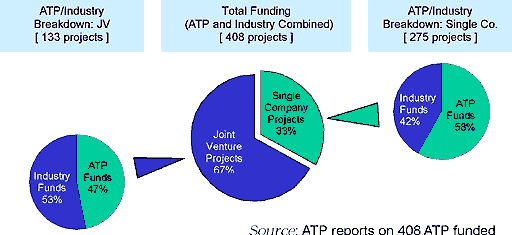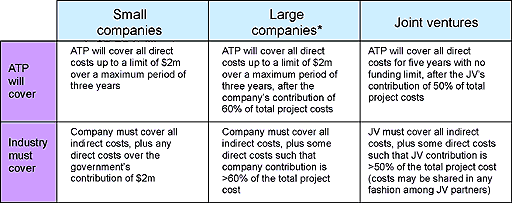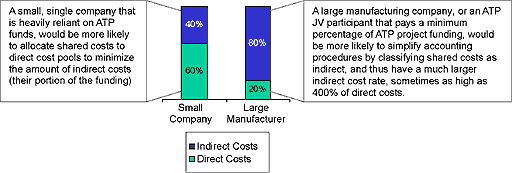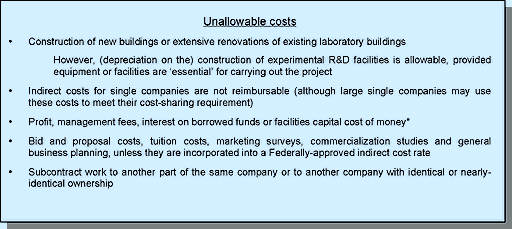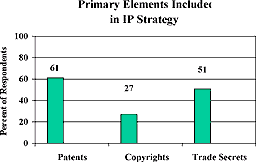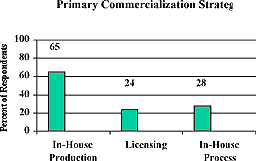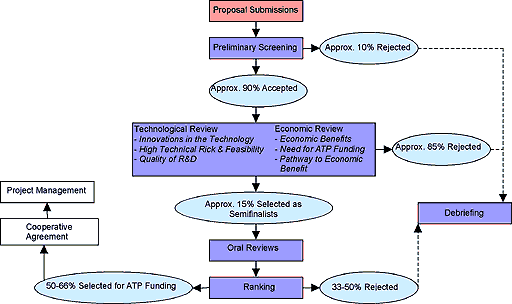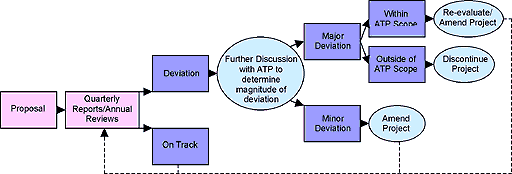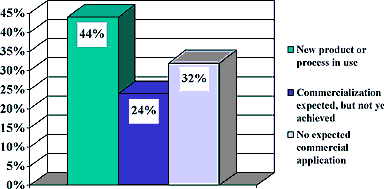イントロダクション
米国先端技術プログラム(ATP)
本調査の目的は以下四つの問題意識に対して明確な回答を模索することにある。
- 民間がATPの経費総額に占める一定の比率を負担するというATPの経費分担ポリシーのもとで、何が経費として計上され、何が計上されないのか。また官民の内訳にはどのような意味があるのか。
- ATPプロジェクトから生まれた知的財産権の扱いはどうなるのか。
- ATPの助成対象となったプロジェクトの成果が助成を受けた企業に利益をもたらした場合、この利益を国庫へ還元する制度はあるのか。
- ATPプロジェクトは何をもって終了されるのか。プロジェクトが順調に進まず、何の成果も生まない場合、どのようにこれを終了させるのか。
本報告書は上記四つの問題に沿って構成されている。
- 第1章:ATPとその沿革
- 第2章:助成のメカニズム(問題1)
- 第3章:知的財産権の扱い(問題2)
- 第4章:利益の扱いに関する哲学(問題3)
- 第5章:プロジェクトの目標設定、監視、終了にまつわるプロセス(問題4)
本調査の当初の目的は3つの事例を取り上げ、これを詳しく分析しつつ、上記の問題に回答を見出すことであった。しかしながら、調査を進める過程で、少ない事例を深く掘り下げるよりも多くの事例を大局的に網羅するほうがより効果的であるとの判断に至った。結果として、本報告書では全体にわたって多くの事例が紹介されることとなった。
第1章 概要
ATP Mission and Focus ・・・・・・・・・
先端技術プログラム(ATP)の狙いは、民間主導のパートナーシップを通してハイリスクな技術開発を推進し、それによって米国経済の成長を刺激することにある。
 ATPは商務省管轄のNational
Institute of Standards and Technology(NIST)を構成する四つの機関のうちの一つで、米国の経済利益拡大をその究極的な目的としている。
ATPは商務省管轄のNational
Institute of Standards and Technology(NIST)を構成する四つの機関のうちの一つで、米国の経済利益拡大をその究極的な目的としている。
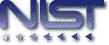 ATPは特にハイリスクな基礎技術の開発を助成の対象としているが、これは革新的な製品、サービス、あるいは産業プロセスの開発を推進し、それによって米国の企業および産業の機会拡大と競争力強化を図るためである。
ATPは特にハイリスクな基礎技術の開発を助成の対象としているが、これは革新的な製品、サービス、あるいは産業プロセスの開発を推進し、それによって米国の企業および産業の機会拡大と競争力強化を図るためである。
 ATPはあくまでも民間主導のプログラムであり、営利企業が主体となってプロジェクトの企画・提案・実施を進め、民間負担分の資金を拠出する。
ATPはあくまでも民間主導のプログラムであり、営利企業が主体となってプロジェクトの企画・提案・実施を進め、民間負担分の資金を拠出する。
- ATPは官から民への補助金(grant)ではなく、官民の協定(cooperative agreement)という考え方に立って、プロジェクトの遂行に対して適切な関与、管理、監督を行う。
Historical Overview of the ATP ・・・・・・・・・
1988年の創設以来、ATPはこれまでに9件の一般枠コンペと30件の特別枠コンペを実施し、1,010社の参加企業とともに431件のプロジェクトを助成してきた。
- ATPはOmnibus Trade and Competitiveness Act of 1988によって創設され、American
Technology Preeminence Act of 1991に基づいて修正された。
- 応募者の業界、技術分野を問わない一般枠コンペ(General Competition)は1990年の初回以来、これまでに9回(毎年1回)実施された。1999年度一般枠コンペの参加申込の締切りは1999年4月14日となっている。
- 特別枠コンペ(Focused Program Competition)は明確に定義された特定の技術および事業目標の達成を目的とした複数年のプロジェクトを対象としている。1994年から1998年にかけて30回実施され、格別の機会をもたらすと特定された技術分野に対して臨界量の支援を与えてきた。この間、ATPは特別枠のプロジェクトに対して莫大な助成金を投入している。
- 最近になって、この特別枠のコンペは打ち切られた。選考過程が18ヶ月から24ヶ月という長期に及び、手続きが煩雑であると判断されたためである。さらに、特別枠のプログラムが排他的に過ぎたことも打ち切りの一因となった。内容的には優れているのに、厳格な条件に適合せず、助成対象から外れる企画があまりにも多かった。なお、進行中のプロジェクトは打ち切り後も継続される。
- 現在までに合計3,585件の提案書が提出され、うち431件(12%)が助成対象となった。
現在までに計上されたATP予算の総額は15億4,400万ドルにのぼる。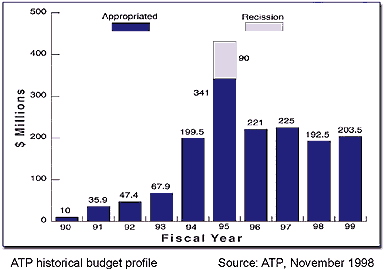
- 1990年から1999年の間に政府が計上したATPの予算総額は15億4,400万ドルにのぼる。
- 初めの4年間の年平均予算額は4,030万ドルだった。
- 過去4年間の年平均予算額は2億1,050万ドルだった。
- 1999年に計上されたATP予算2億350万ドルのうち、6,600万ドルは新規プロジェクトに対する初年度の助成金として支出される。
- ATPの予算決定には政治的要因が大きく作用する。1994年の大幅な増額はクリントン政権発足後、初の予算編成で行われた。クリントンはATPの拡大に意欲的で、当初、1997年までに6億8,000万ドルへの増額を計画していた。一方、共和党が議会で過半数を掌握した1998年の予算編成ではATP予算が減額されている。
※1995年の予算取り消しは災害復興資金(ロス地震を含む)に充てるために行われたもの。
Technological Focus ・・・・・・・・・
ATPは先端技術の開発を目的として民間と共同でハイリスクな研究開発事業に資金を提供するが、製品開発には参加しない。
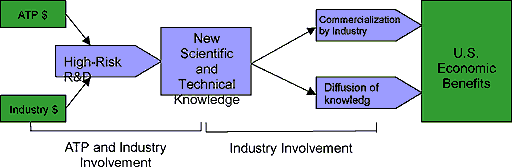
Industry Participation ・・・・・・・・・
ATPプロジェクトは単一企業によるものと、大企業、中小企業、大学、政府の研究機関などから成るジョイントベンチャーによるものとに大別される。
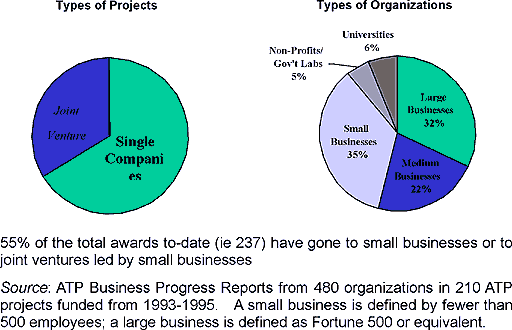
ATP Funding Mechanisms ・・・・・・・・・
ATPの先端技術プロジェクト431件に対する助成金27億8,300万ドルのうち、民間財源からの拠出が50パーセントを超える。
- ATPの助成対象となったプロジェクト431件の助成総額は27億8,300万ドルにのぼる。うち50.2パーセントに相当する13億9,700万ドルが民間財源から、残り49.8パーセントに相当する13億8,600万ドルがATP予算から拠出された※。
- 単一企業の場合、助成額は3年間で200万ドルを上限とし、間接経費はすべて企業側が負担する。また年収27億2,100万ドル以上の大規模企業については、経費総額の最低60パーセントを負担しなければならない。
- ジョイントベンチャーの場合、助成額に上限はなく、JV側の負担額は経費総額の50パーセント以上となっている。
- コストシェアのガイドラインは議会によって策定されたため、大企業優遇の印象を与えないようにするなど、政治的な配慮が大きく作用している。
※13億8,600万ドルはATPが民間に提供した金額である。議会が計上したATP予算$1.544Bのうち、残り$158Mは運営経費等、その他の経費(SBIRへの税金を含む)に充てられた。
IP from ATP Projects ・・・・・・・・・
ATPプロジェクトから発生した知的財産権はすべてプロジェクトに関わった営利企業の所有に帰する。
- ATPはATPプロジェクトから生まれた知的財産権(IP)を米国で設立された営利企業に所有させると規定している。
- 政府は政府によるIPの使用を確保するため、royalty-free、non-exclusiveなIP使用権を留保している。
- ジョイントベンチャーに参加した大学および非営利の研究機関に対しては、知的財産権の所有を認めていない。ただし、特許権使用料の支払を受けることは可能である。
Profits from ATP Projects ・・・・・・・・・
ATPは製品開発や商品化の段階には関与せず、すべての利益は民間に帰属するものとしている。
- ATPは当該技術について製品開発が可能な段階に至るまでの研究活動を助成し、その後の製品開発もしくは商品化を模索する活動には参加しない。
- 最も効率的な商品化の方法は市場に決めさせよ、というのがATPの哲学である。ただし、ATPとNISTは適切な方法による商品化を確実にするため、IPのライセンス権を保持している。
- 営利化の主要な戦略は新製品・新サービスの開発、テクノロジーのライセンシングなどである。
ATP Project Goals and Parameters ・・・・・・・・・
ATPプロジェクトの提案書は達成すべき目標を明確に示さなければならない。
- ATPプロジェクトの提案書には、プロジェクトの達成目標、詳細な研究プラン、具体的な資金配分、終了期日が明確に示される。
- ATPのガイドラインは選考の際の審査基準、助成期間、助成額の上限、計画変更にまつわる手続き等を定めている。
ATP Impact ・・・・・・・・・
ATPはハイリスクなR&Dの促進、R&Dの規模拡大、市場化の早期達成に大きく貢献しているようである。
- ATPは情報システム、コンピュータ・システム、製造、素材開発、バイオテクノロジー、エレクトロニクス、化学薬品、ケミカル加工など、様々な分野のプロジェクトを助成している。
- ATPプロジェクトの参加企業の大部分が、ATPの助成対象となった技術分野において民間のR&D投資が増えたと指摘している。
- ATPプロジェクトの参加企業を調査したところ、回答者の70%が「ATPの助成によってR&Dの規模が拡大した」、「技術的リスクを負うことに、より積極的になった」と答えている。
- プロジェクト参加企業の86%が、ATPの支援を梃子に、ATP助成対象分野におけるR&D事業を加速させている。
第2章 助成のメカニズム
ATP / Industry Cost Sharing ・・・・・・・・・
ATPがこれまでに助成してきたプロジェクトのうち、単一企業プロジェクトの補助率は58パーセント、ジョイントベンチャーの補助率は47パーセントで、総合すると経費全体に占めるATPの助成額は50パーセントを上回る。
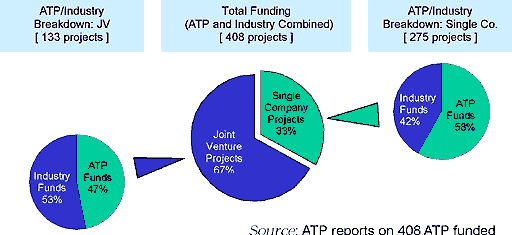
ATP Funding Guideline ・・・・・・・・・
助成のガイドラインは応募者の性質ごとに明確な条件を定めている。
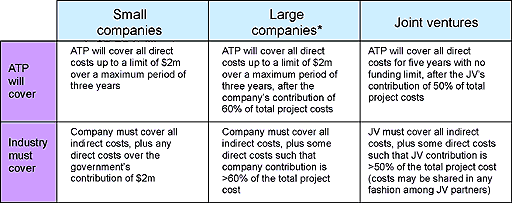
間接経費を正しく確定することが適切な企業負担を確保する秘訣である。
- 大企業とジョイントベンチャーの場合、企業側の出資には会社がプロジェクトのために計上する間接経費が含まれる。
- 理論上、企業は実際にはプロジェクトに関連しない会社の間接経費を関連すると主張しうるし、(作業スペースの確保や上級管理職の時間を根拠に)企業側の負担額を誇張することもできる。
- この場合、プロジェクトの経費総額が一見膨らむばかりでなく、企業側の負担も実際より大きく見える。つまり、企業側が“実質的な金銭”の拠出を少なく済ませることも可能となる。
- この問題を回避するため、ATPはプロジェクトの間接経費として計上可能な費目とそうでない費目、および合理的なコストの直間比率に関する業界標準(業界によって大きく異なる)を厳格に規定している。
- 応募者から提案されるコストシェアの金額は可能な限り低く設定される傾向にある。
Direct vs Indirect Costs ・・・・・・・・・
ATPによる直接経費と間接経費の定義は一般に公正妥当と認められる会計原則(Generally Accepted
Accounting Principles、GAAP)に準拠している。
直接経費は当該プロジェクトの活動経費として直ちにそれと判別しうる経費、および政府の経費原則にしたがってATPが承認する経費をさす。
- ATPプロジェクトに従事する職員の給与・賃金
- 賃金外給付(医療保険等)
- プロジェクト関連の出張旅費
- ATPプロジェクトに限定して使用される機材
- 材料および必需品
- サブコントラクト(主導的なコントラクタに対し、直接経費、間接経費、収益の総額を“経費”として請求)
間接経費はATP関連の活動とは直ちに結びつかない一般的な目的、もしくは共通の目的に対して支出される経費をさす。間接経費の比率は協議のうえ決定されるか、もしくはATPが助成交付の裁定から90日以内に承認する。
- 一般管理費(役員の給与・経費、人事・会計等にかかる経費、図書費等)
- 施設の運営・保守費
- 建物・機材の減価償却費
※ 間接経費の比率が過剰なほど高く設定されている(よって企業側の負担が人為的に膨張させられている)場合、この比率が下げられ、よってプロジェクトの予算総額も下がる。またこのために企業側の負担が許容される最低限度を下回れば(大企業もしくはJVの場合)、ATPの拠出額が下げられる。ただし、現実的にはこの状況は非常に稀である。
Indirect Cost Calculation ・・・・・・・・・
間接経費の確定は“科学的というより芸術的な”プロセスによる。このため直接経費に対する間接経費の割合はプロジェクトによってしばしば大きく上下(25%_400%)する。
間接経費の確定プロセスには基準らしい基準が存在しない。確定のプロセスに働く要因は以下の通りである。
- 会社の規模と固定費の規模
- 業種:メーカーの固定費・間接費はサービス業のそれより高い。
- 経費配分のベース:メーカーは概して総間接費をベースとし、サービス業は概して直接的な給与をベースとしている。
- 資金源:資金調達の方法は直接経費と間接経費の計上アプローチに影響を与える。
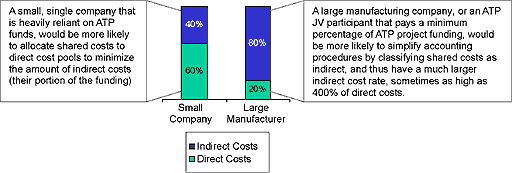
Cost Sharing Guidelines ・・・・・・・・・
ATPはATPプロジェクトに対する企業側の負担分について、充当可能な資金源を明確に定めている。
企業のコストシェアに充当しうる資金
- 州政府・地方自治体からの助成金
- 助成金受給者、もしくはサブコントラクタ以外で連邦政府と関係のないサードパーティからの現物出資(機材、研究機器、ソフトウェア、必需品等)
- 現物出資の価額については、ATP実施規定に特段の定めのないかぎり、OMB Circular A-110、Subpart
C、Section 23にしたがって査定され、ATPプロジェクトの使用に供された部分を比例配分で算出する。
- コストシェアとして充当可能な現物出資の総額は、プロジェクトの総経費のうち連邦政府以外から調達した資金の30パーセントを上限とする。
企業のコストシェアに充当しえない資金
- ATP以外の連邦政府助成金
- 埋没原価
- サブコントラクタ(サブコントラクタの手数料を人為的に膨らませ、企業側のコストシェアを見かけ上吊り上げるという事態を回避するため)
Unallowable Costs ・・・・・・・・・
Federal Acquisition Regulation(FAR)もしくは行政管理予算局(OMB)の経費原則のもとでは通常認められる経費であっても、ATPプロジェクトにおいては許容されない経費のタイプが存在する。
- 一般的に、連邦政府との契約は、契約業者にとっては“営利事業”であり、したがって利益創出を意図するものである。
- これに対して、ATPプロジェクトは助成金受給者が市場で利益を創出できるようにすることを目的としている。
- したがって、受給者がATP助成対象の研究活動で“儲ける”ことは認められない。
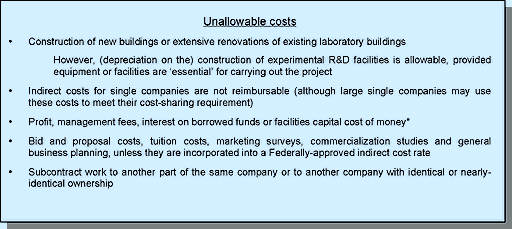
Funding Case Studies ・・・・・・・・・・・・・・
ATP助成の期間と金額はプロジェクトのタイプと規模によって大きく変動する。
| プロジェクト |
タイプ |
期間 (年) |
助成金総額 |
ATPの補助率 |
Affymetrix, Inc.
DNA Diagnostics |
JV |
5.0 |
$62.97M |
49.9% |
Kopin Corp.
Display Technology |
JV |
3.2 |
$12.44M |
49.0% |
Al Ware
Artificial Intelligence Software |
JV |
4.7 |
$7.62M |
49.7% |
Texas Instruments
Integrated Cicuitry Insulation |
Single |
3.0 |
$5.56M |
35.5% |
Third Wave Technologies, Inc.
DNA Diagnostics |
Single |
2.0 |
$2.77M |
72.2% |
Nonvolatile Electronics, Inc.
Magnetoresistive Computer Memory |
Single |
3.0 |
$2.61M |
66.7% |
第3章 ATPプロジェクトから生まれるIP
Commercial Ownership of all IP ・・・・・・・・・・・・・・
ATPは開発事業から商用化への見込みが最も高い組織、すなわち民間の営利企業に知的財産権(IP)を委ねることを意図している。
- 米国経済を刺激するというATPのミッションに鑑みて、ATPから発生する特許はすべて米国内で設立された営利組織に帰属させる。ATPプロジェクトに関わる大学、非営利団体には特許の所有が認められていない。ただし、権利所有者から特許権使用料を受け取ることは可能である(現在、議会はこの規定の再検討を進めている)。
- ATPから発生する著作権は、通常の著作権と同じ扱いで創案者に帰属させる。
- 助成応募者が単一企業である場合、所有権の扱いは明瞭に定義される。
- 助成応募者がジョイントベンチャーの場合、ATPの条件にしたがいつつ、JVの構成企業がIPの帰属について交渉のうえ決定しなければならない。
- IPの所有者はIPを他者にライセンスすることができる。
Government Rights ・・・・・・・・・・・・・・
IPの所有権が民間の参加者に帰属する一方、ATPはATP cooperative agreementによってIPに対する権利を保護措置的に留保している。
- 政府は政府によるIPの使用を確保するため、royalty-free、non-exclusiveなIP使用権を留保している。企業秘密は非公開。なお、これまでにこの権利が行使されたことは一度もない。
- NISTは助成金受給者に対して、商品化の達成に同人の特許を必要とする“信頼するに足る申請者に対し、状況に照らして合理的と判断される条件で”
特許権の使用権付与を要求する権利を留保している。非常に極端なケースとして、権利保有者に欺瞞の意図が認められた場合、同保有者に特許権使用料を支払う義務は一切生じない。なお現在まで、NISTがこの権利を行使したことはない。
IP Strategies ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
知的財産権をめぐる諸戦略
知的財産権の扱いをめぐってATPの助成金受給者が実施する主たる戦略には、特許権取得、著作権保護、企業秘密としての維持がある。
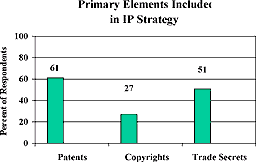
IP in Joint Ventures ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ジョイントベンチャーでのIPの扱い
ジョイントベンチャーの参加企業がIPの扱いに関して協議するとき、ATPはこの交渉に関与しない。またIPをめぐる取り決めはジョイントベンチャーの性質によって大きく異なる。
- 大規模企業一社と小規模企業数社から成るジョイントベンチャーの場合、大企業が(主導的な立場に立つ)“リード・カンパニー”としてプロジェクトから発生するすべての知的財産権を保有し、それ以外のJV参加企業が非独占的な使用権を要求する資格を保持する。この場合、通常は権利保有者に対する権利使用料の支払いが発生する。
- 同等規模の企業から成るジョイントベンチャーの場合、各社がそれぞれの成果について特許権を取得し、他のJV参加企業が非独占的な使用権を要求する資格を保持する。この場合も、通常は権利保有者に対する権利使用料の支払いが発生する。
IP Procedures ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ATPは特許権と著作権の処遇および報告について明確な手続きを定めている。
- 特許出願品の考案者がATP助成金受給者の“特許権代表人”に対してその開示を行い、それから2ヶ月以内にこの特許権代表人がATPに対して特許出願品の開示を行う。また特許権が付与され次第、ATPに対してこれを告知しなければならない。
- 助成金受給者は適切な著作権表示で政府の援助を認知する。
- 研究成果を出版するか否かは助成金受給者が判断する。
IP Case Studies ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ATPプロジェクトから発生したIPの権利保有者は、このIPを社内の製品開発に応用することもできるし、第三者へのライセンシングによって一回限りもしくは継続的な収入を得ることも可能である。
| プロジェクト |
事 例 |
Affymetrix, Inc.
DNA Diagnostics |
- 複数の特許権を取得
- 研究成果をもとにいくつかの新製品、新システムを発売
- 30件を超えるライセンス契約、およびJV事業(Beckman Coulter Inc.、Eos Biotechnology、Hewlett
Packard、Incyte Pharmaceuticals、Merck、OncorMed、Parke-Davis Pharmaceutical
Division等)を創出
|
Nonvolatile Electronics, Inc.
Magnetoresistive Computer Memory |
- Honeywell, Inc.とのライセンス契約
- Motorola, Inc.とのJVで開発技術を商用化
- スピンオフのアプリケーション製品を発売
|
Texas Instruments
Integrated Cicuitry Insulation |
- 20余りの特許権を取得
- 10件の技術論文を出版
- 加工技術を絶縁体メーカー等にライセンシング
|
Third Wave Technologies, Inc.
DNA Diagnostics |
- 20余りの特許権を取得。今後5年にわたって、さらに多数の特許権を取得する予定。
- 当該技術に基づいて3件の新製品を発売
- 大手製薬会社数社とライセンス契約を交渉
|
第4章 ATPプロジェクトから生まれる利益
Private Sector Profits ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ATPプロジェクトの成功がもたらす利益は、すべてこれを創出した企業の所有に帰する。
- 連邦政府は法人課税※以外にATP助成の研究活動がもたらす利益の還元メカニズムを持っていない。政府は“プロフィットシェア”を要求しないうえ、知的財産権を所有していないことから、著作権使用料も受け取らない。
- 連邦政府の研究機関は総じて、またとりわけATPは、米国の経済的利益の保全を目的としている。民間セクターの利益を民間セクターに留め置くという方針は、この利益がそこでインセンティブとして作用し、あるいはさらなる成長促進のための再投資に回されうることから、先の目的に適うと考えられる。
- 連邦政府が営利企業として活動することは法律で禁止されており、直接的な投資利益の追求は認められていない。
- この方針がために、連邦の拠出する助成金は、事実上、私企業にとって直接的な返済義務を伴わない莫大なボーナスと言える。結果として、助成金獲得のコンペに対する企業の参加意欲が高まり、より優良なプロジェクトだけが助成されることにつながる。
※ 法人課税には給与支払税が含まれる。ちなみに1994年のATPプロジェクト開始当初、Third Wave Technologiesの従業員は6名だったが、1996年の終了時には72名に増えていた(現在は92名)。
Avenue
ATPプロジェクトの参加者とそのパートナーらは、民間セクター内で、さまざまな戦略をもってATPプロジェクトの成果を利益につなげている。
参加企業はATP関連の技術開発が、パフォーマンスの改善、コスト削減、市場化に至る期間
- 29%が100%もしくはそれ以上のパフォーマンスアップを見込んでいる。
- 28%が25%もしくはそれ以上のコスト削減を期待している。
- 80%が市場化に至る期間について少なくとも1年の期間短縮を期待しており、62%が2年もしくはそれ以上の期間短縮を期待している。
営利化の戦略
- 65%が主たる営利化戦略の一環として製品もしくはサービスの社内生産を計画している。
- 79%がライセンシングを営利化の方法候補に掲げ、24%が主たる戦略の一環として位置付けることを検討している。
- 28%が新しいプロセスの社内使用を計画している。
Source: ATP Business Progress Reports from
207 projects funded 1993-1995
Primary Commercialization Strategies ・・・・・・・・・
いくつかの戦略を
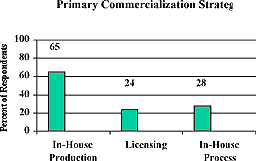
Deployment of Technologies ・・・・・・・・・
1993年から1995年の間に助成を受けたATPプロジェクトの参加企業を調べたところ、いずれもATP関連のテクノロジーからすでに収入を得ているか、もしくはその方向に向かって順調に進んでいた。
- 技術開発の結果として、新たな営利機会の創出を見込む参加企業が過半数(59%)を超え、残り41パーセントも製品もしくはプロセスの改善を見込んでいる。なお、アプリケーションのうち35パーセントは市場のニーズや問題に応える“世界初の”ソリューションと考えられるものであった。
- 新技術のうち、製品面に反映されるものが3分の2以上(65%)を占め 、残りは製造プロセスもしくはサービスへの応用となっている。
- 調査対象となったプロジェクトのうち、26件が助成後1年か2年という“早い段階”で収入を得ていた。プロトタイプおよび初期的なスピンオフ製品の販売利益は2,000万ドルを超え、ライセンス契約から入る特許権使用料は44万5,000ドルにのぼる。
- ほとんどの参加企業はATP助成から4年以内に収入の道を開くことを期待している。
Source: ATP Business Progress Reports from
207 projects funded 1993-1995
Paths to Commercialization ・・・・・・・・・
ATPの助成は企業が取り組む“科学的に実証可能な”テクノロジーからプロトタイプへの移行を支援するもので、この段階に到達して以降は市場の原理に則って商用化が進む。
研究成果を商用化に至らしめる典型的なアプローチ
- ベンチャーキャピタル、他企業もしくは政府による助成
- 株式公開
- 大企業との提携
- 大企業による買収
- 自力で商用化を推進
Commercialization / Profit Case Studies ・・・・・・・・・
ATPの助成金受給者はATPの助成対象活動を梃子に新製品の商品化に漕ぎつけ、追加的な財源確保や提携によって事業目的の達成を目指している。
| プロジェクト |
商品化・営利活動の事例 |
Affymetrix, Inc.
1994-99
DNA Diagnostics |
- 最初の製品(GeneChipョ Systems)を1996年半ばに商品化、1997年には$4.8Mの利益を出している
- NIH及びその他の政府・企業パートナーから後続財源を確保
- 1996年6月に株式公開、$92Mを調達。
- 1997年から1998年、GeneChipョ の販売増進に伴って製品収益が$22.8Mにアップ(377%増)
|
Al Ware
1994-99
Artifical Intelligence Software |
- 人口知能技術Process Advisorを商品化
- 1997年、Computer Associates Int’lによって買収
|
Kopin Corp.
1994-98
Display Technology |
- Motorolaと提携、CyberDisplay凾xースに新製品を開発、製造、販売(新規の製品カテゴリーの創出を含む)
- Siemens、Wireless、Gemplus、FujiFilm Microdevicesら、Motorola以外のOEMパートナーとも契約
- 1997年から1998年にかけて製品収益が77%増($13.1Mから$23.2Mへ)。10万台を超すCyberDisplay凾フ出荷もこの増収に貢献した
- Industry Weekの1998 “25 Technologies of the Year“を受賞
|
Nonvolatile Electronics, Inc.
Magnetoresistive Computer Memory |
- MRAMチップの商品化を目的としてMotoralaと提携、1999年内の商品化を目指している
- Motorolaの資本参加(12%)
- 二次製品GMRセンサーを商品化、収入$500,000以上
|
Texas Instruments
Integrated Cicuitry Insulation |
- 素材開発のためにNanoPore, Inc.と提携
- 1998年、Allied Signal, Inc.がNanoPoreのスピンオフを買収、Nanoglass(素材)の販売活動にあたる
- Nanoglassの顧客(半導体メーカー、統合回線メーカー等)に対して加工技術のライセンシングを検討
|
Third Wave Technologies, Inc.
DNA Diagnostics |
- 1996年半ばに最初の製品キットを商品化、1996年末までに$300,000の収益達成
- NIH及びDOEから後続財源を確保
- 1998年半ばまでに3つの新製品を発売、収入の見積は5年以内に$100M以上
- 大手製薬会社及び農芸会社と技術の販売/ライセンシングを交渉中
|
第5章 プロジェクトの達成目標とパラメータ
Proposal Process ・・・・・・・・・
ATPプロジェクトのパラメータは企画書提出の段階で明確に定められ、プロジェクトの目標、期間、予算等も具体的に示される。
- ATPに提出される企画書は科学的・技術的メリット(50%)と総合的な経済的メリット(50%)に基づいて審査される。
- いずれの企画もその主体は営利企業で、プロジェクトのガイドラインは単一企業に対する助成について3年間で200万ドルの上限、ジョイントベンチャーに対する助成について5年間の期間的上限を定めている。
- 複数年契約の予算はATPの承認を以って修正できるが、予算全体は増額されない。
- 企画書は以下の要素を具体的に示さなければならない。
- 潜在的な商業的利益と達成のための戦略
- 商業的利益の実現を阻む現下の技術的な障壁
- 技術的な障壁と研究開発の目的との関連性
- 技術的な障壁を克服するための具体的な研究開発計画
Proposal Review and Selection ・・・・・・・・・
企画書の選抜プロセスは予選、科学・技術・実務分野の専門家によるピアレヴュー、口頭審査、最終格付から成る。
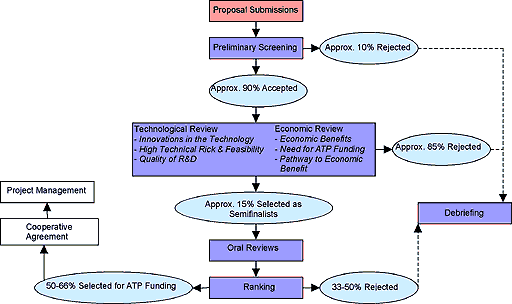
Project Oversight ・・・・・・・・・
ATPはプロジェクトの進捗状況をモニターするため、特定の監視活動と監査を義務づけている。
- 助成金受給者はプロジェクトの立ち上げ段階、終了段階、および年に一度行われる当該プロジェクトに配属された技術担当および実務担当のプロジェクト・マネジャーとのミーティングに出席しなければならない。
- 助成金受給者はATPに対して四半期ごとに財務、技術、実務報告書を提出する。
- 助成金受給者は、必要に応じて、NISTがATPの効果を評価するために行う特別調査への参加を求められる。
- 助成金を受給する企業が大規模な組織改変を行う場合、新しい経営陣はATPに対し、改変後も承認済みのプロジェクトの目標を首尾一貫追求する旨の確認書を提出しなければならない。
- ジョイントベンチャーの場合、主導権を持つリード・カンパニーがJV参加企業の取りまとめとプロジェクト管理に責任を持ち、ATPとの連絡役を務める。
Project Payment ・・・・・・・・・
ATPの助成金は分割で支払われ、企業側もATPの支払に合わせて相応のコストシェアを拠出する。この仕組みにより、ATPは速やかな撤退の道を確保している。
- ATPの助成金は分割(通常は四半期ごと)で支払われる。企業側も支払の各段階で同等比率の資金拠出を行わなければならない。
- この段階的な分割払いは、プロジェクトの査察過程で不正な活動が認められた場合、あるいはプロジェクトが目的から大きく逸脱していると判断された場合、政府が直ちに助成を停止し、損失をすでに支払済みの助成金に留めるための措置である※1。
- 同様に、プロジェクトの達成目標が変更された、もしくは適切でないと判明した場合、あるいは助成金受給者の周辺事情に変化が生じた場合(例えば、外国企業に買収されるなど)、Public
Law 102-245にしたがって直ちに助成金の支払を停止できる。
- $300K以上のプロジェクトについては、独立の会計監査人もしくは“Resident Cognizant Federal
Auditor(ATPが任命する政府の監査人)”がATP指定の間隔※2で正式な監査を行うよう義務づけている。なお、監査にかかる費用は直接経費とみなされ、政府がこれを負担する。
※1 政府は必要に応じて空費分の助成金を裁判で回収することもできるため、実際には政府が“ロスを出す”状況は考えにくい。
※2 2年未満のプロジェクトはプロジェクトの終了時、2_4年のプロジェクトは初年度の終わりとプロジェクトの終了時、5年のプロジェクトは1年目、3年目、5年目の終わりに監査を行う。
Project Management ・・・・・・・・・
当初の計画に些少の修正が加えられることは間々あるが(ATPの承認を必要とする)、助成金受給者が大幅な軌道修正を行うことは稀である。
- ATPは、結果さえ当初の意図に矛盾しなければ、“柔軟”な姿勢でプロジェクトの管理にあたるとしているが、助成金受給者が大幅な軌道修正を行うには相当に説得力のある論拠を示さなければならない。
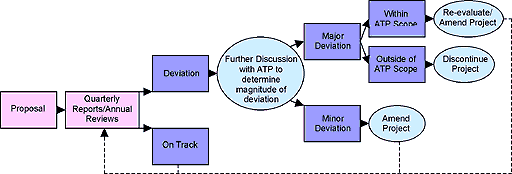
Sample Progress Data ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
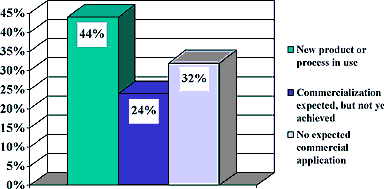
ATPプロジェクトの最初の50件について、支援開始から4~6年後の進捗状況を評価したところ、著しい成果が示された。
 ATPはあくまでも民間主導のプログラムであり、営利企業が主体となってプロジェクトの企画・提案・実施を進め、民間負担分の資金を拠出する。
ATPはあくまでも民間主導のプログラムであり、営利企業が主体となってプロジェクトの企画・提案・実施を進め、民間負担分の資金を拠出する。 ATPはあくまでも民間主導のプログラムであり、営利企業が主体となってプロジェクトの企画・提案・実施を進め、民間負担分の資金を拠出する。
ATPはあくまでも民間主導のプログラムであり、営利企業が主体となってプロジェクトの企画・提案・実施を進め、民間負担分の資金を拠出する。